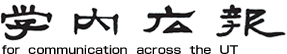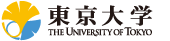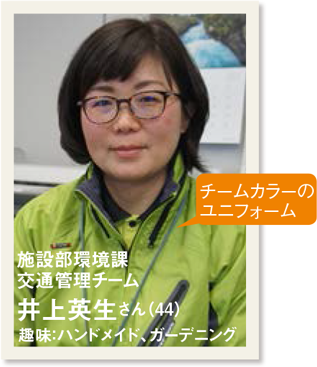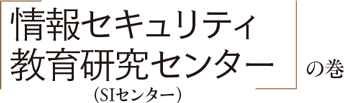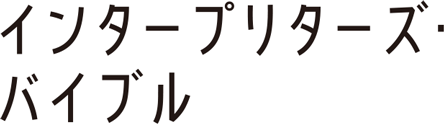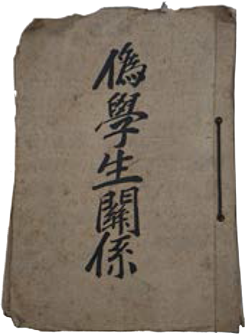第1回
第1回
岩手県大槌町にある大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センターを舞台に、大気海洋研究所と社会科学研究所がタッグを組む地域連携プロジェクトがスタートしました。海をベースに三陸各地の地域アイデンティティを再構築し、地域に希望を育む人材を育成するという文理融合型の試みです。本学の皆様が羨むような取り組みの様子をお伝えします。
「海と希望の学校 in 三陸」開校!
准教授

大気海洋研究所と社会科学研究所との文理融合型プロジェクト「海と希望の学校 in 三陸」が開校しました。
三陸の沖合には暖流と寒流がぶつかり合い、豊かな漁場が広がっています。入り組んだ海岸線に沿って点在する村々には、各湾固有の風土や文化が根付いてきました。しかし、そこでは過疎・高齢化の問題や東日本大震災による被害を乗り越えた先の希望、あるいは将来への展望が求められています。岩手県大槌町に建つ大気海洋研究所附属国際沿岸海洋研究センターは、津波被害の実態調査を進める中で、もう一歩進んだ地域復興への貢献にはそこに居住されている方々の暮らしぶりを知る必要があることに気付きました。海の特徴と住む街の特徴とは、人々の生活を通じて深く結びついているはずです。そこで、当センターと、釜石市に研究拠点を置く社会科学研究所とが連携し、「海と希望の学校 in 三陸」を開始することにいたしました。
このプロジェクトでは、
- 三陸各湾の海の特徴、そこに生息する生物とその変動を明らかにする。
- 地域ごとの暮らしと文化の特徴(地域(ローカル)・アイデンティティ)を明らかにする。
- 地域ごとの可能性を地元の小・中・高校生たちとともに考え、将来への希望を見出すとともに、その実現を目指す人材を育成していく。
こういったことを目指しています。
すでに開始したイベントもあります。例えば、小中高校の生徒対象の「対話型授業」については、2018年7月のセンター開所式の前日に、大槌学園4年生をセンターに招いて「ふれあい体験」を実施しました。エントランスホール天井に描かれている、海の生命観をテーマとした「生命のアーキペラゴ」(「学内広報」no.1513表紙)を見ながら、作者・大小島真木氏やセンター・スタッフによる講義を行いました(写真1)。今年2月には盛岡第一高校で出前授業を行いました。また、3月には釜石高校SSHの生徒さんたちをセンターに招き、海洋観測やサケの鱗を用いた生物実習(写真2)のほか、海洋関連書籍の書評合戦「海のビブリオバトル」、生徒さん自身に三陸名物の磯ラーメンを作ってもらい、磯とは何かを知ってもらう「磯ラーメン大会」を行いました(写真3・4)。
今後は、様々な手段を用いて三陸沿岸の魅力・活力・底力を発信していきます。センターには展示室「おおつち海の勉強室」を今年夏以降に開設する予定です。また、「海と希望の学校 in 三陸 盛岡分校」を設置し、内陸部にも三陸の情報を発信していきます。なおSNSについてはFacebookやTwitterを開設しており、センターや大槌とその周辺の毎日の様子を配信中です。都会の方からすると非日常的なコンテンツに溢れています。「@umitokibo」で検索してみてください。
今年度の目玉として、3月にリアス線※が開通した三陸鉄道とジョイントで列車を利用してのイベント「海と希望の学校 on 三鉄」を開催し、地域の皆様に海を知り、身近に感じてもらう機会を設けたいとも考えています。
今後をぜひ楽しみにしていてください。どうぞよろしくお願いいたします。