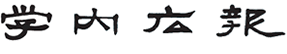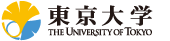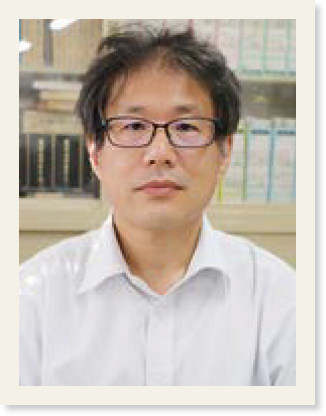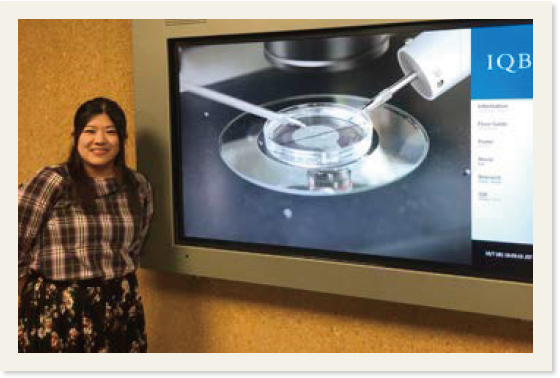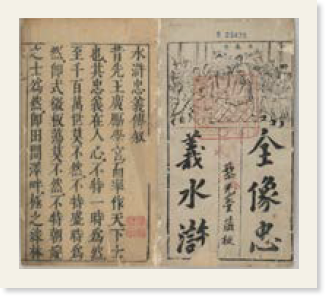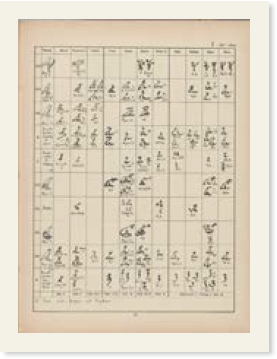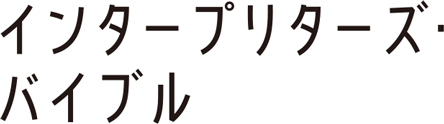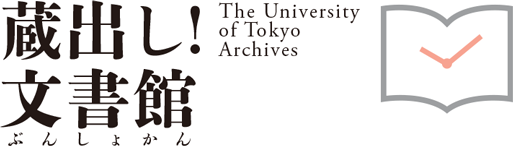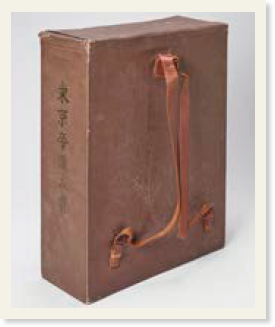第10回
第10回
三陸を舞台に、岩手県大槌町にある大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センターと、社会科学研究所とがタッグを組んで行う地域連携プロジェクト――海をベースに三陸各地の地域アイデンティティを再構築し、地域に希望を育む人材を育成するという文理融合型の取り組み――です。3年目を迎えたわれわれの活動や地域の取り組みなどを紹介します。
大槌高校はま研究会

特任研究員

私が所属していた大型海洋生物の生態を扱う研究室の学生たちに進学のきっかけを聞いてみたことがあります。すると、必ずしも幼少期からこうした動物が好きだったという人ばかりではありませんでした。私自身も中学・高校と陸上競技部での部活動に明け暮れていましたが、研修旅行で連れて行かれた大学が水族館を持っていて「なんだか楽しそう」と思ったことが進路選択に影響しました。今回は、こうした将来に影響する体験になるかもしれない、岩手県立大槌高校と協力して行っている取り組みをご紹介します。
大槌高校に今年発足した「はま研究会(通称:はま研)」は、研究者が収集してきたアワビの殻を磨いてタコによる捕食跡の穴を探す作業や、ウミガメの排泄物の仕分けや彼らが記録してきたビデオ映像の確認作業、水質調査を目的とした川での採水作業、生物を飼育している水槽の掃除など、“研究における普段の地道な作業”を研究者と一緒に週2~3回(1回につき数人が参加)の頻度で行っています。これまでは華々しい研究成果について紹介することが多かったので、当初は“果たしてこれは楽しいのだろうか……?”という気持ちでいっぱいでした。しかし、黙々と楽しそうに「捕食跡あった!(アワビ)」「これヒジキじゃね?(ウミガメ排泄物)」と言いながら作業をする姿を見てほっとするとともに、彼らのなんでも楽しんでしまう能力に驚かされました。また、作業中は「この前は○○を釣りに行った」とか「○○海岸で○○した」など、自然と海に関する話題が出ることが多く、新たな三陸の海の魅力に気づかされることもありました。
はま研の活動で得られたデータには、より詳細な分析を必要とするものもありますが、中にはそのままでも十分に学術的価値があるものもあります。数年後、何の変哲もない普通の県立高校が“東大の実験所がある大槌町”という地の利を生かして学術会議で研究発表を行うことになれば、それは素晴らしいことだと思います。さらに妄想を広げ、5年後10年後に沿岸センターの研究室に入った学生が「実は高校時代にはま研でした」なんてことになれば、この上ない喜びです。いかにして早く良い成果を上げるかという効率性や即効性のある事柄に目が向けられがちなご時世ですが、すぐさま成果や利益には直結しなくともいつか大きく花開くかもしれない種を少しずつでも蒔き続けることが、海と希望の学校、ひいては沿岸センターのような地方の附置研の使命なのかもしれない(※あくまでも個人的な意見です)。そんなことを考えさせてくれる良い機会を与えてくれた高校生たちに感謝しつつ、この活動を私自身も楽しみながら続けていきたいと思います。