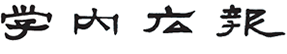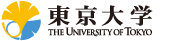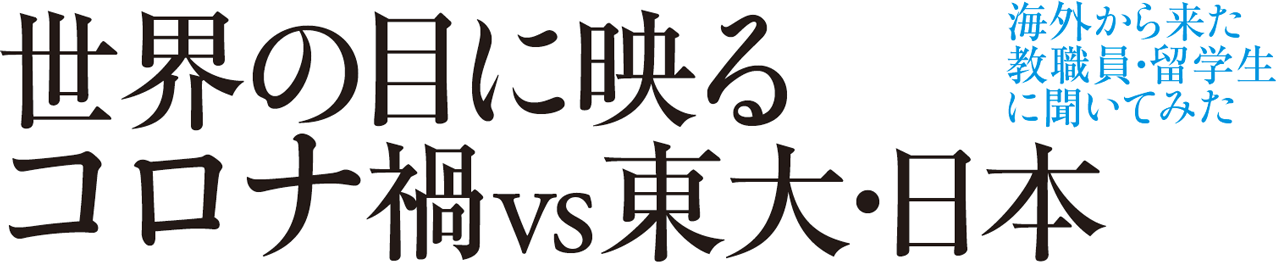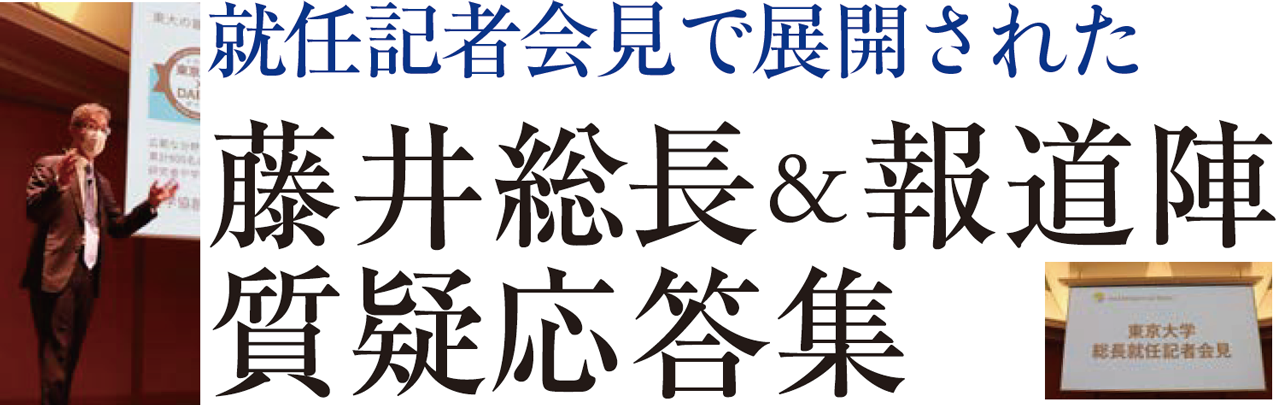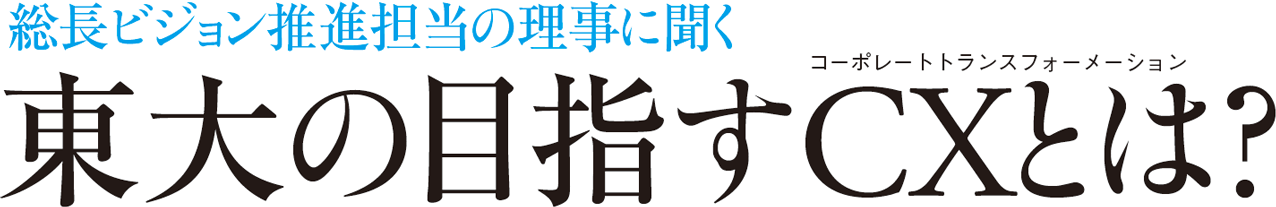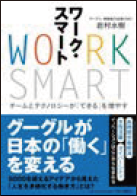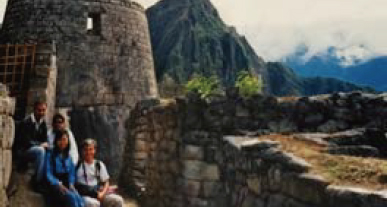コロナ禍が世界に、日本に広がって早や1年数ヶ月。この間、日本の社会も東京大学も、コロナ禍の試練にさらされてきました。オンライン授業や在宅勤務が日常的なものとなってキャンパスの風景は一変しましたが、「密」な満員電車は相変わらず……。そんな日本社会の様子や東大の舵取りは、グローバルな目にはどのように映るでしょうか。そこで今回、東大で活動している海外出身の仲間10人にお声がけし、コロナ禍下の大学生活や社会観察についてメールアンケートを実施しました。地に足の着いた生活者の目線、冷静に状況を捉え、問題点を見出す研究者の目線──なるほどと思う見方、ハッとさせられる声をお届けします。
❶コロナ禍の下での大学生活で困ったことは? ❷東大のコロナ対応で不満な点、満足な点は? ❸日本と母国のコロナ対応を比べてどうですか? ❹コロナ禍の日本で「ヘンだ」と感じることは? ❺コロナ禍に関して大学に言いたいことは?
日本は効率的な国という評価は幻だったかな?
❶教員側や学生側を問わず、対面授業と比べてオンライン授業で刺激や楽しさがかなり削げている気がします。研究面でも、共同研究はオンラインでももちろん十分可能であるものの、共同研究者と同じ空気を吸わないとインスピレーションがなかなか湧いてきません。❷直ちに授業をオンラインに切り替える判断をし、教職員全員が新しい仕組みに積極的に取り組んで、全力を尽くして実行したことは高く評価しています。❸ベルギーの政治は相変わらず大カオスですが、なんと、ワクチン接種は非常に効率良く実施されていることに少し驚きました。日本は、ベルギーなどでずっと効率的な国と評価されてきましたが、それは幻だったかな?❹日本での生活が長いので今更何かに大変驚くことはまずないと思いますが、「この企画は明らかに不可能だ、コロナ禍下で避けるべきだ」とみんな思っていても、その事実を認める責任者が全く現れないという悪い癖がいつまで続くのでしょうね。❺「オンラインで大丈夫じゃないか」と思わないでほしい。教育のため、また研究のために。
数理科学研究科教授
Ralph Willox さん

PCR などの検査を大学に提供してほしい
❶私の仕事の多くはリモートでできるので、職場から家への切り替えは簡単でした。在宅勤務の方が生産性が高く、心身の健康にも有効です。そのかわり電気代など自己負担の経費がかかるので、カバーしてもらえるとよいのですが。❷職場で働く必要があるとき、症状に疑いがあるとき、同僚の陽性が判明したときなどには、PCR検査や抗体検査を大学に提供してほしいです。❸マスクに抵抗がなく、公共の場での物理的接触(抱擁、握手など)の少ない日本の文化が感染を軽減したはず。ただ、日本も英国も人より経済を重視したように見えました。❹五輪への執着と、リモートワークに熱心でない雰囲気もあったことは疑問。コロナ禍は他国より遅かったのでニュージーランドのように対応に成功した国から学べたはずが、実際は対応に失敗した国々と同じことになってしまったようです。長期的戦略を欠いたのでは?❺大学でワクチンの接種と開発を進め、有効性と信頼性を実証していくとよいと思います。
広報戦略本部特任専門員
Rohan Mehra さん

世界と日本との「時差」が今後際立つかも
❶オンライン授業では人間関係を築きにくい上、討論の相手の顔が見えないのは疎外感が増し、つらいと感じます。相談施設に問い合わせても返事が来ない時もあったので、対応を確認し続ける必要がありました。❷ PC・ルーターの貸出やオンライン受講のための教室開放はよかったです。Wifi環境の弱さや図書館・院生室の利用時間の短縮は不便な点。❸ブルガリアでは、コロナ対策は「新しい生活様式」に慣れるためではなく「異常なる生活様式」の克服のためにあると理解されていますが、日本はそれと逆で、異常な状態を日常化してしまっているように感じます。❹「自粛」「不急不要の外出」など意味不明な言葉で対策が行なわれるのは変ですね。政府→自治体→組織→個人の順で最終的に自己判断・自己責任に委ねられていて、その状況を社会が疑問なく受け入れているのも不思議です。❺動き始めた世界と緊急事態宣言を延長した日本との「時差」が際立ちそう。大学だけでも(というより、大学だからこそ)今の状況に慣れてほしくないです。
総合文化研究科修士課程
Viktoriya Nikolova さん

日本人の慎重さのプラス面とマイナス面
❶論文提出前最後のデータを取得する頃にコロナ禍が発生し、先が見えない状況で研究を続けるのは非常に大変でした。❷研究への影響に鑑みれば、大学は費用をかけてでも定期的な検査を提供できたはずだと思います。研究者や学生には、病気だけでなく、自分が感染して研究室閉鎖の要因になるのを恐れる人もおり、そのストレスの軽減策もあるべきです。大学と研究主宰者(PI)が早い段階から密に連絡をくれたのは重要でした。❸日本人は当初から状況を理解し、ウイルス拡散防止にはマスクの着用が重要だとわかっていたし、諸外国と違い、政府が罰則付きで命令しなくても人々は集まるのを避けていました。一方、トルコでは検査を無料で提供しており、日本もそうしてほしいですね。❹感染が増えた時期でさえ電車では社会的距離が保たれなかったこと。❺日本人は少し慎重すぎると感じていましたが、今回はこれが蔓延を防ぐ肝でした。ワクチンに対しても慎重なようですが、もし日本が最初から迅速に開発を進めていたら、世界は最も信頼できるワクチンを手に入れていたでしょう。
ニューロインテリジェンス国際研究機構
特任助教 Ucar Hasan さん

研究は不便でも日常はそれほど変わりません
❶私の研究は沖縄でのフィールドワークが主体のため、移動制限で大きな影響を受けました。オンライン授業では他の学生と直接話せず、仲間とつながるのが難しいです。家族を訪ね、ダンスに通い、映画館に行くといった生活が当然ではなくなりました。❷躊躇せず授業をオンライン化し、活動制限レベルを制御したのは英断。健康管理フォームや入口のIDスキャナーなど、感染者の追跡に役立つ対策もよかったです。❸市民の意識の高さ、公共空間での安全対策(マスク着用、消毒剤提供、飲食店の座席間の距離確保)は日本の長所。ワクチン情報の不足、マスクなどのパニック買い、緊急事態の線引きがブレ続けたのは短所かな。米国ではワクチンの展開が早く、経済再開のタイムラインが明確でした。❹多くの人がマスクを着用し、飲食店が8時に閉店し、映画館がときに営業していない点を除けば、日常生活は以前とさほど変わりません。LAでは外出できず不平をこぼす人もいましたが、私は日本ではそうは感じませんでした。
新領域創成科学研究科修士課程
Destiny Johnson さん

東大発の安心なオンライン授業システムを
❶教職員は同僚、学生と接触しなくてはなりません。外国人の教職員、留学生は帰国の際にPCR検査を受けなくてはならないので、学内で新型コロナウイルスの検査を受けられる体制を作った方が良いかと思います。❷会議や授業のオンライン化が早かったのはよいですが、医療体制や政策などの提言をもっと積極的に行うべきです。Zoomには情報流出の懸念があるので、安心して利用できるオンライン授業システムを開発するとよいと考えます。❸日本の水際対策は手ぬるいです。台湾では入国者に14日間の隔離を求めて違反には罰金を課す一方、隔離専用ホテルを政府が提供し、移動には防疫タクシーの制度もあります。日本も14日の隔離は求めますが、移動の手配は本人任せ。変異株の流行地からの入国者に6日の隔離を求めるだけなのも疑問です。❹出入国への対応が外国人には厳しいのに日本人にはゆるいなど、身内に甘いですね。感染拡大中なのにグループで会食したり、行楽地で遊んだり、マスクを外して雑談したりする人を見かけます。
東洋文化研究所助教
黄 偉修 さん

日本の打つ手は「接地気」しすぎかも
❶昨年4月に入学しましたが、1年間、同級生や先輩と対面で会ったことがほぼなく、大学院に通っている実感がありません。『礼記』の「独学にして友無ければ、則ち孤陋にして聞くこと寡し」の状態です。❷日本政府の学生支援緊急給付金の募集が始まった頃、留学生には特に厳しい要件が課されていると一部報道がありましたが、東大の事務から、あきらめて申請を控える学生がいるのではないかと心配だ、ぜひ相談して申請を検討してほしい、という理事の呼びかけのメールが届きました。留学生にそこまで配慮しているのかと感動しました。❸うちわ会食、巨大イカ像設置……疑問に思う政策が多く、不思議でした。庶民の生活実感を理解して大衆に受ける政策を打つという意味の「接地気」(地に足が着いた感じ)という流行語が中国にありますが、日本はある意味で接地気しすぎかも。❹コロナ禍なのに、日本では緊急事態宣言でも要請することしかできず、政府の権限の弱さと国民の自由度に驚きました。
総合文化研究科修士課程
鍾 周哲 さん
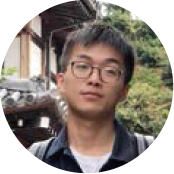
オンライン学会で海外の研究者から刺激
❶留学生の人間関係はたいてい大学生活でつながっているので、それができなくなったのはきついです。指導教員以外の先生とも会いにくくなりました。学内の感染情報が少なく、当初英語での発信が不足していたのは留学生には不安でした。研究に集中できたこと、きらめく発想を持つ海外の研究者にオンライン学会で出会えたことはよかったです。❷理学部のルーター貸出に感謝です。先生方から学生の体調を慮る連絡があったのも印象的でした。学外者の入構制限もよかった。でも、守衛が常に立っているのは大変なので椅子を用意したらいいのに。❸感染防止のため外国人との外食を控えよとの指針を出した自治体があると報道で知り、明らかな差別だと思いました。❹ワクチン接種率の低さが不思議。私はオリ・パラの期間はずっと家にいるつもりです。❺論文の査読プロセスが前より大幅に遅くなりました。年限が限られる大学院生には大きなストレスです。学生に対しては、より人情味のあるあたたかな雰囲気を醸成してほしいです。
理学系研究科博士課程
HyeJeong Kim さん

駒場→本郷の移動がないのは不幸中の幸い
❶最も難しいのは、オンライン授業で注意力を維持することです。研究面では、実験系の作業では状況に対応するのに少し時間がかかりましたが、新しいやり方をすればうまく進められそう。思うように旅行できないことを除けば日常生活に大きな影響はありません。授業を受けるのに駒場から本郷に行く必要がないのは不幸中の幸いかも。❷満足です。大学は活動制限に関して厳しすぎとゆるすぎの間でバランスを取っています。キャンパスのフードトラックで美味しいものが食べられないのは残念ですが。ただ、アルバイトしないといけない学生や留学生にとって今の状況は死活問題かもしれず、大学が経済的なサポートを提供しているとは聞いていますが、心配です。❸日本とタイは比較になりません。私はタイ政府には非常に不満です(笑)。日本は企業や住民への支援や補償の面が順調に進んでいると思います。ただ、ワクチン接種は遅すぎ。過去に何か問題があったせいで遅れたと聞きますが、本来ならもっと速くできたはずです。
工学系研究科修士課程
Natthajuks Pholsen さん
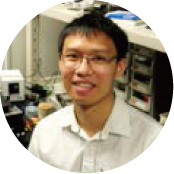
対応が似ていたインドネシアと日本
❶オンライン授業では先生や友達と直接やり取りができず、違和感を覚えましたが、次第に慣れました。通学に時間を使わなくてよいのは助かりました。特に初期は家で退屈な日々が続きましたが、今はもう慣れたものです。メンタルヘルスのサポートは特に初期に重要だったと思います。❷コロナ禍が始まった2020年春、大学の授業が延期されるのか予定通り行われるのかが心配でしたが、東大は学事暦を変更せず授業をオンライン化すると迅速に通知しました。正しい決定でした。また、東大のウェブサイトはCOVID-19に関して有益でした。❸日本では非常事態宣言、インドネシアでは大規模な社会的制限でしたが、内容はほぼ同じでした。ロックダウンではなく、公共の場が一時的に閉鎖され、プロトコルの遵守が奨励されました。生産力が低下しても経済が止まらなかった一方、状況を制御できず感染も止まりませんでした。❺東大の構成員がこの不確実な状況に適応し、大学生活がスムーズに進むことを願います。
公共政策大学院修士課程
Wahyunindia Rahman さん