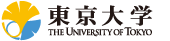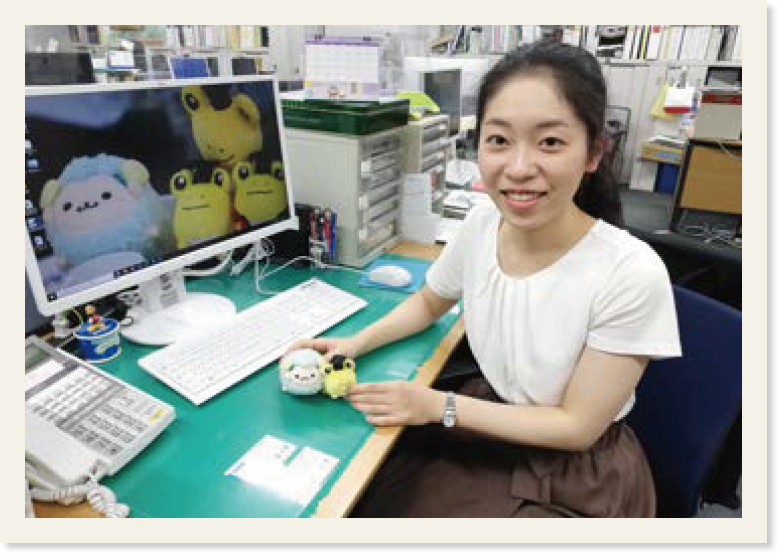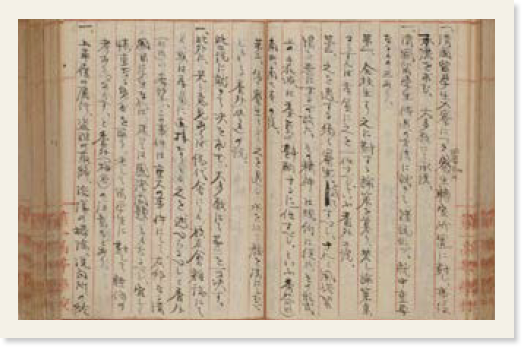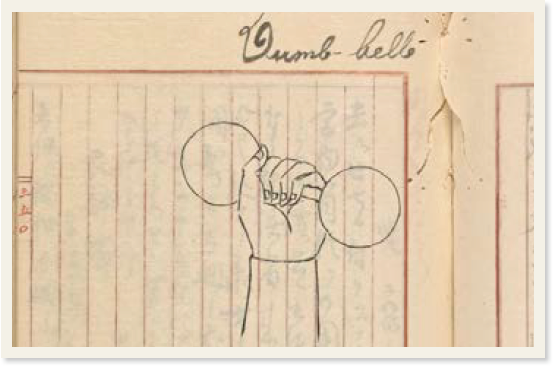第16回
第16回
岩手県大槌町にある大気海洋研究所・国際沿岸海洋研究センターを舞台に、社会科学研究所とタッグを組んで行う地域連携プロジェクト―海をベースに三陸各地の地域アイデンティティを再構築し、地域の希望となる人材の育成を目指す文理融合型の取組み―です。4年目を迎えたわれわれの活動や地域の取組みなどを紹介します。
地域の方との対話を楽しむ「海のおはなし会」

特任研究員

2021年の春にオープンした「おおつち海の勉強室」(no.1547 / 2021.6.24)。この夏、海の勉強室ではじめての企画、「海のおはなし会」を開催しました。三陸沿岸はウミガメの生息域のほぼ北限であり、夏の間にたくさんのウミガメが来遊することから、海のおはなし会の第1弾は「ほぼ北限のウミガメ研究」とし、大槌町近辺でこれまでに行われてきたウミガメの生態研究についてお話ししました。新型コロナウイルス感染者の全国的な増加のため、人数を制限した上での開催でしたが、岩手県在住の15名の方にご参加いただきました。
海のおはなし会ではまず、ウミガメの生活史やオスとメスの見分け方といった基本的な生態の解説を行い、三陸にやってくるウミガメの種類や成長段階、食べ物、三陸を出発した後の移動の経路など、これまでの調査で明らかになったことをお話ししました。また、ウミガメの背中から撮影した海中映像を上映し、ウミガメがワタリガニを追いかけたり、大きなヨシキリザメに遭遇したりする様子をご覧いただきました。参加者にウミガメを身近に感じてもらったところで、屋外の水槽で一時的に飼育されているアオウミガメ(近くの定置網に迷いこんだ個体です)を観察していただきました。足につけた標識番号から個体を識別できることや、どこかの海や砂浜で再びこのウミガメが見つけられたら、移動してきた経路や成長の速度などがわかったりすることを説明しました。また、実際にそのウミガメに触れていただきました。大人も子供もウミガメを触りながら食い入るように観察していました。その際、「ウミガメが夏にしかいないのはなぜですか?」(答え: 夏以外は水温が低すぎるので、南下するから)や「このあたりにくるウミガメは何歳くらいですか?」(答え: 詳しい年齢は実は分からない。標識を装着して詳しいデータを収集している)といったような質問も出ました。
おはなし会の最後には、参加者に観察したアオウミガメの名付け親になっていただきました。この個体は今年16番目に混獲されたこと、海のおはなし会の開催が8月だったことから、「いろ(16)は(8)」ちゃんと名付けられ、参加者に見送られながら近くの船着場から放流されました。おはなし会が終わった後も数名が勉強室にのこられ、追加の質問などをいただきました。少人数で開催したことで、参加者との距離がぐっと縮まり、自由な対話が生まれたのではないかと思います。今後も、海の生物や海洋環境に関する研究を通して、地域の方と深い関係を築いていけたらと思っています。