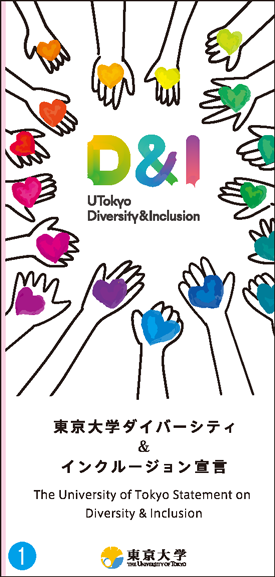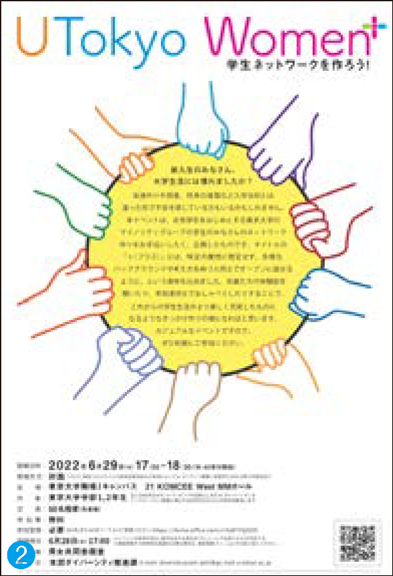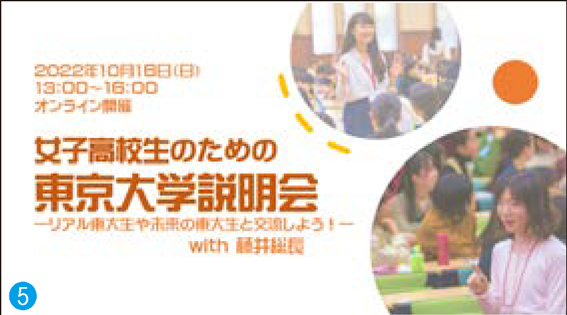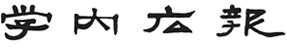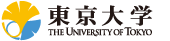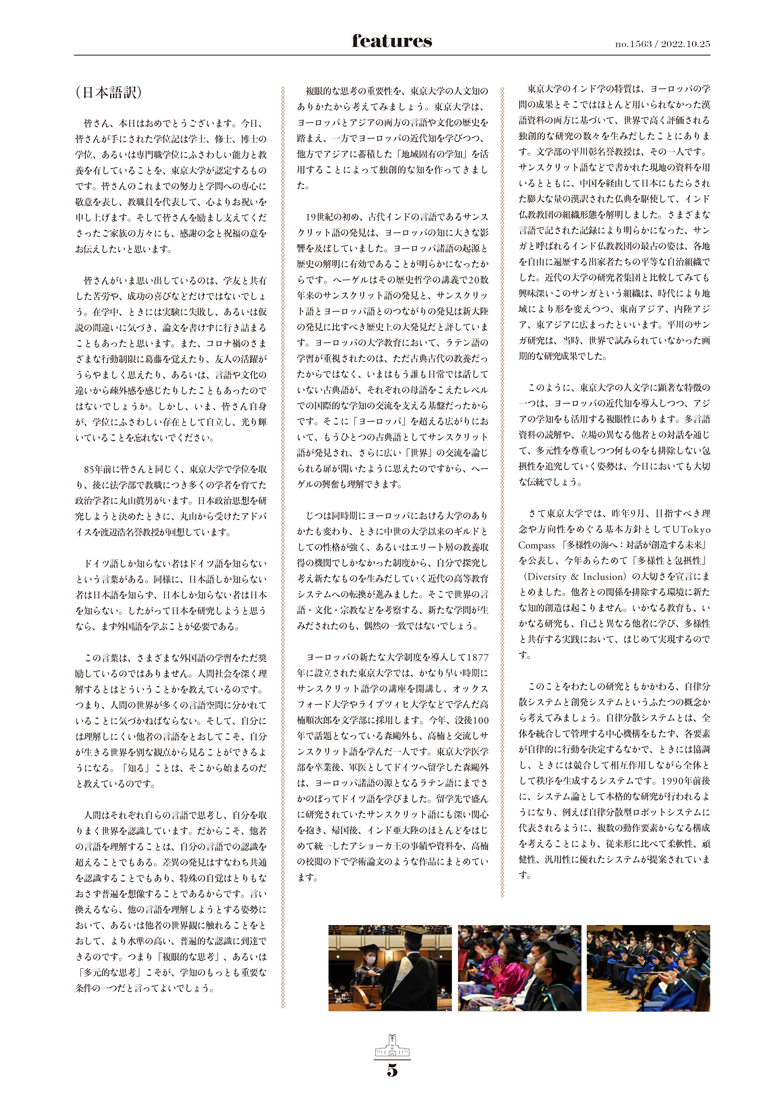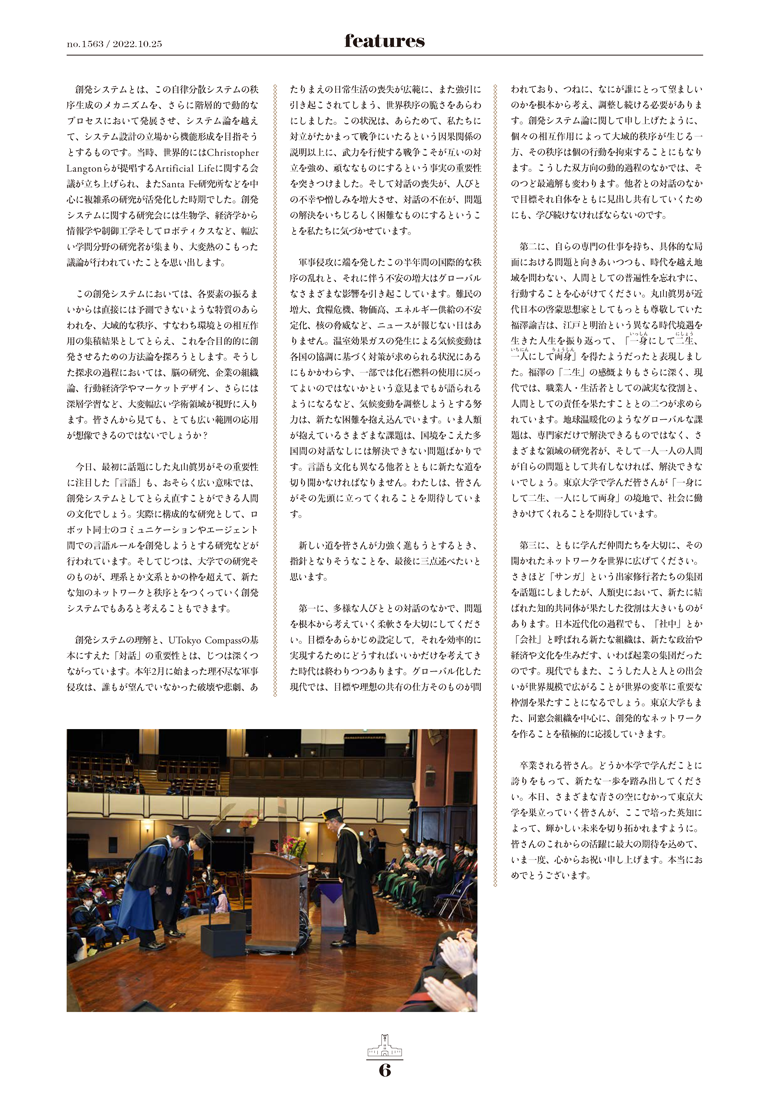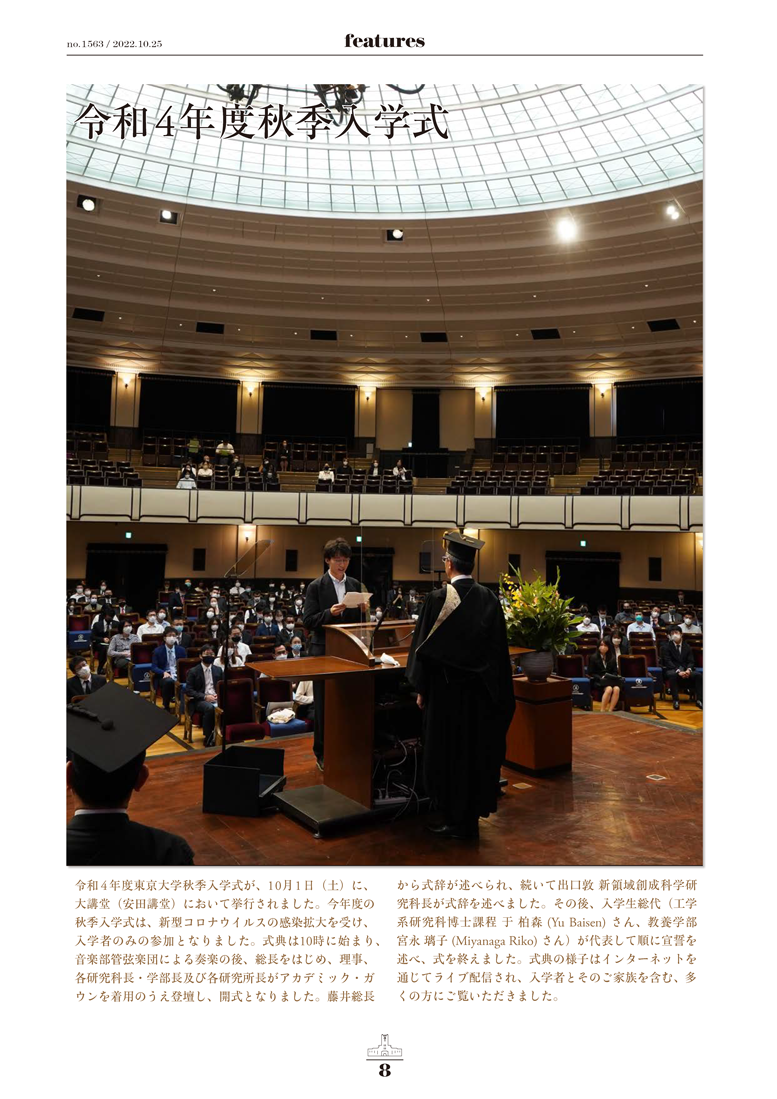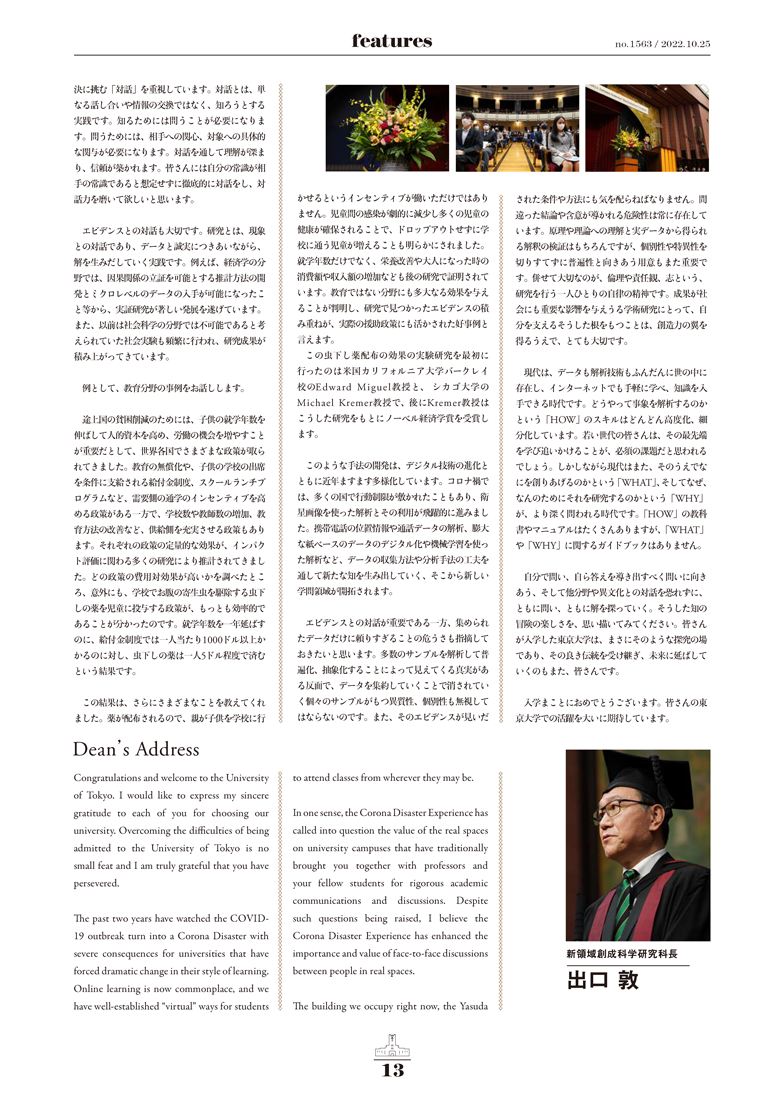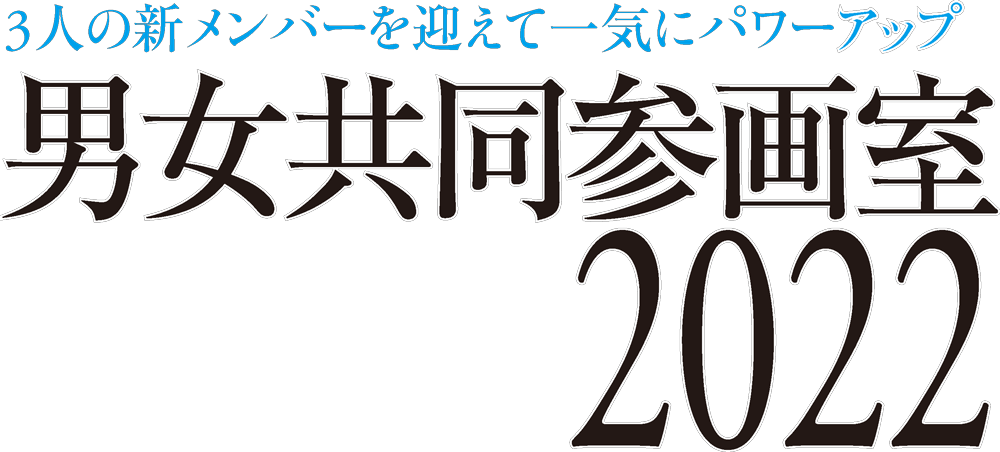2003年策定の東京大学男女共同参画基本計画を推進するため、2006年に総長直轄組織として発足した男女共同参画室。2010年以降は各部局から選出された教員が兼任の形で職員とともに活動してきましたが、今年度は特任教員1人と特任研究員2人が着任し、新しい体制での活動が始まっています。これまで大学等で男女共同参画に取り組んできた副室長と、ジャーナリストや大学院生の顔も持つ室員の皆さんに、生まれ変わった今年度の参画室について紹介してもらいました。


学外や学生の声も知る室員
――自己紹介をお願いできますか。
小川 専門は社会学・ジェンダー研究です。これまで他大学等で全学の男女共同参画やダイバーシティ推進に取り組んできました。また、学部等でのジェンダー関連講義、女性大学院生や女性研究者への支援、JST※のダイバーシティ補助事業の運営に携わりました。政府や自治体、大学の男女共同参画・ダイバーシティ関連の調査研究にも従事してきました。そうした経験を活かし、東大の男女共同参画、D&I※の推進、多様な構成員の活動が尊重される教育研究環境の整備等に貢献したいと思い、着任しました。
中野 東大卒業後に新聞記者として働き、2015年からはフリーのジャーナリストとして、女性活躍や子育てと仕事の両立などについて発信してきました。同時期に教育学研究科の博士課程に入り、本田由紀先生の研究室で母親の教育役割について研究してきました。学部の頃に東大の環境を改善する活動をしていて、博士課程でも何か貢献したいなと思っていた頃に参画室の公募を知り、応募しました。
安東 私は総合文化研究科博士課程の学生で、板津木綿子先生の研究室にいますが、妊娠・出産を経験した際に問題点に気付きました。たとえば子どもを市の保育園に入れたくても学生だと優先度が低いんです。調べると、「大学院学生の保育園利用に関するご理解のお願い」という書類を作成してくれる部局とそれが存在しない部局があり、学生対応に差があることに問題を感じました。学生向けの制度の不十分さを少しでも改善できたらいいなと思って参画室に来たんです。
※科学技術振興機構 ※Diversiity & Inclusion
多様な活動の発信の強化を
――中の人になってみて、東大の男女共同参画室は他大と比べてどうですか?
小川 東大では、これまで男女共同参画室や各部局において、男女共同参画に関する様々な取り組みが行われてきました。他大学との関連で見ても、JSTの女性研究者支援モデル育成事業や女性研究者養成システム改革加速事業の採択を受け、早い時期から女性研究者の増加策や研究環境の整備、後進の育成に取り組んでいます。2017年には、女性学生の増加を目指した住まい支援等独自の取り組みを実施し、2018年に「東京都女性活躍推進大賞」優秀賞を受賞しています。吉江尚子男女共同参画室長のもと、多様な取り組みをさらに発信していきたいと思います。今年度から専任として着任し、あらためて新しい体制を立ち上げるという感触を持ちつつ、林香里理事・副学長を中心に大学が強力にD&I推進に向けて取り組んでいると感じています。
中野 以前と比べると意識の変化は明らかです。たとえば10年前は、ダイバーシティの意義を一から説明しないといけませんでしたが、今その点はすでに合意ができています。ただ、組織が非常に大きく、変えたほうがいい点が様々なレベルで山積みです。手をつけられるところから一つずつやるしかありません。これは有志としての活動ですが、小学生を持つ構成員向けに小さなサマースクールを行いました。小学生の親には夏休みにどうするかという心配があります。全体から見ればごく一部の話ですが、今回は子どものデータを必要とする研究室と提携することもできました。学内のニーズをマッチングすると広がりがあるかもしれません。
安東 私も規模の大きさと大学として施策を実行することの難しさを日々感じます。歴史も長く、何かを変えることは簡単じゃないけど、変わらないといけない。やりたいこととやる必要があることがありますが、いまは後者をこなす段階です。やらなくてはならないことが多いから私たちがいるのだとも思います。
参画室が企画した初の講義
――たとえばどんなことですか?
小川 10月から前期課程で行う学術フロンティア講義「ジェンダー不平等を考える」を開講しています。伊藤たかね副学長にご尽力いただき、本講義を立ち上げました。オムニバス形式で様々な角度からジェンダーを切り口に展開しています。昨年度から前期課程学生向けに公開されている啓発動画※に続くダイバーシティ教育の取り組みです。教職員向けには、伊藤副学長を座長として、男女共同参画室のもとにジェンダー・ジャスティス研修WGを新たに設置し、ジェンダー・ジャスティス意識の向上を狙う研修についての検討を進めています。また、部局からの要望を受け、アンコンシャス・バイアスに関するコンテンツも作成し、FD※等で部局の教授会等を対象とする講演会を実施しています。また、男女共同参画やD&Iに関して海外研究機関の先進事例と比較して東大の実情を検討し、今後とるべき方策を考えてまいります。海外トップ大学では、ジェンダー平等などに関するデータの収集と分析を行い、公表しています。東大でもこのようなデータの可視化を進め、客観的データに基づいた施策を展開していきたいと思います。
※「学生生活におけるダイバーシティ・インクルージョン」
※Faculty Development
| 担当教員(所属) | テーマ | |
|---|---|---|
| 第1回 | 小川真理子(情報学環) | ガイダンスとイントロダクション |
| 第2回 | 飯野由里子(教育学研究科) | ジェンダー「平等」:3つの視点 |
| 第3回 | 前田健太郎(公共政策学連携研究部) | 民主主義とジェンダー |
| 第4回 | 今水寛(人文社会系研究科) | 心理学・神経科学から見た「男性脳・女性脳」 |
| 第5回 | 村和明(人文社会系研究科) | 日本史学とジェンダー:対象として、方法として |
| 第6回 | 板津木綿子(情報学環) | ポピュラーカルチャーとジェンダー |
| 第7回 | 横山広美(カブリ数物連携宇宙研究機構) | 理系になぜ女性が少ないのか |
| 第8回 | 浅井幸子(教育学研究科) | 教育におけるジェンダー |
| 第9回 | 武藤香織(医科学研究所) | 生命・医療倫理とジェンダー不平等 |
| 第10回 | 矢口祐人(情報学環) | キャンパス景観とジェンダー |
| 第11回 | 伊藤たかね(情報学環) | 言語とジェンダー |
| 第12回 | 小川真理子 | グループディスカッション |
| 第13回 | 小川真理子 | まとめ |
↑Aセメスターに教養学部前期課程で開講されているオムニバス講義。10人の教員が各々の専門分野の視点からジェンダーを論じ小川副室長が全体を統括します。
多数派の意識を変える努力も
中野 そもそも入学する学生の属性に偏りがあり、その延長で研究者にも偏りがあります。偏りをならす努力をしながら、組織に入って困っているマイノリティを支援し、マジョリティ側の意識を変える努力もしないといけない。様々なレベルの問題に同時並行でアプローチする必要があります。
安東 言わばいろいろな面を針でちょんちょん刺している状況。大砲を放つのは難し←Aセメスターに教養学部前期課程で開講されているオムニバス講義。10人の教員が各々の専門分野の視点からジェンダーを論じ小川副室長が全体を統括します。いです。ちくちく積み重ねたものがいつかバーンとはじければいいのですが。
――いま感じている課題と教職員へのメッセージをいただけますか。
中野 我々は主に男女の問題にまず取り組んでいますが、D&Iはもちろんこれだけではありません。たとえば自立しているように見える東大の教員の中にも、問題を抱えて支援が必要な人がいるはず。そうした人の味方にもなりたいです。
小川 男性の育休取得促進も重要ですね。私たちは決して女性の支援だけ行っているわけではないことをお伝えしたいです。D&Iに関心がない人にどのように声を届けていくのかも課題と捉えています。
安東 困難を感じている構成員の声を集めて拡声すれば、問題意識がなかった人にも届くはずです。米国ではジェンダーの話はもう終わって次の問題に進んでいます。日本のトップとされる東大がそこで遅れを取らないことが、日本社会全体にもいい影響を与えると信じています。