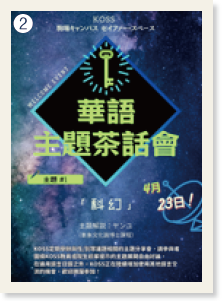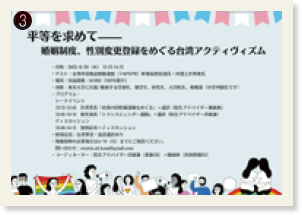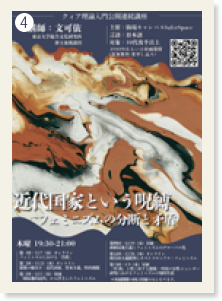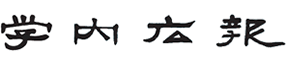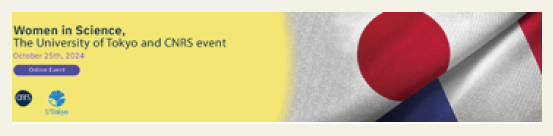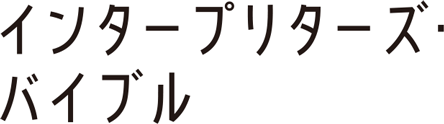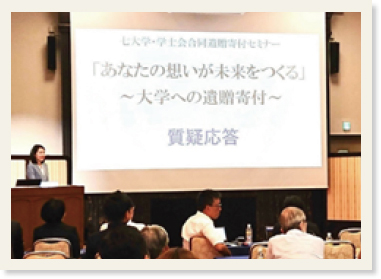東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、いま、次々に新しい取組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学の構成員に知っておいてほしい教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。
ダイバーシティと言語
/D&I部門KOSS(駒場キャンパスSAFER SPACE)の取り組み
英語と「華語」に着目して活動
于 KOSSの活動はジェンダー/セクシュアリティが中心ですが、D&Iのイシューではエスニシティや国籍の問題も切り離せません。そこで注目したのが言語で、私たちには二つの問題意識があります。一つは、蓄積されてきたフェミニズムやクィアといった学術的議論のほとんどが英語によるものだったこと。もう一つは、KOSSの活動が現実的に主に日本語話者が対象の前提となっていること。そこで、多様な学生に利用してもらうことを目指して多言語での活動を進め、切口として英語と「華語」に着目しました。
張 「華語」とは、個別な国や民族、あるいは特定の集団を限定せず、差異がありながらも共通に使用できる中華系の言語を強調するために用いている表現です。
于 KOSSでは2022年から英語と華語に対応した開室日も設けています。現在、約15人の院生スタッフが活動しています。その一部は多言語開室を担当しています。
張 私は「華語主題茶話會」を担当しています。今年の4月に実施した回のテーマはSFの意の「科幻」。チラシには世界で大ヒットした小説の『三体』のアンテナをモチーフにデザインしました。過去には「第三人称」がテーマの回も開催しました。たとえば、男性に「他」、女性に「她」を用いる華語の三人称は欧米の文章を翻訳するために生じたもの。日本の「彼」「彼女」も同様です。三人称の代名詞についてジェンダー構造における権力のアンバランスの面から話しました。
魏 ちなみに繁体字では神を表す三人称の「祂」や動物を表す「牠」があります。
市川 私は学部生スタッフとして今年の新歓ティーパーティーの英語開室を担当しました。日本語はできますが、高校まで海外だったので国内事情に疎く、自分の居場所を探せませんでした。日本語ができない方ならなおさらなはず。大学でも通称名の使用法とか寮の性別の扱いとか言語の障壁があるとわからない点が多々あります。大学がD&Iを掲げるなら解決すべき部分だと思います。
非英語圏の地域の経験に学ぶ
于 日本語圏・英語圏以外の運動や議論が見えづらく取り上げられる機会が少ないことに鑑みて、北京の同志運動※、台湾の婚姻制度・性別変更をめぐるアクティヴィズムなど、英語圏以外の地域に注目したイベントも開催してきました。
魏 去年4月、台湾伴侶権益推動連盟の皆さんを招いてトークイベントを行いました。2019年にアジアで初めて同性婚を法制化した台湾で、その実現のために尽力した皆さんです。逐次通訳を自分たちで行いながら、婚姻平等法案起草から国際同性婚、性別変更登録訴訟に至るまでの実際の歩みを話していただきました。
于 これらのKOSSの多言語でのイベントは留学生へのアウトリーチも兼ねていましたが、そこに見落としがあると分かりました。そのきっかけはKOSSが主催したポストイットアクションという活動です。会場に大きなボードを置き、自分のもやもやを付箋に書いて貼り、皆で話し合うもの。その書き込みで、日本人と留学生という分け方ではどちらにも当てはまらない人がいると気づきました。
張 たとえば「留学生と日本人学生の交流会」というより「留学生と国内学生の交流会」のほうが望ましいわけです。
市川 私は名前を見ると日本人と思われがちですが、中華文化圏の影響を受けて育ちました。日本人と留学生、という二項対立だとこぼれる人がいるというのは、実感としてわかります。
于 日本人がマジョリティの東大において、「日本人」という枠組みを当たり前の前提とすることを超えた、より包摂的な空間作りが、KOSSにとってもこれからの課題になると思います。言語以外の取り組みもこれから探っていきたいです。