創立以来、東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、次々に新しい取り組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学のすべての構成員が知っておくべき教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。
この10年の国際化と今後の方向性を確認
/教養教育高度化機構シンポジウム「教養教育におけるグローバル化の新段階」
教授原 和之

――駒場におけるグローバル化を振り返るシンポジウムだったんですね。
「2009年に東大が「グローバル30」に採択されて10年の節目を迎えるのを機に企画しました。学生の受け入れ・送り出しでは、PEAKやUSTEPなどの仕組みを整え、個別に行われてきた研修などの単位化も行いました。外国語教育では、ALESS/ALESA、FLOWと演習を展開し、トライリンガル・プログラム(TLP)も広がっています。そうした10年間を概観し、次の方向性を探ろうとの意図でした。新しい試みをやりやすく、今後の芽になる短期の取組みに焦点をあてました」
中国語未履修者が中国に覚醒
「第1部では、南京大学との学生交流フィールドワーク、国際連合との連携、東アジアリベラルアーツイニシアティブ(EALAI)の取組みについて、第2部では、TLPで行う海外研修、国際連携を進めるための運用について、現場の先生が紹介しました。また、参加する側の声も拾おうと、3人の学生に登壇してもらいました。EALAIで中国に行った学生は、中国語は未履修でしたが面白そうだからと参加し、最初は何もできませんでしたが、滞在中に語学が急激に上達して中国語検定の最高位に到達。その後、彼はあらためて長期留学も行ったそうです」
――参加を機に目覚めたんですね。
「EALAIでは中国語履修が必須条件ではなく、英語で参加できる体制だったのが奏功したようです。こうした取組みには学生が参加する際のハードルが低いことが重要だとあらためて感じます」
――グローバル化の課題は何ですか。
「海外との行き来が珍しくない時代に、参加者の手応えをどう持たせるか。送り出しでは日本語を学ぶ現地の学生と組ませるのが一つの方法。南京大学とのプログラムのように、現地学生と東大生がペアで行うフィールドワークは、手間が多くて大変ですが、総じて好評です。受け入れでは、東大ならではの経験をしてもらうことが重要です。以前と違い、今は来日経験者も多いですからね」
学生引率の「ワンオペ問題」とは
「海外で学生を引率する際のマンパワーも問題です。引率者が仮に一人の場合、不測の事態が起こると対処に追われて活動が回りません。現地コーディネーターの支えがあるだけでだいぶ違いますが、人件費はなかなか増やせません。教員が添乗員の役目もする状況を改善しないと質も量も広がらないでしょう。取組みが属人的になりがちという問題もあります。個人の縁を機に活動が始まるのはいいことですが、継続には組織体制が必要です。教員の多忙や異動などの要因で取組みが終わるのはもったいないことです」
――見えてきた方向性を教えて下さい。
「駒場にはすでにいろいろな国の人がいます。彼らと日本人学生の接点を増やすのが鍵でしょう。これは海外に日本人学生を送り出すよりも少ないコストと努力でできるはずです。たとえば、USTEPの留学生と一般学生の両方が参加できる英語の授業がありますが、参加する日本人学生は少ないのが現状です。語学力というよりも広報の問題かもしれません。特定の国でなく漠然と国際経験をしたい1・2年生は少なくないので、そこに訴えかけるのが有効だろうと思っています」
| 開会挨拶 | 石田淳 |
|---|---|
| 趣旨説明 | 西中村浩 |
| 基調講演/教養学部のグローバル化 | 月脚達彦 |
| 他者を理解する、人と人との付き合い方を学ぶ | 白佐立 |
| SDGs時代における国際機関との連携 | 井筒節 |
| 東アジア・西太平洋地域諸大学との教育交流 | 岩月純一 |
| トライリンガル・プログラムらしい海外研修とは何か? | 石井剛 |
| 学生のモビリティ拡大に伴う支援 | 君康道 大澤麻里子 |
| 学生セッション | |
| 総合討論 | |
| 閉会挨拶 | 原和之 |
| ポスターセッション・懇談会 |
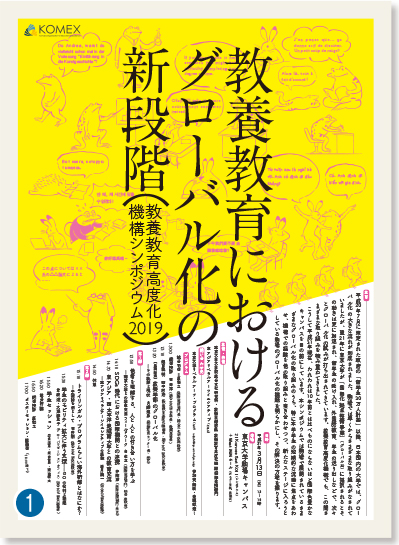


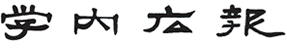
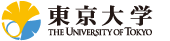



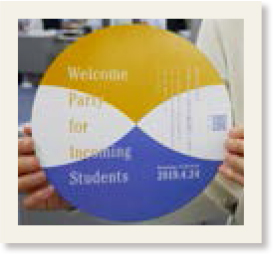



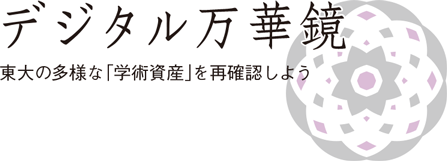
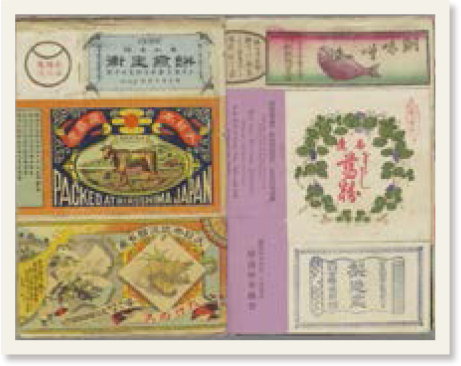
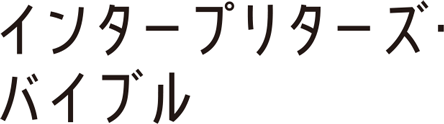
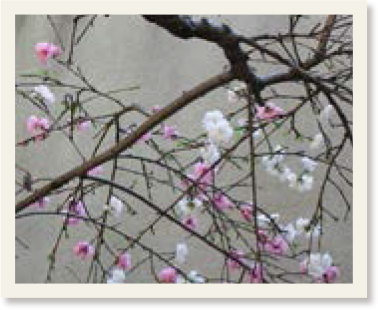


 研究員」に就任し、先端研側にも交流相手がほしいね、という話が進んで生まれたのがボク。生みの親で「VRくまモン」などを担当する檜山敦先生も熊本出身だよ。
研究員」に就任し、先端研側にも交流相手がほしいね、という話が進んで生まれたのがボク。生みの親で「VRくまモン」などを担当する檜山敦先生も熊本出身だよ。