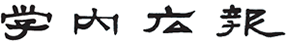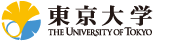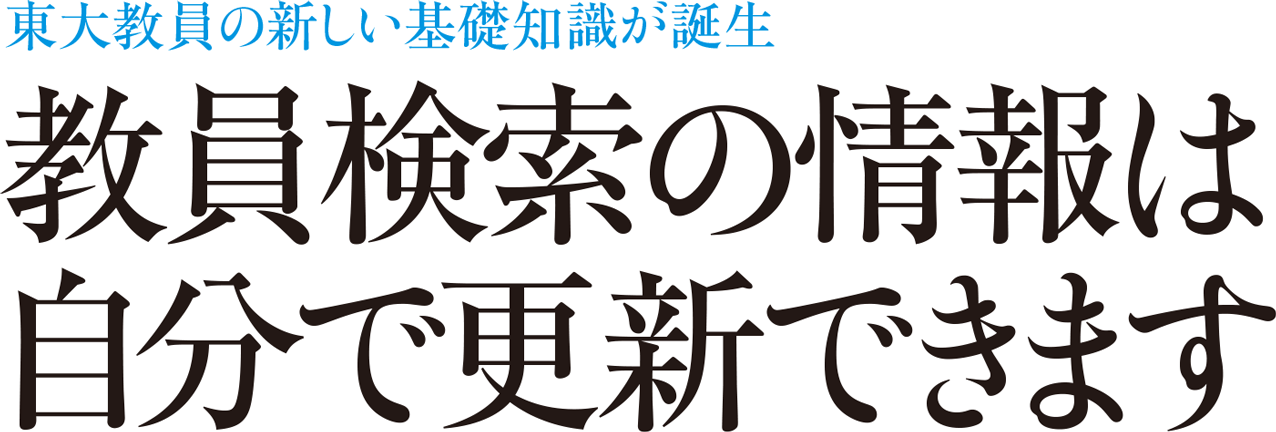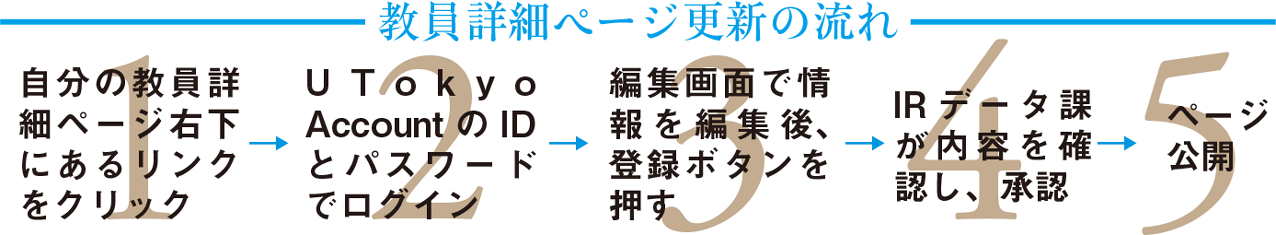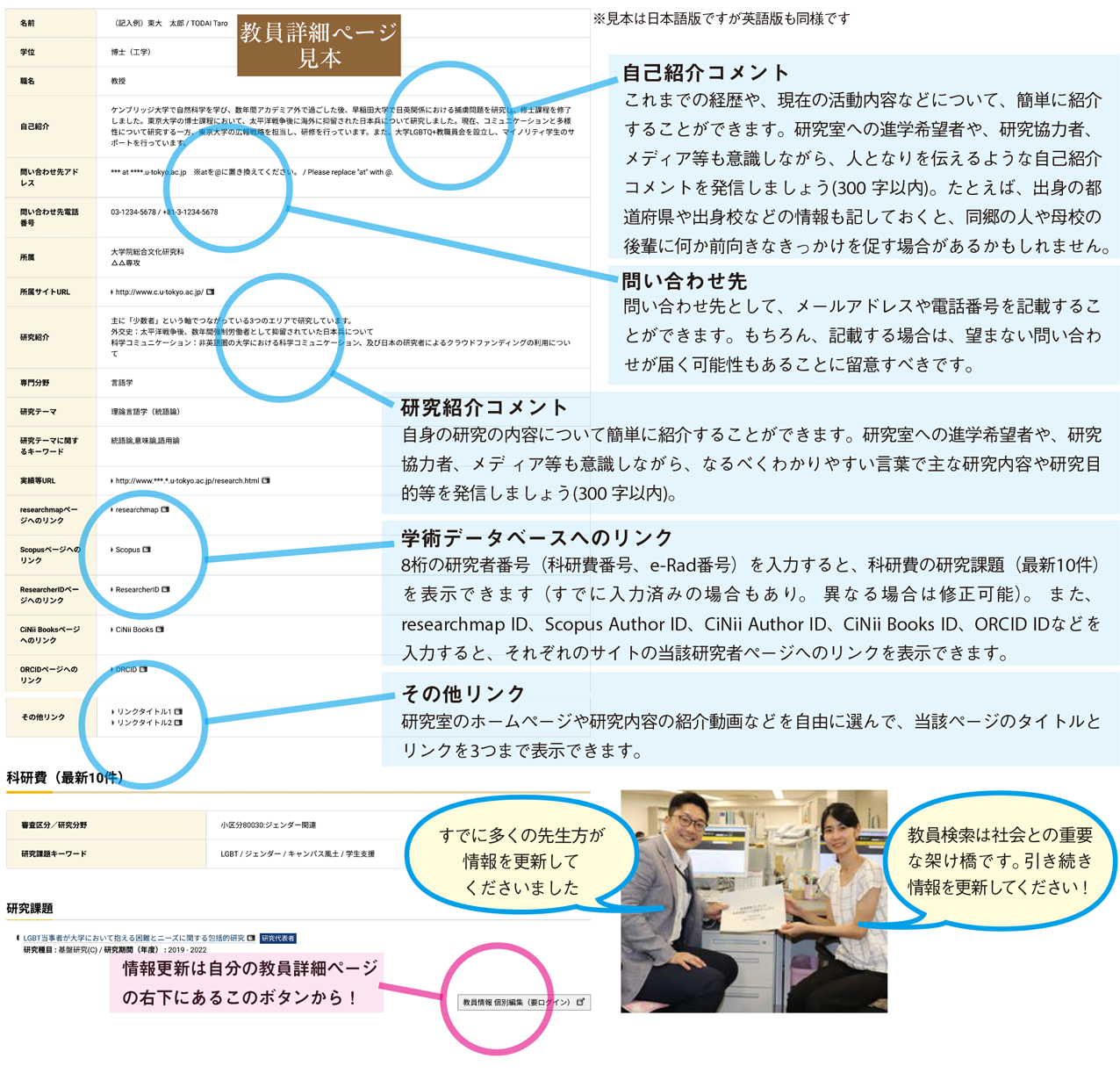新制東京大学の第1回入学式が行われたのと同じ7月7日、教養学部の創立70周年記念シンポジウムが900番教室にて開催されました。ビデオメッセージ紹介や2つの記念講演が展開された第1部に続き、第2部では現役教員と駒場にご縁が深い方が登壇し、駒場におけるユニークな研究・教育活動、すなわち「駒場スタイル」について議論しました。1時間にわたって展開された議論の模様をダイジェストでお届けします。






1駒場スタイルとは?
武田●まず、駒場スタイルとは何かについて。思い浮かぶのは、研究・教育の総合性、学際性がもたらす知的な活力、ユニークな人材輩出、既存の枠にはまらない研究、実践的な問題解決能力の育成あたりですが、いかがでしょうか。なお、発言は一人3分以内でお願いします。
学問的彷徨い人も落ち着ける場所
岡ノ谷●私は小鳥のさえずりなどから人間の言語の進化を探る研究をしています。最初は千葉大学の文学部でした。小鳥の脳を調べていると「それは文学部でやること?」と言われました。その後、理化学研究所に移りました。すると「理研で言葉の研究を?」と言われました。そんな学問的彷徨い人だった私が落ち着いたのが駒場です。駒場スタイルとは、文理融合の学際研究をし、それを支える教養教育を行うことだと思います。ただ、駒場でも文系と理系の壁は感じます。それを乗り越える仕組みを作ることが重要ですが、なかなか難しいのも現状です。
鹿毛●私は学生を野放しにすることで知られる京都大学の出身です。東大に着任して、教員が学生を細かく指導していることを知り、東大生は大変だと思いました。教員にとっても、前期課程の授業をするのは大変です。たとえば一般政治学の授業では、全体を俯瞰して教えることが求められ、自分の苦手な部分もきちんとカバーしないといけません。生半可なことをいうと厳しく突っ込まれますから、周到な準備が必要で、それも毎年やり直さないといけない。教えるほうも非常に勉強になり、それが自分の専門にフィードバックされていると感じます。学生にも効果があるとよいのですが。
金子●私は生命とは何かを理論物理を用いて研究しています。こうした分野の研究体験ゼミに、1年生が意外とハマります。まだ専門にわかれておらず、自分が知りたいことに必要なものを素直に学ぼうとするからです。学際というと、学問分野がわかれていてそれを架橋するような印象がありますが、振り返れば学問分野がいまのようになってからせいぜい100年ぐらい。人類の長いスケールからみたら短いものです。学問がわかれる以前に立ち返って考える。それが駒場スタイルにつながるように思います。
西崎●駒場の魅力は、開放性、風通しのよさ、優れた先生と才気ある学生がいることだと思います。そして、新しもの好きな面と古いものを大切にする面の両方がある。私の分野でいうと、南原繁、矢内原忠雄のお二人がアメリカの研究者との交流を1950年代に始めていたのが現在のアメリカ太平洋地域研究センターに生きています。歴史を大事にしながら新しいものを積み重ねていくのが特徴的。一方で思うんですが、学生の頃は学際性なんてわかりませんでした。私は4年生になって基礎がなっていないことを痛感して学外に出ました。教養教育、学際性の難しさの表われ。学生の目から見てどうなのかを考えないといけないと思います。
自由すぎたので大学を離れました
東●私は駒場で科学史・科学哲学から表象文化論に進みました。そこで社会と大学を自由に横断することを教えてもらった。哲学は社会と関係し、学内と学外を横断しないと意味がない。大学院時代から出版界隈で仕事をしたのは、そういうことを許容する環境があったからこそ。ただ、その後は大学から離れました。どうして大学でうまくいかなかったかというと、皮肉なことに、駒場が自由すぎたのだと思います。駒場スタイルとは自由であることではないでしょうか。
2駒場スタイルの発信
武田●次のトピックに移ります。教養学部は東大の中で知名度が低いという声があります。東大というと安田講堂や赤門が有名ですが、どちらも本郷キャンパスのものです。駒場の留学生には「教養学部に赤門がなくて残念」といわれます。今後の発信はどうすればよいでしょう。
西崎●教員も学生も卒業生も、個々の活躍は目立っていて、発信力はあると思います。私はGPEAKに関わってきました。様々な国の学生がいて刺激的ですが、国際プログラムの運営は非常に大変です。普通の授業プラスαの仕事になり、教員には試練です。短期的なサイクルで動かす傾向があるが、長い目で見た地道な活動と、覚悟と資源も必要です。産学連携の点で言えば、70周年記念の本※では、大隅先生が、昔は産学連携反対がスローガンだった、と話していました。今では軍事研究を考えないといけません。軍事研究は予算だけでなく発想の点でも他の学問分野に影響を及ぼします。発信についても広い視野で見たほうがいいでしょう。
必死に発信する必要はないかも
金子●駒場の理系は発信が下手だと思います。多くの人は大隅先生=東工大と思っていますからね。うちの学科からは総長大賞が2年連続で出ました。東大のベスト学科といってもいい。でもその割にPRできていません。ただ、その受賞者は、円城塔※の小説を読んで興味を持ってうちの研究室に来ました。あまり必死に宣伝せず、「じわじわ発信」でいいのではと思う。気づいたら駒場の人だった、という奥床しさも駒場スタイルでは?
鹿毛●大学は研究の水準こそが価値。水準を上げ、それを見て学生が集まり、さらに水準が上がって……というのが、知名度を上げる近道です。私のいる社会科学専攻では、計量政治学の世界的研究者が輩出しています。プリンストン大学教授の今井耕介さん、MIT准教授の山本鉄平さん……。海外で東大教員だというと「法学部じゃないのか」と聞かれますが、そこで彼らの名を出すと納得されます。「卒業生の七光り」ですね。卓越した研究者を出し続けることに尽きます。
岡ノ谷●研究室から学生が巣立ち、自ずと発信してくれています。学位を取った後フルートを吹いて生きている人、卒論をもとに小説を書いて新人賞をもらった人、同志社大学の研究所を駒場色に染め直している人、文系だったが自然にプログラミングを身につけて企業で活躍している人……。卒業生が発信するのが駒場スタイルだと思います。思うに、21世紀の教養人には心と体の理解が重要です。それには文系の知識と考え方が必須となるでしょう。人工知能をやるなら、現象学も他我問題も心の科学も知らないとまずい。語学もそうです。外国語を学ぶのは世界の多様性を知ること。Google翻訳がいくら発展しても人間自身が語学をやらないといけない。そうした姿勢を駒場が発信するのが大事です。
東●駒場時代の指導教員だった高橋哲哉先生と本※で対談しました。高橋先生はデリダを研究していて、私が院生だった頃、文芸評論家の加藤典洋さんと歴史主体論争をしていました。簡単にいえば、第二次大戦の犠牲者を誰が追悼すべきかという話。私はもともと高橋先生のデリダ解釈に異論もありましたが、先生がデリダ哲学を使いながら現実に関わる様子を見ていて、哲学者は個々の解釈の違いを超えて社会に介入しないといけないと思ったんです。発信そのものが教育となって学生を育てるのだと思います。
武田●それぞれのお立場での発言が随所で響き合っているのが面白いですね。

※金子研究室出身の作家。ペンネームは金子先生の小説に登場するプログラムの名が由来
3駒場スタイルの未来
武田●最後は未来についてです。駒場スタイルはどのように維持すればいいのか。学際性は伝統ですが、ゆえに制度に取り込まれていないか。教員の忙しさはどうすればいいか。また、構成員の多様性はどのように確保すべきでしょうか。
大学は奇跡を生む場である
金子●リアルの世界でないとできないのは奇跡を生むことです。AIに奇跡は起こせません。何もできなかった学生が数年後に大化けするのを見ることがある。あれは奇跡。奇跡を生む場であることが大学の使命です。研究室という共通の場で学生と向き合っているうちにそれはたまには起きる。教養とは冗談をわかり合えること。冗談が通じ合う場で何か生まれる。なので、教員は忙しい雰囲気を出してはダメ。多忙でも冗談を言って不思議な場を保ち続ける。それを自信を持ってやるのがいいと思います。
西崎●私はグローバル地域研究機構の機構長をやっています。いろいろな地域の研究センターをつなげて一つの枠組みを作るもの。課題は相互の研究を可視化することです。皆面白いことをやっているが互いに何をやっているか知らない。これは駒場の一つの現状です。誰に向けての可視化か。学外はもちろん、学内の教員相互の可視化もすべきです。イベントなどの情報も含めて。大学院生も自分の研究に専念しすぎてほかの研究を知らない面があります。多様な研究のエクスポージャーが駒場の未来につながるはず。
岡ノ谷●金子先生のように体力ある先生ばかりではありません。改革しようとすればするほど研究時間は減る。駒場には改革を拒否してきた歴史があります。秋入学の議論で駒場は反対しました。入試への英語民間試験導入に関しても英語部会が明確に反対しました。対象によっては改革をしないことを主張する勇気が駒場にはある。今後も持ち続けるべきです。構成員の多様性でいうと、今日は6人中3人が東大卒以外。こういう場に東大文化に染まらない人がもっと入るべき。東大出身者はまじめにやりすぎる傾向がある。きっちりやらないことも文化に入れたい。
鹿毛●本※の原稿を書くにあたって調べてみると、駒場の教員と事務職員の比率は4対1でした。ハーバードだと1対4、プリンストンは1対5です。どれだけ教員が事務仕事をしているかという話。職員が何人分も働いているともいえますが、やはり厳しい。たとえば、研究費を事務仕事の人件費に回す手はあるかもしれません。
東●私は会社を経営していて、マネジメントに興味があります。そうすると改革をどんどんやりたくなる。でも、私の本の読者にはそんなこと関係ないんです。本を読みたいだけ。大学を見る社会も同じで、学内の施策なんて興味がない。大学が出す研究成果しか気にしない。研究成果を生み続けるしかないでしょう。
武田●全員きっちり話してくれましたね。話を聞いていて、研究倫理が問われるときこそ駒場の学際的性格が役立つ、と思いました。学生への可視化も本当に大事です。PEAKの授業は一般学生も対象なのに履修者は少ない。PEAK生の刺激は一般学生にも大きいのに、そのことの可視化が十分ではないのだと思います。
金子●体力で頑張っているわけではなくて。忙しくないようにするためには、だめなものにNoということが必要です。
岡ノ谷●同感です。この前、新学術領域研究の見直しで、複合領域をやめるという話が出た際、駒場が否定されたように感じました。そこにNoを言いたい。いろいろな複合からしか新しいものは生まれないと思います。あと、私は学生に論駁されるのが好きで、よく論駁されています。ある学生は、研究室に来た理由として、「先生ぐらいでなれるなら俺もなれるだろうと思った」と言いました。そういうところを見せてあげることは駒場の雰囲気の良さにつながるのかもしれません。
武田●それは謙遜がすぎますね。でも、学生と教員の関係のよさというのは確かに駒場の特徴でしょう。それが今後も変わらず続いていくことを願いつつ、ラウンドテーブルを締めさせていただきます。
※上記は抄録です。発言は省略されている場合があります。
| 総長挨拶 ❶ | 五神 真 |
| 学部長挨拶 ❷ | 太田邦史 |
| ビデオメッセージ ❸ | 大隅良典 (東京大学特別栄誉教授) |
| パイプオルガン演奏 ❹ | ヘルマン ゴチェフスキ教授 |
| 記念講演1 ❺ 「駒場に期待すること-教養知と環境」 |
浅島誠 (東京大学名誉教授) |
| 記念講演2 ❻ 「共感できない人が隣にいる。ライン交換、どうしますか?」 |
ロバート キャンベル (東京大学名誉教授) |
| パイプオルガン演奏 | 中川岳 |
| ショートメッセージ | 小川桂一郎名誉教授、佐藤俊樹教授、ジョン ボチャラリ名誉教授、長崎暢子名誉教授、石田淳教授 |
| ラウンドテーブル 「駒場スタイルの未来」 |
東浩紀、岡ノ谷一夫、鹿毛利枝子、金子邦彦、西崎文子、武田将明 |
| 閉会挨拶 ❼ | 石田淳 |
総合司会 渡邊あゆみ(NHKエグゼクティブアナウンサー)


浅島先生は、駒場農学校との敷地交換で本郷から駒場に移った一高の歴史、そしてそこから現在に至るまでの教養学部の歴史を概観。混沌とした現代社会では、知識と知恵と知力の総和である「教養知」の必要性が高まっていると述べました。キャンベル先生は、「想像」に「思いやり」とルビをつけた江戸時代の文献や、子どもと同伴でないと入れないロンドンの公園などを例に、昨年の入学式の祝辞につながる話をされました。70周年記念事業実行委員長を務めた石田先生は、この事業には「駒場ヒストリア」という隠しタイトルがあったというエピソードを紹介しながら、3時間半に及ぶ会に幕を下ろしました。

Design: Takuya Abe