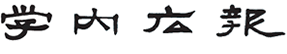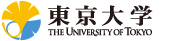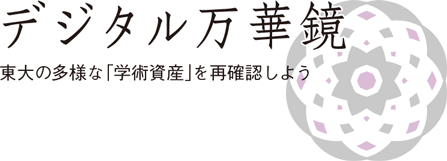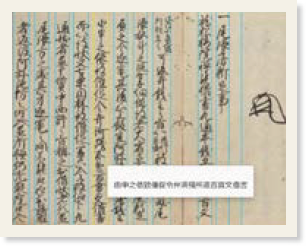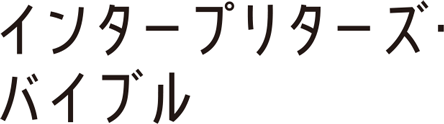創立以来、東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、いま、次々に新しい取り組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学のすべての構成員がぜひ知っておくべき教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。
リベラル・アーツ教育の学内連携を推進
/KOMEX新機構長に聞く

松尾基之
――2度目の機構長就任ですね。
「前に機構長を2期4年務め、この2年は財務委員長として機構に携わりましたが、今回機構長として再登板となりました」
――では第3期松尾時代の指針などを。
「機構の運営方針は研究科長が議長を務める戦略会議で定めますが、リベラル・アーツ教育を行っている他部局との連携を強化することを指針の1つにしたいと思います。2015年に機構内の重複感を調整するために8つあった部門を7つに再編しましたが、今度は全学に目を向け、リベラル・アーツ教育に関する学内部局間連携を高めようというわけです」
新しい連携研究機構にも参画
「10月1日に発足するEdTech連携研究機構には総合文化研究科も加わります。参加教員は開一夫先生、坂口菊恵先生、椿本弥生先生、私。つまり機構に所属する3人が参加します。連携研究機構への参加は、リベラル・アーツ教育の学内連携の第一歩となります。EducationとTechnologyを掛け合わせるEdTechは、教育工学に縁が深く、教養教育の高度化を担う機構と重なる部分も大きいのです」
――教育工学だとアクティブラーニング部門の吉田塁先生が専門家でしたね。
「実は吉田先生は大学総合教育研究センターに移りました。機構とは活動の分野が近く、もともと交流が盛んなんです。学問の入口にいる1・2年生が学問領域の全体像をつかむための学術俯瞰講義を、これまでも両者で協力して実施してきましたが、吉田先生の縁も活かしてより連携を深めるつもりです。たとえば、蓄積した講義映像をもっと活用するなど、知恵を出し合っていきたいですね」
「もう一つ進めたいのは機構内連携です。各々の取組みは総じて評価が高いのに、機構としての活動と認知されないのはもったいないと常々感じていました。そこで目をつけたのがSDGsです。実は一部局でSDGs全体をカバーできるのは総合文化研究科だけ。機構でも複数部門でSDGsに関わる活動を行ってきました」
SDGs 教育のプラットフォームに
「3年半の時限プロジェクトとして、9月1日に「SDGs教育推進プラットフォーム」を立ち上げました。環境エネルギーについて長く研究してきた瀬川浩司先生(環境エネルギー科学特別部門)、国連と連携した取組みを行ってきた井筒節先生(国際連携部門)、国際研修を通して学生に軍縮を考えさせてきた岡田晃枝先生(初年次教育部門)……。7部門が個々に進めてきたSDGs関連の取組みに横串を通して可視化します。プラットフォームに特任の教員を配置し、関連する授業などの取組みを発信していきます。11月15日には、瀬川先生が中心となって教養学部70周年記念事業の一環でSDGs関連のシンポジウムを行います」
「専任と特任で25人、兼任を入れると50人を数える機構の所属教員がアクティブに活動できるようにするのが機構長の役目だと思っています。能力を発揮できる環境を整え、東大全体の教養教育のレベルアップにつなげたいですね」
――前身の教養教育開発機構から数えると14年。手応えはいかがですか。
「昔の学生は少し引っ込み思案なところがありましたが、近頃はアクティブラーニング一つとっても慣れていると思いますね。機構だけの影響とはもちろん言えませんが、学生が概してオープンになってきているようには感じています」
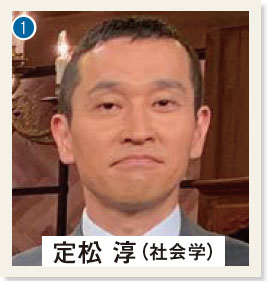

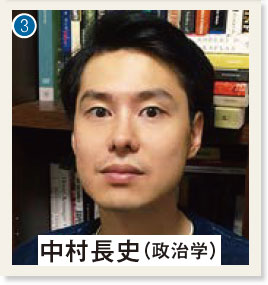
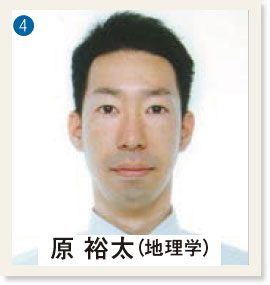
| 2014 年度 | 岡田晃枝、山邉昭則 |
| 2015 年度 | 岡田晃枝、坂口菊恵、白佐立 |
| 2016 年度 | 岡田晃枝、坂口菊恵、中村優希 |
| 2017 年度 | 坂口菊恵、井筒節、江間有沙、吉田塁 |
| 2018 年度 | 椿本弥生、吉田塁 |
| 2019 年度 | 岡本佳子、中村優希、堀まゆみ |
「機構では、各教員が前年度の実績を書いて提出した自己申告シートを執行委員会が採点し、表彰しています。賞金はありませんが、CVに書ける正式なものです」