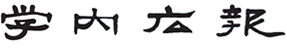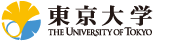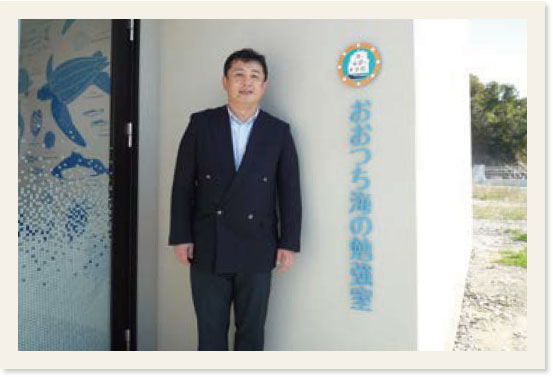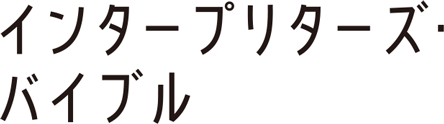創立以来、東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、いま、次々に新しい取組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学の構成員に知っておいてほしい教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。
日本にいる移民と教育を受ける権利の関係は?
/全学自由研究ゼミナール「多文化社会と教育―移民の子どもたちをめぐる現状と課題の理解」
特任講師 髙橋史子

――着任したばかりだそうですね。
「9月までは教育学部の助教でした。東大ではこれが最初の授業です。自分が学生時代に受講した全学自由研究ゼミナールを担うとは感慨深いです」
「私は移民の教育に関する国際比較を専門としています。今回は、移民の子どもの教育にはどんな困難があり、どういう取組みがなされてきたのかを理解するための授業を、と考えて企画しました。全13回のうち、第8回までは教科書※をベースにして移民の教育に関する知識を学びます。毎回課題の章を決めて学生に読み込んできてもらい、授業で内容を深めます。第9回以降は、各々が気になるテーマを決め、関心が近い者同士でグループを組み、グループワークでリサーチ活動と発表を行った後、レポートを書く、という流れです」
教育の権利は国民だけのもの?
――日本にいる移民の子どもの教育にはどんな問題があるのでしょうか。
「他の先進国では国民以外にも教育を受ける権利を認めている場合が多いんですが、日本では、教育を受ける権利が国民にのみ保証され、外国籍の子どもには保証されていません。もちろん行政も対応を進めていますが、移民の子の教育は、自治体や現場の教員たち、地域のNPOやボランティアの努力に支えられてきた面が大きいといえます。一方、国は外国人労働者の受け入れを拡げており、今年は「移民元年」と呼ばれています。受け入れ制度の整備なしでの受け入れ拡大では、学校現場の混乱だけでなく、不就学や低学力を招きかねません。この現状と課題は多くの人が共有すべきだと思います」
――いろいろ知りませんでした。では授業で留意していることは何でしょうか。
「授業ではなるべく具体的な事例に触れてもらうようにしています。教科書の学習など、抽象的な面の理解には強いので、少しでも具体的な理解を促そうと心がけています。第9回以降のグループワークでは、NPOや学校や企業など、問題設定に応じて最適な訪問先を自分で決め、自分でアポを取って行動することを課す予定です」
移民教育に反対する人も含めて
――今後の展開で考えていることなどはありますか。
「日本では、日本人であることで生じるメリットと外国人であることで生じるデメリットがあり、メリットを享受している側はその点に無自覚になりがちです。たとえば、移民教育には反対だという学生もいるでしょう。来年度はそうした違う意見を持つ学生も巻きこんできちんと議論できるようにしたいと思っています。違う価値観を持つ学生も参加できるような工夫を心がけます」
「教育に限らず、法律、医療、労働など、多文化社会としての日本の課題というテーマに拡げようかとも考えています。関連するNPO、外国人労働者を多く雇用している企業、ジャーナリストなど、学外の皆さんにも加わっていただいて、学生とともに議論する場を設定したいと思っています。社会連携部門の一員として授業を開いた形にしたい。ブランドデザインスタジオのような企業とのコラボレーションの形も探っていくつもりです」

| 1 | ガイダンス・国際移動と日本社会 |
| 2 | 日本社会の多文化化 オールドカマー、ニューカマー、海外帰国者、留学生 |
| 3-5 | 移動する子ども・若者の生活世界 家庭、学校、地域、労働市場、トランスナショナルな生活世界、グローバリゼーションと教育格差 |
| 6-8 | 多様性の包摂に向けた教育 アメリカの多文化教育、多文化共生と日本の教育、外国人学校、オルタナティブな教育 |
| 9-12 | グループ決め、グループリサーチ |
| 13 | グループ発表 |

※授業で教科書に使っている書籍『移民から教育を考える』(額賀美紗子・芝野淳一・三浦綾希子編/ナカニシヤ出版/2019年9月刊)には、髙橋先生の論考とコラムも