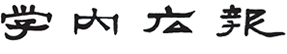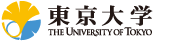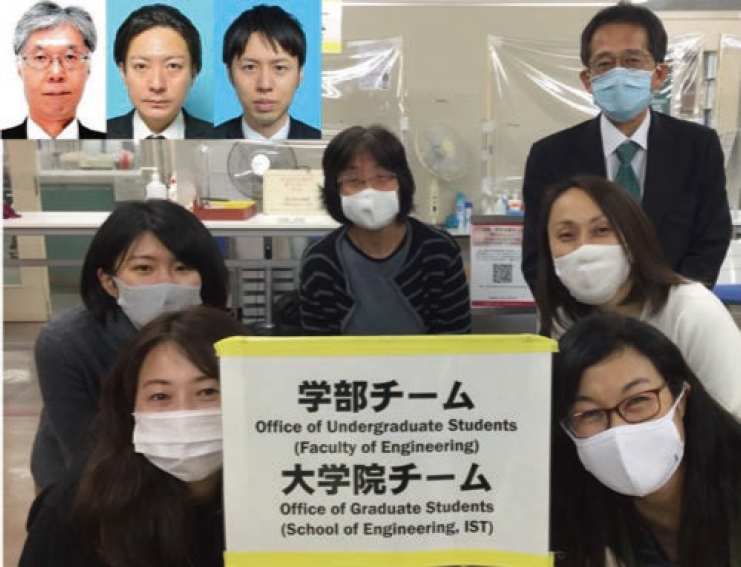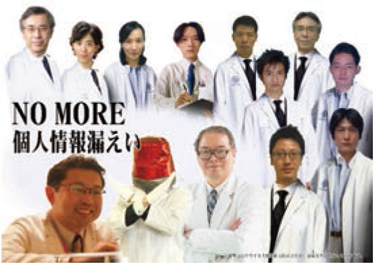「新図書館計画アカデミック・コモンズ」の締めくくりとして総合図書館4階にオープンしたアジア研究図書館。初代館長の小野塚先生に館の特徴と展望をご紹介いただき、館の構築を支援してきたアジア研究図書館上廣倫理財団寄付研究部門(Uehiro Project for the Asian Research Library, 略称U-PARL)の2人の先生にも話を聞きました。「研究する図書館」とはどういうものなんでしょうか?
※コモンズ=共有財、入会地
館長に聞きました
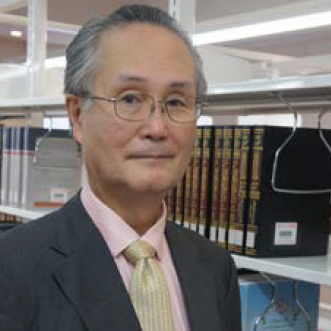
研究機能を併せ持つ図書館へ
――構想が始まったのは2013年でしょうか。
附属図書館長だった古田元夫先生を中心に本格的な議論を始めたのがその頃ですが、最初の構想は2009年です。私は2015年から準備部会に加わり、館がまだない2018年4月に館長になりました。5万冊収蔵可能な開架部分に加え、地下の自動書庫に各部局図書館から提供される本を何十万冊か収蔵予定で、どんな本をいただけそうかの事前調査を進めています。学内に散在するアジア関連資料を集めて利活用するのが狙いです。各専門分野の第一線の研究には向かないがアジア研究の歴史的価値は高い本は文理を問わずあり、図書館の多くはスペースが逼迫しています。自動書庫には十分な余力があるし、地震があっても安心。そう考えていただければありがたいです。



――館の最大の特徴はなんでしょうか。
研究機能を併せ持つ図書館であることです。学内の数多ある図書館の中で「研究」を冠するのは当館だけ。その機能は主に3つあります。第一は、文献を手に取りながら共同研究ができる、学内外のアジア研究者が集まるハブとなること。第二は、サブジェクト・ライブラリアンを設置して利用する研究者を支援すること。第三は、大学院生などを育ててそのサブジェクト・ライブラリアンを養成することです。
――聞き馴染みのない呼び名ですね。
研究者であると同時に図書館員として利用者の支援をする人をいいます。何か調べたい場合に相談すると、研究者の立場からこんな資料がありますよと助言をしてくれる人。日本でサブジェクト・ライブラリアンがいる館は一部に限られます。試みはいくつかあったものの定着はしていないのが現状で、東大が設置を決めたのは大きな意味を持ちます。将来的には主な大学間でポストを連携させられないかと考えています。大学間を移動しながらキャリアパスを昇る仕組みを整えたいんです。
図書館員の任も務める研究者?
――普通の図書館員も本に詳しいですよね。
サブジェクト・ライブラリアンは研究者ですからその館にない資料についても幅広く知っています。私は労働史が専門ですが、海外の専門図書館では随分と助けてもらいました。私が知っている資料の情報を共有することもありました。サブジェクト・ライブラリアンの存在が研究を進展させるのは確実です。U-PARLとの連携に加え、来年度から附属図書館にアジア研究図書館研究開発部門を置き、専任3人+兼任2人の体制で動き出します。実質的にはこの5人がアジア研究図書館の研究機能と養成機能を果たしていきます。
――資料探しはGoogleでは足りませんか?
デジタル化はもちろん重要ですが、必要な情報のかなりの部分はまだ紙の状態です。研究者が何かを調べ始めたら、電子化された情報だけでは行き詰まることも多い。たとえば私の分野で重要な企業の取締役会の議事録は手書きの現物を見るしかなく、癖字で読めなかったりもしますが、サブジェクト・ライブラリアンなら当たりがつくかもしれません。
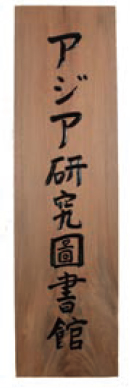
――今後が楽しみですが、課題は?
引き続き収蔵図書の整理を進めることと、研究機能を実装することです。人の面でもお金の面でもやらないといけないことばかり。当初の理想を形にするにはあと10年はかかるでしょう。大変な事業ですが、成し遂げれば世界のアジア研究は飛躍的に進むはずです。アジアの大学として世界に貢献する旨は東大憲章に明記されていますが、これは当館抜きではあり得ません。まだ最初の小さな一歩ですが、大きな一歩を踏み出したとも思っています。
U-PARL の皆さんにも聞きました

蓑輪顕量(部門長/人文社会系研究科教授) U-PARLは上廣倫理財団のご支援を受けて2014年から活動しています。5年1期として今年度が2期の2年目。1 期目には主にアジア研究図書館の構築支援を行い、2期目は協働型アジア研究拠点の形成を主務としています。地域-言語-主題という三段階から成るアジア研究図書館のオリジナル書誌分類を整備したのは1 期目の大きな成果でした。スタッフは、兼務教員4、特任教員2、特任研究員6、事務補佐員3、そのほか部局図書館からの本の移管を担う学術支援職員9という24人体制。私は2016年度から部門長を務めています。U-PARLは附属図書館設置の研究部門であり、第2期は、協働型アジア研究の拠点形成、研究図書館の機能開拓研究、人材育成と社会還元、アジア研究図書館の構築支援という4つのミッションに取り組んでいます。
現在、協働型アジア研究として7人の研究者が7つのプロジェクト(下表)を主宰しています。アジアに関わること、図書館ならではの研究資源を利活用することがテーマです。アジア研究は学内の様々な部局で進んでいますが、U-PARLは図書館ならではのアジア研究の姿を示す役割が大きいと考えています。
永井正勝(副部門長/特任准教授) 多様な資料を擁する図書館は、いわばディシプリンが横断する場。だからこその「協働型」研究なんです。唯一のルールは、一人でやらないこと。学内外を問わず、必ずほかの人を巻き込む形で研究するのが私たちU-PARLのスタイルです。
蓑輪 モットーは「むすび、ひらく」です。プロジェクトを通じて人々を繋ぐ意識を持つということで、「リエゾン」のイメージも含みます。サブジェクト・ライブラリアンの仕事を体現する言葉でもあります。
永井 もちろん部門内でも互いに刺激をし合うのが常で、ランチタイムの雑談からは、アジアンライブラリーカフェというシリーズが生まれました。研究の知見を一般の人に還元する場で、「文字を支える書字材料」「アジアの言語を語ろう」「古典籍 on flickr!」などこれまでに6回開催しました。また、昨年度はアジア各国の図書館を紹介する一冊、今年度は本の分類法を考える一冊を上梓しましたが、来年度には各々の研究成果を本にまとめて出版する予定です。
蓑輪 ほかにもシンポジウムやワークショップは精力的に行っています。11月にはウルドゥー語資料の目録作成、12月にはIIIFに準拠した画像公開の方法を扱いました。3月には、ヒューマニティーズセンター、東アジア藝文書院と連携し、「サブジェクト・ライブラリアンの将来像」と題した開館記念シンポジウムを実施します。というのも、アメリカの主な大学にはサブジェクト・ライブラリアンが配置されており、研究者に対する研究支援等の活動を行っているのですが、日本ではまだ根付いておらず、日本語訳も定まらない状況だからです。アジア研究図書館を軸にサブジェクト・ライブラリアンという重要な役割への理解を広げていきたいと思っています。
| オリエント世界を対象とした研究資源のデジタル化とその利活用に関する研究 | 永井正勝 |
|---|---|
| アジア情報資源の組織化に関する研究:目録作成マニュアルの作成 | 徳原靖浩 |
| 東京大学所蔵水滸伝諸版本に関する研究 | 荒木達雄 |
| 「ジャイナ教混淆サンスクリット辞典」構築のための基礎的研究 | 河﨑 豊 |
| ムハンマド・ハキーム・ハーン著『選史』チャガタイ語訳写本の研究 | 河原弥生 |
| 海外フィールドワーク収集データのオープン化に関する研究:村落研究を事例に | 澁谷由紀 |
| 壬辰戦争からみる16・17 世紀東アジア | 中尾道子 |
http://u-parl.lib.u-tokyo.ac.jp