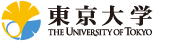第1128回

オンライン時代の建築空間の豊かさについて
2020年4月からはじまったオンライン授業の経験もそろそろ1年となる。その利便性と限界の両面もよく見えてきた1年であった。今後ますます、その長所を伸ばし短所を補う努力がなされていくことだろう。それはサイバー・フィジカルの融合とか、DX(Digital Transformation)とか呼ばれている試みである。
建築学の専門家という立場から、筆者はいま、圧倒的なスピードで技術革新が進むネットワーク上のCyberspaceに対応して、物理空間(Physical Space) がどのように変容(transform)していくのか、ということに関心を抱いている。
Zoomの講義や会議に没入するためには、目の前の2次元ディスプレイ上の視覚情報とヘッドフォンから聞こえてくる音声に集中し、自分自身がいま存在しているはずの3次元空間(居室)を完全に無視する必要がある。ときおり、Cyberspaceの中に完全に意識を集中させた講義や会議を終わらせると、その疲れ方は並大抵のものではない。その時間、人は視覚と聴覚以外の情報を遮断し、椅子とキーボードとマウスのみが物理空間との唯一の繋がりとなっているのだ。
こうした体験を繰り返す中で、多くの人々は、自宅や職場の物理的な環境に改めて目を向けるようになった。この状況のなかで自宅や職場の物理的環境に必要となるのは、居心地の良さや、その場所への愛着といった、きわめて感覚的な側面である。だがじつは、モダニズム以来の建築理論は、建築やインテリアの物質性がもたらす愛着やあたたかみの側面ではなく、機能性や合理性ばかりを重視してきた。だがいまやCyberspaceの機能性や合理性は、Physical Space のそれを軽々と超えてしまったのだ。
だからこそ、DXが進む未来的な住環境、教育環境、職場環境における物理空間が目指すべきは、無機質で未来的なSFのような空間ではないように思うのだ。むしろ人間的であたたかみがあり、居心地の良い空間という基本に立ち返ることが重要だと思う。
東大生たちのことを考えても、わざわざ大学に来て授業を受ける機会には、これぞ東京大学、というAcademic Atmosphereを体験して欲しい。歴史と伝統に裏打ちされた東京大学のキャンパスでの体験こそが、学生にとっても教職員にとっても、帰属意識と母校愛の源泉となると思うのである。
加藤耕一
(工学系研究科)