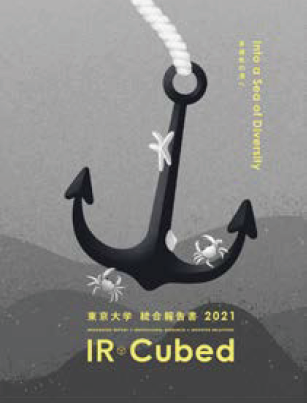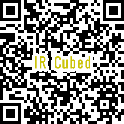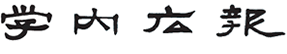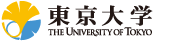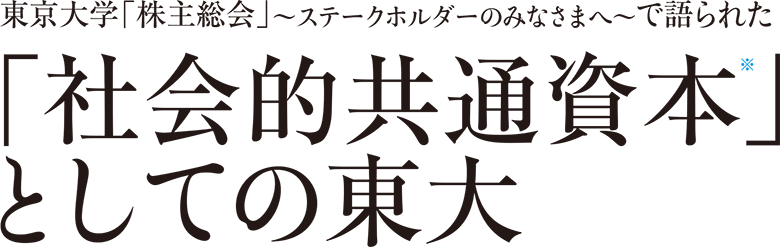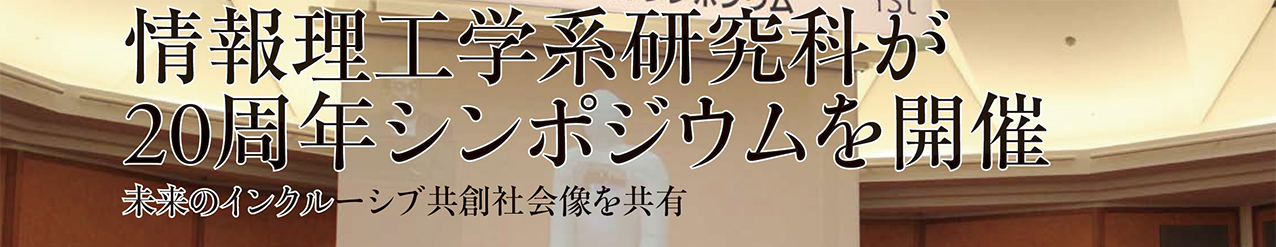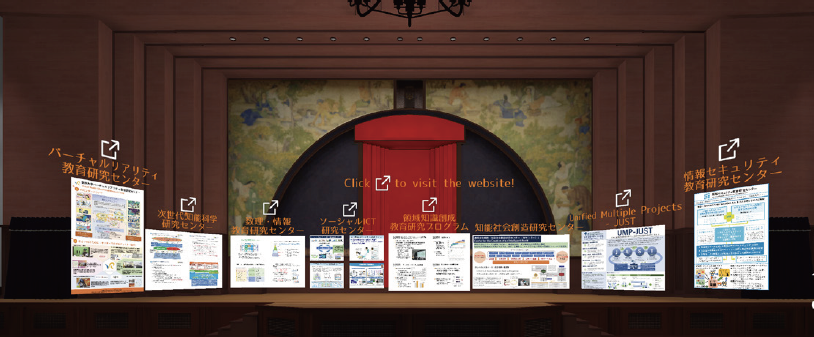多様なステークホルダーの皆様を「株主」と位置づけ、学外有識者と本学教職員との意見交換から大学経営のヒントを得ることを目的に行っている「株主総会」。7回目の今回は「『社会的共通資本』としての東京大学の役割」をテーマに、本学が「社会的共通資本」としての役割を果たすために何ができるのか、多様な背景を持つ学内外の方々と幅広く議論しました。11月26日にオンライン公開された特別座談会の模様の一部を紹介します。
※「ゆたかな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を持続的、安定的に維持することを可能にするような社会的装置を意味する」(宇沢弘文著『社会的共通資本』岩波新書/2000年刊より)。


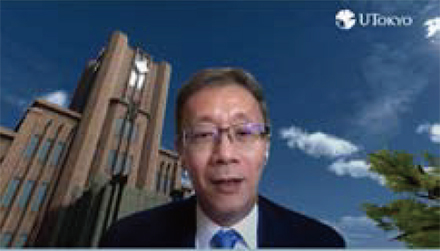

| 「UTokyo Compass」の説明 | 藤井輝夫 |
| 財務戦略説明 | 相原博昭 |
| FSIの活動報告 | 坂田一郎 |
| FSI事業報告① 海と希望の学校 in 三陸 | 青山 潤 |
| FSI事業報告② ハビタット・イノベーション・プロジェクト | 出口 敦 |
| 特別座談会 | |
| QAセッション | |






当日の司会は財務部決算課の青木志帆課長が担当。ライブで行われたQAセッションでは、特別座談会に参加した皆さんに加えて坂田先生が登壇してMCを務め、視聴者からの質問に応じました。
自動車の費用検討から生じた概念
鶴見 社会的共通資本は宇沢弘文先生が提唱した概念で、もとは自動車の社会的費用を考える中で生じたものでした。自動車は非常に便利ですが、一方で交通事故や道路整備や公害の問題もあり、それらを総合して考えないといけない存在です。社会全体で担わなければならない後者の領域を社会的共通資本と捉えようという提案でした。大学も多くの意味で社会的共通資本と言える、というのが総長の考えですね。
藤井 私は社会的共通資本を二つの役割で捉えています。一つは教育としての役割。宇沢先生も書いていますが、大学はまさにその担い手です。もう一つは人類が直面する課題に対して解を見出す基盤としての役割。教育と課題解決の担い手であり、社会的共通資本そのものでもあるのが大学だと思います。
占部 父の宇沢弘文は教育に関してはソースティン・ウェブレンの言葉をよく引用しました。彼は、大学は真理としての知識の蓄積を行う場だと記しています。これは大学特有の役割だと感じます。大学は自由な知識欲や職人気質に基づいて学究を極める場であり、社会的共通資本としての重要性は明らかだという指摘でした。
鶴見 資本といえば蓄積が連想されますが、知を蓄積することから新しい価値を生むのが大学だと思えばいいでしょうか。
小林 蓄積された知は重要な社会的共通資本です。ただ、資本は活用されないと意味がないかもしれません。大学は蓄積された知を教育を通じて拡散し活用できるようにしないといけませんが、教育とは別の方法で拡散する方法を生むのも東大の役割だと思います。
鶴見 私の研究分野でも蓄積は進んでいますが、それを多くの人に活用してもらえているかというと、まだまだ余地があると感じます。
藤井 今日の株主総会も、大学の知の蓄積を活用してほしいという思いをこめて行っています。未来社会協創の枠組みで学外の皆さんとともに蓄積した知を使って課題に向き合い、私たちの資本である知の蓄積を積極的に活用する動きを進めています。UTokyo Compassでは、対話重視の姿勢を打ち出しました。学内外で対話を繰り返し、社会の課題にともに向き合うことで、知を活用し、新しい知を生み出し、それがまた蓄積されるという循環の姿を想定しています。
お金を出し合って作る公園の価値
鶴見 私の理解では、社会的共通資本の典型は公園です。一軒一軒の家には庭があったりなかったりで、大きな庭は一部の家にしかありません。でも、お金を出し合って大きな公園を一つ作れば皆が利用でき、それが新しい価値を生みます。公園作りは掛け声をかける人がいないと始まらず、調整する人がいないと実現に至りません。そこが重要だと思います。対話とは対等な立場で話すことで、公園なら公園の専門家と利用者が対等に話すのが鍵。大学にはそうした側面があります。教室では背景に関係なく対等な立場で議論することに価値があります。大学が社会的共通資本である所以は、一人で考えてもわからないことを多様な人々とともに対等な立場で考える場であることだと思います。
占部 私は普段は内科医をしていますが、コロナ禍では医療が社会的共通資本だと痛感しました。パンデミック下の日本で重症患者の受け入れが柔軟にできていたのは大学の附属病院だと思います。教育を担う存在であると同時に、制度資本としての医療の活動も包含しているのが大学で、その両輪があるからこそコロナ禍にも対応できたのではないでしょうか。
小林 私は経済界に関わっています。昨今はESG※経営が盛んに叫ばれていて、企業は二つのプレッシャーの下にあります。非財務的な価値を重視せよとの重圧と、財務的なリターンを生み出せとの重圧です。この重圧の下でどうサステナブルな経営にしていくのかが大きな課題です。インパクト投資一つとっても、何をインパクトとするのか、投資でどんな影響を社会に及ぼすかを検証しないといけません。ベンチャー投資も社会課題解決の意欲だけでは続きません。大学は企業と違い様々な分野を幅広く持っていることに価値があります。特に教育の場では横串を刺してほしい。横串を刺す手法やその効果を測る仕組みも研究してほしいです。産と学でいいスパイラルを生むことを期待します。
鶴見 企業でも社会の課題を解決して役立ちたいと思うところは増えています。それらをつなぐのが大学かもしれません。自然にまかせていると出会わない知識を引き合わせることも知を蓄積する大学の役割でしょう。大学は18歳や19歳の人が入学することが多いですが、社会に出た人が大学に戻って知見を伝えることも重要です。大学もそれを推進すべきです。
小林 これから先の時代に必要なことは我々の世代にはもうわかりません。これから社会を担う人が何を求めるのかを発信することが重要です。そこから社会は多くのヒントを得られるはず。それを促すのも大学の役割だと思います。
鶴見 知識の受容が主である高校までと違い、大学では自分から発信することが重要ですが、その切り替えはなかなか難しい面があります。そこを教育の力で伸ばせるとよいですね。
※Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)
医療と同時に医療者育成も担う
藤井 医療は社会的共通資本の最たるものです。大学は医療を担うと同時に、その担い手を育てることも行っています。これは経済原理だけで測ってはいけないものです。教育と医療は大学の重要な役割だと最近は特に強く感じます。ESG投資のEとSは特に横串が通せる部分だと思います。宇沢先生が書いたように、文化的・社会的な発展が重要な要素です。インパクト投資では時間軸の問題が難しい。たとえば30年後の大きなインパクトはいま大学で行われている基礎研究から出るかもしれません。そこを社会に支えていただけるよう大学側が努力しないといけない。時間軸の長い活動をどう捉えるか、経済界と対話しながら考えたいです。知の蓄積を資本として活用する際の要点だと思います。
占部 父は大学が独立行政法人化したときに嘆いていました。ペガサスの片方の翼がもがれたように感じていたでしょう。社会的共通資本は国や地域で守っていくべきものです。大学が独立行政法人化した際には国からの翼がもがれたと感じ、地域からのサポートが進んだ際には翼が戻ってきたと感じたかもしれない。父は極端なことを言う人でもありました。投資では投資先の成長が最大の満足であり、投資で得た利益には100%課税せよと言っていました。100年、1000年先も見据えて市場から離れて考える場が大学だと言いたかったのではないでしょうか。
鶴見 長期的視点は社会的共通資本で重要なポイントですね。宇沢先生は東大に対しても過激な提言はされていたでしょうか。
占部 『経済と人間の旅』という父の著書に、東大紛争の頃に書いた東大改革論が入っています。そこでは、駒場を4年制にして全寮制のリベラルアーツのカレッジにせよと書いています。学生が恒常的に深い対話をする場という意味合いが大きかったのではないかなと思います。
鶴見 忙しくても、寝食をともにする場があれば自然と対話が生まれるのかもしれませんね。
小林 長く産学連携が叫ばれ、技術分野の研究では結果が出てきましたが、それ以外の分野では結果が見えづらいのが現状です。社会変革のいまこそ産学で連携して社会をよりよくするチャンス。東大には、産学連携についても幅広い側面で社会への影響を及ぼしてほしいです。
占部 私としては、ぜひ父が残した本を手に取って“原典”を読んでいただくことを願っています。そうすれば深い気づきがあるはずです。
藤井 皆さんと話しながら大学と社会をさらに発展させたいとあらためて思いました。私たちは深刻に物事を考えないといけない状況にいます。様々な人をつなぎ、大学という社会的共通資本がより活用されるよう励みたいと思います。
QAセッションより
Q 外から大学に期待する役割は?
占部 学問を突き詰める場所であることを大事にしてほしいです。リベラルアーツのような答のない問いを考える場、魂の尊厳を守る場でもあってほしいと思います。
小林 経済界は特定のアジェンダへの答を期待しがちですが、大学の一番大きな価値は人をつくること。学問や対話などを通じて人格の柱をつくることに期待します。
Q リカレント教育についてはどういう方針ですか?
藤井 専門家のネットワークをもつ強みを活かし、社会人に学んでもらうだけでなく、社会の要請を大学が学ぶことも強調したいです。双方向のリカレント教育はCompassのキーワードの一つです。これから具体化していきます。
鶴見 私の研究室に50代の社会人が入ってきました。プラスチックの成型機械の会社で勤めてきた人で、業務を通してポーランドの同業者のやり方を不思議に感じ、そこを研究したいとのこと。これは社会を知らない学生では気づかないテーマです。ある分野で長く働いたからこそ生じる疑問を大学に持ち込んでもらうことは大学にとって非常によいことです。人文社会分野でも有意義なキャッチボールができると思っています。