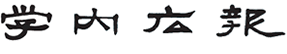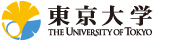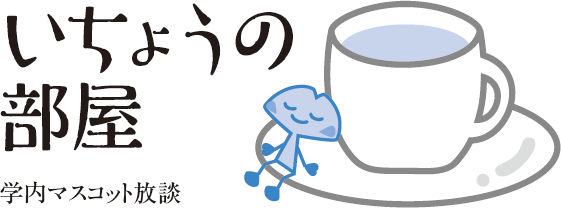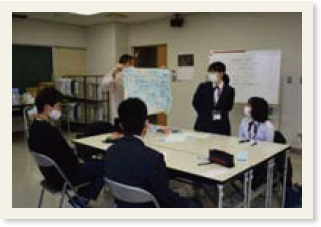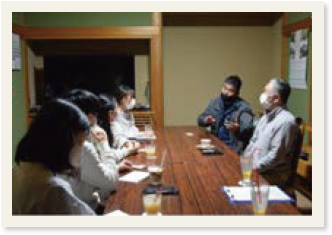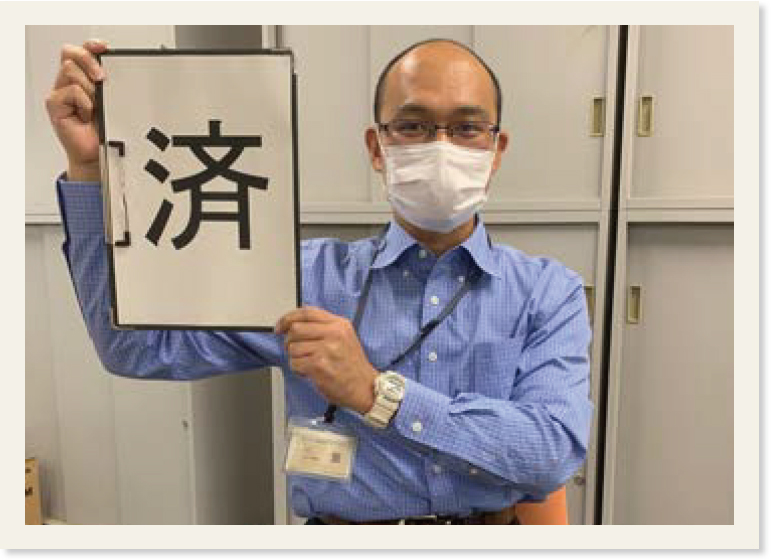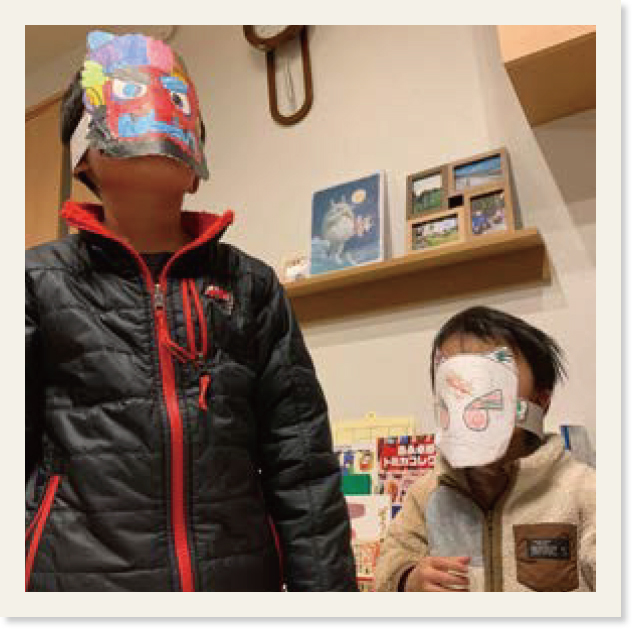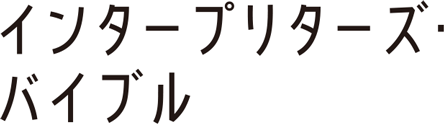創立以来、東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、いま、次々に新しい取組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学の構成員に知っておいてほしい教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。
社会と協働する教養教育の姿を実例から探る
/シンポジウム「大学における社会連携による教育の可能性」
教授 渡邊雄一郎

――毎年恒例のKOMEXシンポジウム。今回は社会連携部門が担当したんですね。
「近年は情勢の変化が急ですが、社会の人たちはそれに対応しています。社会連携部門は、リアルタイムに変化と向き合う人たちの協力をいただき、コロナ禍でもオンラインで社会の現場から学生に声を届ける試みを続けています。そうした活動例をシンポジウムで共有しました」
コンサル会社や音楽家との協働
「難民問題などの研究に軸を置きながらビジネスに関する授業などを手がける髙橋史子先生は、コンサルティング会社アクセンチュアと連携した取組みを紹介しました。インタビューを通して現代社会の課題を捉え、どうすべきかを探る。まとめを企業のトップにプレゼンして評価をもらうインターンシップのような試みも行っています。様々な人と対話することが重要ですが、学生がいきなり見知らぬ人と話す機会を作るのは簡単ではないし、妙な勧誘を受けるかもという懸念もあります。大学側が安全を担保する形でこうした機会を提供しているわけです」
「音楽史やサウンドデザインを研究する山上揚平先生は、作曲家とともに音を題材に感性を磨く表現・創作の授業を紹介しました。たとえばゲームソフトに流れるメロディのような音の表現について学び、何かしらの意図をもって音色を創る体験をしてもらう。従来の枠に収まらない授業ですが、感性を磨くことが知性にポジティブな影響を与える可能性が指摘されています。従来はなかった、感性を使った社会認識や他者との関わりを体験することに意味があります」
――ブランドデザインスタジオや渋谷QWSや金曜特別講座などの紹介のほか、学外の方の講演もありましたね。
「筑紫一夫さんは学校建築を得意とする建築家です。以前、新しい教養教育に相応しい教室の姿を議論し具現化した成果が21 KOMCEEでした。従来の教室のように一方向を向くのでなく、対等に顔がイーブンに見える状況・場を目指した建物です。地元の人とともに活動し自分たちの学びにもなるというコンセプトで保育施設と保育士育成の場を組み合わせた相模女子大学など、筑紫さんが手がけたほかの事例もお話しいただきました」
教育はオープンにすることが肝
――登壇した皆さんによるパネルディスカッションはどのようなものでしたか。
「視聴者の質問に答える形でした。たとえば「渋谷QWSのような試みは東京だからできるのでは?」という質問には、規模の違いはあるが同様の試みは各地でできる、聞かれればノウハウは誰にでも伝えると野城智也先生が返答されました。事例紹介だけでなく、それを活用してほしいという気持ちが滲み出たパネルだったと思います。教育に関わることは抱え込むのでなくオープンにすることが大切です。シンポジウムの報告書を活用しながら卒業生の皆さんや、新たな民間のパートナーと関係を築きたいと思います」
「私自身は昔から何かものを作りたいと思っていて、東大に入学した当時は工学部志望でした。でも、教養学部で受けた授業の中で自然が作ってきたものは人工物よりスゴいと思い、生命科学の道を選んだんです。学生時代は教養教育の価値に気づかないものですが、歳を重ねると学んだことの意味がわかってきます。教養教育はその瞬間的なものではなく一生にわたるものです。環境問題も国際情勢もSDGsも、何か一つの専門分野を学ぶだけでは解決できないでしょう。分野を越えて考えることが必要です。私たち教養学部は、そのために試行錯誤を続けなければいけないと思っています」
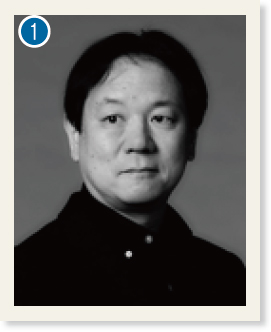
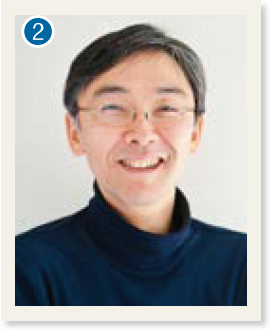
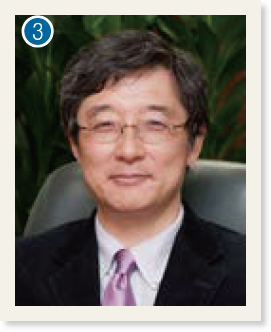
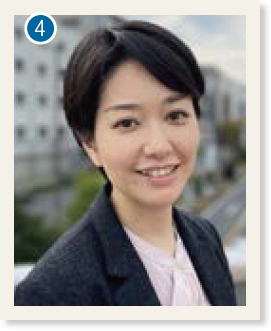



| 開会挨拶 | 森山工(教養学部長) |
|---|---|
| KOMEX紹介 | 網野徹哉(KOMEX 機構長) |
| 趣旨紹介 | 渡邊雄一郎 |
| アクティブラーニング型授業の10年 | |
| ❶宮澤正憲(社会連携部門特任教授) | |
| 教養教育における学外展開の可能性 | |
| ❷筑紫一夫(株式会社 学校計画 代表取締役) | |
| 渋谷QWSと東京大学 | |
| ❸野城智也 ( 生産技術研究所教授) | |
| 大学の学びと「社会」の接続 | |
| ❹髙橋史子(社会連携部門特任講師) | |
| 教養教育としての表現・創作実習の試み | |
| ❺山上揚平(社会連携部門特任講師) | |
| 高校生と大学生のための金曜特別講座 | |
| ❻新井宗仁(総合文化研究科教授) | |
| 質疑応答・パネルディスカッション | |
| 閉会挨拶 | 真船文隆(教養学部副学部長) |