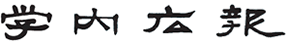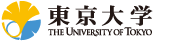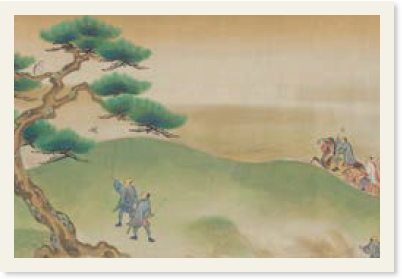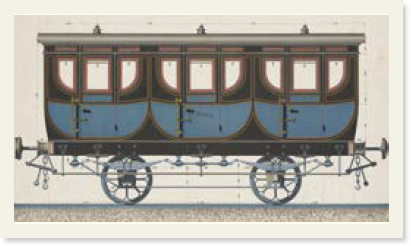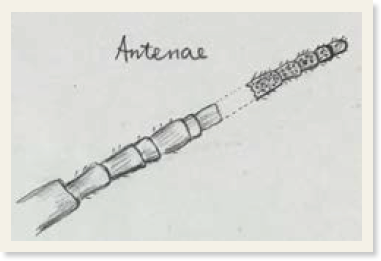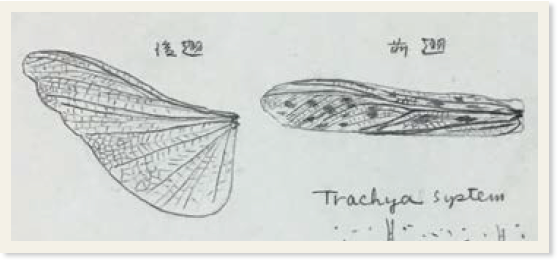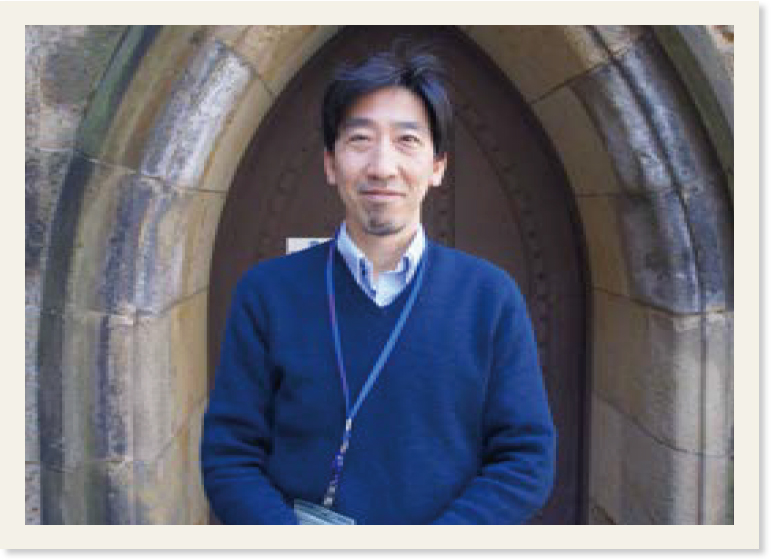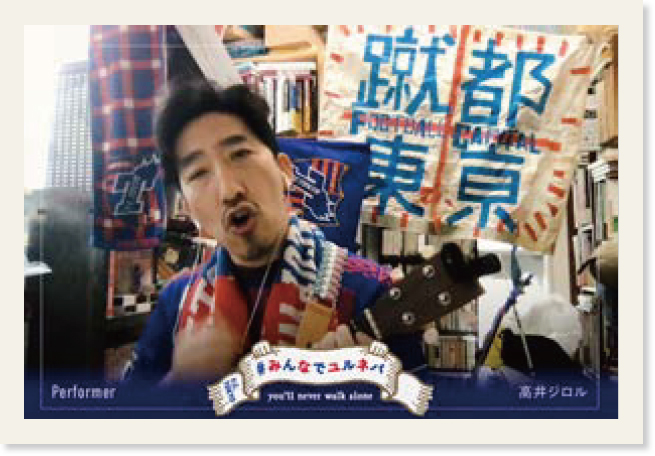第20回
第20回
岩手県大槌町にある大気海洋研究所附属国際・地域連携研究センターを舞台に、社会科学研究所とタッグを組んで行う地域連携プロジェクト―海をベースに三陸各地の地域アイデンティティを再構築し、地域の希望となる人材の育成を目指す文理融合型の取組み―です。5年目を迎え、活動はさらに展開していきます。
海ごみと希望の学校 in 三陸 ~環境モニタリングを通じて地域を知る~
地域連携研究部門准教授


今回は当センターが「NPO法人環境パートナシップいわて」と「いわて海洋コンソーシアム」とともに行ったWebイベント「森と海をつなぐプロジェクト企画」について紹介したいと思います。このイベントは三陸海岸に流れ着く海ごみをはじめ、岩手県沿岸部で起きている環境問題を紹介するために企画されましたが、このイベントのなかで当センターの早川淳助教と大槌高校・はま研究会(詳しくは第10回記事(no.1539 / 2020.10.26)をご覧ください)の海ごみ研究班が大槌町内で継続している海岸への漂着ごみの調査結果を高校生たちが紹介してくれました。
イベントは漂流物学会会長である大気海洋研究所の道田豊教授による「漂着ごみはどこから来てどこにいくのか」と題した講演で我が国をとりまく海流とごみを含む漂着物の特徴を概観するところからはじまり、早川助教による大槌湾での海ごみ調査の趣旨と取り組みの紹介のあと、海ごみ研究班の高校生2名による調査結果の報告がありました。つづく大槌町町議会議員で岩手県地球温暖化防止活動推進員の臼澤良一議員による「大槌町のごみ減量化やリサイクル・自然保護の取り組みについて」(代理講演 櫻井則彰推進員)と題した講演では、大槌町での海岸清掃イベントやごみ減量に向けた大槌町の施策の紹介があり、参加者は海ごみを取り巻く現状と、人々の取り組みについて情報交換をすることができました。
海ごみ研究班によるオンラインイベントでの講演は、緊張は見られたものの、今回で2回目ということもあり、練習の成果がいかんなく発揮された発表でした。道田教授からも「既に学会で発表できるレベル」とのコメントがありましたが、他の参加者からも学会発表かのような質問がつぎつぎに出され、2人とも自分の言葉で考えを述べていました。講演に対する質疑応答も終わり、ほっとしたようすの2人でしたが、調査から発表までの一連の活動に対する感想も聞いてみました。炎天下や身を切るような寒風が吹きすさぶなかの採取と、実験室での地道な分別といった作業の大変さだけでなく、「自分の地域のことが分かる」と述べていたことが印象的でした。今回は他地域との調査結果の比較が可能な調査方法を採用したこともあり、この町の海ごみがもつ特性を考えることができたほか、その特性に関連するこの地域の海洋学的特性について紹介することが多々ありました。それらが彼らのこころに残っていてくれていたようです。この地域連携プロジェクトが彼らへの教育支援だけでなく、プロジェクトの特色でもあるローカルアイデンティティの再構築にも貢献していると感じられた出来事でした。今後も様々な工夫を凝らして、我々の研究成果を地域振興に役立てていきたいと思います。