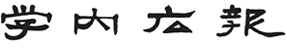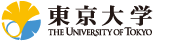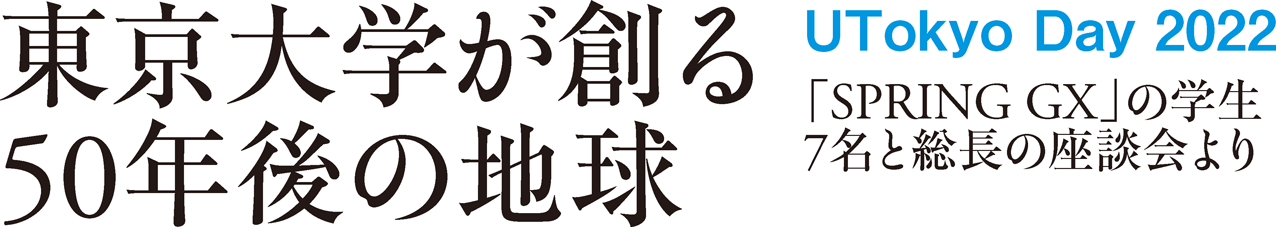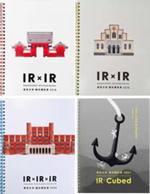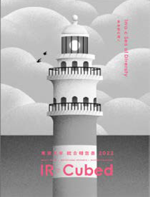12月1日~2日、現代が直面する課題と未来の人類社会のあり方について話し合う「東京フォーラム 2022 Shaping the Future」が開催されました。4回目となる今回のテーマは、哲学と科学の対話。30人以上の識者が会場の安田講堂とオンライン空間に集い、議論を展開しました。2日間で14を数えたプログラムから、初日のハイレベルトークセッション「哲学と科学の対話――新しい啓蒙に向かって」で展開された対話の大意を紹介します。

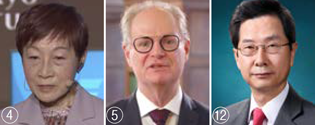






初日には、藤井輝夫総長①と韓国SKグループのチェ・テウォン会長②による開会挨拶に続き、潘基文 元国連事務総長③、長谷川眞理子 総合研究大学院大学学長④、ポール・アリヴィサトス シカゴ大学学長⑤の3人が基調講演。ハイレベルトークセッションの後、パネルディスカッション1「世界共通価値としてのグローバル・コモンズの責任ある管理」⑥を行いました。2日目には、「世界哲学は世界の諸危機にどう対決するか?」⑦、「持続可能な将来への社会変容に向けて」⑧、「ロボットやAIと歩むこれからの社会はどうなる?」⑨、「安全保障と気候変動の複合課題」⑩をテーマに掲げる4つのパネルを行った後、全5パネルの代表と藤井総長による総括セッション⑪を実施。最後に藤井総長とChey Institute for Advanced Studiesのパク・イングク院長⑫が閉会挨拶を述べました。総合司会は前回に続いてNHKアナウンサーの山本美希さんが担当しました。

中島 このセッションでは、今求められている新しい啓蒙(new enlightenment)について4先生と考えたいと思います。
新しい啓蒙主義の三本柱とは?
ガブリエル 世界が危機的状況にある今、哲学の一分野である倫理学がこれまで以上に重要です。道徳的事実は、人間として何をなすべきかに関わるもので、共通の人間性に基づく責任の結果として生じます。倫理は人間以外の動物や自然にも向けられるべき道徳的なリアリズムだと言えます。新しい啓蒙におけるヒューマニズムは、人間中心主義ではありません。人工知能や生命科学の発展を経て人間を全ての中心とすることに意味がなくなったのです。新しい啓蒙では普遍性を多様性から捉えます。文化の違いを越えつつも、多様性を捉えた探究を行うことで初めて普遍性が獲得できます。普遍性は、以前の啓蒙の時代のように理性や生物学だけに基づくものではありません。地域ごとの違いを捉えた上で、新しい普遍性をボトムアップで作る必要があります。リアリズム、ヒューマニズム、普遍性が、私の考える新しい啓蒙主義の三本柱です。
大栗 アッペルとハーケンは1976年にコンピュータを使って四色定理を証明し、ボエボツキーは2013年に数学的証明をコンピュータで実行可能にし、フラットアイアン研究所のグループは今年、30年分のデータをニューラルネットワークに学習させることで万有引力の法則を再発見しました。このような発展は、人間が法則を発見するとはどういう意味なのかという問いを立てたのです。かつての啓蒙主義は、理性と観察可能な証拠を重視する科学的手法を用いれば、確証バイアスや集団思考といった傾向を修正できると考えました。その後科学が発展すると、人工の心を含む他者の心による推論に依存する必要が生じました。同時に、文明の存続に重要な影響を及ぼす問題では、科学的手法で偏見や誤った信念を正すことが難しくなっています。それらを前に、哲学者は世界を理解するための新しい社会的想像を提供できるでしょうか。
ローカルに根ざす新しい普遍性
イ かつての啓蒙は、人間は合理的で主体的な存在であると捉えました。それによって民主主義が進展した一方、世界の多様性が十分認識されていないという制約もありました。新しい啓蒙の時代には、世界各地の特性を認識し、新たな科学的発見と技術の進展を取り入れ、地球温暖化や気候変動といった課題に、科学者と哲学者の両方で対応しないといけません。近年、ローカルなコンテンツに普遍性が現れているのが興味深いと思います。世界で人気を博した『イカゲーム』は韓国ローカルの話ですが、扱うテーマは普遍的でした。グローバルがローカルに、ローカルがグローバルになっている状況があります。ローカルに根ざす新しい普遍性が重要です。多様性と複雑性を新しい普遍性のなかでどう実現するのか。ライプニッツは「一から多へ」と言いました。普遍性は一つではなく、特定の地域や文化に各々の普遍性があります。こうした普遍性を軸にすれば、世界の人々が協力して課題に向かいあえるかもしれません。
立場の弱い人を守る対話の場
隠岐 17~18世紀に未分化だった哲学と科学は、かつての啓蒙の時代の末期に分かれました。カントは『純粋理性批判』で、哲学者は理性の立法者であり、数学者や博物学者そして論理学者は理性の芸術家だと述べています。Scientistという語を作ったヒューウェルにとって、科学者はもはや哲学者ではなく、特定の分野で働く専門家でした。フランス革命後、社会は秩序の象徴として専門を持つ科学者を必要とし、哲学の役割は弱くなりました。しかし、20世紀後半に状況が一変し、科学と社会の相互作用で起こる問題において、哲学、特に倫理学の重要性が再認識されました。原発のように、科学なしには扱えないが科学だけでは解決できない問題のためです。福島の事故を経て倫理的評価を科学に埋め込む動きが進み、哲学はいまやあらゆる場で求められています。新しい啓蒙は多様な個人間のコミュニケーションの困難を克服することによってのみ達成できます。バイアスや集団思考の存在を前提に、曖昧で複雑な対話に関わる必要があります。それには、立場の弱い人を守ること、効果的な対話の場を用意することが重要です。
ガブリエル 科学は政治や経済をも左右します。核兵器や原発も科学の成果物です。哲学と科学がもっと対話すべきなのは明白ですが、原子力をどう扱えばいいかを倫理学が知っているわけではありません。知識のやりとりを通してこそ新しい方向性が見えてきます。人間が動物であるとはどういうことか、世界を理解するとはどういうことであるのかといった問いは、すべて倫理的な問題への回答に貢献します。哲学者は人工知能の研究者や物理学者と協力すべきです。共通の目的は、人間とは何かを理解することです。かつての啓蒙は人間を合理的動物と捉えましたが、それは正しくありませんでした。必要なのは専門化が進みすぎた諸学を統合することです。学者以外の人も含んで、より大きな社会まで変えていこうとする取り組みが必要です。それが新しい啓蒙の出発点になります。
有益性に基づく具体的手法を
大栗 かつての啓蒙は成功した、と私は言いたいと思います。限定的ですが確実に問題を解決する具体的手法を提供したからです。しかし解決できない問題も存在します。事実を理解し解釈するとはどういうことなのか。気候変動、原子力の利用など、科学的手法だけでは解決できない問題があります。合意を目指して多様な人々がともに問題に向かうことが重要です。具体的ではっきりした手法を作らないといけません。道徳、リアリズム、普遍性といった視点を取り込むことが必要です。こうした概念を具体的手法に結びつけるにはどうすればいいのか、有益性に基づいて判断する必要があります。
イ 新しい啓蒙は、古い啓蒙が達成したのと同じような成功を収められるのか。私は可能だと思いますが、自問自答を続けなければなりません。今後どのような基盤に基づいて道徳的なリアリズムを考えるべきか。手法の問題も重要です。古い啓蒙では、合理的であることに注目すれば状況を脱却できると皆が合意していましたが、今はそうした合意がありません。過去と比べ、自分と違う意見をうまく扱えるようになっているのかも疑問です。SNSの時代に、コミュニケーション力は逆に下がっているように見えます。新しい啓蒙を考えるにあたっては、まず何が今足りないかを明確にすべきかもしれません。
隠岐 皆さんの話に励まされました。対話の可能性に期待しています。多くの分野の人が関わりながら共同の知恵を作り、広い視点で明るい未来を目指せるのではないかと感じます。ただ、浮かんだ疑問もあります。人工知能が万有引力の法則を再発見したと聞いて驚きましたが、これは自然現象の理解と言ってよいのでしょうか。理解とは何なのかを考え直す機会だと思います。人間を理解することが重要だと言われましたが、それにはどのような理解が必要でしょうか。一つの理解で満足できるのでしょうか。非常に多様な理解がありえます。人間を理解することは複雑で難しい。新しい啓蒙は、どういう理解が意味あるものなのかという大問題にも取り組まないといけません。
中島 新しい啓蒙を考えると、哲学と科学が作った社会的想像を抜本的に変える必要があります。そのためには、哲学も科学も自らを変容すべきなのです。省察にして反射であるreflectionは互いに撓みあうことですが、哲学と科学は相互に映し出しあうことで、深いところで互いに撓みあう必要があるでしょう。新しい社会的想像をもって人間がともに生きていくことを考えれば、哲学と科学の新しい協働の可能性も広がります。倫理の基盤を考え直すことで、私たちの理解に対する新しい理解も生まれるのです。今日の対話は、哲学と科学の本格的な対話を始めるよい契機となったと思います。