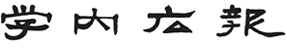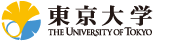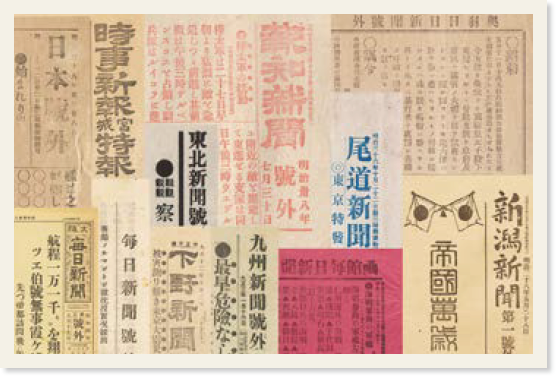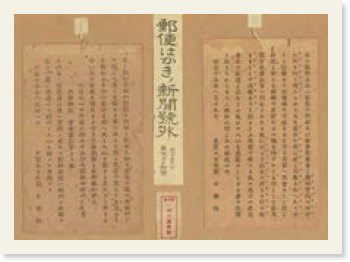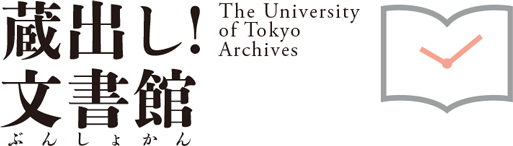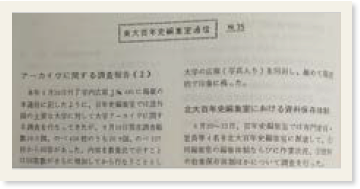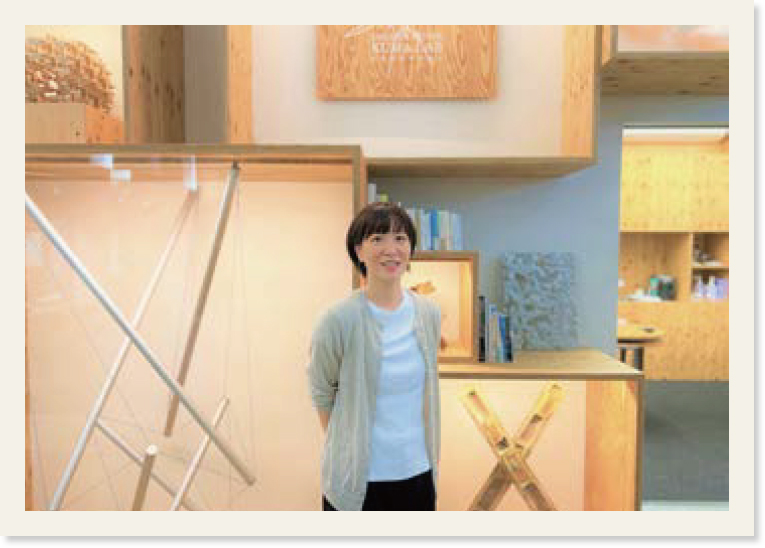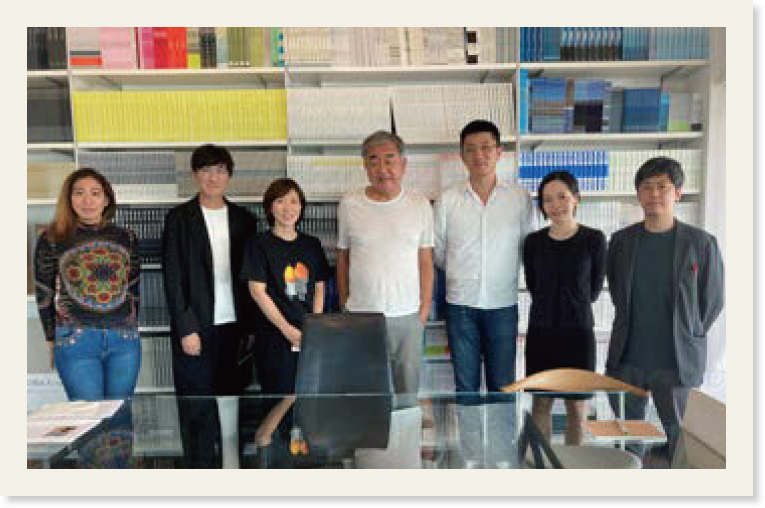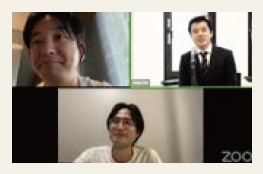第23回
第23回
岩手県大槌町にある大気海洋研究所附属国際・地域連携研究センターを舞台に、社会科学研究所とタッグを組んで行う地域連携プロジェクト―海をベースに三陸各地の地域アイデンティティを再構築し、地域の希望となる人材の育成を目指す文理融合型の取組み―です。5年目を迎え、活動はさらに展開していきます。
「海と希望の学園祭 in Kamaishi」開催
地域連携研究部門(大槌研究拠点)准教授


今年度、最終年度を迎えている「海と希望の学校 in 三陸」ですが、新型コロナウイルス感染症拡大の問題が発生して以来、控えめな活動を余儀なくされていました。最近になって、本事業をともに行っている社会科学研究所(社研)の先生方がようやく釜石に来ることが可能になったこともあり、今後の活動の景気づけにと、玄田有史・社研所長の声がけで急遽「海と希望の学園祭 in Kamaishi」を行うことになりました。
11月5日(土)、6日(日)に釜石市が主催、大気海洋研究所(大海研)・社研・先端科学技術研究センター(杉山正和・所長)が後援で、釜石情報交流センター・釜石市民ホール「TETTO」で行いました。5日は、野田武則・釜石市長、河村知彦・大海研所長挨拶のあと、3研究所・所長による講演を行いました。その後、河東英宜・かまいしDMC代表取締役にも加わっていただき、「海と希望のまち釡石」と題し、パネル・ディスカッションを行いました(写真1)。昼食時には宮古市立重茂中学校の生徒も駆けつけ、郷土芸能(鶏舞・剣舞・魹埼太鼓)を披露してくれました(写真2)。
翌日の6日は、近年、社会問題化している海洋プラスチックごみ問題を扱った映画「プラスチックの海」(2016年公開)の上映会を皮切りに、沿岸地域で生じている社会的課題をビジネスとして解決する取り組みを紹介するトーク・イベント「海と希望のソーシャルビジネス(中村寛樹・社研准教授ほか)」のほか、学術講演(宇野重規・社研教授「民主主義は海から生まれた」、佐藤克文・大海研教授「バイオロギングで実現する海洋生物と人の持続可能な共生社会」)を行いました。
バルーン・アート(写真3)で飾られた華やかな会場で、当センターは2日間を通して「希望の缶詰作り」や少し季節外れでしたが「タッチプール」を行いました(写真4)。また、釜石で活動をしている文京学院大学も「海のいきものかんむり作り」などのワークショップを開いてくださいました。大槌町の(株)ササキプラスチックによる射的の釣り版「キャスティング体験」は、景品も豪華で子供たちに大人気でした。海上保安庁・釜石海上保安部、海洋研究開発機構、三陸ジオ・パークなどにもブースを設置していただきました。
すでに今年度の予定が決まっていた中で新たに学園祭を行うことは、簡単なことではありませんでした。しかし、多くの人に参加していただいたことに加え、3つの研究所と釜石市をはじめとする多くの異なる組織がもたらす相乗効果で、学園祭は大変賑やかなものになり、盛会裏に終えることができました。来年度以降も続けていくことになりそうです。