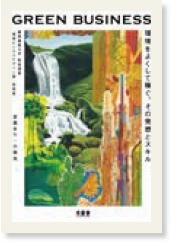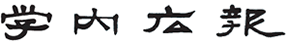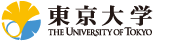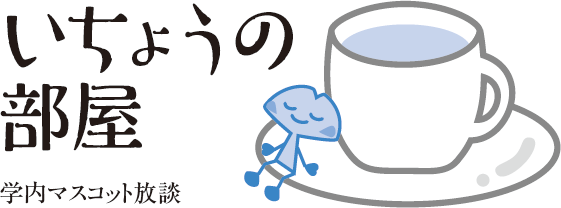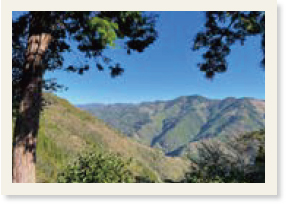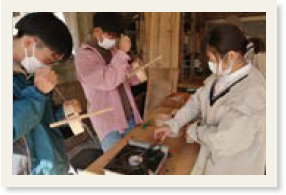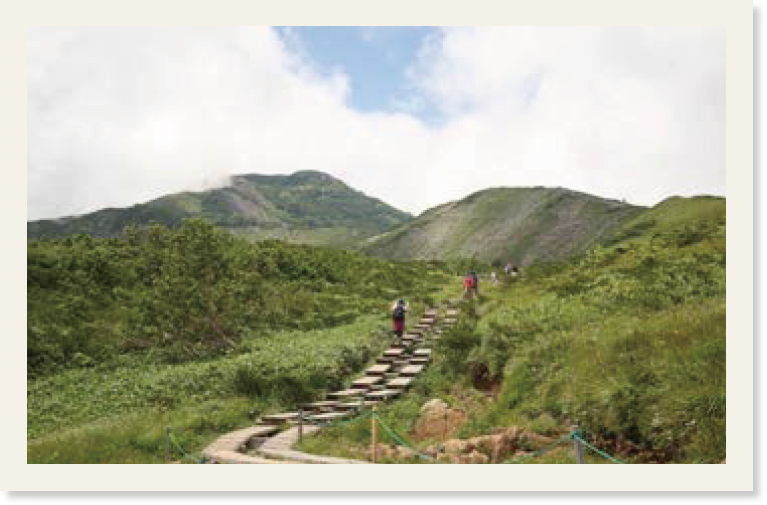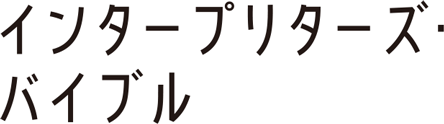創立以来、東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、いま、次々に新しい取組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学の構成員に知っておいてほしい教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。
環境ビジネスの実践者と具体的に学ぶ
/全学自由研究ゼミナール「Road to 2050 :グリーンビジネスの方法論」
客員教授 吉高まり

――吉高先生は、気候変動分野を中心とする環境金融コンサルティング業務に長年従事してこられたんですね。
「はい。2009年に慶應義塾大学の環境系の講義に呼ばれ、30か国以上で関わった排出権ビジネスの話をしたのを機に、大学院の授業を受け持ちました。そこで知り合った小林光先生にお声がけいただき、今年度から駒場で授業を始めました。環境ビジネスの第一線で活躍するゲストの話を題材に議論を進め、最後に学生たちが自分の環境ビジネスを提案するという内容です。環境への関心が強く、環境分野で起業を志す受講生ばかりでした」
「SDGsネイティブ」を対象に
「東大では1年生が相手で、そこに魅力を感じました。いまの若い人は、幼い頃から環境や社会の問題に関心が高いSDGsネイティブ&デジタルネイティブ。彼らが環境ビジネスを進めれば可能性は大きく広がるはずです。旧世代があまり手がけていない環境ビジネスは若者にとってやりがいがあるもの。環境問題がコストでなく収益を生むこと、金融の世界が変化しつつあることを教えています」
――ゲスト講師はどんな人でしたか?
「一人は、CO2の見える化サービスを展「SDGsネイティブ」を対象に開するスタートアップ企業ゼロボードの渡慶次道隆さん(東大工学部出身)。近年は情報開示が不十分だと金融機関の融資を受けにくく、企業は事業に関わるCO2排出量を示す必要に迫られます。生産量や電力消費量といった企業の活動量をクラウドに入力することでサプライチェーン全体の排出量を算定して提供するゼロボードは、2021年の創業ですが、従業員数は100人を超え、導入社数は2,200以上。20億円もの資金調達に成功したことに学生たちは驚いていました」
生物多様性保全の情報開示も
「もう一人はキリンホールディングスCSV戦略部の小此木陽子さん。キリンは2010年に生物多様性保全宣言を発表しました。気候変動の情報開示ではTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の枠組みが使われますが、自然資本の件でも同様の枠組み作りが進んでいます。たとえば「午後の紅茶」を作るのに自然環境や生物多様性にどの程度依存しているかを示すわけです。定量化が難しい生物多様性の問題をビジネスに結びつけて考えるのは、まだ少し難しかったようです」
――学生のプレゼンではどんな案が?
「スタートアップのピッチを模し、収益性を考慮することも求めました。企業、市民、自治体を巻き込む生分解性プラスチック循環ビジネス、カーボンニュートラルを目指す中小企業対象のマッチングサービス、 環境を守る事業が評価されるプラットフォーム、繁殖力が強くて生態系バランスを崩しがちな竹を粉にして肥料や素材に使うという竹資源地域循環など、どれも練られていて驚きました」
「今回、ゲスト講師以外にも、田中良先生がオブザーバー参加したほか、COP27の会場で知り合った環境NGO(Climate Youth Japan)の学生にも話してもらいました。ゲストの皆さんや受講生のネットワークが広がるといいなと思います」
「私は、途上国を中心に30か国以上を訪問してグリーンビジネスの組成に携わった経験を活かし、三菱UFJリサーチ&コンサルティングのフェローとして活動する一方、 金融庁サステナブルファイナンス有識者会議のメンバーを務め、自ら設立した一般社団法人バーチュデザインで地域創生の仕事もしています。サステナビリティの視点は教育にも政治にも地域にも活きます。具体的な事例を示せると共感を生みます。日本を変えたいと思う若者をエンカレッジする授業を続けます」
| 1 | 最近のエコビジネス情勢について |
|---|---|
| 2-3 | 『GREEN BUSINESS』講義(工学的側面、法的側面、経済的側面) |
| 4 | 『GREEN BUSINESS』講義(企業の側、金融の側) |
| 5 | スタートアップ企業の講義&討論 |
| 6 | エネルギー系エコビジネスの講義 |
| 7 | エネルギー系エコビジネスの討論、COP27からの帰国報告 |
| 8 | グループワークの中間報告など |
| 9-10 | リサイクル系ビジネスの講義&討論 |
| 11-12 | 生物資源系ビジネスの講義&討論 |
| 13 | 学生によるプレゼンと講評 |
授業は、吉高先生と小林光先生(環境エネルギー科学特別部門客員教授/1554号本欄に登場)の二人によって行われました