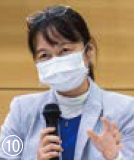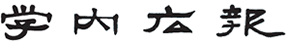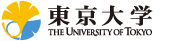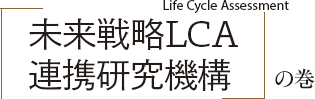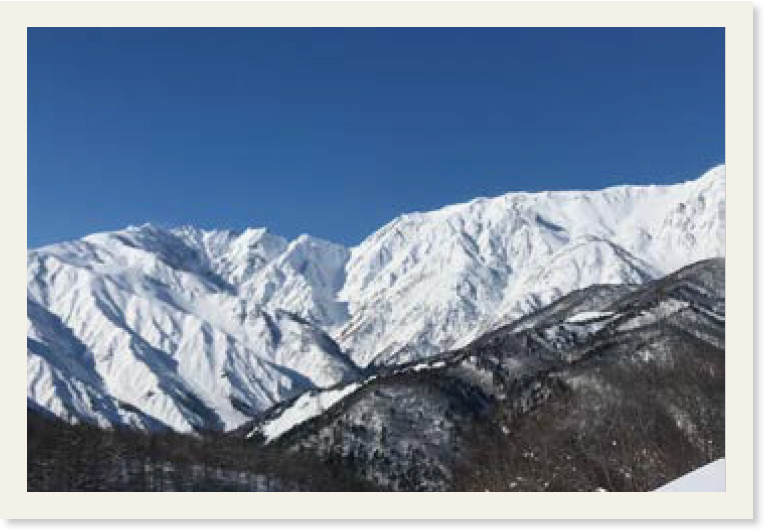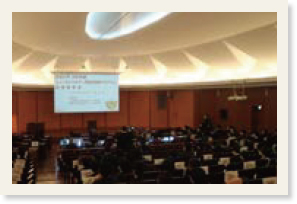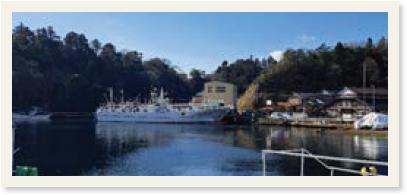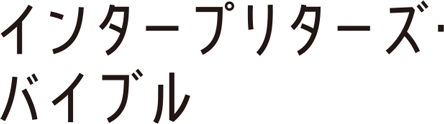創立以来、東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、いま、次々に新しい取組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学の構成員に知っておいてほしい教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。
学問の垣根を越えてSDGsの現在地を確認
/教養教育高度化機構シンポジウム2023「「変革」の現状と行方」

――年に一度の機構シンポジウム。今回は部門横断型組織のSDGs教育推進プラットフォームが企画したんですね。
「私は初年次教育部門ですが、SDGsに関わる授業を続けている関係で、このプラットフォームにも参画しています。周知が進むSDGsですが、果たして各々の課題は今どのような状況にあるのかを確認しようと考え、そこに駒場らしさを重ねて検討して出てきたのが、現実を見極める目を養うための教育ということでした。様々な分野の専門家がいて、多岐にわたるSDGsのほとんどの項目をカバーできるのが駒場だと認識しています」
理想のためにまず現実を捉える
「SDGsの前身であるMDGsのときは、全体では目標に近づいたように見えますが、一方で貧しい国々の状況はあまり変わりませんでした。その反省を経てできたのがSDGsであり「誰一人取り残さない」の理念です。たとえば太陽光発電を推進するだけでは不十分で、世界を俯瞰して見ないといけません。「風が吹いたら桶屋が儲かる」の全体を自らの目で確かめる学生を増やしたい。そのためにまず現実の姿を捉えることが必要だということで企画したのがこのシンポジウムです」
――パネルでは「場違いな感じ」と複数の先生が話していたのが印象的でした。
「SDGsの目標17が掲げるマルチステークホルダー・パートナーシップを学問分野の垣根を越えた協力も含むものと捉えてのテーマ設定でした。今回お声がけしたのは、普段からSDGsを看板に掲げている先生方ではなく、実はSDGsに関係していると聞けばなるほどと思える研究をしている皆さんです。SDGsの企画では技術の話に偏りがちですが、よい技術があっても社会に適用できるかはわからず、実際には史学や文学や社会や制度も大きく関わってきます。今回の人選は、多分野の研究者が関わり合うのがSDGsだというメッセージでもありました」
「ディスカッションでは、各々の研究をSDGsの現状に絡めてお話しいただき、分野の垣根を越えた取組みや、社会問題を解決に導く複合的視座を持つ人材をどう育てるべきかも議論したかったのですが、時間が足りませんでした。全体でコンテンツが多すぎたかもしれません。一つ一つの料理はすごく手が込んでおいしいのにじっくり味わえず一気にお腹に流し込む感じになったのは反省点です」
異分野の研究者を繋ぐ場にも
「今回、SDGsをキーワードに異分野の研究者を結び付ける場にもなるといいなと思っていました。初顔合わせの人が多かったんですが、パネル終了後、これを機会に何かやろうと話す先生方を見ることができました。今回登壇した先生たちとプラットフォームとの間でも今後いっしょに何かできないかなと思います」
――今後の活動予定などありますか?
「昨年3月にプラットフォーム主催で「SDGsビジネスアイデア学生発表会:社会を変えるために東大生ができること」をオンラインで実施しました。SDGsの実現に関わりたい学生に発表の機会を与え、実務家や研究者や市民からフィードバックをもらおうというものです。たとえば前回は、医学部の学生が血液透析の待ち時間を使ってまつげやネイルのケアができるようにしてはどうかというアイデアを発表したところ、当事者が見て率直な意見をくれました。この発表会の2回目を実施して、学生たちの探求心と社会貢献の心を刺激したいと思っています」
| 開会挨拶、 機構紹介、 基調講演 |
真船文隆(総合文化研究科)①、網野徹哉(教養教育高度化機構長)②、石井菜穂子(理事)③ |
|---|---|
| 第1部 講演 「SDGsの現在地」 |
「国連から見たSDGsの今」井筒節(国際連携部門)④、「開発途上国の現場におけるSDGsの現状」成田詠子さん(国連人口基金駐日事務所長)⑤、「開発経済学から見たSDGsの今」澤田康幸(経済学研究科)⑥、「気候変動による健康影響とSDGs」橋爪真弘(医学系研究科)⑦、「誰一人取り残さない社会」福島智(先端科学技術研究センター)⑧ |
| 学生団体紹介など | Climate Youth Japan、UNiTeほか |
| 第2部 パネル 「パートナーシップを 通してSDGsの その先へ」 |
榎原雅治(史料編纂所)⑨、キハラハント愛(総合文化研究科)⑩、白波瀬佐和子(人文社会系研究科)⑪、額賀美紗子(教育学研究科)⑫、瀬川浩司(環境エネルギー科学特別部門長)⑬、原和之(国際連携部門長)⑭ モデレーター:岡田晃枝 |
| 閉会挨拶、 総合司会 |
廣野善幸(科学技術インタープリター養成部門長)⑮、松本真由美(環境エネルギー科学特別部門⑯ |