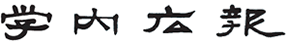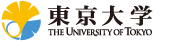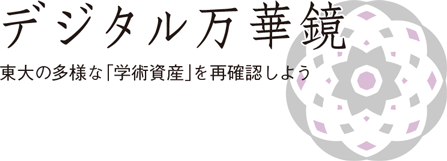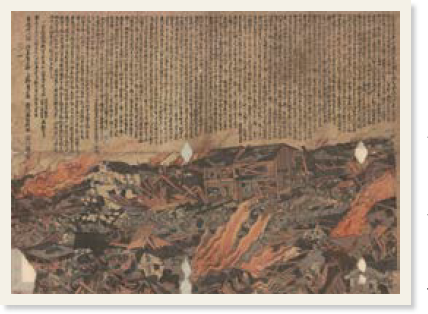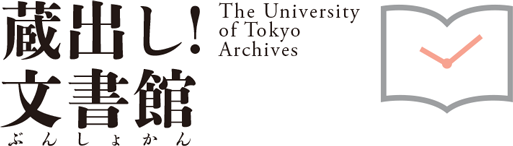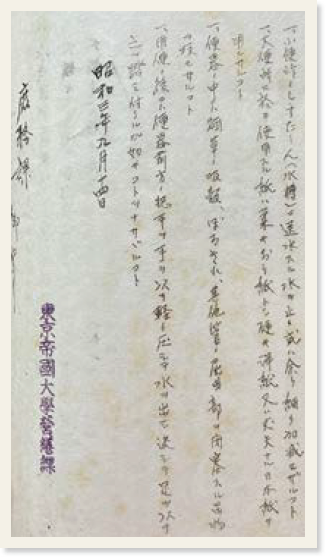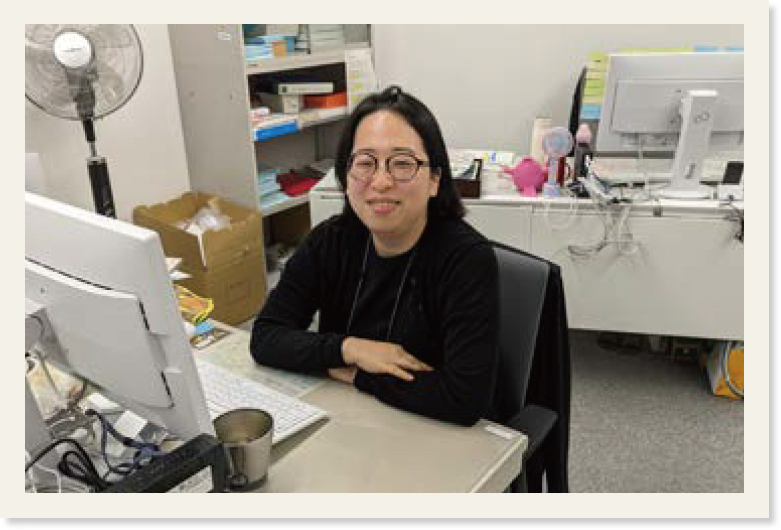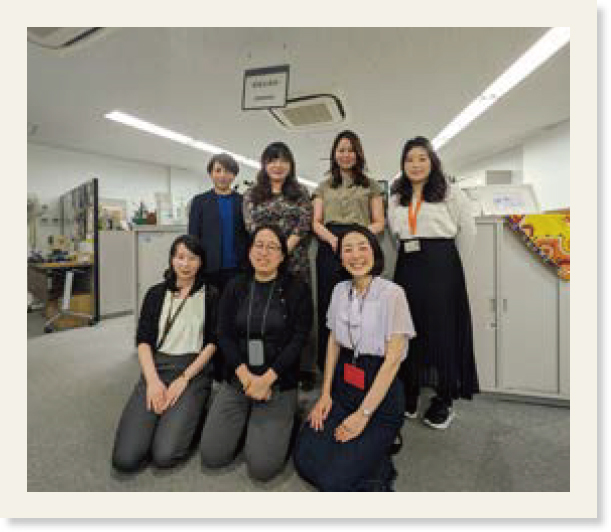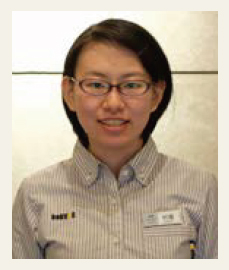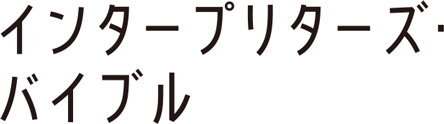第26回
岩手県大槌町にある大気海洋研究所・大槌沿岸センターを舞台に、社会科学研究所とタッグを組んで行う地域連携プロジェクト―海をベースにしたローカルアイデンティティの再構築を通じ、地域の希望となる人材の育成を目指す文理融合型の取組み―です。研究機関であると同時に地域社会の一員としての役割を果たすべく、活動を展開しています。
政治学者、三陸に向かう―おのがデモンに聞け
比較現代政治部門教授


私は政治学者である。政治思想史が専門で、『アメリカのデモクラシー』を書いたフランスの思想家、トクヴィルを中心に研究を進めてきた。そんな私が不思議な運命の巡り合わせで、岩手県の釜石市を中心に、三陸地域との深いご縁を持つことになった。それにしてもなぜ、フランス政治思想史の研究者は三陸に向かったのか。
直接のきっかけは、社会科学研究所のプロジェクト「希望学」であった。地域における希望を考えるなら、一度、釜石に来てみたらいい。そんな誘いの言葉に、かつて製鉄業で日本の高度経済成長を支えたこの地を訪問したのが、自分の運命の曲がり角であった。高炉の火が消えた釜石で、地域の新たな希望を模索する魅力的な人々と出会ったことが、足繁くこの街に通う原動力となった。東日本大震災で、釜石を含む三陸海岸が甚大な被害を受けたことは、この地域への私の思いをさらに募らせた。
思いを加速したのが、大気海洋研究所と連携して行う新事業「海と希望の学校in三陸」である。海とそこに暮らす生物を研究する専門家とのコラボは、私の認識を大きく変えた。そう、いうまでもなく三陸はリアス海岸で有名である。入り江と入り江で、目にする風景はまったく違ってくる。三陸鉄道(NHKの朝ドラ「あまちゃん」の北鉄のモデルである)に乗れば、一つ一つの入り江に異なる集落があり、暮らしがあることがわかるはずだ。当然、生き物も違ってくる。取れるわかめだって同じではない。日本は長い海岸線に囲まれた国であり、海と山と川が織りなす豊かさこそが、その最大の恵みなのである。
しかし、そこで「待てよ」という声が聞こえてくる。「政治学に先生はいない……おのがデモンに聞け」と言ったのは東大の元総長である南原繁である(都築勉『おのがデモンに聞け』)。デモンとは、自分の内なる神の声であろう。そのデモンが「お前は三陸の地で何を見つけたのだ」と問いかけてくるのだ。私は三陸の地で何を見つけたのか。ただ、地域の人々の厚情と海の恵みを享受しただけなのか。
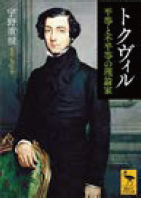
先月号で、大気海洋研究所の青山潤先生にご紹介いただいたように、三陸の中学校で講義もさせていただいた。わかめのおいしさを中学生に自慢され、それに対抗したわけではないが、「三陸の歴史もすごいぞ。江戸時代の三閉伊一揆では、地域の住民が立ち上がって、地域の困難を広く社会に訴えたんだ。それは民主主義だったんだ」と思わず、口走ってしまった。日本の民主主義は決して近代になってゼロから始まったわけではない。日本の伝統的な地域社会に民主主義の実践を見出すことも可能ではないか。
昨年、釜石で開催された「海と希望の学園祭」では「民主主義は海から生まれた」と題して話をさせていただいた。本気である。民主主義の起源を探って海を渡り、アメリカを旅したトクヴィルも喜んでくれると思っている。