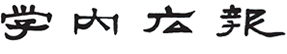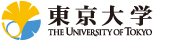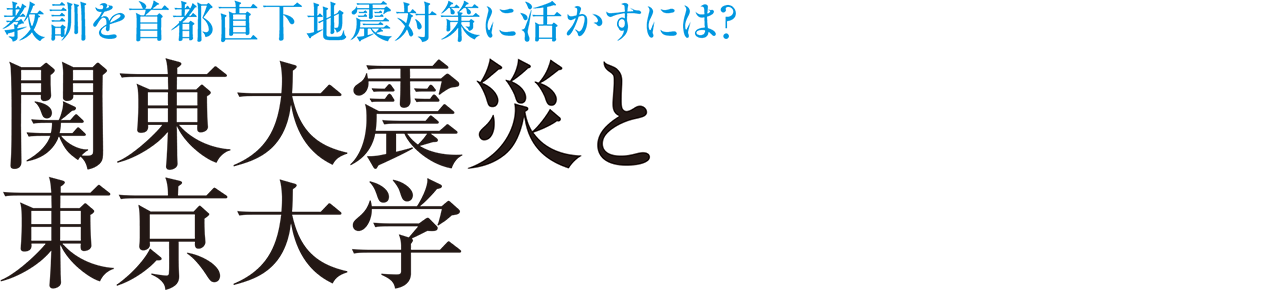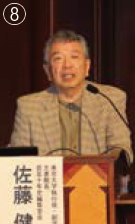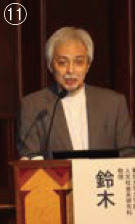7月23日と30日の2日間にわたって安田講堂で開催されたシンポジウム「関東大震災と東京大学」。関東大震災の全体像と当時の東京大学の貢献をテーマに、幅広い分野の研究者が一堂に会して講演を行いました。情報学環、地震研究所、生産技術研究所、災害・復興知連携研究機構が共催したこのシンポジウムの中から、30日に行われたパネルディスカッションの一部を紹介します。
第Ⅲ部 パネルディスカッション「関東大震災の教訓を首都直下地震対策に活かす」より
地震関連の研究や技術の進歩
1923年9月1日11時58分に発生した大正関東地震。マグニチュード7.9と推定される激しい揺れによって建物が倒壊し、大規模火災にも見舞われ、10万5千人以上が犠牲になりました(関東大震災)。それから100年。自然災害に関する研究が行われ、技術が進歩し、都市の姿も大きく変化しました。では100年前と比べて、都市は安全になったのか。脆弱性が高まった点はあるのか。そして来るべき巨大地震にどのように備えていくべきか。コーディネーターを務めた情報学環総合防災情報研究センター長の目黒公郎先生から出されたお題について、さまざまな分野の第一人者が意見を交わしました。
100年前と比べて良くなった点としてパネリストたちが指摘したのが、数多くの分野で地震関連の研究が進み、1923年の関東地震の全容や地震そのもののメカニズムに関する理解が深まったこと。それによって建物の不燃化や耐震化が進み、自治体などでは避難計画が作成され、大規模な火災から避難するための広域避難場所も確保されるようになりました。
巨大地震や津波を研究する地震研究所の佐竹健治先生は、100年前は地震の規模を表すマグニチュードという指標もなければ、プレート境界型地震ということも分かっていなかったと言い、「ハザードの基礎的研究はかなり進んできた」と述べました。関東大震災の断層モデルができたことで、どういう地殻変動や津波が起きるかという予測をできるようになったと説明し、「大正より前に発生した関東地震を調べることによって、今後の発生確率なども計算することが可能になりました」と地震学の進展について語りました。
東京都が2022年5月に公表した大正関東地震をモデルに算出した被害想定によると、建物被害は54,962棟で死者は1,777人。東京都の濱中哲彦防災計画課長は一概に比較できるものではないがと断ったうえで、100年前と比べて大きく被害が減少していると説明しました。「震災、戦後復興、それから高度成長期の都市基盤整備など、これまで進めてきた都市づくりの成果といえるのではないかと思います」。
地震火災や耐震化に残る課題
一方で、まだまだ課題はあります。その一つが、関東大震災で多くの犠牲者を出すことになった大規模火災に関する対策。減災まちづくりを専門とする先端科学技術研究センターの廣井悠先生は、この100年で耐火性能の高いエリアは増えたがそれは一部だと指摘し、「まだまだ密集市街地を中心として我が国の都市は燃える」と警鐘を鳴らしました。世帯あたりの出火件数(出火率)は100年前より減っていますが、世帯数が増えているため件数は増えていると説明し、地震火災発生時の避難の難しさにも言及しました。「多分この中で、私も含めて地震火災から逃げた経験のある人はいないと思います。それぐらい稀な現象で、地震火災は津波や水害より複雑で難しいです」と語り、都市火災経験の希薄化が非常に憂慮すべき問題だと指摘。「地震火災のイメージ力をどう養うかが、重要なポイントになるのではないかと思います」。
建物の耐震設計を専門とする地震研究所の楠浩一先生は、耐震設計が新しい知見を反映したものに更新されても、建物が入れ替わるのには40~50年かかることが問題だと話しました。つまり、町にある多くの建物は依然として旧基準で建ったものだということ。それが顕著になったのは1995年の阪神淡路大震災だと述べました。「耐震設計を更新することと同時に、既存の建物の耐震診断、耐震補強を進めることが、来るべき大地震に対する最も必要な対策になります」。
「災害はその社会の一番の弱点を的確に突いてくる」と語ったのは景観論を研究する工学系研究科の中井祐先生。まだ都市計画も整備されていない時代に東京に人口が集中し、高密度で質の低い市街地がどんどんできたところに関東大震災が発生したと語りました。それによりバラック同然だった住宅が全壊し、一面が火の海になり犠牲が大きくなったと指摘。「災害時は弱い人にしわ寄せが行きやすい」と言い、そのような人たちがシビアな状況に陥らないような地域のあり方を再構築することが大事だと話しました。
人間の心の弱さを認識しておく
歴史的教訓も忘れてはいけません。関東大震災では流言蜚語が広がり朝鮮人虐殺が起こりました。日本近代史が専門の人文社会系研究科の鈴木淳先生は、朝鮮人虐殺についての研究が重ねられたことによって、報道や行政機関などが「外国人をめぐる流言蜚語が起こらない、あるいはそれによる暴行事件などが起こらないように、常に意識するようになったのは、歴史の教訓が生かされた最大の成果ではないか」と述べました。一方で、また大災害が発生したときは全く同じ流言は防げても、形を変えて蜚語などが襲ってくるのではないかと懸念も示しました。
避難の方法と場所を再度確認
流言に関して鈴木先生と同様の見方を述べたのが、情報学環総合防災情報研究センターの関谷直也先生。コロナ禍下の米国で起きたアジア人への暴力などに触れ、「災禍においては今も弱い人を攻撃するということは変わっていません。災禍における心の弱さを認識することが重要ではないか」と話しました。そして、そこを改善するためには、教育、広報などソフト対策をしっかり行っていくことが重要だと語りました。
災害時の情報発信の難しさを語ったのは、27年間生放送の番組に携わってきた情報学環客員研究員の有働由美子さん。地震が起きた時は電気と通信が一番打撃を受けやすく、緊急地震速報などを出して呼びかけても、その情報が一番届いてほしい人に届かないことが課題だと話しました。情報学環の関谷先生も災害時の情報伝達の難しさについて指摘し、この100年の節目を機に、情報がない中で避難しなければいけないことを認識し、避難方法や避難場所など確認することが重要だと述べました。
最後に、コーディネーターを務めた目黒先生は、大災害で何が起こったのかという全体像を皆で作り上げ、それを共有することが大切だと語りました。それぞれの地域での課題を抽出し、その改善に向けた方法を定期的に議論していくことが重要だと話してディスカッションを締めくくりました。
| 開会挨拶1 /藤井輝夫(総長)⑮ 開会挨拶2 /岡部徹(生産技術研究所)⑯ 趣旨・企画説明/目黒公郎(情報学環)⑰ 閉会挨拶/古村孝志(地震研究所)⑱ | ||
|---|---|---|
| 第Ⅰ部 関東大震災の全体像 | ||
| 講演1 | 関東地震のメカニズム、過去の発生履歴と将来の発生確率 | 佐竹健治(地震研究所)① |
| 講演2 | 大正関東地震の揺れを考える | 三宅弘恵(地震研究所)② |
| 講演3 | 大正関東地震から始まった我が国の耐震設計 | 楠 浩一(地震研究所)③ |
| 講演4 | 地盤災害、結局解決されなかった課題 | 東畑郁生(関東学院大学)④ |
| 講演5 | 関東大震災の市街地焼失:現代の市街地の火災危険性を考える | 加藤孝明(生産技術研究所)⑤ |
| 講演6 | 関東大震災の社会的影響 | 関谷直也(情報学環)⑥ |
| 講演7 | 関東地震と地震研究の進展 | 酒井慎一(情報学環)⑦ |
| 開会挨拶/山内祐平(情報学環)⑲ 趣旨・企画説明/目黒公郎 閉会挨拶/佐藤健二 | ||
| 第Ⅱ部 関東大震災と東京大学の貢献 | ||
| 講演8 | 東京大学と関東大震災 | 佐藤健二(文書館長)⑧ |
| 講演9 | 東京大学第二外科の震災対応 | 赤川 学(人文社会系研究科)⑨ |
| 講演10 | 東京大学第二外科の傷病者の外科手術 | 鈴木晃仁(人文社会系研究科)⑩ |
| 講演11 | 東京帝国大学学生救護団の成り立ちと活動 | 鈴木 淳(人文社会系研究科)⑪ |
| 講演12 | 帝都復興の現場における東京大学教員と卒業生たち | 中井 祐(工学系研究科)⑫ |
| 講演13 | 東京大学キャンパスと関東大震災 | 加藤耕一(工学系研究科)⑬ |
| 講演14 | 大正大震災の写真資料のカラー化 | 渡邉英徳(情報学環)⑭ |
| 第Ⅲ部 パネルディスカッション | ||
| 「関東大震災の教訓を首都直下地震対策に活かす」 | ||



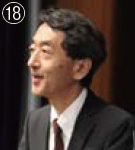





大正関東地震
100年記念グッズ発売中
関東大震災から100年の節目を記念して地震研究所が地震波形をモチーフにしたグッズを作りました。UTCCと国立科学博物館で販売しています。
◉1923関東地震波形ハンカチ

イギリスの物理学者で工学者のジェームズ・ユーイング(明治11~16年に東京帝国大学理学部教授)が開発した円盤式地震計で録った関東大震災の波形を、東北で栽培されたコットンを使用したハンカチにあしらったものです。この地震計は、円盤が回転し、煤をつけた記録紙に地震動が記録されるというもの。元の記録は保管庫に所蔵されているため、日常的に使用できるハンカチにデザインしました。¥700(税込)
◉1923関東地震波形缶パン

東京帝国大学教授で地震学者の今村明恒先生が開発した「今村式2倍強震計」による関東大震災の揺れの記録をあしらった備蓄用食パンの缶詰め。この機械式地震計はドラム缶に巻き付けたアート紙に石油ランプから出る煤をまんべんなく付着させ、針先で記録紙を引っ掻くことで揺れを刻み付けるというもの。震災発生時には本郷の地震学教室に置かれていました。缶内の乾パンの賞味期限は3年間です。¥550(税込)