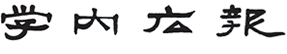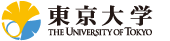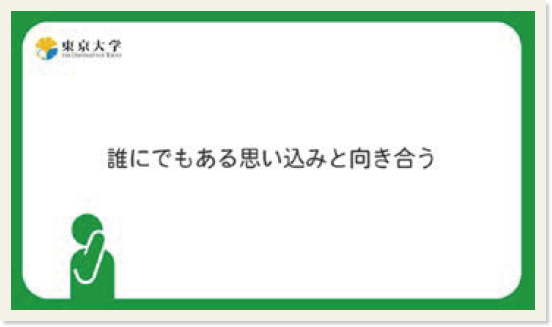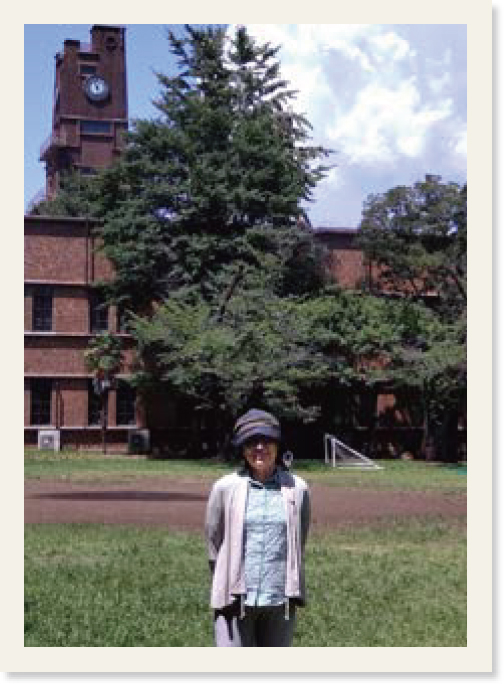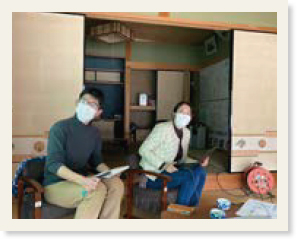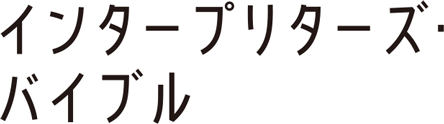創立以来、東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、いま、次々に新しい取組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学の構成員に知っておいてほしい教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。
3部門を統合して「教育DX」推進の新部門に
/教養教育高度化機構(KOMEX)第5代機構長に聞く

生成系AIも検討するEX部門
――今年度、組織が変わりましたね。
「時代ごとのニーズに対応する形での部門名変更はこれまでも何度かありましたが、今回は部門の統合も行いました。一番大きな変化は、自然科学教育高度化部門、初年次教育部門、アクティブラーニング部門を統合して、EX(Educational Transformation)部門としたことです。UTokyo Compassが目指す「教育DX」をKOMEXでも推進しようとの方針のもと、前機構長の頃から準備を進めてきたもので、3部門の統合により23人のメンバーを擁する大所帯となりました。旧3部門が担ってきた活動を引き続き行うのに加え、教養教育におけるデジタル技術についても検討します。生成系AIの利用では成績評価をどうするかといった問題もありますが、技術的変化をしかと受け止めて教育DXに活かすことが重要で、その中核を担うのがEX部門です。具体的な検討はこれからですが、EX部門が担当する来年3月のシンポジウムで何らか方向性を示せるかと思います」
「もう一つの新部門が、前回の本欄に登場したD&I部門です。駒場キャンパスSaferSpace(KOSS)の運営に加え、前期課程教育へのD&I実装を重要な任務と考えて設置しました。昨年のAセメスターから福永玄弥先生と飯田麻結先生を中心に準備を進め、4月から講義と演習のD&I関連授業を行っています」
――部門名称の変更もありました。
「科学技術インタープリター養成部門を科学技術コミュニケーション部門に変更しました。2010年から続く大学院の副専攻科目、科学技術インタープリター養成プログラムの運営が主たる任務ですが、科学技術コミュニケーションの研究と発信も重要なミッションに据えており、より内実に沿った名前に更新した形です。「ネイチャー・ウォッチング」や「科学コミュニケーション・カフェ」のような企画も加え、教育・研究・発信という3つの柱を軸に活動を展開していきます」
元法務技官や精神科医も加入
――新しい先生も続々と増えています。
「EX部門の初年次教育担当に宮島謙・横沢匠の両先生が加わりました。社会連携部門には、金曜特別講座担当の小檜山明恵先生に加え、法務省矯正局の法務技官兼法務教官の経験がある山岡あゆち先生が4月に着任しました。環境エネルギー科学特別部門には、部門長の瀬川浩司先生とともに有機系太陽電池などの研究に携わってきた中崎城太郎先生と野々村一輝先生が6月に加わりました。SDGs教育推進プラットフォームには、国際協力機構で活動してきた精神科医の田中英三郎先生が9月に着任します。先述のD&I部門のお二人も含め、多様な背景を持つ先生方が集ってくれました」
「教養学部の前期教養教育において、部会や学科といった従来の枠組みに収まらない分野を担うのがKOMEXです。その多くは、横断的だったり、先進的だったり、社会に近いところから出てくる分野です。社会連携部門の活動はもちろんですが、D&I部門やEX部門、2019年度に発足したSDGs教育推進プラットフォームも、その流れで生まれたものだと言えるでしょう。社会の変化に応じて大学の組織も変わります。成長し続けることを運命づけられたKOMEXの機構長としてその流れを止めないよう努めます」



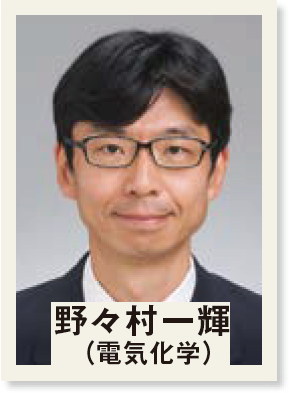
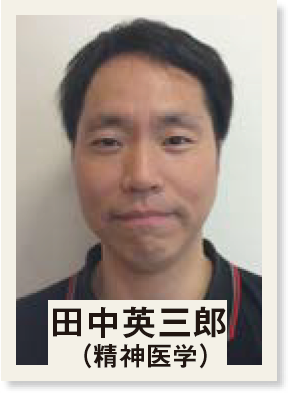
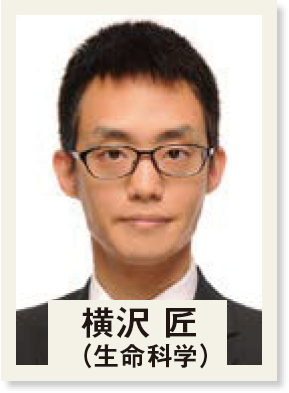

| 8月28日 | 「異次元エネルギーショックへの日本の対応」東京財団政策研究所オンラインシンポジウム(後援/環境エネルギー科学特別部門) |
|---|---|
| 9月3日 | ワークショップ「第4回 東大生がつくるSDGsの授業」(EX部門) |
| 9月21日 | 第7回 模擬国連ワークショップ(EX部門) |