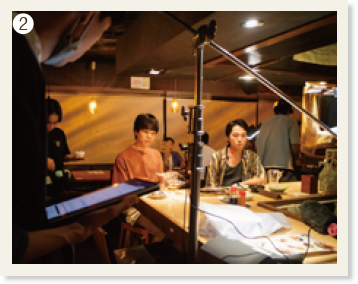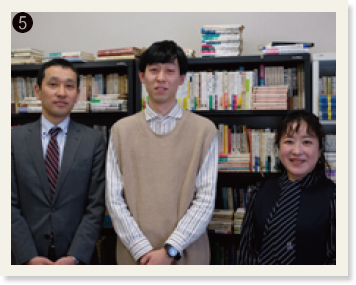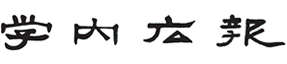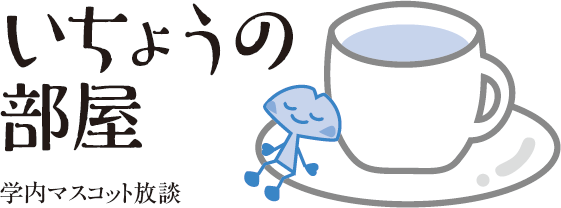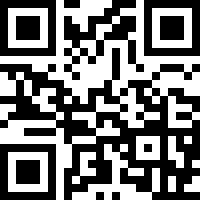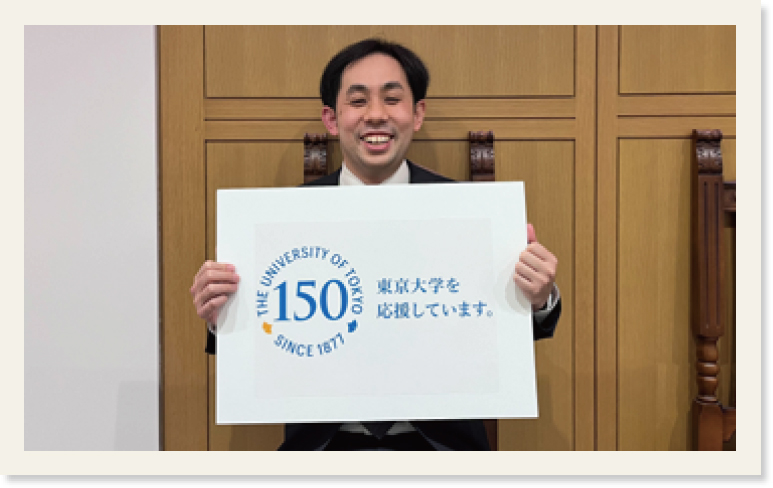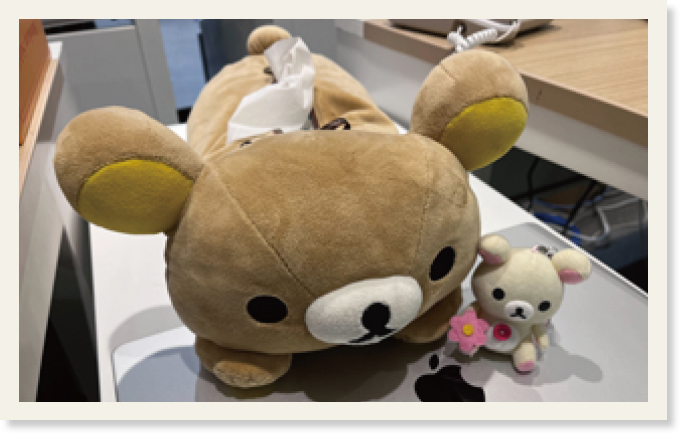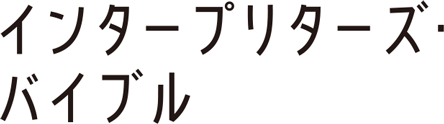創立以来、東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、いま、次々に新しい取組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学の構成員に知っておいてほしい教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。
映画で描く科学コミュニケーションの可能性
/科学技術インタープリター養成プログラム2023年度修了生作品

日常のなかの気候変動を描く
――映画を修論のテーマにしたんですね。
「専門は理論物理学で、すごく簡単に言うと重力の研究です。理論物理だけではなく、2つの主軸を持ちたいとの思いから映画もつくってきました。副専攻での修了研究で取り上げた映画『温帯の君へ』の脚本は、2年くらいかけて執筆していたものです。気候変動という言葉を使わずに気候変動を表現した映画をつくろうと取り組んできたのですが、納得がいかず書いては修正するという作業を繰り返していました。方向性を変えるしかないなと思っていたタイミングで副専攻のテーマを決めることになり、脚本を全面的に書き直すことにしました」
「この映画では恋愛を通じて気候変動問題を描いています。大学生カップルの一方が気候変動に目覚め、認識や考え方の違いで衝突し、その後互いの認識を理解する。科学コミュニケーションでいう「欠如モデル」的な、自文化中心主義を乗り越えるまでの物語です。気候変動に関する現状に目を向けると、積極的に行動する人を揶揄したり、行動しない人を攻撃したりという対立が見られます。そこで争っているのは生産性がありません。結局どこかで解決しなければいけないタイミングがくるわけで、そこに向かって我々はどうすべきか考えるべきじゃないかということが出発点です」
――多くの層にリーチするための工夫は?
「私たちが普段しているような会話や人間関係の日常を通して気候変動を描く、というアプローチをとりました。気候変動という科学的なテーマを描こうと思うと、気候変動に関する情報をセリフの中に入れてしまい、押しつけがましくなってしまったりします。登場人物を私たちの代弁者として描くのではなく、受け手側に近い感覚をもつ登場人物を置いて、その登場人物同士のコミュニケーションのなかで気候変動を描くということを意識しました」
「気候変動に関心あるないに関わらず楽しめる映画になっていると思うので、多くの人に見ていただきたいです」
作品は劇場公開する予定
――映画を通して伝えたいことは?
「見た後にポジティブな気持ちになってもらえたらと思います。そしてそこに、『自分たちとつながっていることなのでは』といった何かしら引っかかりがあってほしい。映画では気候変動を描いていますが、恋愛でも、友人関係でも、どこかで認識の違いというものは必ずあります。そこをコミュニケーションを通して乗り越えるということを繰り返していけば、やがては社会的な動きにつながっていくのではないかと考えています」
──今後について教えてください。
「この副専攻では多様なバックグラウンドを持つ人たちと出会い、議論を重ね、自分の中の知見を広げることができました。科学コミュニケーションは必ずしも科学だけではなく、政治や社会問題のように『難しい』とか『理解できない』と思われている物事一般に通じる考え方です。これからの時代に必要な科学の視点だと思います。4月に一般企業に就職しますが、社会に出る直前にそれを学べたことは自分の中で大きいです。映画は今後も撮り続けていきたいです。『温帯の君へ』は今年4月に完成する予定です。少し先になるかと思いますが、劇場公開もする予定なので、ぜひ見にきてください」