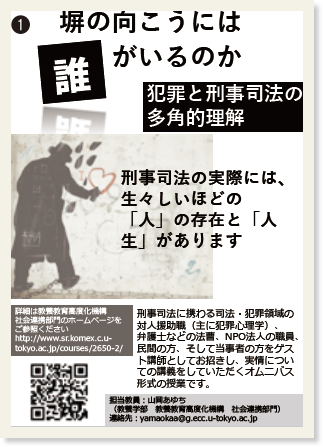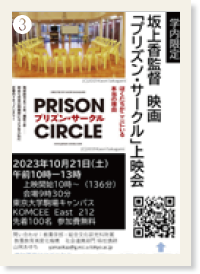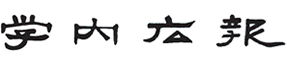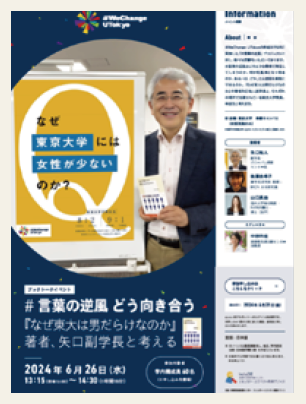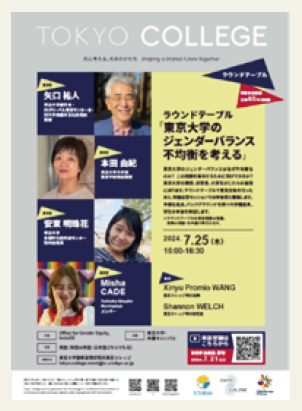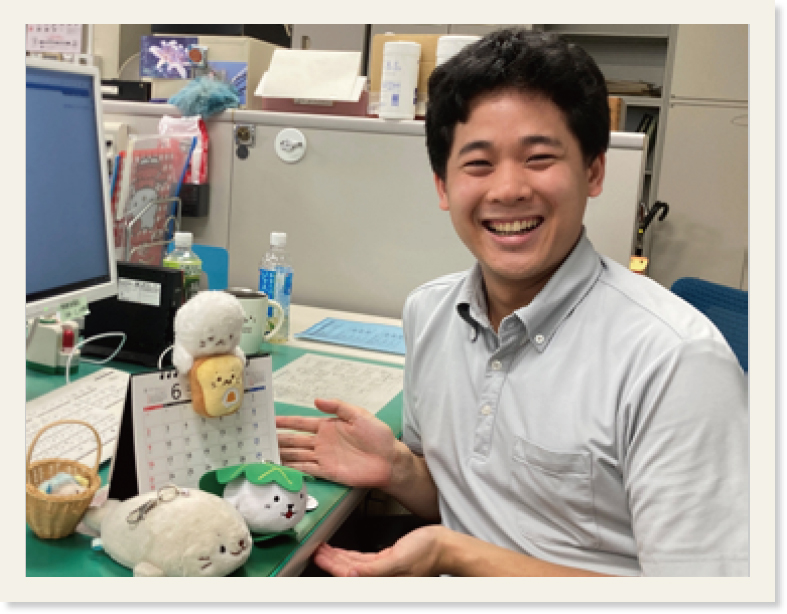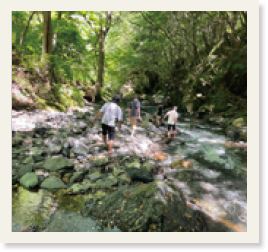東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、いま、次々に新しい取組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学の構成員に知っておいてほしい教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。
犯罪における当事者たちから学ぶ刑事司法のリアル
/全学自由研究ゼミナール「 塀の向こうには誰がいるのか : 犯罪と刑事司法の多角的理解」
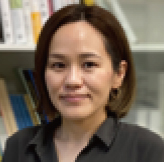
矯正局での経験をキャンパスへ
――前職は法務省だったそうですね。
「私は大学で法学と心理学を学んだ後、法務省矯正局の職員となりました。非行少年や受刑者の方々と面接し、どんな働きかけが必要か、その人の課題や強みは何かなどをアセスメントする心理職です。多くの非行や犯罪といわれる行動の裏側にその人の生きづらさに触れる中で問題意識が芽生え、法律を学ぶ学生に知ってほしいことや、心理学を学ぶ学生にも法律を知ってほしいという思いが出てきました。経験を教育に活かしたいと考え、2023年4月に教養学部に赴任しました」
「昨年度から行っているのは、弁護士、元検察官、出所後の支援を担う人、元受刑者、犯罪被害の当事者などの皆さんをお招きして話してもらう授業です。前回は40人定員のところ60人の応募がありました。テレビなどで見たセンセーショナルな事件をもとに犯罪を捉えている学生が多いんですが、様々な立場の人の話を聞くなかで、罪を犯した人も一人の人間であることや、ずっと罪を犯しているわけではないことに気づきます。罪を犯したら罰するべきであると思っていたのが、そう単純な話でもないと思って苦しむ。学生たちには、その苦しさを経た上で法曹になってほしいし、法学のテキストだけでは見えないものに向き合ってほしい。専門書の向こうに人生があるよというのが私のメッセージです。他人が違う考えを持っていることを前提に、心理学と社会学の両面から犯罪を捉えながら、各々が自分で考えてほしいと思っています」
――犯罪における当事者の話をじかに聞くというのはかなりしんどそうです。
当事者の肉声に圧倒されて…
「教室の空気はもちろん重いです。学生にはしんどすぎる場合は部屋から出てかまわないと伝える一方で、話してくださる気持ちを想像して、どうしても寝てしまいそうだったら休んでも構わないと釘を刺しています。犯罪に関わる自分の経験を話すことの重みについて、学生に考えてほしい。自分の話をするのは本当に大変なことなんです。ただ、私があえて言わなくても学生は皆緊張して聞いており、圧倒されて言葉が出ないことも多いようですね。一人ひとりが塀の向こう側を知ることが、世のヘイトや偏見をなくすことにつながるはずです」
「学生の多くはこれまで犯罪や非行との接点がなく、メディアで犯罪報道を見て、自分と関係のない世界だと思っているでしょう。でも、たとえば暴力を振るう非行少年は身近に感じられなくても、学校になじめないとか、友達がいないとか、親が教育にうるさすぎるといった問題なら、東大生にもピンとくるはずです」
――受験のストレスで鬱になってしまうような学生もいるでしょうね。
「人は犯罪を松葉杖として使うことがあります。周りに助けてくれる人がおらず、他に方法がなかったときに、やむなく犯罪に手を出してしまう。傷害事件や薬物依存の裏にある孤独や困りごとから自分との「連続性」を感じてほしいんです。たとえば依存は誰にも起こり得ます。依存先が薬物や酒などだと犯罪につながりがちですが、依存先が健全なものだったらそうはなりません。同じように孤独や困りごとを抱えていても、犯罪に進む人と踏みとどまる人がいます。その違いはいったい何かを自分の人生と結びつけながら考えてもらえたら、と思っています」
| 第1回 | オリエンテーション、日本の犯罪の動向、少年・成人の刑事司法の概要 |
|---|---|
| 第2回 | 施設内処遇の実際 |
| 第3-4回 | 加害者の内的世界について体感する |
| 第5-6回 | 法曹の立場から |
| 第7回 | 社会での立ち直り支援 |
| 第8回 | 社会内処遇について |
| 第9回 | 加害者家族の支援 |
| 第10回 | 犯罪学における犯罪に関する主要理論(1) |
| 第11回 | 犯罪被害者の立場から望むこと |
| 第12回 | 犯罪学における犯罪に関する主要理論(2)と再犯防止 |
| 第13回 | 振り返りとミニプレゼン |