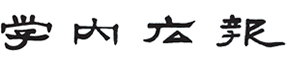第1177回

知の探求者、未来への架け橋
「研究者って発明をする人でしょ?」と六歳の娘は言う。私が研究者という仕事を娘に説明しようとしたとき、どう説明していいものか思索を巡らせた。
研究者とは、新しい知を発見し、社会に貢献する発明を行い、教育を担う存在だ。しかし、それぞれの研究者がどこに重きを置くかによって、その姿は大きく異なって見えることがある。ある人は純粋に新しい知の探求に力を注ぎ、ある人は社会課題の解決を重視し、またある人は教育に情熱を持つ。この多様な側面は対立するものではなく、むしろ相互補完的な関係にある。
確かに、研究の本質は未知の領域を切り開くことにある。量子力学でいえば、当初は理論的な探求であったものが、のちに半導体技術や情報科学の発展に結びついた例もあるように、新たな知の発見は長期的に社会に貢献する可能性を秘めている。一方で、現代の研究者は、気候変動や医療、エネルギー問題といった喫緊の社会課題の解決に資する実践的研究に取り組むことが求められている。再生医療の進展やAI技術の応用は、純粋な探求心と社会的要請の両方が相まって実現した成果の一例だ。
また、研究室は教育の場でもある。そこには学生から社会人まで多様な人々が在籍し、研究を通じて学ぶ。研究室は基本的に、数年でメンバーが入れ替わる場所であり、研究主宰者のみがいつまでもそこに残る。学生や若手研究者が成長し、それぞれの高みを目指して巣立っていくことこそが、研究室の本質であり、教育の本質でもあると感じる。
知の探求、社会貢献、教育――これらは独立したものではなく、むしろ重なり合い、補い合う関係にある。基礎研究の成果が応用研究を通じて社会に実装されることで、さらなる知的探求の可能性が広がる。
そのためには、産官学が連携し、基礎研究から生まれた知見が社会実装へと橋渡しされる形を確立することで、理論と応用が相互に発展していく好循環を生み出していくことが重要だ。政府の支援や大学の教育機関としての役割、産業界との協力が相互に作用し、新たな知識の創出と社会実装の橋渡しとなることが求められる。
研究者とは何か。その本質を表す言葉を考えると、「橋をかける人」なのかもしれない。知と知の間、理論と実践の間、教育と研究の間、過去と未来の間に橋をかける。それが研究者の使命であり、私が娘に伝えたい「研究者という仕事」なのである。
星野歩子
(先端科学技術研究センター)