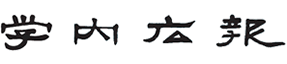第1180回

変わること
AIの研究・教育に携わっていて痛感するのは、「学ぶべきこと」が急速に変化しているということです。10年前には、ディープラーニングの出現が大きな変化をもたらしましたが、さらに生成AIの登場で様相は一変しました。言語処理やロボットなど多くの分野が急速に変化しています。技術の活用も、事前学習、事後学習というパラダイムに変わり、APIを活用したアプリ開発も容易になりました。
学生による生成AIの活用も急速に進んでいます。いろいろな人の話から総合的に推測するに、学生は社会のなかで最も生成AIを活用しているカテゴリのひとつだと思います。課題提出やテスト準備の場面で、おそらく私たち教員が気づかないほど徹底的に活用されています。オンラインテストを生成AIを使って答えるという「悪い」使い方もされていると思いますし、生成AIを使って課題提出のレポートも作成されています。さらには、それが生成AIで作ったものだとバレないような工夫も頑張っているはずです。そして、口頭試問に備えるため、レポート内容を自分に分かりやすく説明させるといった使い方もされているでしょう。あるいは、講義資料や教科書を読み込ませ、要点を自分に説明させ、分からないところについて対話することで、文章全体を読まなくても短時間で効率的に内容を掴むということも行われているはずです。
こうした学び方は、「手を抜いている」と見えるかもしれません。しかし考えてみると、政治家や経営者などの社会の重要な意思決定者は、「レク(レクチャー)」を受けることが当たり前です。会議前に担当者から要点の説明を受け、いくつか質問を交えて理解を深めます。こうした短時間での効率的な知的インプットの方法を、学生も個人で実現できるようになったと考えることもできるのではないでしょうか。学び盛りの若い時代から、こうした「レク」を自由自在に受けることができれば、科学技術全体、社会全体に対しての俯瞰的な理解、総合的な理解が我々の世代よりもずっと進むのかもしれません。
新しい技術が登場したとき、大人が「使っていい・悪い」と線を引くのは、あまり意味がないように思います。私たち自身もかつてそうであったように、若い世代は新しい技術を自然に取り入れ、自分なりのやり方で時代に合った力を身につけていきます。
そう考えると、大学もまた、変化の時代にふさわしい組織へと変わる必要があります。特にAI教育においては、学年や専攻に縛られるべきではありません。「学びたい」と思った瞬間に学べる環境を整えることが重要です。若い人が教えること、実践的であること、形式にとらわれないことも大切です。
私の研究室では、学内外のたくさんの方にご指導をいただきながら、制度の枠を超えた挑戦を続けています。AIという変化の象徴を通じて、大学全体が次の時代にふさわしい姿へと変わっていくことを願っています。
松尾 豊
(工学系研究科)