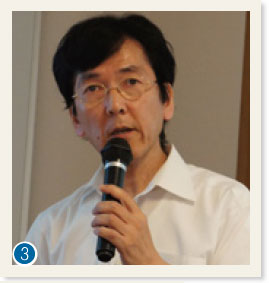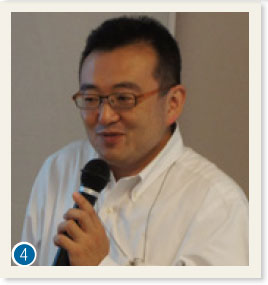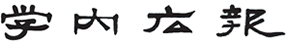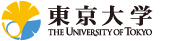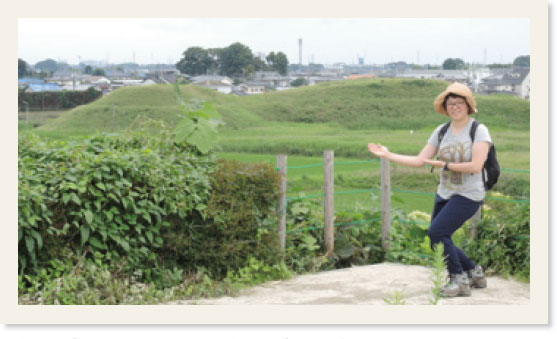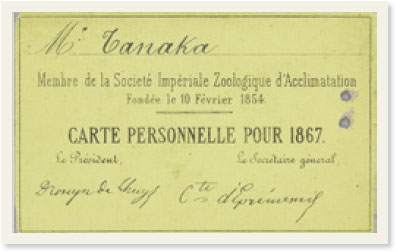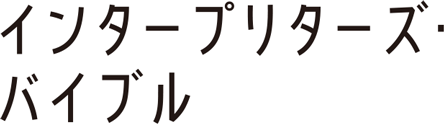創立以来、東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、次々に新しい取り組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学のすべての構成員が知っておくべき教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。
リベラル・アーツとオープンイノベーション
/産官学コンソーシアム「サステイナブル未来社会創造プラットフォーム」
教授瀬川浩司

エネルギーを機軸にして
――産官学でエネルギーを基軸に未来社会をデザインするオープンイノベーションの取組みだそうですね。
「はい。私の研究は太陽電池や再生可能エネルギーですが、パナソニックを中心としてエネルギー領域の事業を行う企業や政府関係者が集まり、産学協創推進本部が事務局となって昨年2月から勉強会を重ねてきました。そのなかで、未来社会の具体的なデザインなしにはエネルギーのマネジメントなど考えられない、という共通認識に至りました。分野を超えた取り組みで、リベラルアーツ的センスが求められるわけです。このため、建設、鉄道、自動車、エネルギーインフラ、商社、など業種をこえた企業や地方自治体にも声をかけ、昨年秋から産官学にまたがる形に広げ、産学連携の点から先端科学技術研究センター内に正式に産官学コンソーシアム事務局を置くことになりました。KOMEXの環境エネルギー科学特別部門が運営主体となります」
――勉強会とは何が違うのですか。
「議論や意見交換で終わるのではなく、実際のアクションにつなげたいという思いが強いです。企業の皆様には事業のノウハウを、自治体の皆様には実証の場をご提供いただき、段階的に検証を進めながらサステイナブル社会の実現に少しでも貢献したい。そのための仕組みとして選んだ形がコンソーシアムです。重点課題として、日本のエネルギーシステムのあるべき姿の追究と地域創生を機軸とした日本のあるべき姿の追究の2つを掲げました。賛同企業の皆様から年会費を集め、原資とします。基本はオープンイノベーションですが、知的財産権が発生した場合は発案者に帰属することを明記し、企業から参画しやすくしています」
――6月26日にはコンソーシアムの準備会合がありましたね。
「この会合は7回目の勉強会も兼ねています。今回のテーマは「地方創成とエネルギー」ですが、第一部では、内閣府地方創生推進事務局の村上敬亮審議官をお招きし、「地方創生とsuper city」の題で講演いただきました。給与を首都圏と同等にすれば地方経済はすぐ活性化する、今後は地域の生産者が生産物の価値を説明できなければいけない、社会的課題の言語化が足りない、地方創生は4年目の死の谷を乗り切ることが重要……。様々な気づきを与えていただくお話でした」
2024 年度までに社会実装を
「第二部では、地域未来社会連携研究機構長の松原宏先生と、先端研で地域共創リビングラボを展開している小泉秀樹先生に講演いただきました。松原先生は、学内で個々に進んできた地域社会連携の活動をつなげるためにできた機構の概要と、機構としての活動が進む三重や北陸での事例を紹介されました。小泉先生は、市民と自治体と企業と大学が連携して地域の課題解決を実践するリビングラボの概要と、先端研がいわき市や小布施町などで進めているリビングラボの事例について紹介されました。地域創生について、コンソーシアムが重点課題として取り組む際の重要な視座をご提供いただきました」
――今後どんな展開を考えていますか。
「今年度は現状把握と課題抽出に重きを置き、2020年度に実行計画を定めて準備を進め、2021年度に小規模実証を実施、2023年度に中規模実証、2024年度に評価・まとめを、と考えています。8月まではオープン参加の期間を設け、その後は会員登録していただいた皆様と活動を進めます。8月27日には「次世代通信5Gとエネルギー」をテーマにしたシンポジウムを、11月にはSDGsをテーマにしたシンポジウムも予定しています。私たちの今後の活動にご期待ください」