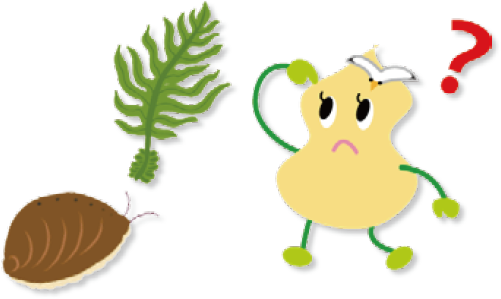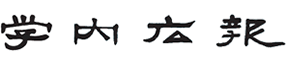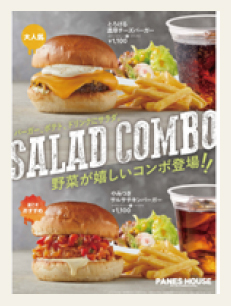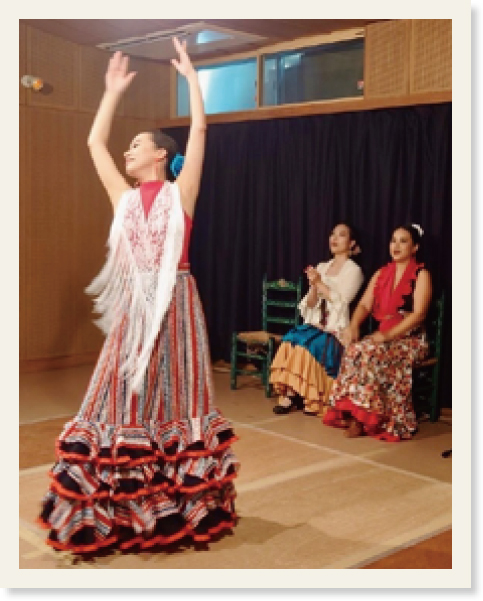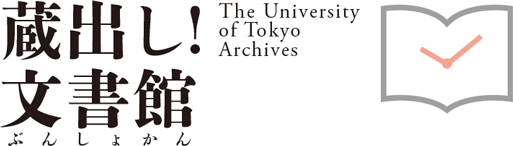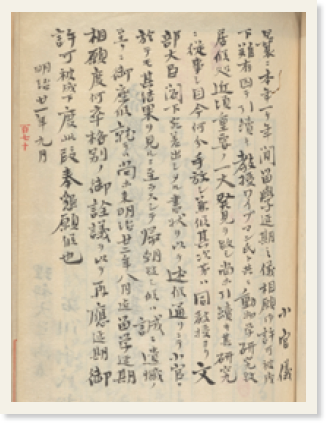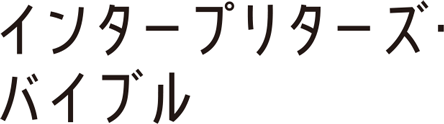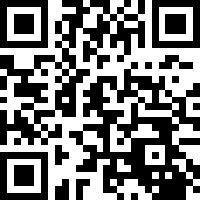第32回
大気海洋研究所と社会科学研究所が取り組む地域連携プロジェクト――海をベースにローカルアイデンティティを再構築し、地域の希望となる人材の育成を目指す文理融合型の取組み――です。東日本大震災からの復興を目的に岩手県大槌町の大気海洋研究所・大槌沿岸センターを舞台に始まった活動は、多くの共感を得て各地へ波及し始めています。
目指せ、「すくすく海洋学」!
地域連携研究部門 准教授

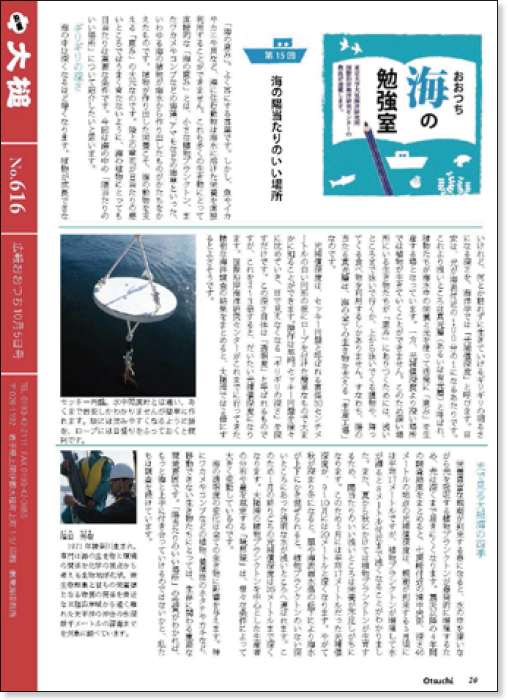
大槌沿岸センターを含む大気海洋研究所の教員たちは、研究結果や様々な取り組みを連載記事として学内の広報誌だけでなく、町の広報誌や新聞紙上にて紹介してきました。始まりは大槌町の広報誌『広報おおつち』の「おおつち 海の勉強室」でした(2014年8月~2016年3月、月1回)。センター教員内でこの話が持ち上がった時、率直に「地域の方々に活動内容を紹介できる良い機会だ」と感じましたが、それは東日本大震災の直後にあった印象的な体験と切り離せません。
私たちは震災のあった2か月後の2011年5月より大槌湾内の環境を調査していましたが、2011年の終わりごろに地域の小学校にてこれら活動の紹介を行った時のことです。高学年の生徒から「海はゴミだらけでダメになってしまったのだから、何をしても無駄」という趣旨の発言がありました。話しているうちにテレビなどで放映される津波や海底の瓦礫の映像に対するインパクトの強さから、生徒さんが想像する海の中の様子と観測結果の間には強い乖離があることが分かってきました。調査結果の発信はそれまでにも行ってきたつもりでしたが、主に漁業者に対してのものであり、一般の方が震災後の海について手に入れられる情報に比して、あまりに少ないものであることを痛感する出来事でした。
『広報おおつち』の町内の一歳児を取り上げる「すくすく赤ちゃん」のコーナーの人気は、町外の方にはおそらく想像がつかないぐらい高いものがあります。親族やご近所の赤ちゃんの愛らしい顔を探している際に私たちの記事にも目を止めてもらえば、そしていつか、同じように楽しみにしてもらえるようになれば…。
いざ、自分の出番が来て書き始めてみると、自身の専門分野が生物地球化学ということもあり、研究内容を紹介する難しさに行き当たりました。化学反応式を使わないどころか、小学校卒業までに学習する内容で理解できるように説明することは難しく、初稿を書き上げた時は、書き出しの部分で「化学が苦手な方にはちょっと難しいかもしれませんが、今回はお付き合いください」と白旗を上げるような体たらくでした。当然ながらセンターの教員から「読者に対する思いやりが全く感じられない」とのコメントをいただき、深く反省しながら書き直しましたが、今でもあの時のことを思い出すようにしています。
大気海洋研究所の教職員の連携の下、連載の舞台は『広報おおつち』から『岩手日報』の子供向け紙面「ジュニアウィークリー」、『岩手日報』本紙へと変わりましたが、現在でも研究結果だけでなく、調査などを手伝ってくれている高校生たちの取り組みなどを紹介しています。大槌沿岸センターのメンバーの中には「この間の記事は面白かったですよ」と町内で声を掛けられるものもあるとか。同僚に怒られたあの時から、私も二桁に届く回数の寄稿をしてきたものの、私自身はそのような声をかけてもらえたこともなく、「修行が足りない」と感じる日々ですが、連載自体に対する地域の方々の反響を糧に日々執筆者探しをしております。