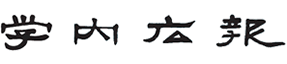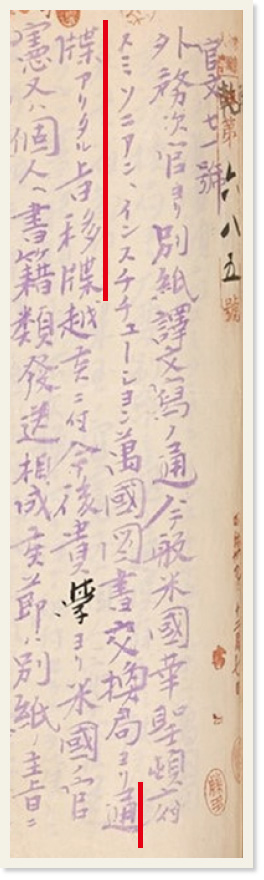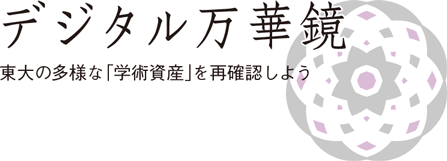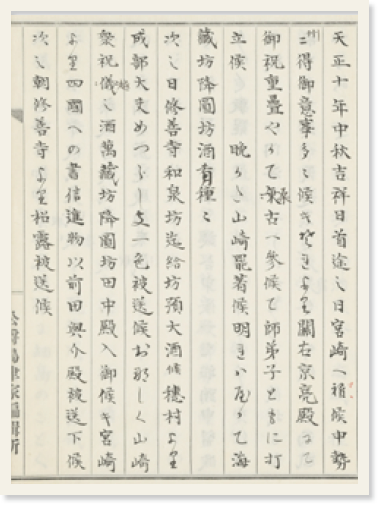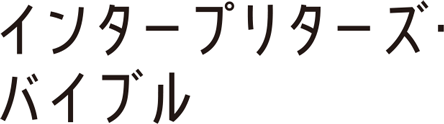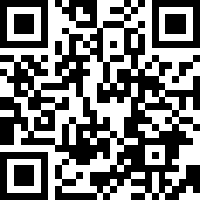第37回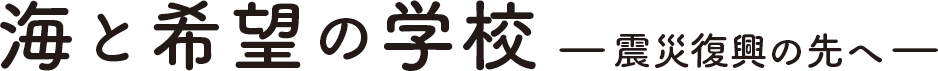
大気海洋研究所と社会科学研究所が取り組む地域連携プロジェクト――海をベースにローカルアイデンティティを再構築し、地域の希望となる人材の育成を目指す文理融合型の取組み――です。東日本大震災からの復興を目的に岩手県大槌町の大気海洋研究所・大槌沿岸センターを舞台に始まった活動は、多くの共感を得て各地へ波及し始めています。
高校生サミット in 奄美~群島をつなぐ探究学習支援の輪~
国際・地域連携研究センター
地域連携研究部門 准教授


FSI事業“亜熱帯・Kuroshio研究拠点の形成と展開”プロジェクト(第30回の記事参照)が2021年に始動し、その専任講師として大気海洋研究所に着任して以来、奄美群島の美しい自然や人情味あふれる人々に魅せられながら、研究や人材育成事業に取り組んでいます。本稿ではプロジェクトの一環として支援している、奄美群島高校探究学習コンソーシアムに関してご紹介します。
奄美群島には12市町村があり、高校は9校ありますが、それらの高校の先生や生徒たちとの話の中で、海水温上昇や赤土流出のサンゴへの被害、大雨や津波への防災対策などに関心を持ち、調査をしたいと考えている生徒がいることがわかりました。しかし、奄美群島には大学がないこともあり、具体的な研究の進め方が分からなかったり、行き詰まってしまうケースもあるようです。また、類似した研究テーマに関心を持つ生徒が各校にいるにもかかわらず、高校間での交流や意見交換の場が少ない状況にありました。
そのような中、奄美群島全体の高校をつなぎ、大学研究者と連携した探究学習の指導体制を構築する「奄美群島高校探究コンソーシアム」が2024年3月に設置されました。そのきっかけになったのは、2023年11月に大気海洋研究所が奄美大島で開催した本プロジェクトのシンポジウムでした。このシンポジウムに参加された地元の大島高校の校長が、奄美群島をフィールドに研究する多くの研究者の姿を目にされたことが大きな転機となり、コンソーシアムの設置に至りました。このコンソーシアムには、奄美群島内の高校9校、7大学、1企業が参加し、大気海洋研究所も参画機関の一つとして高校生の探究学習を支援しています。
2025年3月19日には、第2回「高校生サミット in 奄美」が大島高校で開催され、私も初めて参加しました。各校を代表する生徒たちは、「総合的な探究の時間」での研究成果を発表し、自然、文化、歴史、教育など地域の課題にアプローチしていました。テーマは多様でしたが、その根底には「自分たちの地域をより良くしたい」という熱い奄美愛(郷土愛)や強い意志が感じられました。
高校生の探究学習の成功には、生徒自身の努力は勿論のこと、地域の大人たちの支援も欠かせません。多くの地元企業が協賛し、地域サポーターとして高校生の調査取材に協力し、研究に関する助言を行い、彼らの提案を実践する場を提供しています。こうした支援があるからこそ、奄美群島高校探究コンソーシアムは成り立っています。
高校生サミット終了後、コンソーシアムに参画する大学、企業、自治体が集まり意見交換会が開かれたのですが、その会場に飾られていた掛け軸の言葉が心に残っています。それは「箪笥を売り 田を売り 家を売り 盥を売り 全てを売り貧しくても 子供を育てる」というものです。聞けば、オーナーは元中学校校長で、島外に出た(島立ちした)奄美の若者が帰郷した際に集まれる場所を作りたいと考え、定年後に店を開いたとのこと。この日の経験を通じて、奄美群島の人々の、若者の教育への熱意と地域を守り支える気概を感じました。私たちの活動を通じて、奄美群島の環境保全や地球環境を守るために取り組む若者たちが増えることを願っています。