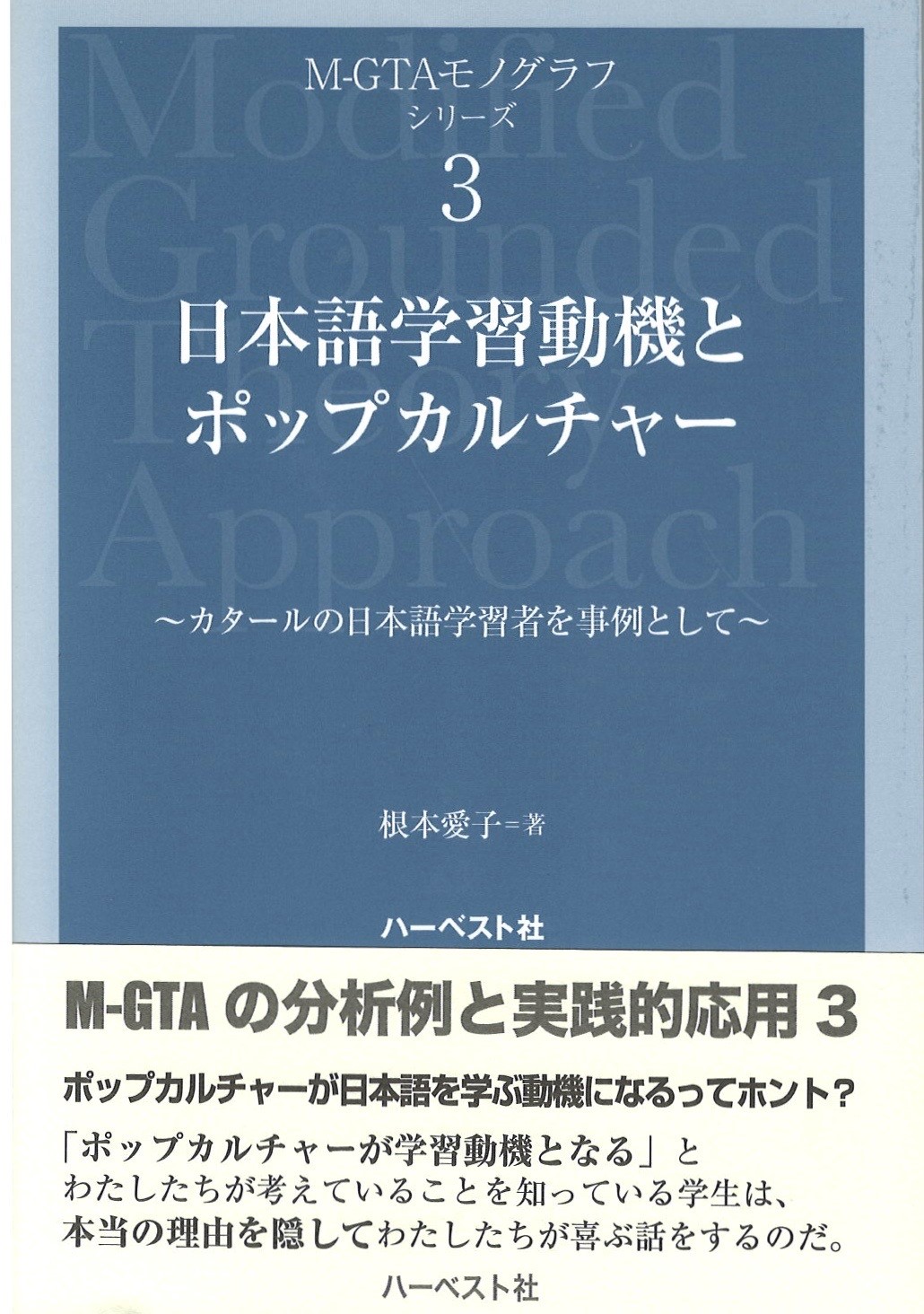
書籍名
M-GTAモノグラフ・シリーズ 3 日本語学習動機とポップカルチャー カタールの日本語学習者を事例として
判型など
191ページ
言語
日本語
発行年月日
2016年3月
ISBN コード
9784863390737
出版社
ハーベスト社
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
本書は、海外の日本語教育現場の教師が、日本語学習者の声に基づき、公的機関が想定する海外日本語教育の促進戦略、および、親日家育成のプロセスの矛盾と誤りを指摘し、促進モデルの代替案を提示した実践的研究である。筆者の博士論文を一部割愛、修正を行い、M-GTA研究会の出版助成を受け、M-GTAモノグラフシリーズの一冊として刊行されたものである。
本書は、クールジャパン政策で想定されている「ポップカルチャーをきっかけに日本に興味を持った者が、日本語学習を開始し、親日家になっていく」という図式が、現場の様子と一致しないという違和感から始まった研究である。日本のポップカルチャーが好きだとしてもその全員が日本語学習者となるわけではなく、それをきっかけに日本語学習を開始したとしてもすぐに止めてしまう学習者が少なくなかったからである。
本書の中心となるのは、ポップカルチャーを学習動機として日本語学習を「開始し、日本語講座を修了した日本語学習者たち」と「開始すると期待されている日本語学習者予備群」へのインタビューである。彼らの日本語を学習する/しないの差はどこから生まれるのか、その中でポップカルチャーはどのような役割を果たしているのかを明らかにすべく、日本との最初の接触、日本・日本語とのこれまでの関わりや興味・関心の変化などをインタビューし、そのインタビュー・データを「M-GTA (Modified Grounded Theory Approach = 修正版グラウンデッドセオリー・アプローチ)」という手法で分析している。
M-GTAとは、データに根ざした分析を基本に、主に社会的相互作用に関するオリジナル、かつ、説得力を持つ応用可能な理論を生み出す質的研究のアプローチの一つである。研究の単なる一技法ではなく、研究主体のあり方を深く問い直す態度であり、指針でもあるものでもある。
政府レベルの教育方針と現場とのズレは日本語教育だけでなく、多様な教育場面でみられることである。こうした中、現場の声・経験を研究の形で発信することは重要である。だが、その発信を「報告」ではなく「研究」とするためには、経験をいかに客観的に述べることができるか、そして、得られた知見をいかに科学的に分析するかが鍵となる。本書は、このようなフィールドが得られた筆者ならではの研究であると同時に、M-GTAを効果的に活用した例だと考えられる。また、教育領域では学習動機や学習意欲の問題は極めて重要で深刻なテーマであることから、普遍的な意義もあるといえよう。
(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 講師 根本 愛子 / 2019)
本の目次
第1章 研究の背景と目的
第2章 海外の日本語学習者と学習動機研究
第3章 調査の設計
第4章 カタール大学日本クラブ学生が日本語学習の (不) 必要性を認識するプロセス
第5章 語学教育センター修了生の日本語学習のプロセス
第6章 海外における日本語教育の今後に向けて



 書籍検索
書籍検索

