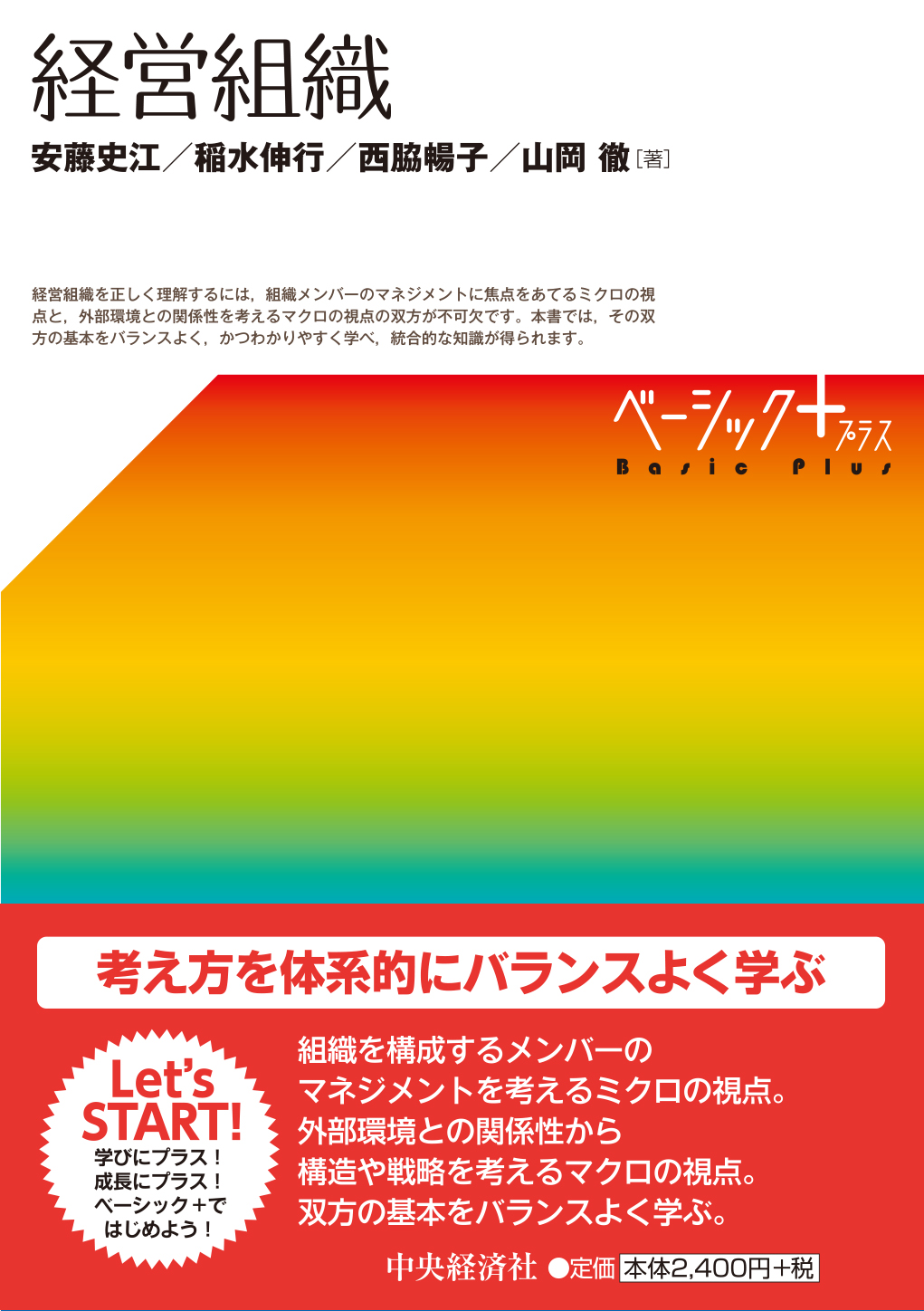私たちにとって「組織」ほど身近な存在はないでしょう。組織に全く所属していないという人はいないと思います。一方で、組織ほど捉えどころがない存在も他にはないでしょう。優秀な人が何人も集まっているにも関わらず成果を上げられない組織もあれば、凡人の集まりにも関わらず目を見張る業績をあげる組織もあります。このような結果を導く組織とはどのようなものでしょうか。また、そうした組織の中で一人一人がよりよく生きるためにはどうすればいいのでしょうか。こうした課題に取り組むのが経営組織論です。
本書は、経営組織論の新しい教科書です。組織を構成するメンバーのマネジメントを考えるミクロの視点と、外部環境との関係性から組織の構造や戦略を考えるマクロの視点の両方をバランスよく学べる構成となっています。また、これだけ動きの激しい世の中にあって、組織も変わっていかなくてはなりません。組織の変革やダイナミズムにも多くの紙幅を割いている点は類書にない特長です。そして、各章の冒頭には、経営の現場を彷彿とさせるエピソードを載せることで、読者の学習意欲を喚起させるとともに、机上の空論で終わらせない配慮もされています。
例えば、私が執筆を担当した章の冒頭のエピソードは次のような感じです。
「今朝、新聞を何気なく眺めていると、友人Aの勤める企業Xが海外市場の開拓に成功して業績好調との見出しが目に入った。記事の詳細を読んでみると、数年前に経営トップが下した意思決定が先見の明のあるもので、それが今期の成功に結びついているらしい。…関連情報を集めてみたところ、確かに合理的な意思決定の結果、成果を出しているという分析をしているものが多い。…その翌週、たまたま友人Aと会食する機会があり、『お前の会社のトップはすごいな。あんなに理詰めで戦略を立てて意思決定をするなんて、なかなかできないぞ』と話を振ったところ、友人A曰く内実は少し違うらしい。…そこに至るまでには紆余曲折があったようである。もともと狙って作った商品は重要な問題を見過ごしていて全く売れず、試行錯誤しているうちに、たまたま別の試供品を思ってもみなかった使い方をしている場面に遭遇し、それにヒントを得て、製品開発を進めたのだという。そこで、方向性が見えてきたので、それに沿って資源を投入してもらって、ようやく成功の道筋が見えてきたということだ。…確かに、経営トップやマネジャーが合理的に意思決定をすることができた方がいい。けれども、企業を取り巻く状況は日々変化しているし、考慮しないといけないことも多い。むしろ、現実の組織の意思決定は混沌としていて、偶然・たまたまということの連続かもしれない。こうした中で少しでも良い意思決定をしていくためにはどうすればいいのだろうか。」
この続きが気になる方は、是非本書を手に取ってみてください。
(紹介文執筆者: 経済学研究科・経済学部 准教授 稲水 伸行 / 2021)
本の目次
第1章 組織とは何か(西脇)
第2章 組織の基礎理論(西脇)
第3章 組織構造と組織デザイン(西脇)
第II部 内部組織のマネジメント
第4章 組織におけるモチベーション(山岡)
第5章 集団力学(安藤)
第6章 組織の意思決定(稲水)
第7章 組織と環境(稲水)
第III部 組織内外のダイナミクス(うごめいている組織)
第8章 組織構造のダイナミクス(稲水)
第9章 組織間関係(安藤)
第10章 組織変革の捉え方(山岡)
第11章 組織変革の進め方(安藤)
第12章 組織のパラドックス(山岡)
第13章 流されず、しなやかに(安藤)



 書籍検索
書籍検索