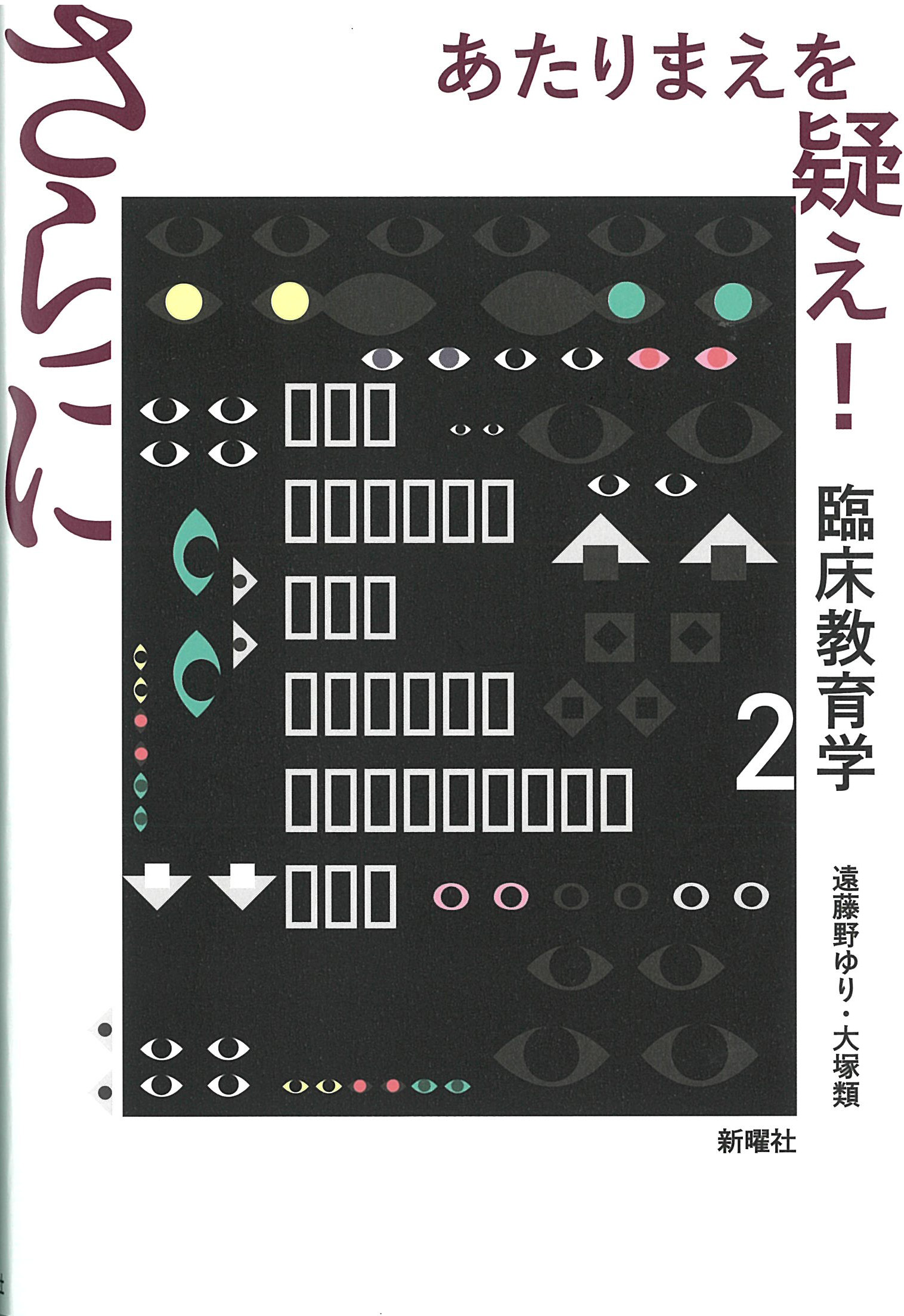
書籍名
臨床教育学2 さらにあたりまえを疑え!
判型など
200ページ、四六判
言語
日本語
発行年月日
2020年1月27日
ISBN コード
9784788516656
出版社
新曜社
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
私たちは、無意識のうちにありとあらゆる場面で、「〇〇はあたりまえだ」という枠組みでものごとを考えている。そしてその枠組みは、「他のみんなもそれをあたりまえだと思っている (に違いない)」という信念になっている。だからこそその枠組みを疑うことが、教育や人間のあり方についての問題を考えることになる。本書に通底しているのは、この3つの観点です。
現象学者のマルティン・ハイデガーが「世間 (das Man, the man)」という卓抜した言葉で表現しているとおり、世間の一員でいることで、つまり、「みんな」と一緒に「ふつう」に「あたりまえ」でいることで、私たちは安心して生活できています。他方で、「世間体が悪い」という言葉があるように、「みんな」「ふつう」「あたりまえ」から逸脱することは、「世間」からの非難や攻撃にさらされることでもあります。
COVID-19に関連した誹謗中傷のニュースを、みなさんもどこかで目や耳にしたことでしょう。「〇〇はあたりまえだ」という信念は、このように時として、そこから逸脱する他者への攻撃を正当化します。しかし例えば、田舎に帰省した人や、感染者や、マスクを着用せずに外出した人々それぞれの背景を知ったら、攻撃や非難などできなくなるかもしれません。さらに、この信念は、そこから逸脱する他者だけではなく、自分自身への攻撃をも正当化します。「みんな」が「あたりまえ」にできている「ひと (世間) 並み」のことさえ私はできない、と自分自身を責めたり嫌いになったりした経験があるひともいるでしょう。でも、この信念に基づいて他者や自分自身を攻撃する前に、立ち止まって自分に問うてみてください。「それって本当に『みんな』がそうしている『ふつう』で『あたりまえ』のことなの?」、と。
「ふつう」「あたりまえ」の呪縛から抜け出すためには、新たな知識と視点が必要になります。そこで本書の各章は、臨床教育的なトピックを一つ取り上げ、そのトピックに関する基礎知識を確認し (第1節)、そのトピックを見直す視点を提示し (第2節)、そのうえでそれについて再考する (第3節) という構造になっています。トピックを再考するための視点は、現象学という哲学から得ています。現象学は、「すべてのものごとは私たちにとっての <現われ (現象)> にすぎない」という立場をとります。現象学的には、私たちが体験することは客観的な「事実」ではなく、主観的な「現われ」の一つになります。したがって、「みんな」も「ふつう」も「あたりまえ」も、「私にとって」「〇〇さんにとって」という条件が付いて相対化されます。
「あたりまえ」を疑って従来とは異なる考え方ができるようになれば、「ふつう」「あたりまえ」から逸脱してしまう他者や自分自身を受容できるようになるはずです。「今までどうして気づかなかったんだろう」と驚くような、自己と他者と世界の再構成が起きること、すべてが新たに違って見えること。このような新しい体験を、本書では「学び」と呼びます。
(紹介文執筆者: 教育学研究科・教育学部 准教授 大塚 類 / 2020)
本の目次
序 章 「さらにあたりまえを疑う」とは?──この世界の存在の基盤としての「ふつう」
第I部 家族のあり方
第1章 家族の形──イメージではなくデータで確かめる (遠藤野ゆり)
第2章 家庭教育──世界と他者を信頼して生きる基盤 (遠藤野ゆり)
第3章 児童虐待──名づけることの功罪 (大塚 類)
第II部 他者とのかかわり
第4章 つながり孤独──SNS時代の人間関係 (大塚 類)
第5章 いじめ──雰囲気を共に生きる (大塚 類)
第6章 恋 愛──可能性を生きる存在 (遠藤野ゆり)
第7章 傾 聴──自他の声を聴く (大塚 類)
第III部 自己との向き合い
第8章 不登校──物語が自己をつくる (遠藤野ゆり)
第9章 発達障害──多様に豊かに認知する (遠藤野ゆり)
第10章 キャリア形成──自分の人生を引き受けて生きる (遠藤野ゆり)
終 章 あたりまえを疑う意義──感情移入で自分の枠を拡げる (大塚 類)
あとがき
索 引



 書籍検索
書籍検索

