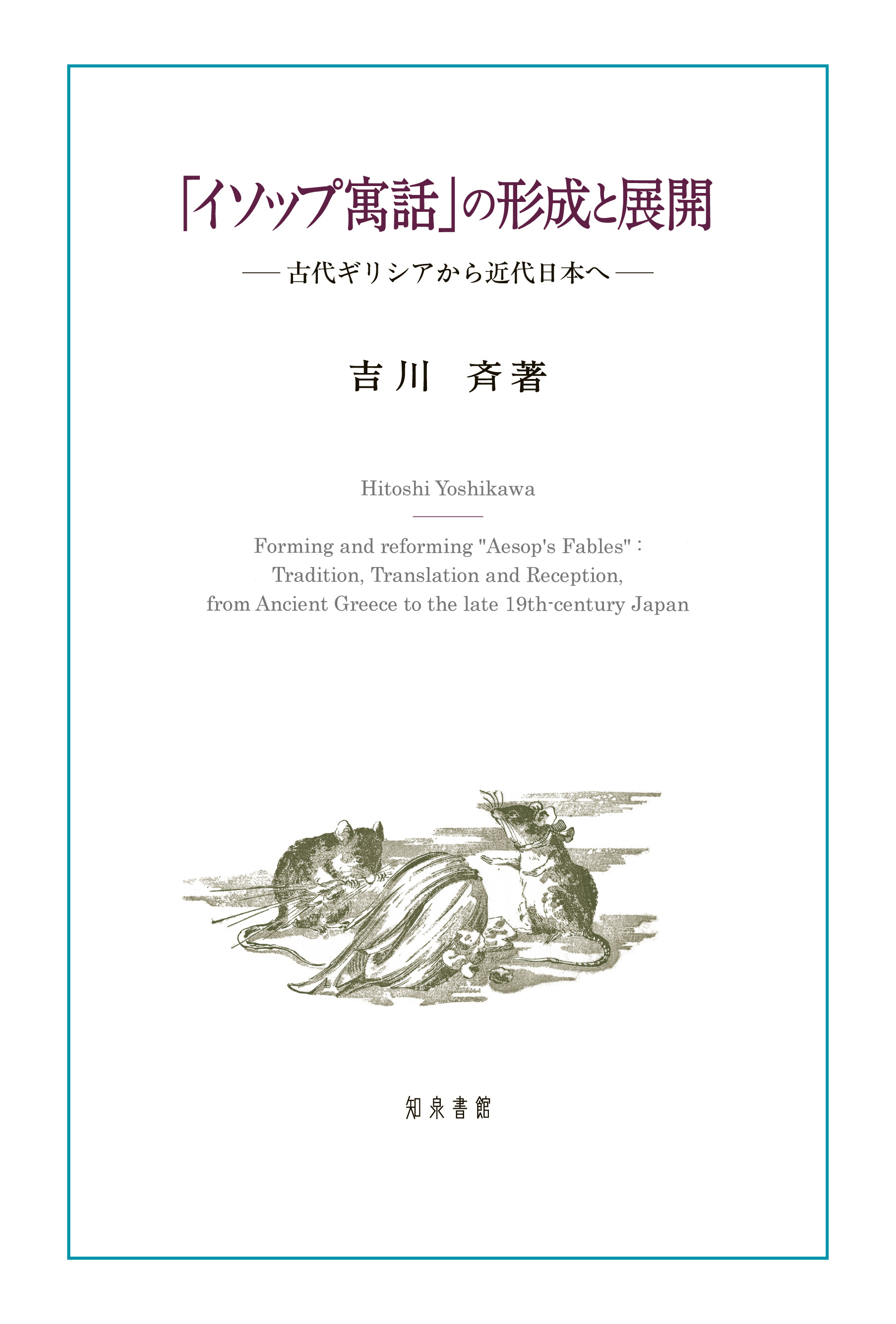
書籍名
「イソップ寓話」の形成と展開 古代ギリシアから近代日本へ
判型など
374ページ、菊判
言語
日本語
発行年月日
2020年1月25日
ISBN コード
9784862853103
出版社
知泉書館
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
本書が主題とする「イソップ寓話」は、日本に伝わった西洋古典素材として歴史が長く、16世紀後半以来近現代に至るまで、日本に様々な形で溶け込んでいます。たとえば現在では誰であれ、「兎と亀」「蟻とキリギリス」などの話はどこかで目や耳にしたことがあるのではないでしょうか。身近にありながら、それが何かを意外と知らない、筆者は日本におけるそのような西洋古典素材の在り方に関心を抱き、研究の対象としてきました。本書は、筆者の博士論文を加筆修正した7章に、学位取得後の論文に基づく2章と書き下ろしの1章を加えたもので、2部10章からなります。書名のとおり、古代ギリシアから近代日本に至る「イソップ寓話」の形成と展開に説明を加えることを目標として、文献学的研究や受容研究など、多岐にわたる内容を含みます。
本書のひとつの仕掛けとして、「寓話」をジャンルとしてではなく、話の「読み方」(話から何か一般的な教訓を読み解く姿勢) とみなす点を挙げられます。この場合、「イソップ寓話」とは、イソップの名を冠する「イソップの話」に「寓話」としての性質が付与されたものであり、「イソップの話」という話の枠組みが先行します。また、イソップは古代ギリシアに存在したとされる人物の名ではありますが、「イソップの話」においては、話の作者名ではなく、ある種の話の集合を示すための一種の看板に過ぎません。
本書第1部では、とくに「イソップ」という枠組みに注目し、古代ギリシア・ローマの作家たちが使用するイソップ関係の用例の分析を積み重ね、イソップの名が附される話の集合に関して、その枠組みの形成と変質から、「イソップ寓話」の形成を論じています。なかでも、アリストテレス『弁論術』および1世紀頃の修辞学者テオン『修辞学初等教程』(Progymnasmata) が示す議論を重視します。いずれの議論も一定の基準を満たした話を「イソップ」の名のもとに集める枠組みとして機能し、とくに後者の議論では、個々の話を独立したものとして評価し、教訓的意味の読み取りを要件とします。1世紀頃から「イソップの話」に関するジャンル意識が明確化することもふまえ、本書ではテオンの議論を後世に拡がる「イソップ寓話」の基点と考えます。
本書第2部では、西洋および近代日本におけるイソップ集の受容と展開を扱っています。イソップ集とは「イソップの話」を集めたものですが、話の体裁として「イソップ寓話」としての在り方が一般化しており、いわば「イソップ寓話」の展開を扱う議論となります。とくに第9章、第10章では、明治初期刊行の渡部温『通俗伊蘇普物語』を中心に、近代日本 (おもに明治期) におけるイソップ集の在り方、そして当時の初等教育に注目しています。本書の議論によって、西洋古代に発する対象が、どのようにして私たちのもとに至り、日本社会に溶け込むことになったのか、その一端を多少なりと明らかにできていれば、と願うばかりです。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 助教 吉川 斉 / 2021)
本の目次
1 はじめに
2 古代の「イソップの話」
3 日本の「イソップの話」
4 「イソップ寓話」の取り扱い
5 本書について
第1部 形成――古代イソップ論
第1章 古代ギリシア・アルカイック期――ヘシオドスとアルキロコス
1 はじめに
2 「イソップ」の年代設定
3 ヘシオドス
4 アルキロコス
5 おわりに――後世のイソップ集の場合
第2章 古代ギリシア・古典期――アリストファネスとプラトン
1 アリストファネス
2 プラトン
3 その他の用例
4 おわりに――古典期の「イソップの話」
第3章 古代ギリシアからローマへ――アリストテレスとその影響
1 アリストテレスと「イソップの話」
2 前1世紀頃までの用例
3 「身体と胃袋の話」にみるアリストテレスの影響
4 おわりに―『弁論術』と「イソップの話」
第4章 ローマ帝政期――修辞学教育とその周辺
1 テオンのミュートス論
2 クインティリアヌス
3 2世紀頃の用例
4 ジャンル意識の形成
5 おわりに――「格言」と「イソップの話」
第5章 古代のイソップ集――ファエドルスとバブリオス
1 1世紀までのイソップ集
2 編者について
3 編者の認識
4 編者と集成
5 おわりに――古代のイソップ集と編者
第2部 展開――西洋から近代日本へ
第6章 アトス写本とイソップ受容――バブリオス集の受容と変質
1 はじめに
2 バブリオスの受容と展開
3 『修辞学初等教程』におけるミュートス
4 アトス写本後辞と編者
5 おわりに
第7章 1505年刊行アルドゥス本のラテン語翻訳
1 はじめに
2 15世紀のラテン語翻訳イソップ集
3 各種ラテン語版の比較検討
4 アルドゥスにおける「翻訳」の信頼性
5 おわりに
第8章 19世紀英国の翻訳イソップ集――「蛙と牛」における母蛙の怒り
1 はじめに
2 「蛙と牛」の話
3 翻訳の原典について
4 19世紀以前の英語版「蛙と牛」
5 「牧草地で草を食む牛」
6 おわりに
第9章 「犬とその影」にみる近代日本イソップ受容
1 はじめに
2 明治初期の「犬とその影」
3 古代の「犬とその影」
4 ジェームズとタウンゼントの参照元
5 再読――明治初期の「犬とその影」
6 おわりに
第10章 近代日本のイソップ受容と初等教育
1 はじめに
2 幕末・明治初期の新聞
3 福沢諭吉『童蒙をしへ草』
4 渡部温『通俗伊蘇普物語』
5 福沢英之助『訓蒙話草』
6 初等教育とイソップ受容
7 おわりに――『通俗伊蘇普物語』普及と出版広告
終章 その後の展開から――接続する「イソップ|寓話」
1 上田万年『新訳伊蘇普物語』
2 上田敏『伊曽保物語考』
3 村田宇一郎『小学実際的教授法』『単級修身教授の実際』
4 「寓話」の拡がりと「イソップ寓話」
あとがき
図版出典
参考文献
索引
欧文目次



 書籍検索
書籍検索

