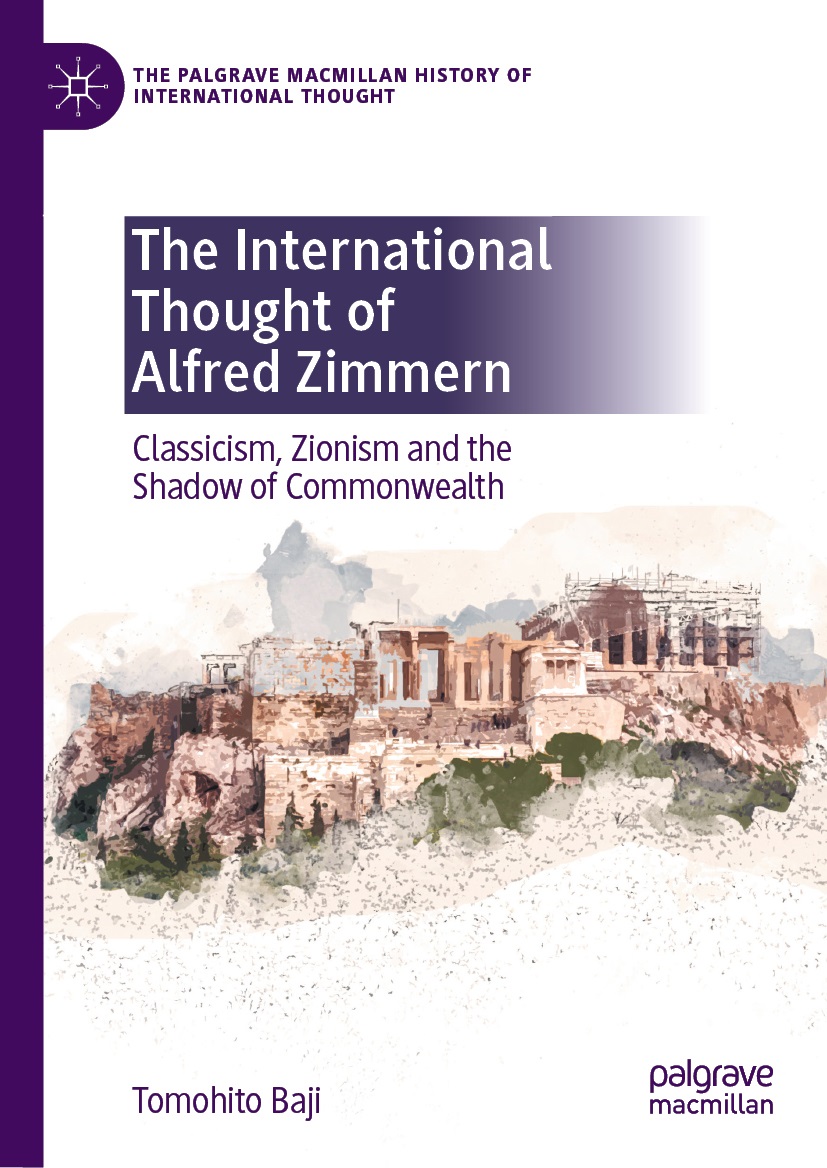
書籍名
Palgrave Macmillan History of International Thought The International Thought of Alfred Zimmern Classicism, Zionism and the Shadow of Commonwealth
判型など
232ページ
言語
英語
発行年月日
2021年
出版社
Palgrave Macmillan
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
国際関係論という学問分野は、どのような知的・政治的文脈において創始されたのだろうか。従来この問いに対し、国際関係論は平和を探求するため、凄惨な第一次世界大戦直後に樹立されたという認識が持たれてきた。この認識は完全に間違いではない。確かに世界最初の国際関係論講座は大戦直後の1919年に、イギリス・ウェールズ大学のアベリストウィス校に設置された (ウッドロー・ウィルソン国際政治学講座)。しかし、それが国際関係論の起源であったかというと、必ずしもそうではない。国際関係を語る学知や言説は、より幅広く、同時代の多彩な分野や実践の中に存在し、そうしたアカデミア内外における様々な理論・思想が後年徐々に国際関係論という学術としてまとまりを持ち始めたと考える方が適切だからである。
本書はそのような国際関係論の複雑な起源の一端を、政治思想史の観点から明らかにしようとするものである。同時にそれは、20世紀前半イギリスの政治・社会思想の一側面を国際関係という視点から照らし出す試みでもある。
このような目的のため、本書が主に分析対象とするのは、アルフレッド・ジマーン (Alfred Zimmern, 1879-1957) という人物の諸著作――出版された著書・論文に加えて、アーカイヴ調査を踏まえての未公刊のエッセイや手紙なども含む――である。ジマーンは、1911年にThe Greek Commonwealthという本を刊行したギリシャ古典学者であり、当時イギリス帝国の再編を画策していたラウンド・テーブル運動における指導的人物の一人であり、さらにシオニズムに一定程度関わっていた人物であった。その彼が、1919年上述のウッドロー・ウィルソン国際政治学講座初代教授に任命されることになる。また彼はその後、オックスフォード大学に新設されたモンタギュー・バートン国際関係論講座の初代教授も務めることになる。古典学や帝国再編運動、シオニズムから出発し、草創期の国際関係論を担うに至ったジマーンの軌跡自体が、まさにこの学問分野の起源の複雑さの一端を示していると言える。加えて、ジマーンは戦間期に国際連盟下の知的協力事業を推進し、第二次大戦時にはUNESCOの設計にも携わることになる。
本書は、これまでヴェールに包まれてきたジマーンの知的軌跡を丹念に辿りながら、20世紀前半の国際関係をめぐる錯綜した思想や言説の独特な一側面を明らかにしている。国際関係について語ることは、単に戦争や平和について語ることではなく、帝国構想や植民地統治、人種主義、政治的・文化的ナショナリズム、さらには古代世界との知的往還関係などと結びついた、一層複雑で、ときに戦争をも希求するアンビヴァレントな現象であった。これを「リアリズム対アイディアリズム」といった草創期国際関係論についてしばしば持ち出される単純な図式へ還元するのは困難である。
国際関係論、政治思想史二つの学術領域に跨る本書が、これら両者に、あるいはいずれかに、関心のある方の目に触れられれば嬉しく思う。
(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 准教授 馬路 智仁 / 2021)
本の目次
1. Introduction: An Apostle of Commonwealth
Tomohito Baji
2. Empire and Classical Republicanism
Tomohito Baji
3. Zionist Internationalism
Tomohito Baji
4. A Turn: From Global Reformism to Euro-Atlanticism
Tomohito Baji
5. Nuclear One-Worldism
Tomohito Baji
6. Epilogue
Tomohito Baji
Back Matter
関連情報
Benjamin Whitlock 評 (『The Round Table』vol.110, Issue 5 628-629ページ 2021年11月)
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00



 書籍検索
書籍検索

