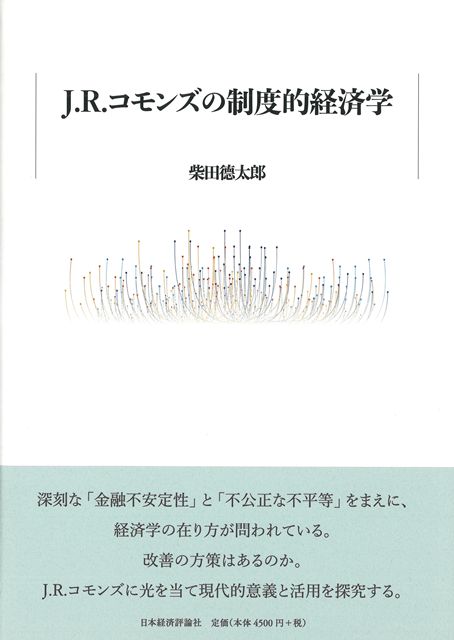
書籍名
J.R.コモンズの制度的経済学
判型など
310ページ、A5判
言語
日本語
発行年月日
2021年10月
ISBN コード
9784818825925
出版社
日本経済評論社
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
J.R.コモンズ (1862-1945) は、T.ヴェブレンと並び称されるアメリカ制度学派の巨頭であるが、彼の理論の独自性はこれまで正当に評価されてこなかった。本書は、こうした低評価を打破すべく、コモンズ制度的経済学のユニークな魅力に迫っている。
人間は「合理性の限界」と「根源的不確実性」という2つの問題に直面している。それゆえ、未来の予測が困難となる。人間は神ではないからである。これがコモンズの人間観である。そこで、人間は「慣習」に依存して行動する。そして、共有される「慣習」が「制度」なのである。では「制度」とは何か。「制度」とは「個人行動を制御し、解放し、拡大する集合行為」である。例えば、私有財産を守る法制度は、他人の財産を奪う自由を禁止することによって、個人の経済活動の自由を拡大するという役割を果たしている。つまり、制度は「合理性の限界」と「不確実性」に直面する我々人間に「義務の調和」を通じて「期待の一致」を保証するものなのである。利害の異なる多様な諸集団間での「義務の調和」によって、公共目的に資する制度が生まれ進化する。
「私有財産制」の進化は資本主義の発展を支え、促進した。「私有財産」の定義は、「有体財産」から債権を表す「無体財産」へ、そして「無形財産」へと拡張されていった。この「無体財産」と「無形財産」は、コモンズ制度進化論の核心を成す概念である。両者は、対照的な性格を帯びている。前者は債権者と債務者の関係であり、権利-義務関係である。法的に強制が可能な契約であり、債権者は無体財産を保有する。この無体財産は負担の法の下にある。債権者は時の経過に伴いあらかじめ決められた (債務者による) 債務支払いから生じる貨幣収入をあてにすることができる。後者は、販売 (生産) 者と購入者の関係で、「自由とリスク」の関係である。販売者は無形財産を保有し、無形財産は機会の法の下にある。無形財産保有者は、将来の不確実な生産物の売却 (他者による生産物の購入) から生じる貨幣収入を期待する。前者は確実な財産であり、後者は不確実な財産である。
現代資本主義の取引を構成するこの2つの財産の性格の違いから景気循環の振幅拡大が生まれる。それは何故か。物価の変動が2種類の対照的な財産価値に異なる影響を与えるからである。物価の上昇は無形財産価値を増価させるが、無体財産価値は変化しない。その結果、実質債務負担が低下し、債務に依存した投資が拡大する。物価の下落は無形財産価値を減価させるが、無体財産価値は変化しない。その結果、実質債務負担が増加し、債務に依存する投資は削減される。物価 (名目価格) の変動が実質債務負担の逆方向への変動をもたらし、バブルの形成と崩壊による景気循環の振幅拡大と金融の不安定化が生み出される。
この金融不安定化を抑制するため、安定化の集合行為が生成する。その第1が中央銀行の協調行動であり、第2が無形財産価値の保護育成である。無形財産価値の健全な増進が、長期的な経済発展の原動力であるからである。このように、コモンズ制度的経済学の独自性は、法政治経済学的アプローチにあるといえよう。
(紹介文執筆者: 経済学研究科・経済学部 名誉教授 柴田 德太郎 / 2024)
本の目次
第1章 プラグマティズムの人間像:習慣から慣習へ
第2章 制度の生成と進化
第3章 私有財産制度の進化
第4章 コモンズの景気循環論
第5章 コモンズの安定化論
第6章 コモンズ制度的経済学の全体像
終 章 コモンズ制度的経済学とは何であったか?
補論1 「見えざる手」と「コンヴェンション」
補論2 表券貨幣説・MMT・制度的経済学
関連情報
高 哲男 (九州大学名誉教授) 評 (『経済学史研究』64巻2号 2023年1月25日)m
https://doi.org/10.5362/jshet.64.2_106
松原隆一郎 評「今週の本棚 2021年「この3冊」 (『毎日新聞』 2021年12月18日)
https://mainichi.jp/articles/20211218/ddm/015/070/013000c
関連記事:
柴田德太郎「なぜ、今、J・R・コモンズなのか?」 (『評論』224号 2022年4月30日)
http://www.nikkeihyo.co.jp/critiques/view/404



 書籍検索
書籍検索

