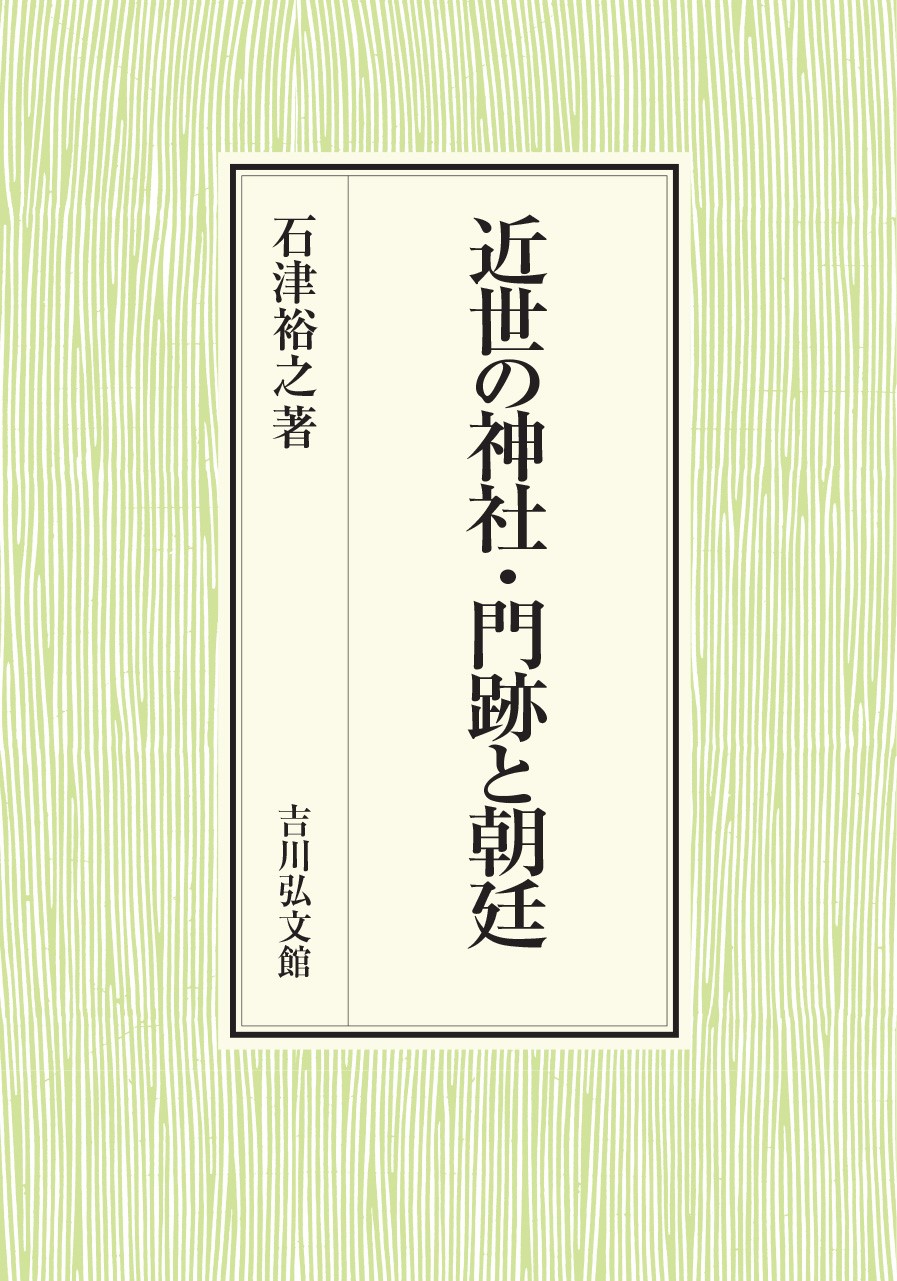
書籍名
近世の神社・門跡と朝廷
判型など
376ページ、A5判
言語
日本語
発行年月日
2024年2月22日
ISBN コード
9784642043618
出版社
吉川弘文館
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
本書は、近世における神社・門跡・朝廷の三者の関わりを論じることで、三者の中でも特に神社と門跡の姿を明らかにしようとしたものである。
第一部では、朝廷との関係という視点から近世における神社の動向を論じた。論点としたのは、神社伝奏と二十二社の二つである。神社伝奏とは、神社と朝廷を取り次ぐメッセンジャーの役割を果たした公家のことである。従来、どの神社をどの公家が担当するかは固定しているとの説が主流であったが、京都に鎮座する北野社 (北野天満宮) について検討を加えた結果、公家側の意向と神社側の意向が絡まる中で神社伝奏を務める公家が変化していた事実を見出した。また、二十二社とは、朝廷より尊崇を受けた二十二の神社のことであるが、二十二社と朝廷の関係は自明視されがちであり、その関係の中で二十二社がいかなる動向を見せていたかについては、踏み込んだ検討が殆どなされてこなかった。二十二社の一つである北野社について分析したところ、近世後期に祭神菅原道真の遠忌法会が初めて勅会として開催されたことを理由とし、北野社が二十二社内での社格を上昇させようと朝廷に働きかけていた事実を明らかにした。
第二部では、近世朝廷で実施されていた門跡に対する統制を検証し、その統制が門跡の動向や存在形態に与えた影響について考察した。門跡とは、天皇・世襲親王家・摂家などの男子が入寺する格式の高い寺院、もしくはその人=門主のことであり、門主の出自に応じて宮門跡・摂家門跡といった格式があった。門跡は、朝廷の一員として朝廷執行部 (門跡を含む朝廷全体の統制を担った関白といった重職の公家) の統制下にあり、当該統制は門跡の存在形態や動向を規定していたといえるが、その具体的な様相は不明瞭な部分が多かった。かかる問題意識に基づき、朝廷執行部による監督の下で宮門跡の相続 (門主の代替わり) はどのように実施されていたのか、朝廷執行部と門跡の取次を担うことで朝廷執行部による門跡統制を実務面で支えた肝煎や御世話人と呼ばれた公家はどのような在り方をしていたのかといった点を解明した。
第三部では、神社と門跡がいかなる関係を有していたかを検討することで、これまで知られていなかった近世における神社と門跡の様相を照射した。神仏習合状態にあった近世には、神社と門跡の間にも一定の関係が取り結ばれていたが、その関係の具体相はこれまで殆ど明らかにされてこなかった。かかる研究状況を踏まえ、北野社と曼殊院門跡の事例などを対象とし、各事例に見られる神社と門跡の関係を分析した。その結果、門跡が補任権や装束着用許可権の掌握を通じて神社構成員の存在形態に深く関与していたことや、神社伝奏の公家と同様、門跡も神社と朝廷の関係を媒介していたことなどを明らかにした。
一見すると関わりを有していたとは想像しがたい近世の神社・門跡・朝廷の三者であるが、実は、上で説明したように複雑な関係を取り結びつつ存在していた。その関係を丹念に解きほぐしつつ、三者それぞれの動向や存在形態を照射したのが本書である。
(紹介文執筆者: 史料編纂所 准教授 石津 裕之 / 2025)
本の目次
第一部 朝廷との関係をめぐる神社の動向
第一章 近世の神社伝奏と神社―北野社を事例として―
第二章 近世中後期の二十二社と朝廷―北野社を事例として―
第二部 朝廷執行部による統制と門跡
第一章 近世中期における宮門跡の相続
第二章 宮門跡の肝煎
第三章 宮門跡の御世話人
第四章 近世僧位僧官の叙任経路をめぐる諸動向―北野社を事例として―
第三部 神社と門跡の関係
第一章 神社・門跡・社僧―宮寺としての近世北野社―
第二章 近世の祇園社と青蓮院・妙法院
補論 近世の石清水八幡宮と門跡
終章 近世における神社・門跡・朝廷の関係史
あとがき
初出一覧
索引



 書籍検索
書籍検索


 eBook
eBook