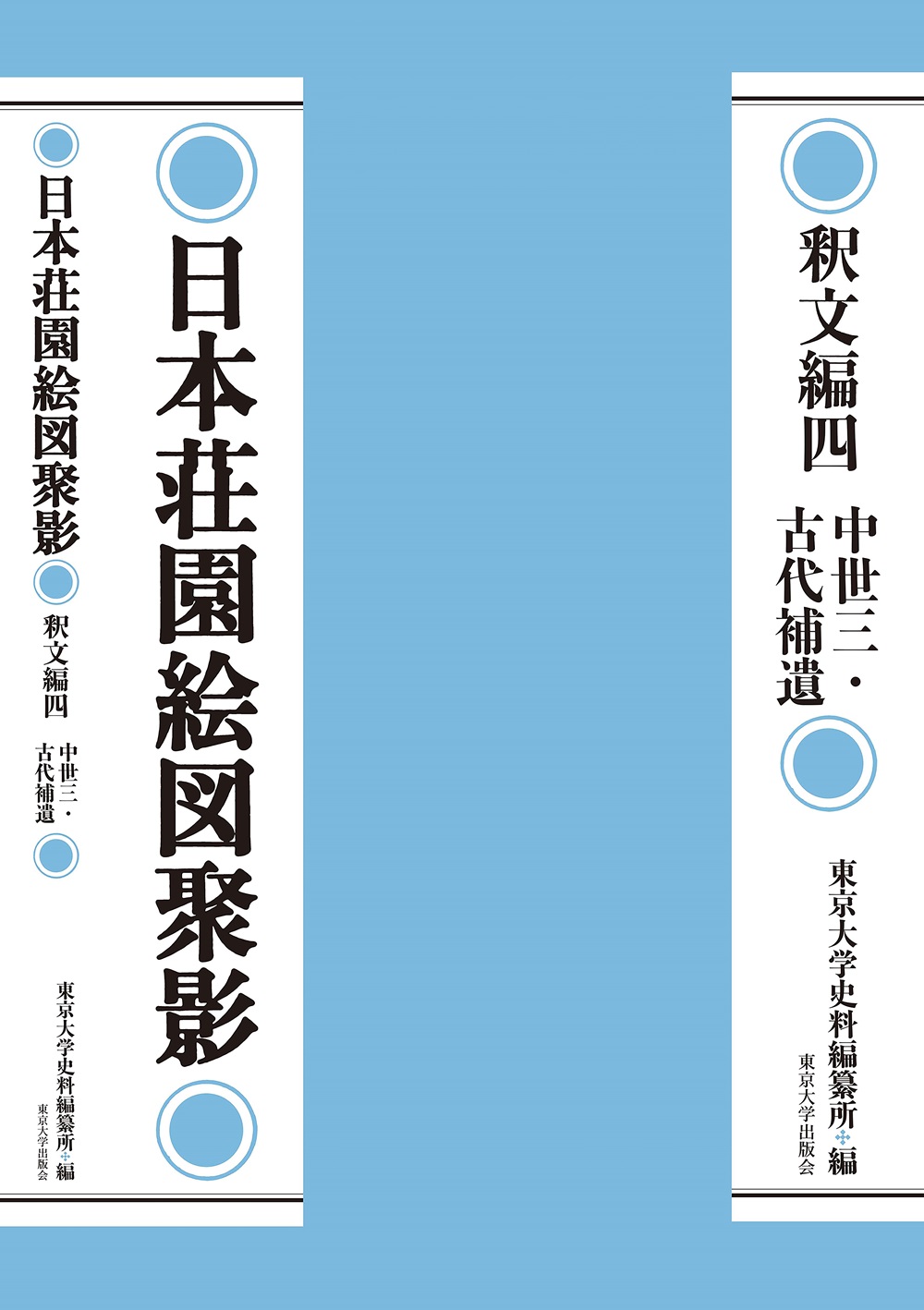
書籍名
日本荘園絵図聚影 釈文編四 中世三・古代補遺
判型など
330ページ
言語
日本語
発行年月日
2024年4月19日
ISBN コード
978-4-13-092830-4
出版社
東京大学出版会
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
史料編纂所では、1890年に内務省の地誌編纂事業が移管されたことから、その蔵書等を引継ぎ、長らく歴史地理の研究分野を設置しています。『日本荘園絵図聚影』は、古代・中世の古絵図を大型図版にて集成するシリーズで、1988年に最初の冊が刊行され、2002年に7冊で完結しました。A3判の帙 (ケース) に、大きいものは二つ折り (つまりA2判) のプレートとして、その多数は新規撮影による写真を収めています。原本自体が大きな場合は、複数のプレートに写真を分割しています。メインの写真はモノクロで安定性を意図し、コロタイプ印刷という精細な技法により、彩色などがあればカラー図版を加えています。大きなテーブルでないと広げられず、気軽にお手に取って頂くことはできませんが、基礎資料集の存在感を感じ取れるでしょう。
ここに採録された絵図は約300点。大きく2グループからなり、正倉院宝物に含まれる奈良時代の荘園図と、12世紀頃から原本が残るようになる中世荘園図が含まれています。荘園は土地支配の制度ですが、ここでは土地の領有や利用に関わる情報を備えた図 (線描を伴い文字の配置に意味がある図面) を緩やかに指し、絵画的表現を伴うことも多いことから、荘園絵図と呼んでいます。寺社の境内のみを描いた絵図や、ごく狭い敷地や建築の指図 (平面図) は除外しており、8~16世紀の日本は、世界的にも古地図が豊富に残る地域と分かります。代表的な荘園絵図は、院政期の荘園制の成立や、鎌倉時代の「下地中分」の説明とともに、教科書で見覚えがあるかもしれません。
この図版編に続き、『日本荘園絵図聚影』釈文編は、2007年に古代分1冊を刊行し、中世分の全3冊がこのほど完結しました。こちらもA3判のプレートとして、各絵図のトレース図 (白描模写) を収め、文字注記を翻刻して記載しています。併せてA4判の解説冊子を添え、基礎情報を補っています。中世分では、プレートとした図も縮小し、トレース図全点を冊子に収めていますので、ざっと全体を把握するには良いでしょう。伝存に粗密はありますが、列島の広い範囲に多様な中世の荘園絵図が残されています。史料集として刊行しているため内容解説は簡潔を旨とし、読んで分かりやすいとは言えませんが、参考文献も網羅的に掲げて研究の糸口としています。
これらの絵図からは、今から700年前、500年前といった頃の景観を知ることができ、いくらか工夫を重ねれば、現在でもその地に立って過去の姿を思い描くことができます。とりわけ、Web上で利用できる地理情報の飛躍的な向上は助けとなります。入手に手間と費用を要した古い空中写真を、今では簡単に見ることができ、高度成長期以降の大規模な改変を受ける以前の、土地の様子を知ることができます。その意味では、稀有に残された古絵図を精密に読み解くことで、古絵図が残されなかった地域の環境とそこで生きた人々の営みとを、復元する可能性も手に入れることになります。
(紹介文執筆者: 史料編纂所 教授 藤原 重雄 / 2024)
本の目次
一 高野山四至絵図 一 (写)
〈中略〉
四六 薩摩国日置北郷中分絵図
補遺一 相模国宝泉寺境内図
〈中略〉
補遺八 明応二年足利義材河内在陣図
古代・補遺一 越中国射水郡鳴戸開田地図
解説冊子
関連情報
https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/publication/shoenezu/
自著紹介:
「出版報告」 (『東京大学史料編纂所報』59、2024年10月)
https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/publication/syoho/shoho0059/2023hensan.pdf#page=36
藤原重雄「新刊紹介『日本荘園絵図聚影』釈文編四 (中世三・古代補遺)」 (『画像史料解析センター通信』No.104 2024年5月)
https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/records/2010380
関連論文:
井上聡「中世荘園絵図研究の軌跡と展望」 (『歴史評論』891 2024年7月)
http://www.maroon.dti.ne.jp/rekikakyo/magazine/contents/kakonomokuji/891.html



 書籍検索
書籍検索

