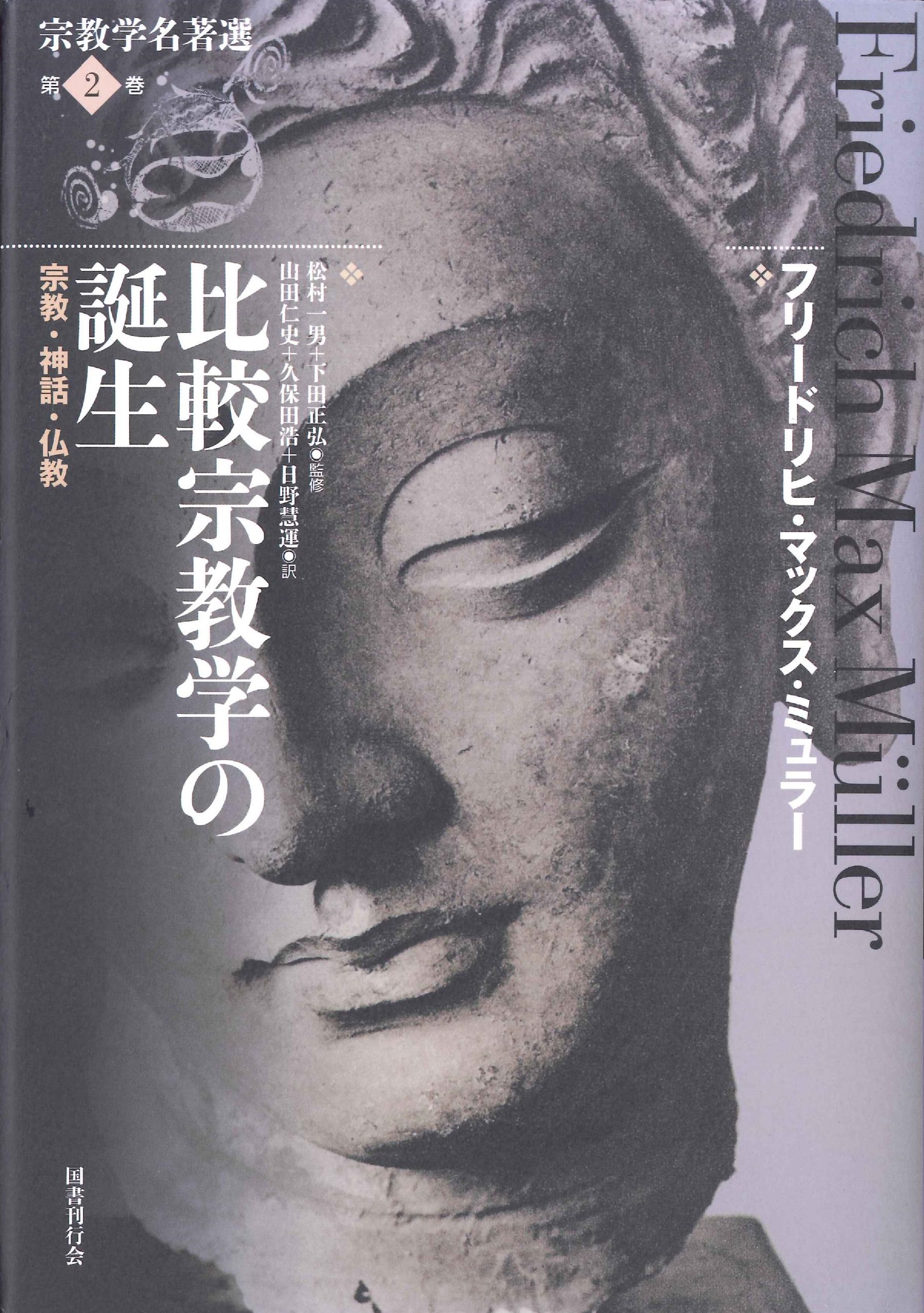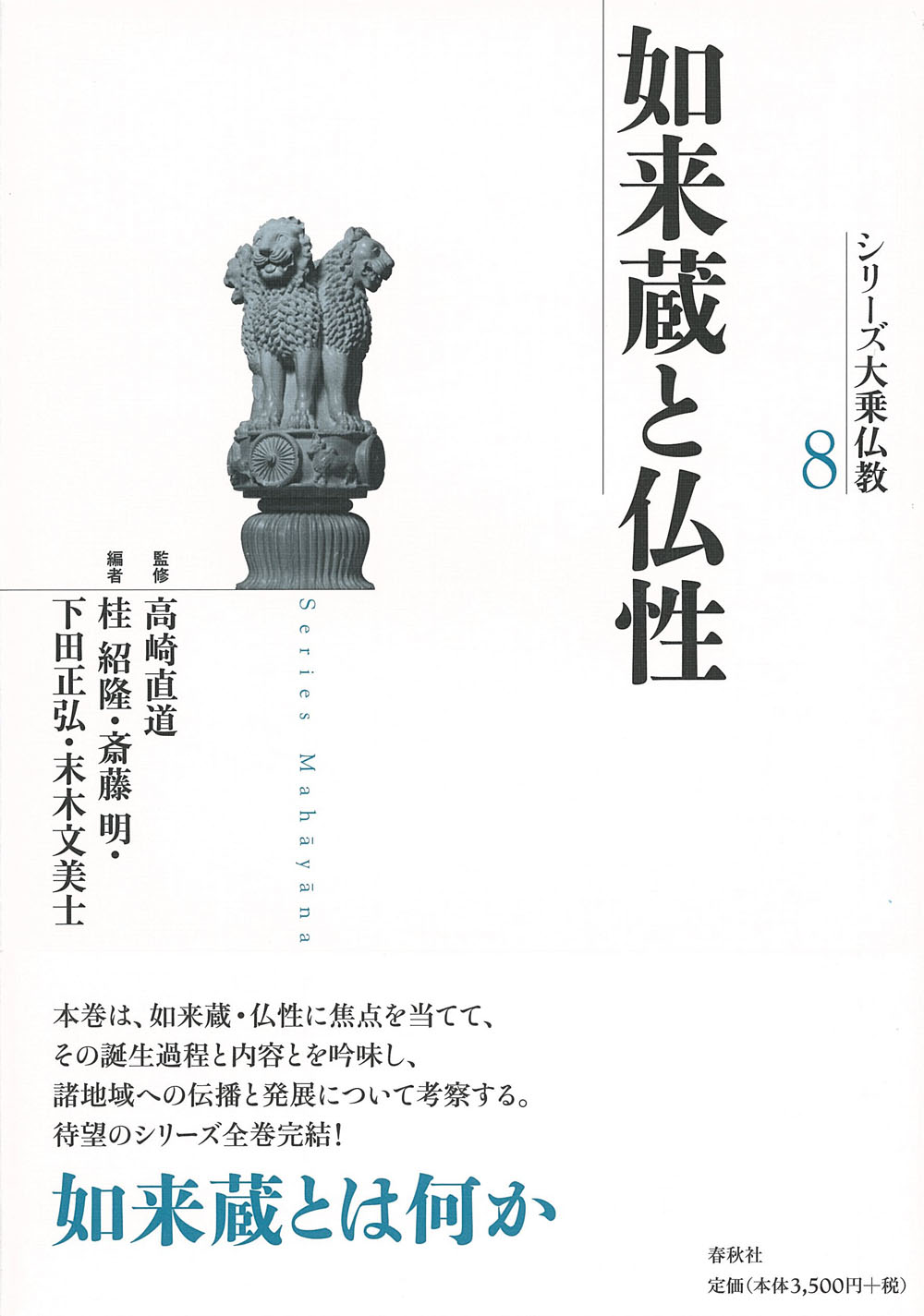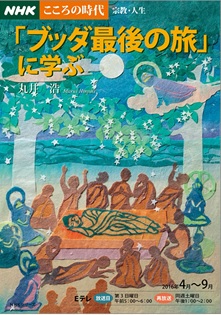フリードリッヒ・マックス・ミュラー (1823 – 1900) は、宗教学の「開祖」であるとともに、近代の人文学史に重要な画期をなした人文学者である。本書は、そのミュラーの業績の中心となる、比較神話学と宗教学、仏教学に関する論文を選別して翻訳し、詳細な文献学的註を付して紹介したものであり、「宗教学名著選」全6巻のなかの一冊として刊行された。
さて、研究の資料や成果の蓄積、発信、交換の方法、研究者育成のための教育制度、学術活動を推進するための学協会制度や学術刊行物の発刊制度など、現在の人文学を成り立たせるための制度的基盤のほとんど万般は、ヨーロッパによって作り上げられた枠組みである。
圧倒的影響力を有するこの西洋人文学の歴史において、かつて大きな変化がすくなくとも二度起きている。第一は、12世紀ルネサンスと14世紀のイタリアルネサンス、さらに遅れて始まった北方ルネサンスであり、第二は、18世紀後葉のインド学の成立と比較言語学の誕生、それにつづくウジェーヌ・ビュルヌフによる近代仏教学の体系化、最後にそれらを踏まえて登場する、19世紀後半のマックス・ミュラーによる宗教学の構築である。
第一と第二の変化のあいだには、認識空間の規模と抽象度の程度において、大きな差異が存在する。ルネサンス期の学者たちの努力は、忘却していた自己の起源の知識を、生活経験世界において復活させることだった。それに対してインド学と比較言語学の成立は、ヨーロッパの言語、宗教、文化を、イスラームを介在させずして、非西洋世界から照らしなおし、ギリシャをさらに遡るヨーロッパ文明の起源を辿るという高度に観念的な企図であり、それを通したかつてない人文学の創出であった。マックス・ミュラーはこの第二の変革を壮大な規模で完成させた。
ミュラーのこの偉業は「東方聖典叢書」の翻訳と編纂の事業に象徴される。ミュラーは聖典の起源を、インド、ペルシャ、中国、パレスチナ、アラビアの五つの「東方」地域に見て取り、その広大な地平を研究対象とすることによって、それまでキリスト教を指す概念であった「宗教」を、キリスト教を超え、ルネサンスをも超えて、仏教までをもうちにふくむ概念へと拡張した。この企図を通して非西洋世界の人文学にヨーロッパ自らの知見を開き、洋の東西の壁を越える、地球規模の人文学の創成にいたる道を開いた。ここであらたに生まれた「東方」とヨーロッパとの関係は、隣人でありながらその存在を否定しつづけてきたそれまでのイスラーム世界との関係と明らかに異なっており、エドワード・サイードの指摘にもかかわらず、オリエンタリズムの枠内におさまるものではない。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 下田 正弘 / 2017)
本の目次
『宗教学論集』序文 (ドイツ人工房からの削り屑、第一巻)
神話の哲学について
宗教学序説 - 王立研究所で行われた四つの講義
仏教の巡礼者たち
涅槃の意味
仏教
仏教の虚無主義について
解題 (山田仁史、久保田浩、日野慧運)
解説 (松村一男、下田正弘)



 書籍検索
書籍検索