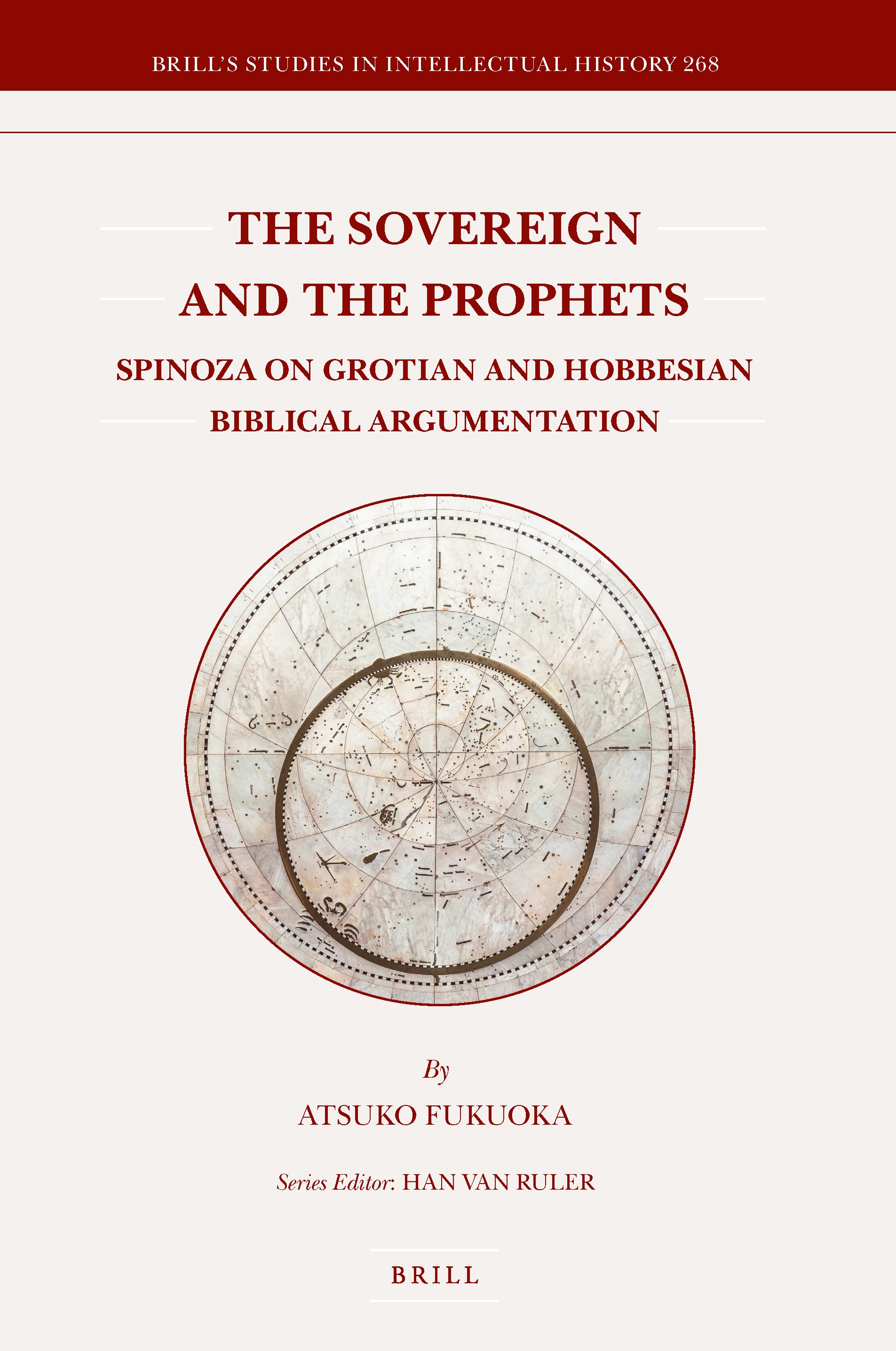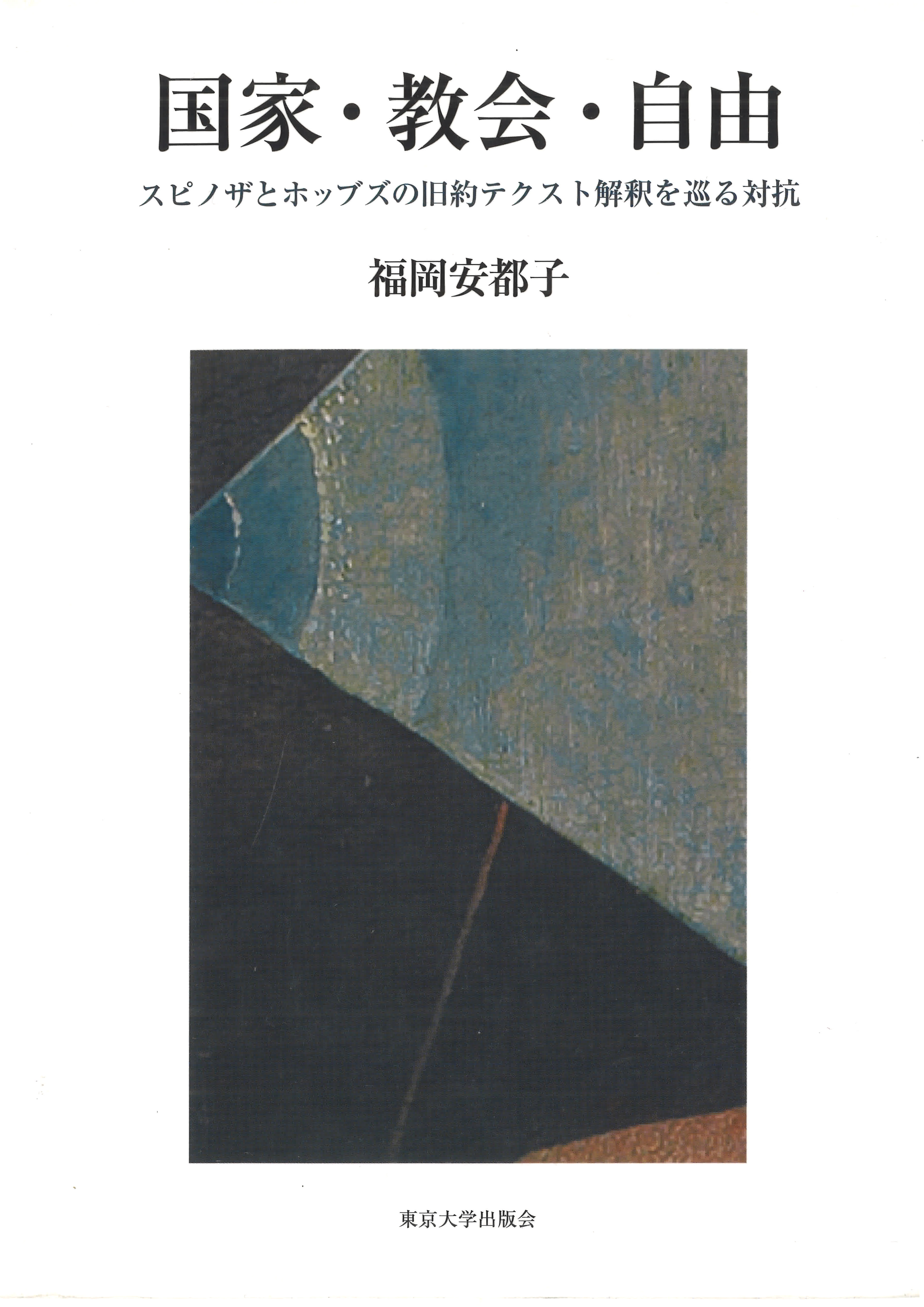
書籍名
国家・教会・自由 スピノザとホッブズの旧約テクスト解釈を巡る対抗
判型など
480ページ、A5判
言語
日本語
発行年月日
2007年12月27日
ISBN コード
978-4-13-036137-8
出版社
東京大学出版会
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
明治以来の「宿題」領域に向けて
日本の法律学は、明治以降、フランスやドイツ、イギリスなどから、法律体系それ自体やその基礎となる考え方を取り入れることで発達してきた。また特に戦後は、これらの国を凌ぐ大国となったアメリカが、日本の法律学にとっても重要な参照対象として加わった。その時代その時代の世界地図は、法学部の研究・教育内容をもまた、直接・間接に規定している。駒場から法学部に進学したとき、「ここでは明治維新がまだ続いている!」という印象を覚えたが、このこともそうした事情に由来するものであろう。
大きく「西洋法の継受」と呼ばれるこの百年余の営みは、単に「輸入法学」として片付けることのできない、比較法的に見ればむしろ創造的なものを多く含むプロセスであった。今日の日本の法律学は、西洋法の理解としても、またわが国で独自の発展を見た各個別領域の点としても、国際的にかなりの水準に達しており、学部生として受けた授業はいずれも刺激的なものばかりであった。
しかしそれでも、このインテンシヴな継受過程の後にもなおいわば「宿題」として残っている、研究の非常に薄い領域が存在することも事実であるように思われる。本書、『国家・教会・自由 - スピノザとホッブズの旧約テクスト解釈を巡る対抗』のテーマに逢着したのは、論文執筆によくあるように幾つかの偶然の重なりによってではあるが、振り返って巨視的に見てみると、本書のテーマは、下記の三つのファクターが重なって生じる空白域に関わっていたように思う。
(1) オランダ語とオランダ史の研究
(2) 学術用語としてのラテン語で書かれた法的・政治的論考の研究
(3) 宗教と国家、特に啓示宗教の特殊性に由来する法的・政治的問題の評価
即ち、(1) は言うまでもなく、明治時代、日本の西洋法の継受が本格的に始動するようになって以降、英・独・仏への傾斜の中で、伝統として途絶えてしまったものである。
(2) については、日本の法学者が留学するようになった欧州は、学術語としてのラテン語が既に退潮した時代であった。対応して、日本の法学研究でラテン語を使うとすれば、それは主としてローマ法か中世法研究というのが相場になった。その結果、ルネサンスからフランス革命の少し前あたりまで、当時の学術語としてのラテン語で発表された法学・政治学上の大作というのはかなり存在しているにもかかわらず、実際上はあまり日が当てられないことともなった。
(3) は、なかなか表現が難しいが、西洋史上、中世的な分権状態から近代国家が成立していく過程で、封建領主やギルドといった半独立の主体から中央の君主に権力が集中させられていくということは、世界史の教科書等でもよく取り上げられる事項と思う。この「俗界」での動きとパラレルな動きが、言うなれば「聖界」、ないし教会と中央権力との関係でも生じたわけであり、今日の政教分離原則や信教の自由、思想・良心の自由、表現の自由などはこの歴史の産物である。しかし、この教会・宗教面での近代国家成立過程は、単なるパワーゲームの次元を超え、極めて高度かつ複雑に発達した「頭の体操」を伴うプロセスであった。この世界で「法」とはまさに聖書であり、神学者・宗教家のみならず、当時の一級の法学者・政治思想家たちもまた、聖書解釈を媒介項にペンのバトルをしている。このように宗教・神学と法的・政治的理論が交錯することは啓示宗教の伝統の中では特異ではなく、否むしろ、政治秩序を安定化させるにはこの宗教・神学と関わる部分をしっかりと交通整理しておくことが必要な社会なのであるが(対応して、特に2000年代以降、欧米ではこの領域の研究が盛んになっているが)、この問題領域は、どうも日本の法学研究ではどちらかというと苦手とされているようである。
本書、『国家・教会・自由』は、(1)~(3) が重なったところに位置している。
即ち本書は、アムステルダム生まれのユダヤ系思想家、スピノザが1670年に出版した『神学・政治論』という著作を取り上げる。『神学・政治論』は、検閲が国家と宗教の双方にとり如何に有害であるかを論証する著作として、今日の「表現の自由」の問題に深く関わるが、スピノザの論証は、旧約聖書の解釈を媒介としている。それは、今日の目からすれば、ほとんど「暗号」である。そこで本書は、メソッドとして、『神学・政治論』が繰り広げている旧約聖書解釈を、当時のオランダでも話題作になっていた、ホッブズの『リヴァイアサン』(1651年) での旧約聖書解釈と比較分析することを通じて読み解くことを試みた。この比較分析を介して、スピノザが当時のオランダの政治社会状況の中で、国家や自由の在り方をどのように構想していたのか、特に、ホッブズの絶対主義的な構想との関係でどのようなオルタナティブを模索しているのかを描くことを試みたのが本書である。本書ではまた、比較のための第三項として、スピノザと同世代のオランダの法学者、ウルリクス・フベルスの国家・教会論を導入として論じている。自ら中道を目指したフベルスの議論は、ホッブズやスピノザが全体の座標軸の中でどこに位置しているのか、大きな見取り図を与えてくれるためである。
(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 准教授 福岡 安都子 / 2017)
本の目次
序章 旧約テクストを介して国家・教会・自由の基層へ
第I部
第一章 公法学者フベルスに見る国家・教会・自由の基本構造
第二章 オランダ17世紀における国家・教会・自由
第三章 『リヴァイアサン』第3部における神と主権者
第II部 スピノザとホッブズ: 旧約テクスト解釈を巡る対抗
第四章 序論
第五章 啓示の媒体
第六章 神の霊
第七章 聖書の権威
終章 総括と展望
関連情報
『国家・教会・自由 増補新装版』 (東京大学出版会 2020年5月21日刊行)
http://www.utp.or.jp/book/b507923.html
書評:
高見勝利「学会展望」『公法研究』70 (2008), pp. 232-233
國分功一郎「雰囲気の力」『環』33 (2008), pp. 322-325
木島泰三『社会思想史研究』33 (2008), pp. 160-164
梅田百合香『イギリス思想史研究』32 (2009), pp. 119-121
上野修『法制史研究』59 (2010), pp. 384-389



 書籍検索
書籍検索