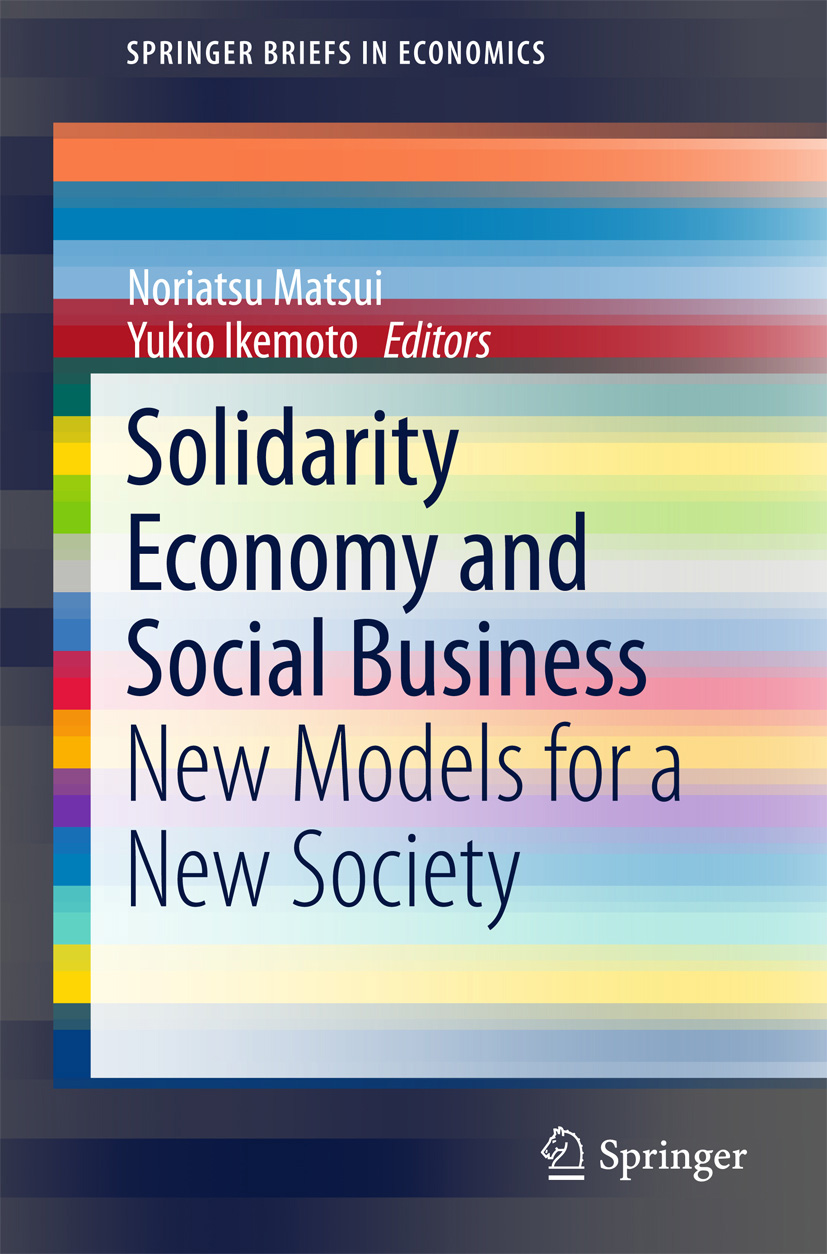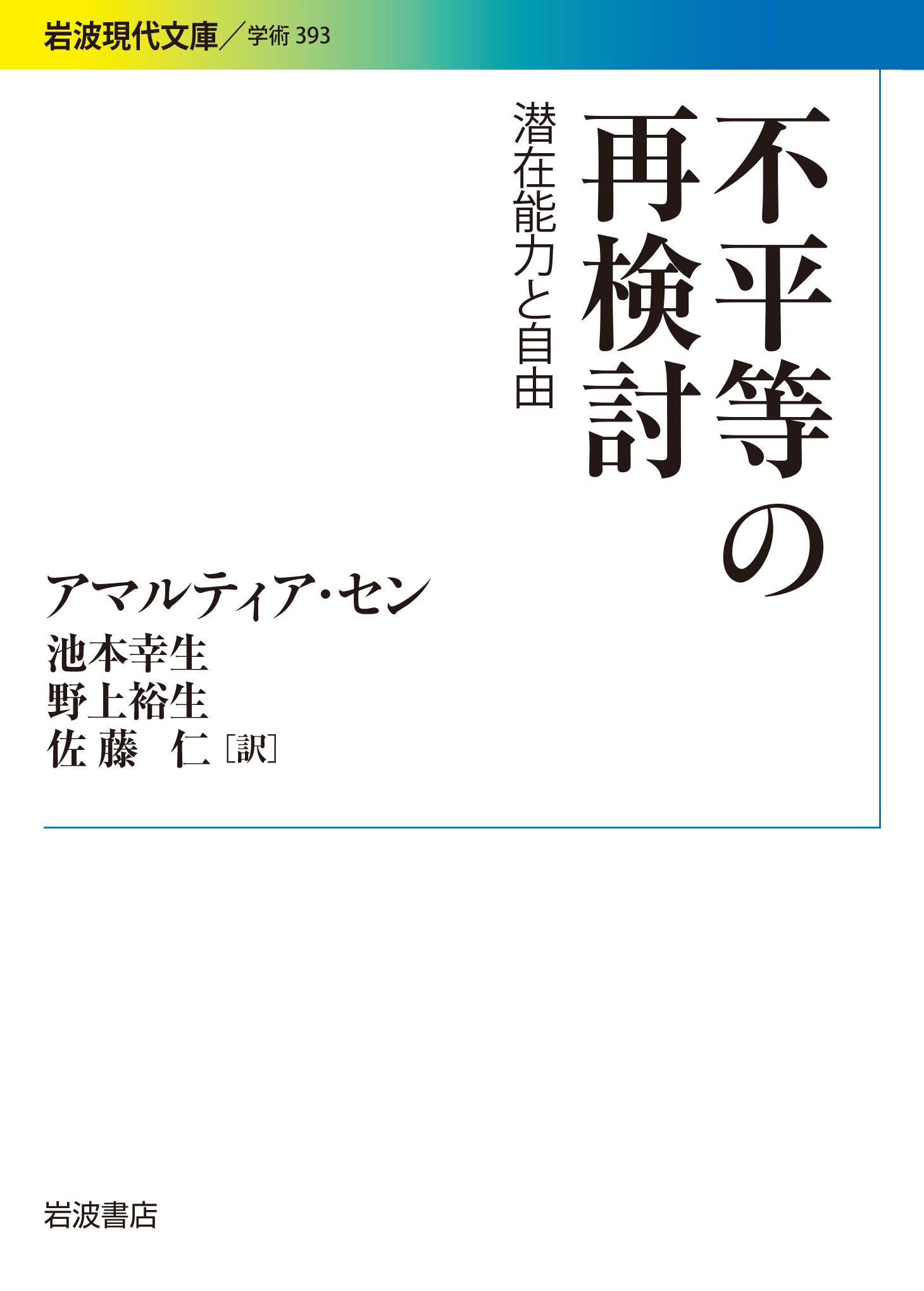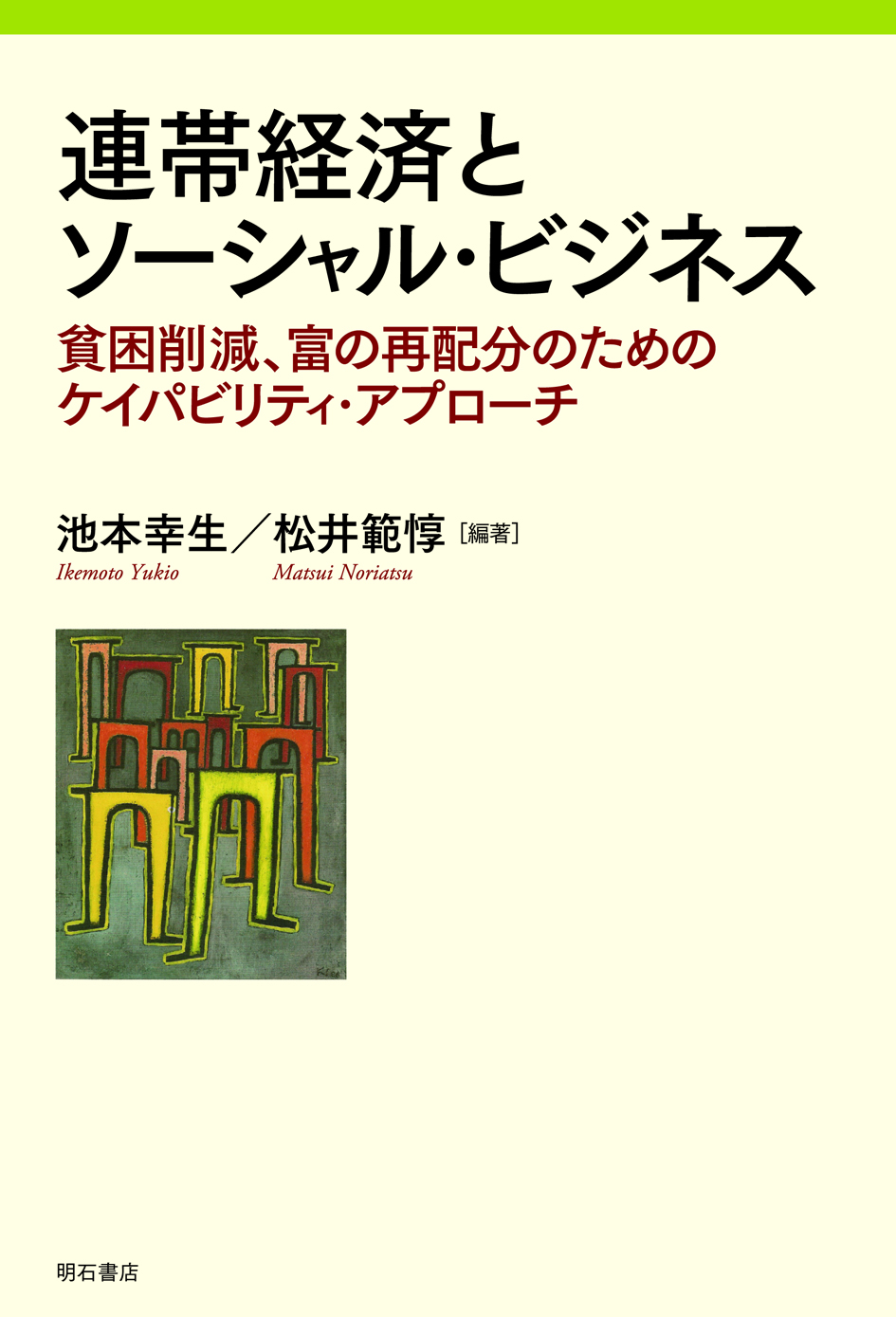
書籍名
連帯経済とソーシャル・ビジネス 貧困削減、富の再分配のためのケイパビリティ・アプローチ
判型など
224ページ、四六判
言語
日本語
発行年月日
2015年4月10日
ISBN コード
978-4-75-034165-1
出版社
明石書店
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
本書は、アマルティア・センのケイパビリティ・アプローチの研究とバングラデシュのグラミン銀行のマイクロクレジットの研究から生まれてきたものである。センのケイパビリティ・アプローチは「人間開発」の理論的基礎となっているものである。「経済開発」が経済に着目するのに、「人間開発」は人の暮らしに着目する。経済が発展しても、その成果が不平等に分配されるときには人々の暮らしが良くならないことも起こりうる。我々の本当の目的は「人々の暮らし」にあり、経済はそのための手段に過ぎない。経済開発は、GDPのような所得指標によって測られる。それに対して、人間開発は人々の暮らしによって測られる。例えば、「健康に生きることができる」、「十分な栄養を摂ることができる」、「読み書きができる」、「社会の活動に参加できる」などを見ていくことになる。これらの「~できる」がケイパビリティである。
ケイパビリティ・アプローチが経済学のアプローチと大きく異なる点は、経済学が利己的な動機しか認めないのに対して、ケイパビリティは、それ以外の様々な動機も認める点にある。グラミン銀行は、5人グループを借り手とし、無担保で融資する。5人グループには連帯責任が発生する。この仕組みを説明するために、自分自身の利益になることしか考えない経済人を仮定する経済学では、連帯責任を強調する。一方、ケイパビリティ・アプローチでは様々な動機を認めるので、5人グループの助け合いを重視する。5人グループを、互いに監視し合う人たちと見るのか、それとも助け合う仲間と見るのかは大きな違いである。後者の方がよほど人間らしい。
利己的な人たちが集まっても連帯感は生れない。しかし、現実には人間は利己的なわけではなく、様々な問題に協力しながら取り組んでいる。社会的な課題に取り組むソーシャル・ビジネスは、人々の結びつきによって、市場が引き起こしてきた問題を解決しようとするものである。例えば、フェアトレードは発展途上国の貧しい人たちの問題を、先進国の消費者が関わることで解決しようとするものであり、両者の「連帯」によって問題を解決しようとする。地域通貨は、市場では取引されない商品やサービスに、地域独自の通貨を発行することで新たに流通するルートを作ろうとする。人のつながりが欠けているところに地域通貨を導入することによって、人々のつながりが生れ、問題を解決しようとする。有機農業が始まった頃、有機農産物の市場はなかったため、有機農産物を求める消費者と、農薬や化学肥料を使いたくないと思っていた農家が直接つながる必要があった。有機農業ではこのような関係を「連帯」という言葉ではなく、「提携」と呼んで大事にしてきた。市場を万能のように言うのは間違いである。市場は多くの問題を残してきた。それを解決するために、人々は市場の外で連帯することによって取り組んでいる。
(紹介文執筆者: 東洋文化研究所 教授 池本 幸生 / 2017)
本の目次
第2章 マイクロクレジット、インクルーシブ・ファイナンスと連帯
第3章 スペインのグラミン型マイクロクレジット
第4章 グラミン・ファミリーのソーシャル・ビジネス
第5章 ヨーロッパの企業とグラミンのソーシャル・ビジネス
第6章 日本の企業とグラミンのソーシャル・ビジネス
第7章 地域通貨と地域の再活性化
第8章 有機農業における連帯の役割
第9章 認証コーヒーと連帯
第10章 韓国における社会的企業の展開



 書籍検索
書籍検索