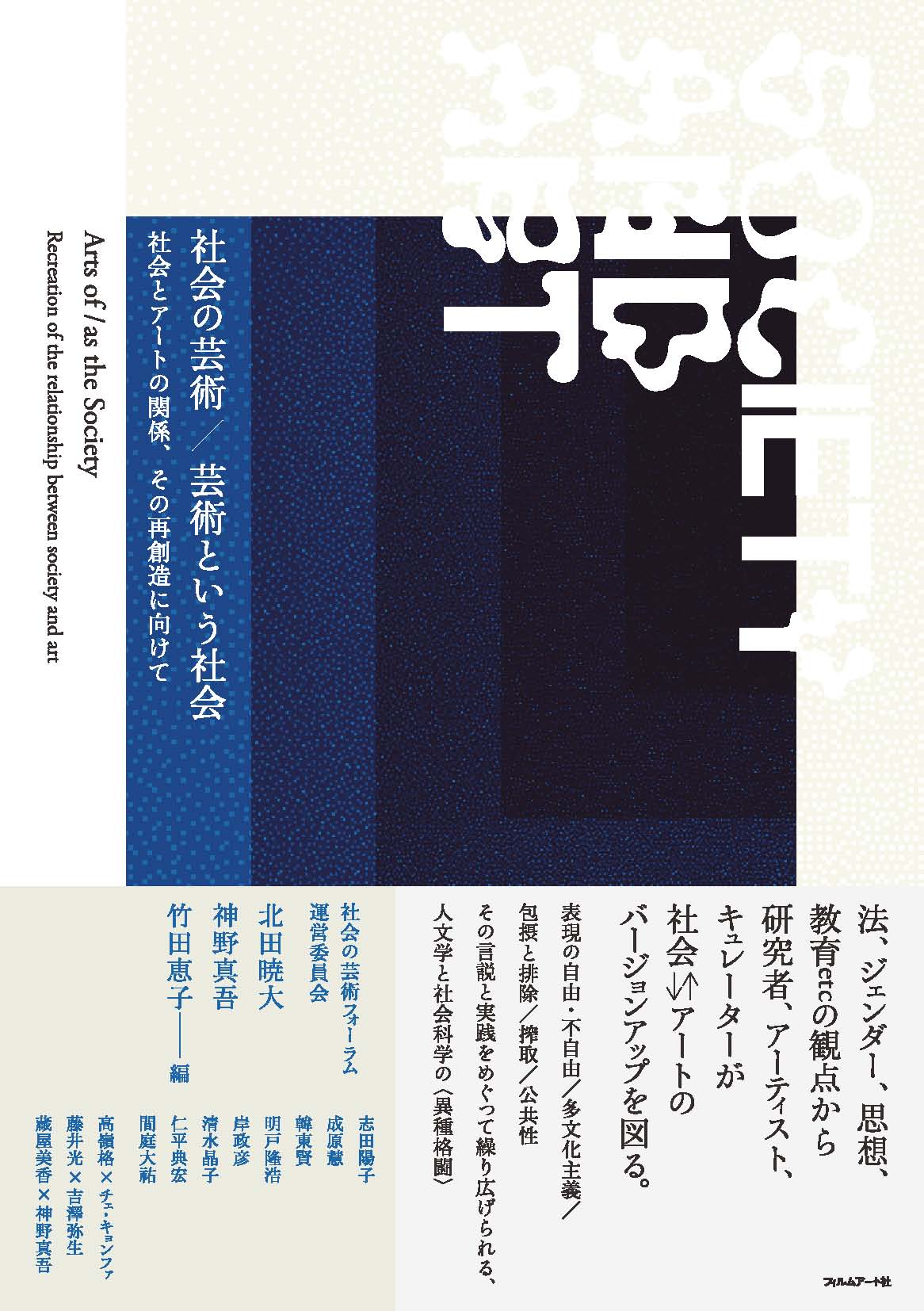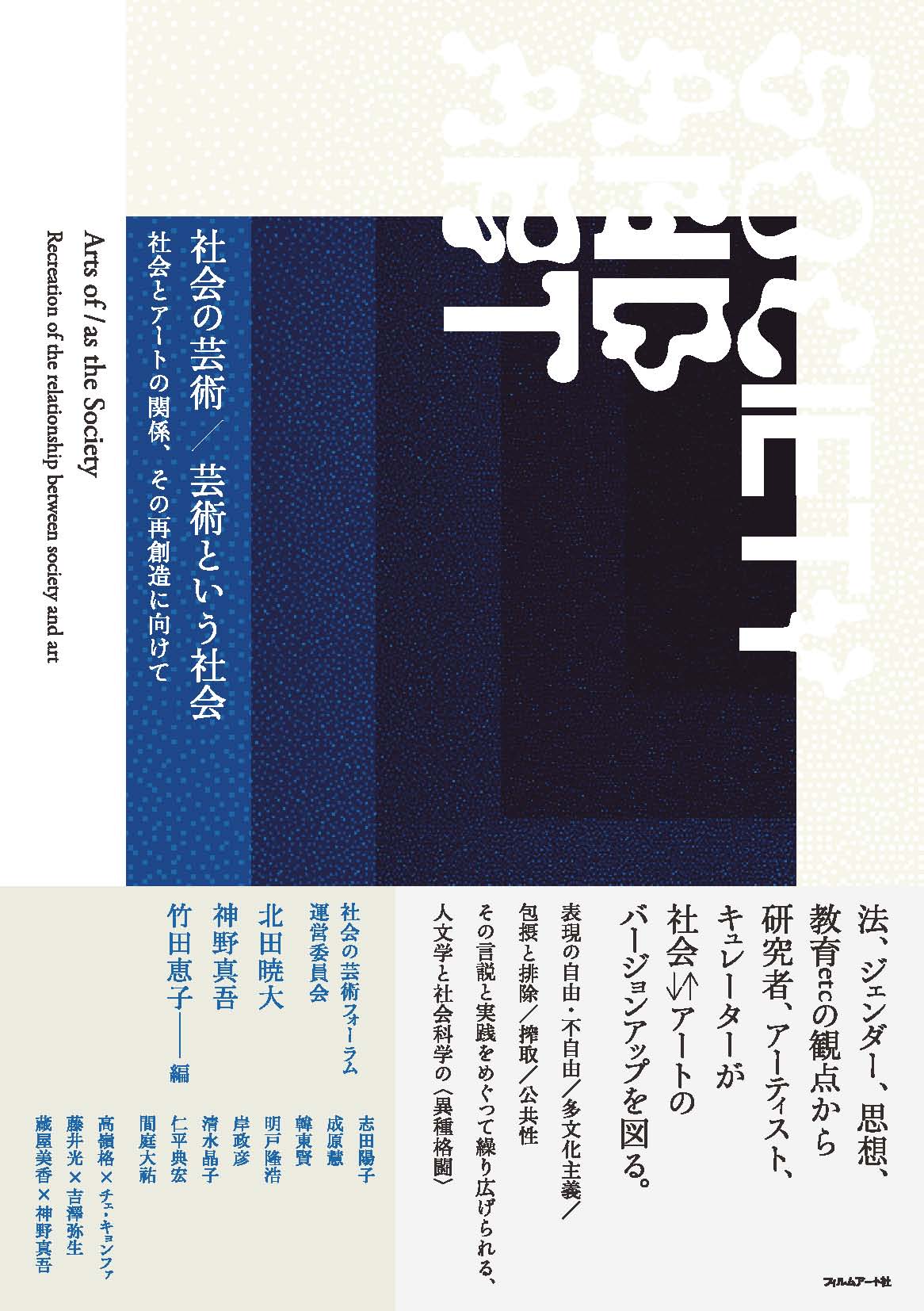
書籍名
社会の芸術 / 芸術という社会 社会とアートの関係、その再創造に向けて
判型など
352ページ、A5判、ソフトカバー
言語
日本語
発行年月日
2016年12月22日
ISBN コード
978-4-8459-1609-2
出版社
フィルムアート社
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
本書は、2015年より情報学環・北田研究室を拠点として創始された「社会の芸術フォーラム」の活動をもとに著された書籍である。「社会の芸術フォーラム」は社会とアートの相互反映性について、多領域の人々とともにアクチュアルな議論を積み重ねてきたが、本書の章立ては、2015年度に開催されたフォーラムのテーマを流用したものである。
世界的に「社会と関与する芸術」が台頭し日本ではとくに2000年代以降、地域や市民を巻き込んだ形でのアートプロジェクトや芸術祭が急激に増加した。美学的な観点からのみ、アートを評価することが難しくなっている。
このような状況下においてアートは「地域活性化」のために道具的に使用されることもある。しかしアートでなくとも可能な「機能」に還元されてしまっている事例もまた少なくないと思われる。アートだからこそ発揮できる機能、代替不可能なアートのあり方を考えていくためには、アートの自律性とともに、社会におけるアートという実践の機能を精査していく必要がある。とりわけ地域の芸術祭やソーシャル・プラクディス、ソーシャリー・エンゲージド・アートという近年の潮流におけるアートは、必然的に関わりを持たざるをえない「社会」なるものと関わるための方法論を切実に問われているのではないだろうか。
社会学者のニクラス・ルーマンは、「社会システム Soziale Systeme」を、(1) 相互行為、(2) 組織、(3) 全体社会 (機能システム) という三つに分類した。芸術にそくしていえば、(1) ではアーティストの制作実践や展示行為、観客の鑑賞など、いわゆる「コミュニケーション」としての社会が問われるだろうし、(2) はいわゆる「アートワールド」、つまりアートをめぐる制度的背景、経済関係、組織構成、ヒエラルヒーなどの社会的なあり方が問われるだろう。そして、(3) では、芸術システムという自律した機能システムが果たす機能、他のシステム(法システムや経済システム等)との関連性が問われることになる。 このように様々な水準における「社会」のあり方を丁寧にたどり返し、社会の複雑性を十分に踏まえながら、次なるアートの実践へとフィードバックしていく回路を整えていく必要がある。
本書では、アートワールドを人文学的・社会科学的な側面から検討し、アートワールドという社会、あるいはアートワールド「と」社会の関係を問い返していきたい。アーティストとキュレーター、批評家、研究者の相互的な討論のプラットフォームを形成し、アートの実践、批評の言語の新しい形を模索する。そうすることによって、「アートと社会の相互反映性」を領域横断的に考察していくことが、「社会の芸術フォーラム」および本書の目的である。
本書および「社会の芸術フォーラム」の試みは、2017年度より東京大学「社会を指向する芸術のためのアートマネジメント育成事業 (AMSEA)」に引き継がれている。
(紹介文執筆者: 情報学環 教授 北田 暁大 / 特任准教授 竹田 恵子 / 2017)
本の目次
第一章 表現の自由・不自由
イントロダクション………北田暁大
[論考]
芸術表現の自由と憲法上の「表現の自由」………志田陽子
制度としての美術館、あるいは表現の「場」と媒介者………成原慧
[フォーラム総括]
表現の自由と規制との間で考えるべきこと………神野真吾
第二章 多文化主義
イントロダクション………北田暁大
[論考]
多文化主義なき多文化社会、日本………韓 東賢
表現の自由/表現が侵害する自由―アートはヘイトスピーチとどう向き合うべきか………明戸隆浩
[フォーラム総括]
多文化主義とアート―アイデンティティの表現をめぐって………神野真吾
第三章 包摂と排除
イントロダクション………神野真吾
[論考]
欲望と正義―山の両側からトンネルを掘る………岸 政彦
ポルノ表現について考えるときに覚えておくべきただ一つのシンプルなこと(あるいはいくつものそれほどシンプルではない議論)………清水晶子
[フォーラム総括]
誰が何から排除されているのか………神野真吾
対談1
現代美術の表現から考える―方法・技術・戦略………高嶺 格×チェ・キョンファ
第四章 搾取
イントロダクション………北田暁大
[論考]
遍在化/空洞化する「搾取」と労働としてのアート―やりがい搾取論を越えて………仁平典宏
[フォーラム総括]
アートにおいて交換される価値とは………神野真吾
対談2
芸術生産の現場から考える―労働・キャリア・マネジメント………藤井 光×吉澤弥生
第五章 公共性
イントロダクション………北田暁大
[論考]
ハーバーマスとアレントの理論から考える「公共性」………間庭大祐
[フォーラム総括]
公共(性)とアート―「社会の芸術」の実現にあたって………神野真吾
対談3
美術館の公共性から考える―コレクション・展示・教育………蔵屋美香×神野真吾
ソーシャリー・エンゲイジド・アートとしての九〇年代京都における社会/芸術運動と『S/N』………竹田恵子
アートの開かれた王室問題―あとがきにかえて………神野真吾
関連情報
社会の芸術/芸術という社会 社会とアートの関係、その再創造に向けて (『REPRE』Vol.30 2017年7月29日)
https://www.repre.org/repre/vol30/books/editing-multiple/syakai/
参考文献 (SEAリサーチラボ)
http://searesearchlab.org/book/shakainogeijutsu.html



 書籍検索
書籍検索