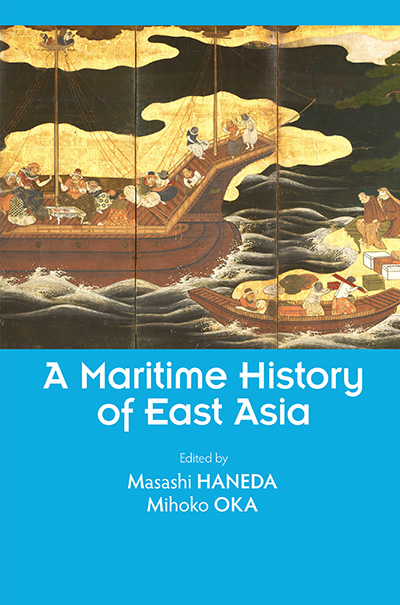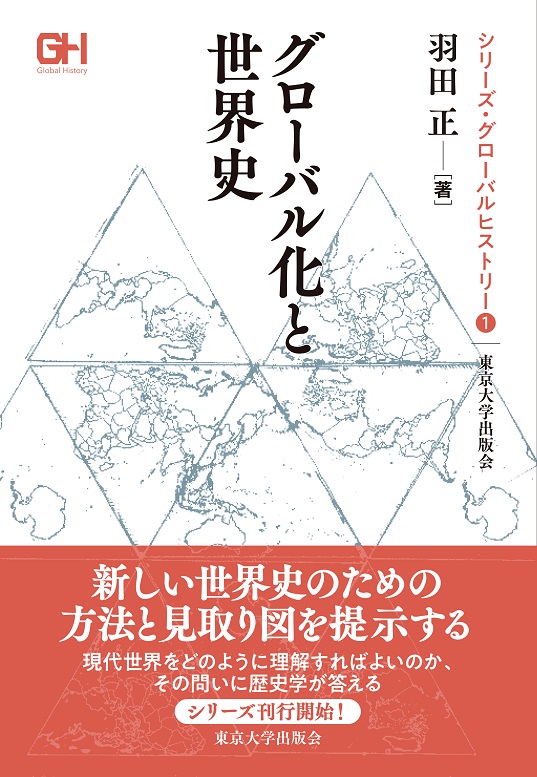
書籍名
シリーズ・グローバルヒストリー 1 グローバル化と世界史
判型など
302ページ、四六判
言語
日本語
発行年月日
2018年3月28日
ISBN コード
978-4-13-025171-6
出版社
東京大学出版会
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
現代の特徴は、経済、政治、情報、文化、環境など多くの側面で世界各地が緊密に結びつき、共時的に連動していることだとしばしば指摘されます。独自に展開される各地域の活動の総和が世界を形成するのではなく、各地域が相互に影響を与えあい、関係を持ちながら、全体として一つの世界を形作っているというのです。
それでは、過去の世界の状況はどうだったのでしょうか。世界は一つではなくバラバラだったのでしょうか。だとすると、現代の状況は、いつどのようにしてなぜ生まれたのでしょう。これらは、現代を深く理解し未来を見通すための重要で根本的な問いです。答えるには過去の世界を全体としてとらえ、解釈する視点が必要になります。しかし、従来の歴史研究では、世界をいくつかの地域、さらには国に分け、それぞれの過去を時間軸、つまり縦軸、に沿って整理し、別々に説明することが常でした。世界の過去、すなわち世界史は、単にこれら別々の過去をたばねたものだと理解されていました。これでは世界全体の過去の状況はよく分かりません。
私たち歴史学者は、ある時期の世界全体の姿を空間軸、すなわち横軸、に沿って把握し説明するような歴史研究を進めなければなりません。それによって、その時期における世界各地の結びつきの状況や程度が分かるでしょう。ある地域の社会構造や政治の仕組み、文化の特徴を、他地域のそれらと比較して明らかにすることもできるでしょう。
現在、私は海外の歴史研究者たちとGlobal History Collaborativeという名称の国際的な教育研究ネットワーク事業を展開しています。そこでは、横軸に沿って世界の過去を把握しようとする研究方法を「グローバルヒストリー」と呼んでいます。私たちはこの方法を用いて世界の過去を新しい角度から解釈し理解しようとしているのです。
二部構成からなる本書には、この国際教育研究ネットワークを通じて海外の歴史研究者と共同で様々な事業を遂行する過程で私が考えたこと、発見したこと、主張したいことが盛り込まれています。第一部では、急激に変貌する現代世界において、特に日本語を使って人文学・社会科学を研究することの意味とこれらの研究が今後の日本と世界で果たすべき新しい役割について論じました。第二部では、グローバルヒストリーの定義と方法、可能性について解説するとともに、それを実際に用いて、四つの特定の時期の世界の姿を、政治体制と社会構造に焦点を絞って、全体として把握することを試みました。
私は、日本人であると同時に地球の住民でもあるという立場を意識して、この書物を著しました。日本語による著作ですが、外国人の読者も想定しています。これまでの他の著作の場合と同じく、本書が外国語に翻訳され、「地球の住民」意識を持つ世界中の人々に広く読まれ、その意見を聞くことができる日が来ることを願っています。
(紹介文執筆者: 東洋文化研究所 教授 羽田 正 / 2018)
本の目次
第I部 人文学・社会科学と現代世界
第1章 人文学・社会科学の「国際化」
第2章 人文学・社会科学の暗黙知
第3章 知の多元化と言語
第4章 グローバル化時代の人文学・社会科学
第II部 新しい世界史とグローバルヒストリー
第5章 世界史の系譜と新しい世界史
第6章 さまざまなGlobal History / グローバルヒストリー
第7章 グローバル人文学・社会科学としてのGlobal History
第8章 グローバルヒストリーの可能性
第9章 新しい世界史のための4枚の見取り図
終 章 未来につながる新しい世界史のために
関連情報
http://coretocore.ioc.u-tokyo.ac.jp/
書籍紹介:
“グローバル社会の枠組みで歴史を紹介”日本経済新聞 (2018年5月16日掲載)
http://coretocore.ioc.u-tokyo.ac.jp/news/2018/06/-524.html
“アジアから見た新しい世界史” (日本経済新聞 2018年8月11日掲載)
https://webreprint.nikkei.co.jp/r/LinkView.aspx?c=27996A100F9449B19F9175D958A2D067
書評:
村上宏昭 (筑波大学人文社会系助教) 評 (週刊読書人ウェブ 2018年12月23日)
「世界史」「グローバルヒストリー」一般向けの教養書が相次いで刊行
https://dokushojin.com/article.html?i=4759



 書籍検索
書籍検索