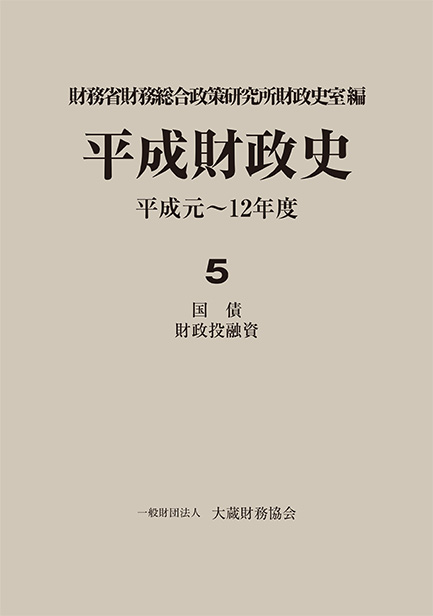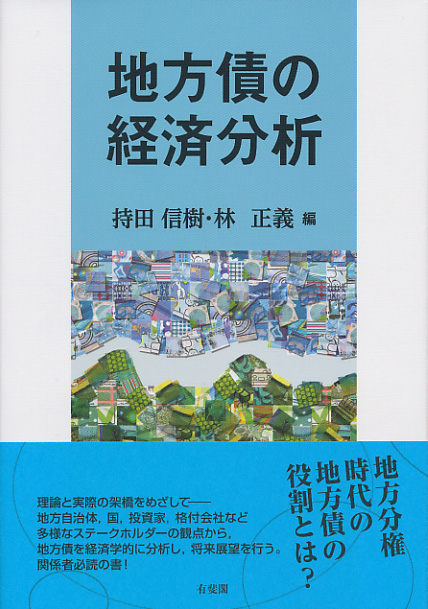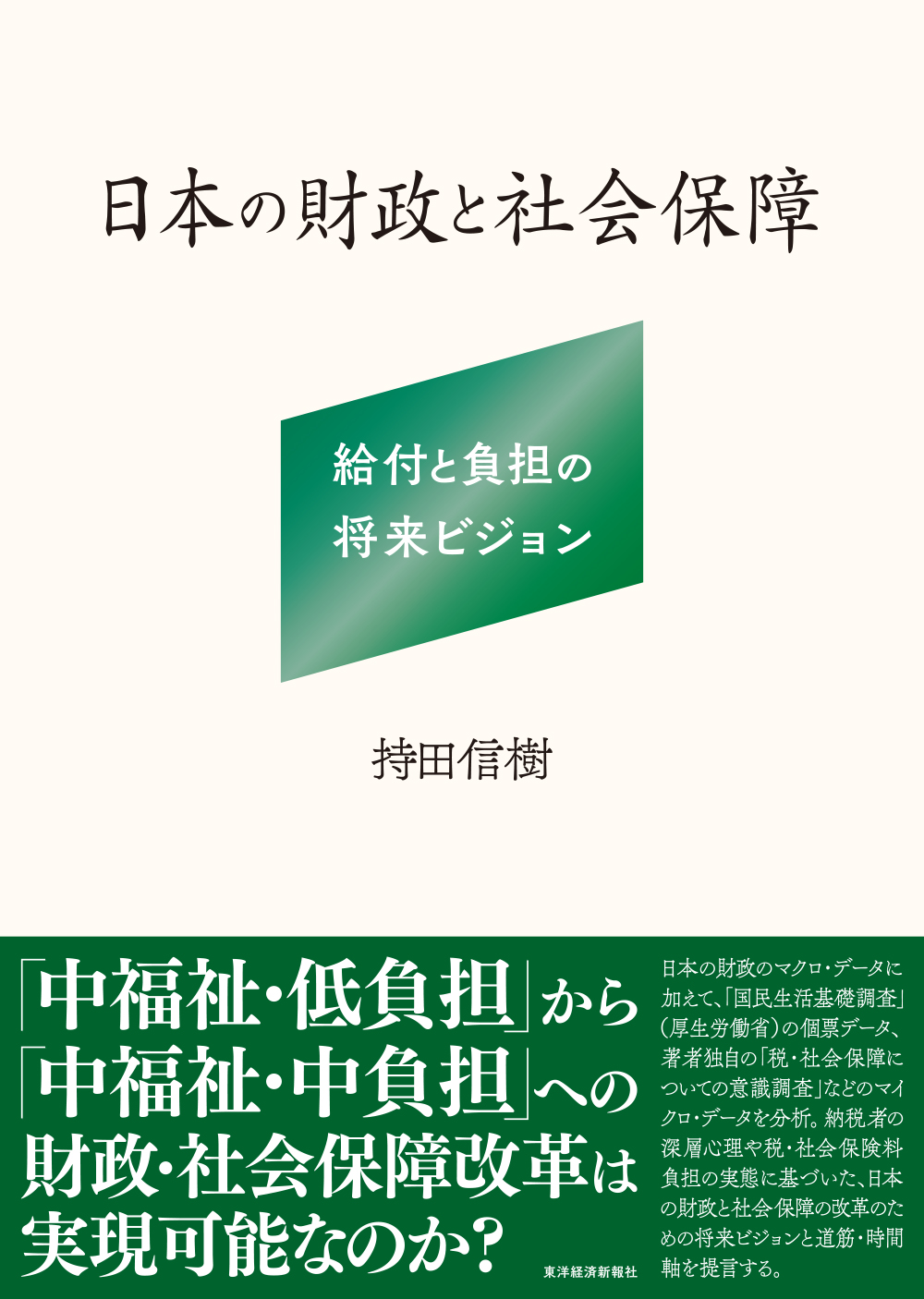
書籍名
日本の財政と社会保障 給付と負担の将来ビジョン
判型など
296ページ、A5判
言語
日本語
発行年月日
2019年3月15日
ISBN コード
9784492701508
出版社
東洋経済新報社
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
日本の財政は、長引く低成長とデフレの後遺症ともいうべき政府債務残高の塊と格闘している。平成の世、わが国の財政は給付に伴う負担を将来に先送りしてきた。国民総生産の2倍を超える政府債務を抱えていることは周知であろう。日本の財政が厳しい状況にあることは経済学者やエコノミストでなくても世の中の多くの人々が感じている。財政健全化および社会保障の持続可能性は、日本経済にとって重要な課題であるというコンセンサスはできている。しかしどうやって進めるかという段階になると意見が対立する。
なぜ日本の財政は最悪の状態になったのだろうか。経済成長によって財政は健全化するのだろうか。社会保障給付の重点化や税・社会保険料の引上げの議論では納税者の視点はどう扱われるべきなのだろうか。消費税増税後の税制改革はどうあるべきか。少子高齢化、家族および労働市場の変容をふまえた社会保障の将来像とは何だろうか。国債残高累増の傾向が続く中で、長期金利が趨勢的に低下している逆説的な状況をどう理解したらよいのだろうか。こうした問に答えるべく、日本財政の診断と処方箋を提示することが本書の目的である。
「中福祉・低負担」から「中福祉・中負担」への財政・社会保障改革は実現可能なのか。本書では分析に際して、日本の財政に関するマクロ・データだけではなく、「国民生活基礎調査(厚生労働省)」の個票データ、および筆者独自の「税・社会保障についての意識調査」などのマイクロ・データまで取り入れた。これによって、納税者の深層心理や税・社会保険料負担の実態が判明した。この分析にもとづき本書では、財政と社会保障の課題に対して、具体的に実現可能な改革のための将来ビジョンと道筋・時間軸の提言を行っている。
また財政健全化という課題に、最新のデータにもとづいて、欧米諸国がいかに取り組んできたのかも考察している。各国の政策担当者や政治家が財政状況の改善に取り組んだ過去のエピソードから、いかなる教訓を導くことができるのだろうか。「痛み」を伴う本格的な財政健全化に着手した動機付けは何であったのか。経済危機の中で財政健全化を行うにはどのようなタイミングで実施し、いかなる戦略やシナリオを描いたのだろうか。国民は財政健全化の結末が公平で効率的であると満足したのか。そして財政健全化を実施する際には、政治家は有権者とどのような契約を結んだのだろうか。
現実の財政問題とその将来について一財政学徒がいいうることは小さい。所詮「畳の上の水練」にすぎないのではないかと考える人もいるかもしれない。しかし、将来の不安や日々の労苦に苛まれながらも「財政」というプリズムを通して希望をみつめる素材を提供できるはずだ。不十分な分析であるが、本書を財政・社会保障に関心をもつ経済学者、エコノミスト、政策担当者、市場関係者、そして一般の方々に読んで頂ければ幸せである。
(紹介文執筆者: 経済学研究科・経済学部 名誉教授 持田 信樹 / 2019)
本の目次
第2章 財政・社会保障改革の軌跡
第3章 消費税増税と日本経済
第4章 幻の財政構造改革
第5章 中福祉・低負担の深層
第6章 社会保障制度の新設計
第7章 税制改革の全体構想
第8章 政府債務の持続可能性
第9章 国債と長期金利
第10章 欧米における財政改革
関連情報
日本財政学会第76回大会 シンポジウム「消費税10%後の租税対策」にてパネラーとして本書の成果を報告 (2019年10月19日)
http://www.gakkai.ne.jp/jipf/convention/76/
東京大学未来ビジョンセンター主催「サステナブルな財政と消費税」にて本書の成果を中心にした基調講演 (2019年6月5日 東京大学本郷キャンパス情報学環・福武ホール)
https://ifi.u-tokyo.ac.jp/event/3663/
書評:
『日本経済新聞』朝刊 2019年5月11日
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO44624750Q9A510C1MY7000/



 書籍検索
書籍検索


 eBook
eBook