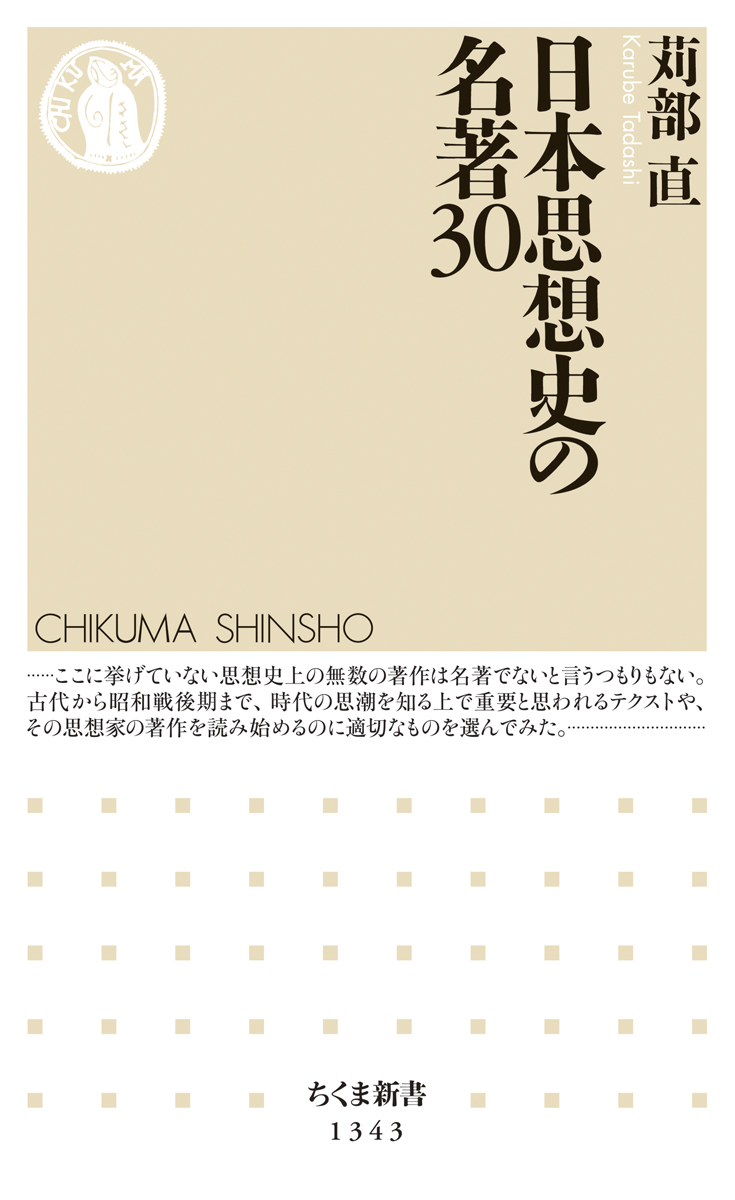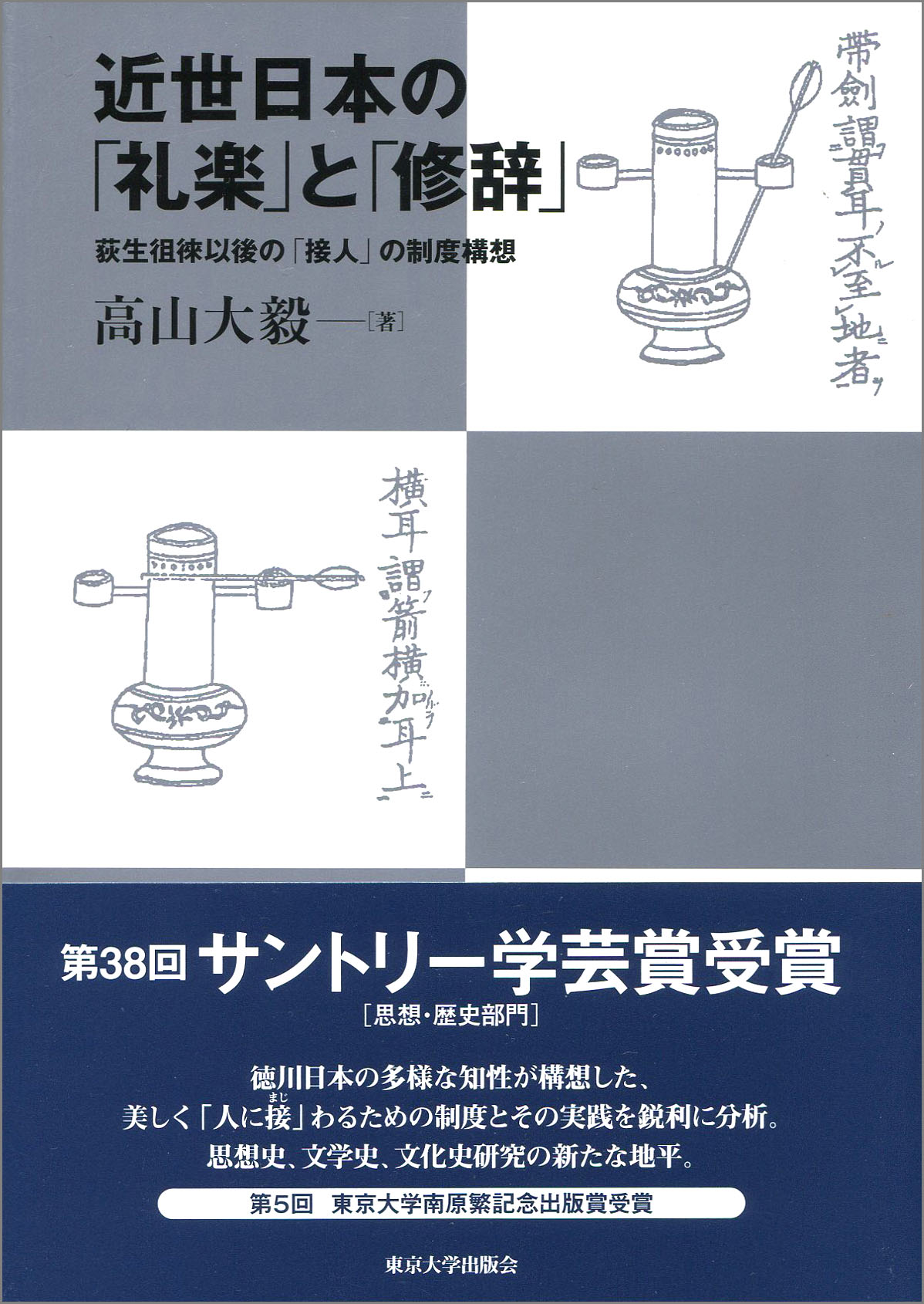
書籍名
近世日本の「礼楽」と「修辞」 荻生徂徠以後の「接人」の制度構想
判型など
416ページ、A5判
言語
日本語
発行年月日
2016年2月29日
ISBN コード
978-4-13-036258-0
出版社
東京大学出版会
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
今世紀の初め頃、学部生だった私は、「日本人」論や「日本文化」論は、そう遠くはないうちに、消滅するものだと思っていた。当時、大学の様々な授業では、国民国家の枠組を前提とする議論は批判されており、また本質主義的な文化論の危うさも盛んに説かれていたからである。地域性・時代性を考慮せずに、「日本人」「日本文化」を一括りにして論じてはならないことは常識となりつつあった。
現在、このような認識は学問の世界では定着しているように見える。しかし今でも、SNSなどを覗いてみると、学術論文を多数発表している研究者でさえ、「日本人」「日本文化」について、素朴かつ粗雑な印象論を述べているのを目にする。中には「欧米では~」(「中国では~」) といった一層大雑把な比較対象を、確たる根拠もなく持ち出して、「日本人」「日本文化」の欠点をあげつらうものもある。 日本 / 欧米 (中国) といった古式ゆかしい対立図式の健在ぶりを見るにつけ、若い頃の自分の予想が楽観的であったことを思わざるを得ない。
時に考えるのは、内容の当否もさることながら、政治問題や社会問題を論じるのに、「日本人」や「日本文化」に言及することは、問題解決に有効なのかということである。Aという問題は「日本人」(「日本文化」) のBという性質に由来する―という論法は、「日本人」(「日本文化」) である限り、その問題は解決できない―という宿命論に接近する。両者を区別することは厳密には可能であっても、多くの「日本人」が前者に後者の意味合いを嗅ぎつけて、反発することは当然の帰結であろう。わざわざ「日本人」「日本文化」に論及しなくても、人類の愚かさの一例として世上の問題を検討し、対応策を提示することは大抵可能であり、そちらの方が無用の反発も招かず、広い支持を得られるのではないか (そもそも真に「日本」特有の問題というのはほとんどなく、他地域にも類似の事案は見られるものである)。
理論的には疑わしく、実践的にはおそらく無益な、贅言としての「日本人」「日本文化」。人々の議論から少しでもそれらを減らすことは、私の願いの一つである。
本書はこのような私の考えと深く結びついている。本書が取り上げるのは、荻生徂徠に始まる、江戸中期以降の人間関係や社交に関する議論の流れである。この一つの学問潮流を例に取っても、その中には様々な型の議論が存在し、それらを単一の「日本的なるもの」に還元して説明することは、個々の思想の魅力を損うだけである。しかも、これらの思想の射程は、現在はおろか未来にさえ及んでいるように私には思える。贅言としての「日本人」「日本文化」に代えて、荻生徂徠や富士谷御杖の所説を引き合いに出すことで、明晰に理解できるようになる問題は多い。本書の一つの企図は、「日本人」論・「日本文化」論的な関心から離れ、近世日本の思想資源の可能性を示すことにあった。
本書は学位論文を元にしているため、原資料の引用が多く、専門外の読者には分かりにくい叙述もある。しかし、おそらく上記のような筆者の目論見を念頭に置いてもらえれば (適宜、専門的な記述を読み飛ばしても構わない)、本書は多くの読者に知的な驚きをもたらすはずであると信じている。
(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 准教授 高山 大毅 / 2019)
本の目次
第一部 「礼楽」
第一章 聖人の「大道術」――荻生徂徠の「礼楽制度」論
第二章 「器」の支配――水足博泉の「太平」構想
第三章 「礼」の遊芸化――田中江南の投壺復興
第四章 遅れてきた「古学」者――會澤正志齋の国制論
第二部 「修辞」
第五章 「人情」理解と「断章取義」――荻生徂徠の文学論
第六章 古文辞派の詩情――田中江南『唐後詩絶句解国字解』
第七章 『滄溟先生尺牘』の時代――古文辞派と漢文書簡
第八章 説得は有効か――「直言」批判と文彩
終 章
関連情報
第五回東京大学南原繁記念出版賞 受賞 (2015年)
http://www.utp.or.jp/news/n20370.html
第38回サントリー学芸賞 (思想・歴史部門) 受賞 (2016年)
苅部 直 (東京大学教授) 評
https://www.suntory.co.jp/sfnd/prize_ssah/detail/201608.html
書籍解説:
自著を語る (東京大学 日本・アジアに関する教育研究ネットワークホームページ 2016年3月18日)
https://asnet-utokyo.jp/publications/introduction/1282
博士論文データベース (東京大学大学院人文社会系研究科・文学部ホームページ 2013年)
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/postgraduate/database/2013/71.html



 書籍検索
書籍検索


 eBook
eBook