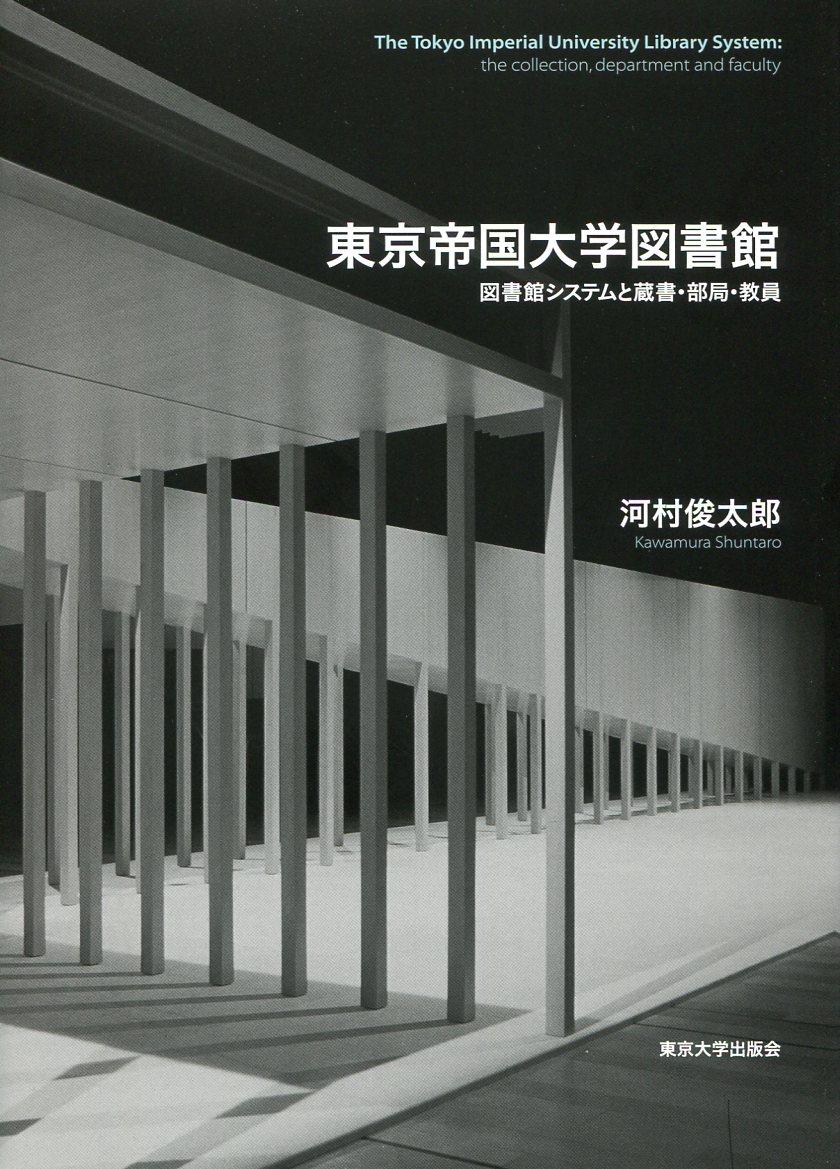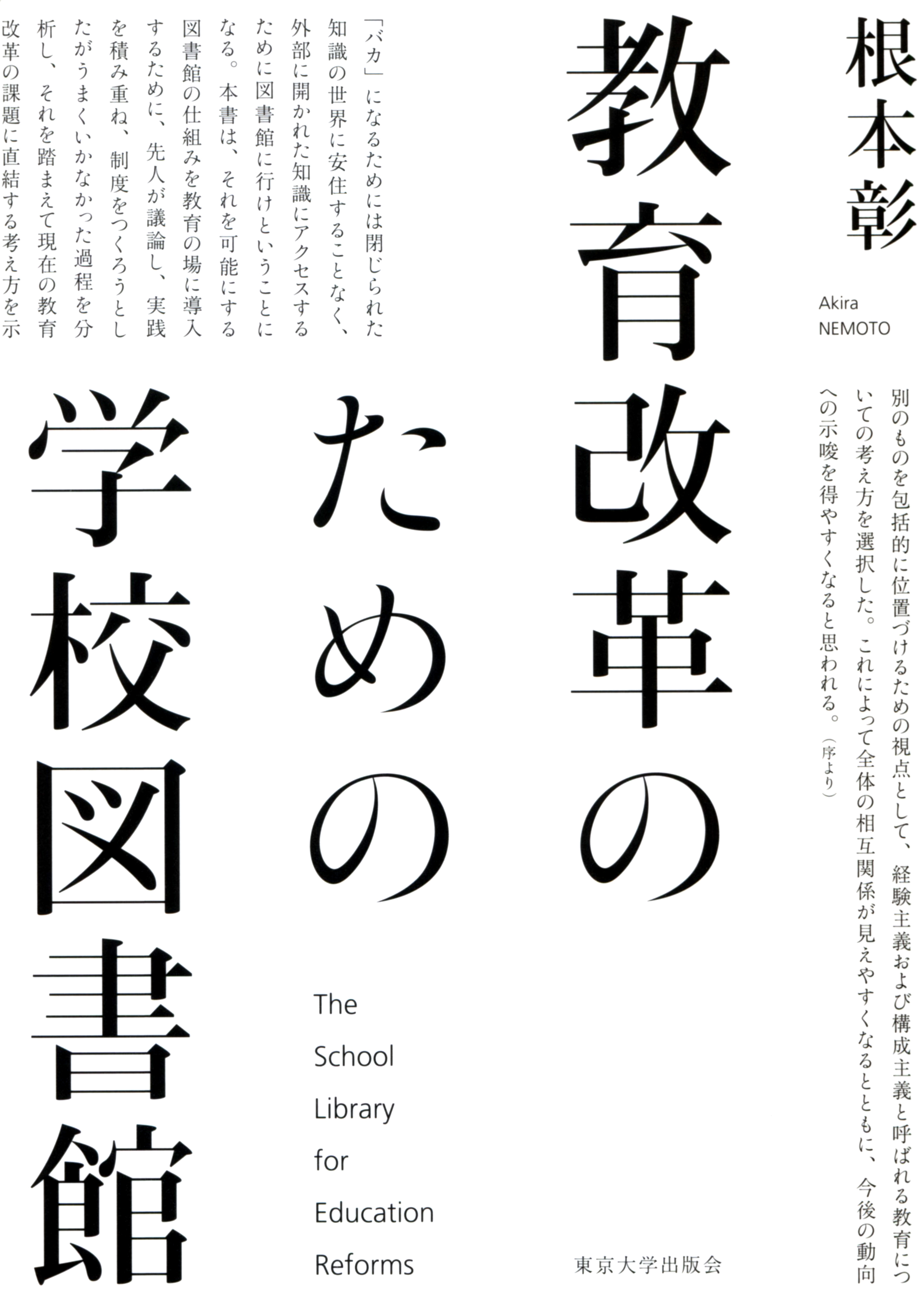
書籍名
教育改革のための学校図書館
判型など
344ページ、A5判
言語
日本語
発行年月日
2019年6月27日
ISBN コード
978-4-13-001008-5
出版社
東京大学出版会
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
この本は、前著『情報リテラシーのための図書館』(みすず書房, 2017) に続いて、私が携わってきた図書館情報学の研究領域のなかで、教育にかかわるものを集大成したものである。とくに今の教育改革と戦後の学校図書館の制度と位置づけがねじれた関係にあったことを整理し、このねじれを解くため提言をしている。
世界的に見て教育方法および教育課程は、知識に関する伝達主義の伝統的モデルから構成主義モデルへと変化しつつあり、欧米では20世紀のうちにそれが進展した。OECDやユネスコのような国際機関はそれをさらにグローバルに展開しようとしている。PISAはその一翼を担うものである。この構成主義教育においては、読解リテラシーをはじめとする言語を介したリテラシーが重要な要素となっている。その起源をたどれば、知を獲得するための有力な方法として哲学的対話法を掲げる古代ギリシアに遡ることができる。この言語論的前提において一貫して重視されるのは、学び手が自分で読んで書き議論する行為を通して、自分自身の考え方をつくりだすことである。こうした学びを支えるものは、自らの経験を反復しながら知識として構成する際に参照する教育的な言語素材である。言語素材は現在では教材としての教育メディアと呼ばれるものであるが、これを制度的に提供する仕組みが必要である。だからそのための有用な教育装置として学校図書館が存在し、そこには学び手に教育的に媒介する専門職員が必要である。
本研究で検討したフランスの中等教育の学校では一校につき一~二名の司書教諭にあたる専任職員が配置されている。アメリカのハワイ州では基本的に学校司書一名と補助的職員一名が配置されている。フィンランドは専門の司書が配置された公共図書館が学校図書館の役割も果たすのが一般的である。また、国際バカロレア (IB) においても、学校図書館を制度化することが基本になっている。
他方、日本では、占領下の教育改革の際に言語教育や経験主義的教育方法が検討され、学校図書館についても一部の学校で積極的に研究されたし、文部省も専任司書教諭の導入も含めて制度化を検討した形跡がある。だが、占領の終了と冷戦体制の開始を背景とした1955年体制下の揺り戻しにより、教育課程行政は系統主義を前提とするものに戻され、学校図書館法は成立したが、その実質的制度化はきわめて限定されたものになった。
文部 (科学) 省の学習指導要領においては1980年代以降、たびたび経験主義的な総合学習や探究型学習の導入が行われるが、そのたびに学力低下を理由とする批判にさらされて、安定して続けることができなかった。ただ、専門的職員を置いて学校図書館を教育課程に組み込みながら探究型の学習活動を進めた学校は少数ではあったが存在している。探究型学習を実施している学校で教育効果が上がっているという報告はあるし、地域全体で探究型学習を政策的に実施している自治体においてもプラスの効果を指摘する人は多い。その効果は、自分を表現する力や集中力や意欲、自己肯定感などの側面で見られるし、上級学校への進学実績に結びついているとの声もある。
こうした歴史的展開と現状認識を元にして、最後に、学校図書館の専門職員配置のための提案を行った。
(紹介文執筆者: 教育学研究科・教育学部 名誉教授 根本 彰 / 2019)
本の目次
第1章 戦後学校図書館制度成立期研究の現状
1 戦後初期教育改革と学校図書館の関係
2 戦後初期教育改革の全体像
3 占領期の学校図書館改革
4 学校図書館制度へのアメリカの影響
5 戦後初期教育改革期の学校図書館史
第2章 占領期における教育改革と学校図書館職員問題
1 学校図書館の法制度
2 占領初期の教育改革と図書館
3 学校図書館基準における「人」の問題
4 teacher librarian と司書教諭,学校司書
5 学校図書館法立法時における司書教諭像
6 学校図書館問題の困難さの淵源
第3章 戦後教育学の出発と学校図書館の関係
1 教育学と学校図書館を結びつけて考える意義
2 戦後教育初期改革と学校図書館
3 戦後初期の学校図書館構想
4 戦後教育学と学校図書館
5 IFEL図書館
6 まとめと課題
第II部 教育改革と学校図書館
第4章 学校図書館における「人」の問題
1 議論の設定と背景
2 戦後初期教育改革と図書館職員の問題
3 学校教育興隆期の学校図書館
4 教育改革と学校図書館法改正
5 ニ職種配置状況の完成
第5章 教育改革と学校図書館の関係を考える
1 学校図書館と図書館の関係に寄せて――物語と情報リテラシー
2 2008年版学習指導要領を読む
3 学校図書館問題への一つの視点
4 21世紀の学校図書館理論は可能か
第6章 教育改革と学校図書館制度確立のための調査報告
1 総合学習・探究型学習と学校図書館
2 探究型学習と学校図書館の関係の実際
3 「調べる学習コンクール」の効果
第III部 外国の学校図書館と専門職員制度
第7章 フランス教育における学校図書館CDI
1 フランス教育の概要
2 フランスの教育改革と学校図書館の沿革
3 学校図書館の実地調査に入って
4 おわりに
第8章 米国ハワイ州の図書館サービスと専門職養成システム
1 図書館員数の概略
2 ハワイ州の図書館と図書館員
3 図書館員制度と養成
4 書物文化の公的装置としての図書館
第IV部 日本の政策的課題
第9章 学校内情報メディア専門職の可能性
1 日本の図書館員養成課程
2 LIPER図書館情報学カリキュラム
3 LIPER学校図書館班中間報告
4 学校内情報メディア専門職の養成案について
5 その後の学校内情報メディア専門職論
第10章 日本の教育改革の課題と学校図書館の可能性
1 歴史的展開のまとめ
2 構造主義学習論と学校図書館
3 教育政策との整合性
4 来るべき学校図書館職員論のためのメモ
関連情報
公開シンポジウム「教育改革のための学校図書館」 (慶應義塾大学三田キャンパス 2019年11月30日開催)
http://oda-senin.blogspot.com/2019/07/blog-post_27.html
著者ブログ:
http://oda-senin.blogspot.com



 書籍検索
書籍検索