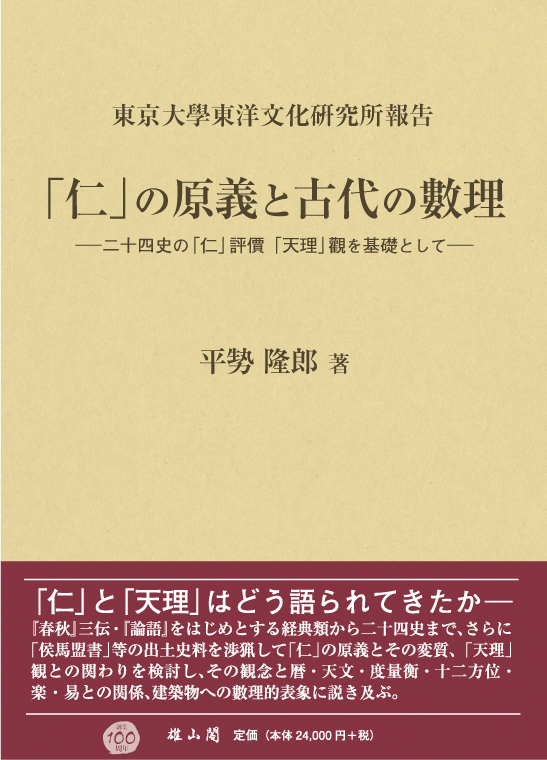
書籍名
「仁」の原義と古代の数理 ―二十四史の「仁」評価「天理」観を基礎として―
判型など
556ページ、B5判、上製、函入
言語
日本語
発行年月日
2016年12月10日
ISBN コード
9784639024538
出版社
雄山閣
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
仁は儒教研究者にとってのキーコンセプトである。その意味として「親愛」・「慈善」・「美徳」・「道徳」・「善徳」等が議論される。欧州の研究者が儒教経典を読む際は、一般に「ベネヴォレンス」の語をもって理解する。しかし、この仁は、近代にいたるまでの2000年、一般の理解とは異なる基本義をもっていた。本書はこのことを発見したことを論じ、さらに始皇帝統一以前に遡り、仁の原義を考察する。
仁概念を理解するには、天理の語を検討しなければならない。わが検討によれば、二十四史において、仁は皇帝の特別な徳であり、官僚を通して天下に及ぼされる (万物一体の仁)。その下位の部署である獄において、官僚は二択を迫られた。厳格に天下の法を執行するか、または皇帝の名の下にその執行をゆるめるかである。ここから、一般に理解される仁の派生義 (官僚の仁徳) が生まれた。
天理概念は二つに分けて議論できる。『舊唐書』以前と『新唐書』以後である。『舊唐書』までは、天地に平面・立面の図形を描いて天理を理解した。それは具体的に建築や仏教寺院の伽藍配置に示された。特に注目したのは正八角形であり、『易』の八卦方位が基礎にある。『新唐書』以後は、そうした考え方が次第になくなった。
戦国時代には、その図形的理解のプロトタイプがある。しかし、現代の研究者はその存在に理解が及んでいない。春秋時代と戦国時代中期以前には、このプロトタイプはまだ出現していない。現代の研究者は、このことにも理解が及んでいない。
戦国中期以後、上記のプロトタイプが出現した後も、天理概念はまだ出現していない。しかし、八卦方位は議論が始まった。三分損益法による音楽の音の作り方によりつつ、これに天文観を重ねて、天・地・人を理解している。
戦国中期にいたるまでは、三分損益法による音の作り方だけを知っていた。そして春秋中期以後に官僚制のプロトタイプを作り、春秋後期以後に仁概念のプロトタイプを作り出した。
小国が存在する中で、県制のプロトタイプが始まったが、小国、県いずれにも族的秩序が残されていた。しかし、大国の武威は小国、県いずれにも及んだ。彼らは国際的な祭祀の場を用いていた。各国と王都を結ぶ宿場もその一つであり、日本の思いやりのような感情をお互いの祭祀の場に対して抱いていた。仁はこの種の大国の武威を背景とする知識であり、思いやりの感情が含まれる。
戦国中期から、小国やプロトタイプの県は官僚制下の県に変わり、仁は官僚制を通して県にもたらされる王の特別な徳となった。二十四史の時代には、仁は皇帝の特別な徳になる。
上記のような変動の結果として、近代の研究者の理解は、春秋時代や戦国時代のそれとやや似たものとなった。そのため二十四史の時代の皇帝の徳を読み取ることができなかった。そして、戦国時代のそれも理解できなかった。そして上記のような仁の原義が春秋時代後期の孔子の時代に存在することも、気づかなかったのである。
本書の結論は、二十四史と伝統的儒教経典に基づく。数理は、三分損益による音楽の音の作り方と平面・立面の図形構成等に基づく (ギリシア・ローマの古典と同様に)。この概要には、「仁」評価自体等について、あえて触れなかった。
(紹介文執筆者: 東洋文化研究所 教授 平㔟 隆郎 / 2019)
本の目次
第一章 正史を通して知る「仁」と「天理」
第一節 正史を通して知る「仁」
第二節 正史を通して知る「天理」
第三節 他の正史の「仁」と「天理」
資料I『史記』・『漢書』・『晉書』・『舊唐書』・『新唐書』・『明史』の「仁」・「天理」
資料II 『後漢書』~『元史』の「仁」
資料III 『後漢書』~『元史』の「天理」
資料IV 緯書の「仁」・「天理」
第二章 先秦史料を通して知る「仁」とその原義
第一節 經典と「仁」
第二節 『春秋』三傳と「仁」
第三節 『論語』の「仁」と侯馬盟書
資料V 『論語』・『孟子』・『荀子』・『韓非子』・『禮記』の「仁」
資料VI 『春秋』三傳の「仁」― 附:『尚書』と『毛詩』の「仁」 等
第三章 古代の數理
第一節 三正説と數理
第二節 天理の物と建築
終章 先行研究とどう關わるか
中文概要
英文概要
あとがき
索引
関連情報
著者からの紹介 (東洋文化研究所ホームページ 2017年1月6日)
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/news/news.php?id=ThuJan261040292017



 書籍検索
書籍検索


