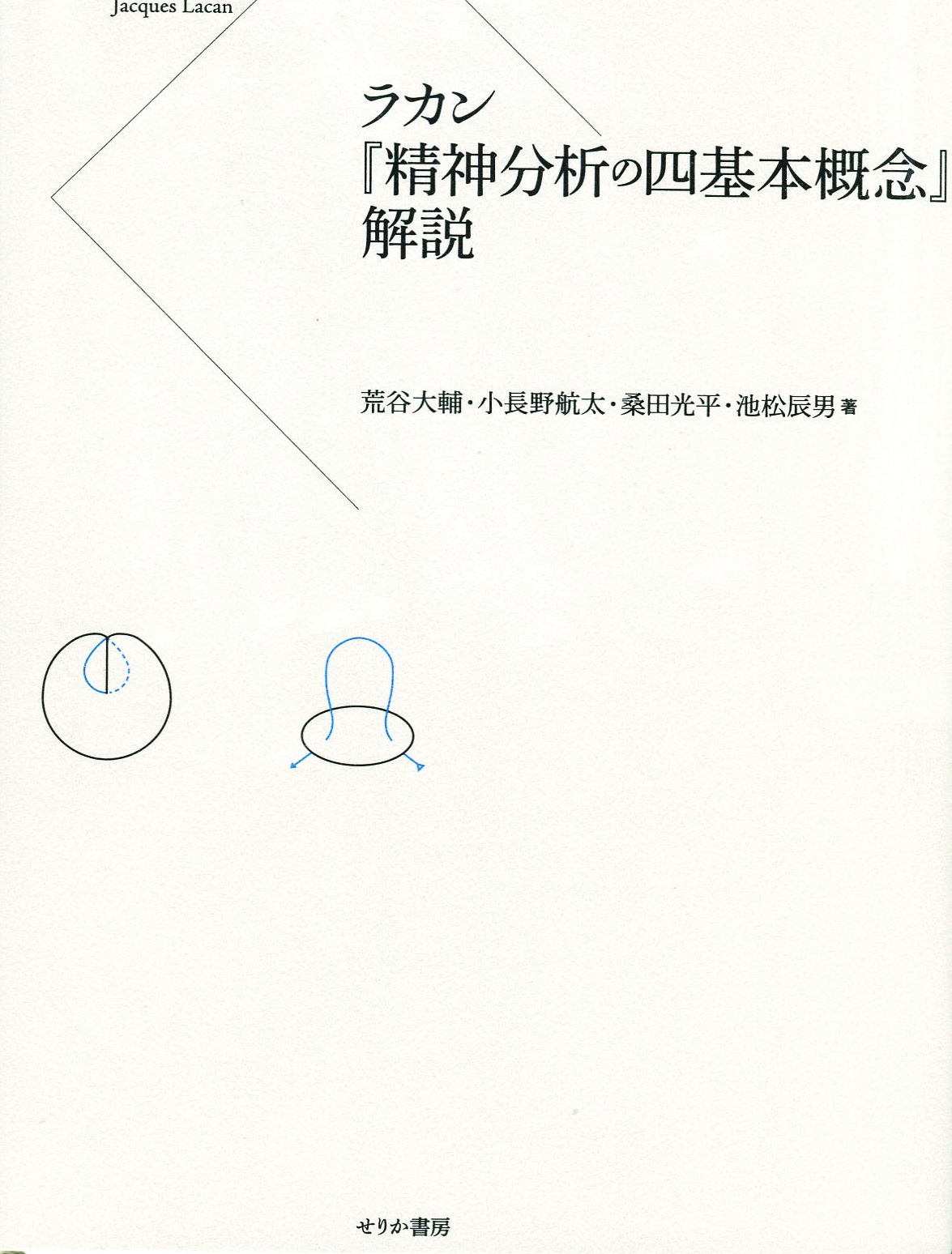19世紀の終わり、ウィーンの神経科医ジーグムント・フロイトがヒステリーの治療法として考案した精神分析が、やがて世界中に広がり近代的な心理療法の原点となったことはよく知られている。定着した先々でそれぞれ異なった発展を遂げることになるこの実践だが、フランスでは人文科学、とりわけ言語学や文学、哲学との密接な関係のうちで、その独自のスタイルが形成された。そしてその中心となったのが、精神分析家ジャック・ラカンである。
古典的な哲学を独自の観点から読み解き取り入れたラカンの議論は、同時代の先進的な哲学者らの関心を惹かずにはいなかった。1950年代以降にラカンが彼らにもたらしたインパクトは、参照や影響というかたちをとることもあれば、競合や反発、さらには激しい批判といったかたちをとることもあった。ただそこにはいつも、二つの営みをあくまで異なったものとして捉える、精神分析「と」哲学、という枠組みが存在していたように思われる。大学的な制度の中ではいかにも自然なものと映る区分だが、なるほどその観点からすれば、ラカンは「精神分析家」であって「哲学者」ではなく、したがって彼の行っていることは「哲学」ではない、ということになるのかもしれない。しかし果たして本当にそうなのか。
本書の著者であるフランスの哲学者アラン・バディウは、こうした制度的な柵 (しがらみ) を軽々と飛び越えて、ラカンは哲学者である、と宣言する。このことにはおそらく彼が二十歳になるかならないかの時期、哲学者としていわば出来上がってしまう前に、ラカンの思想に出会って大きな衝撃を受けたということと深く関係しているだろう。ただこの大胆なテーゼを支えるために、バディウは彼自身、二重の問いを引き受ける必要があった。すなわちそもそも哲学がどのようなものとして考えられているために、ラカンは哲学者ではないとされているのか、という問いであり、そしてにもかかわらず哲学は本来どのようなものであるからこそ、実はラカンは哲学者であると言えるのか、という問いである。そしてこれに対するバディウの答えの核心に置かれているのが、他ならぬこの「反哲学」であった。
「反哲学 (antiphilosophie)」というフランス語は18世紀、啓蒙哲学に反対するキリスト教勢力がこれを標榜していた時代にまで遡る。実際バディウは、一般に哲学を批判的な仕方で、あるいは彼の言い方に従うならば「その信用を失墜させるような」仕方で捉えようとする立場を、この語によって指し示すだろう。ただ同時にバディウにとって「哲学」と「反哲学」は、物理学における「物質」と「反物質」と同様に、哲学がそもそも単一ではない、二重の起源を持つということの謂いでもあった。そしてパルメニデスとヘラクレイトスに体現されるこの二重性が、さしあたり前者の方向へと解消され、その先に展開された〈存在〉をめぐる思考、ハイデガーの所謂「形而上学 (メタフィジック)」が「哲学」の広く受け入れられた姿を規定している一方で、後者に発する系列も完全に途絶えることはなく、「哲学史」の内外で間歇的に顔を覗かせている、とバディウは主張する。したがって彼がこの、古くはストア派から、聖パウロ、パスカル、ルソー、キルケゴール、ニーチェ、ウィトゲンシュタインへと続く「反哲学」の系列の中にラカンを位置づけるとき、それが意味しているのは、ラカンが哲学に反対ないし対立しているということでは決してなく、むしろ彼が哲学の別のあり方を示しているということなのだ。ただしバディウがラカンに与える地位は、単に一反哲学者というにとどまらない。彼はラカンが、この系列を締め括る反哲学者であり「最後の反哲学者」であるとして、そこを起点として開始される「哲学」の新たな姿を思い描こうとするのである。
以上のような構想のもとでラカンの「反哲学」を全9講にわたる講義の形で論ずる本書は、1988年の『存在と出来事』で提示されたバディウ自身の考える哲学のあり方を逆照射すると同時に、1989年の『哲学宣言』でラカンになぜ「哲学の再生の一条件」という重要な地位が与えられたのか、その理由を詳述するものとなっている。そしてそれ以上に、本書は一人の若者が、ラカンの精神分析から受けた衝撃に発する問いを、哲学の道に進んだ後も手放すことなく、実践を含むこの営みの総体に真摯に向き合い続けた結果どのような地点にたどりつくことができたのかを示す、いわば実存を賭した学際研究の可能性についての貴重な証言でもある。ぜひ若い学生の皆さんに手に取ってみてほしい。
(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 教授 原 和之 / 2020)
本の目次
第I講 1994年11月9日
第II講 1994年11月30日
第III講 1994年12月21日
第IV講 1995年1月11日
第V講 1995年1月18日
第VI講 1995年3月15日
第VII講 1995年4月5日
第VIII講 1995年5月31日
第IX講 1995年6月15日
謝辞
訳者あとがき
セミネール一覧
参考文献
人名索引



 書籍検索
書籍検索