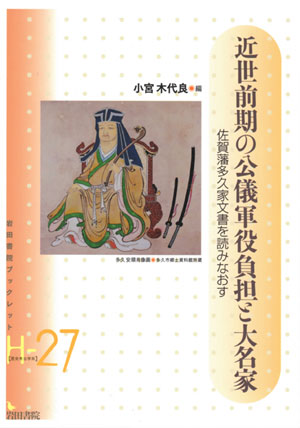
書籍名
岩田書院ブックレット歴史考古学系 H27 近世前期の公儀軍役と大名家 佐賀藩多久家文書を読みなおす
判型など
142ページ、A5判、並製
言語
日本語
発行年月日
2019年3月
ISBN コード
978-4-86602-066-2
出版社
岩田書院
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
本書は、東京大学史料編纂所近世史料部門で近世初期の編年史料集を担当してきたメンバー (編著者を含む)と、佐賀県内の歴史資料館、博物館、文化財行政、図書館等に勤務のメンバー等、あわせて10数名による数年間の共同研究プロジェクトの途中経過報告書である。
本書のタイトルにある公儀軍役とは、日本近世国家成立過程における重要な概念である。本書の目的のひとつは、この公儀軍役の実態分析を深めることであり、その結果、17世紀前半における佐賀藩の公儀軍役負担についての多様な具体相が明らかにされている。
とはいえ、本書の目的はもう一つある。それは、サブタイトルに「佐賀藩多久家文書を読みなおす」とあるように、すでに知られている史料群の読みなおしを行うということである。
多久家文書は、佐賀藩の重臣である多久家に伝来したおもに中世から近世に至る膨大な文書群であり、現在、多久市郷土資料館に所蔵されている。多久家文書のうち、中世から近世初期の部分については、1960年代に、佐賀県立図書館編集の『佐賀県史料集成』の一環として、佐賀大学教授三好不二夫氏の手により、700通余分が活字化され刊行された。
今回、その多久家文書の『佐賀県史料集成』収載分を、私たちが「読みなおす」にいたったのには、以下の経緯がある。
史料編纂所で刊行している編年史料集である『大日本史料』江戸時代初期分の編纂進行のためには、同時に進めていかなくてはならないことがある。日本における歴史資料の現在まで伝存する量は、中世後期分以降のものから等比級数的に増えていくが、とくに江戸時代初期にはいると、地域ごとの広がりも生じてくる。編纂のためには、ひとつひとつの古文書の年次比定が必要である。これまで、大名家文書を中心として、かなりの文書が活字化され、可能な範囲で年次比定がなされてきたが、まだ不十分であり、さらに、大量に残されている大名家臣家文書等にいたっては、ほとんどがこれからの課題である。一方では、地域史の深化のためには、これらの地域ごとの資料群の研究資源化を進め、かつその担い手を増やしていくことが必要となっている。
多久家文書の『佐賀県史料集成』版は、上記のようにきわめて早い段階で、大名家家臣史料群の一部を公刊したものであり、その後の関連研究の進展に大きく寄与しているが、すでに刊行から50年以上を経ており、この間には、関連する他の史料群についての分析も大きく進んでいる。膨大な量をほとんど一人で受け持たれ、刊行ペースの制約等もあったためか、人名比定や年次比定の成果については、一部を除いて示されていない。
本プロジェクトは、以上のような共通認識を前提として、史料編纂所の共同利用・共同研究拠点特定共同研究のひとつとして開始され、その後、科研費による研究として継続し、今年度で通算7年目になる。プロジェクトの参加者全員が、精細な史料画像を共有し、原本の確認をおこないつつ、担当者をきめたひとつひとつの古文書について、その作成者や関係者の居所、内容、形態、関連史料等を確認しつつ、論理的に確定できる年次の検討を重ねてきた。本書は、多久市でおこなった報告シンポジウムでの成果を中心とするが、目次にも示されているように、これらの年次比定過程の明示が大きな柱となっている。
伝来してきた膨大な歴史資料について、上記のような作業を積み重ねていくことは、今後の我々の歴史研究、ひいては歴史認識の精度をあげていくのに欠かせない。そしてそれは、今後も、50年、100年単位で繰り返し見直されていくべくものだと考えている。
(紹介文執筆者: 史料編纂所 教授 小宮 木代良 / 2020)
本の目次
-多久家文書にみる公儀普請- 及川 亘
近世初期の公儀普請と佐賀鍋島家/
現場監督する大名/
「多久家文書」の名古屋城普請関係鍋島勝茂自筆書状
第二章 多久家文書にみる大坂冬の陣後の城割普請 大平直子
「爰元御普請」と将軍の御馬入り/
将軍徳川秀忠の上洛と大坂城の城割普請
第三章 佐賀藩の長崎警備
-正保二年の鍋島勝茂書状を中心に- 清水雅代
正保二年の鍋島勝茂書状/
鍋島勝茂の国許における対応/
鍋島勝茂の江戸における対応
第四章 明清交替情報と佐賀藩の長崎番役 小宮木代良
多久家文書127号の年次比定/
残された疑問-新見の長崎派遣の目的は何か/
明清交替情報を幕府はいつから得ていたか/
大名たちは、明清交替情報をいつどのように認識していたか/佐賀鍋島藩内における明清交替情報への反応
附章一 めでたき春
-寛永十六年正月勝茂親子の将軍御目見え- 松田和子
多久家文書38号の年次比定/
多久家文書509号ゆき消息
附章二 鍋島勝茂自筆文書の特徴
-形態・封式を中心に- 及川 亘
鍋島勝茂自筆文書の形態・封式/
鍋島勝茂自筆文書の傾向
附章三 「御上洛」情報の真偽 佐藤孝之
多久家文書244号の年次比定と御上洛/
多久家文書253号の年次比定と御上洛
附章四 肥前杵島郡白石地域と鍋島勝茂 小宮木代良
多久家文書5号の年次比定/
白石秀之屋敷と鷹狩り/
秀津の勝茂の由緒・文書
関連情報
細川章「多久古文書の村」 (『岩波講座 日本通史 別巻2 地域史研究の現状と課題』、木村礎他編 1994年、岩波書店)



 書籍検索
書籍検索

