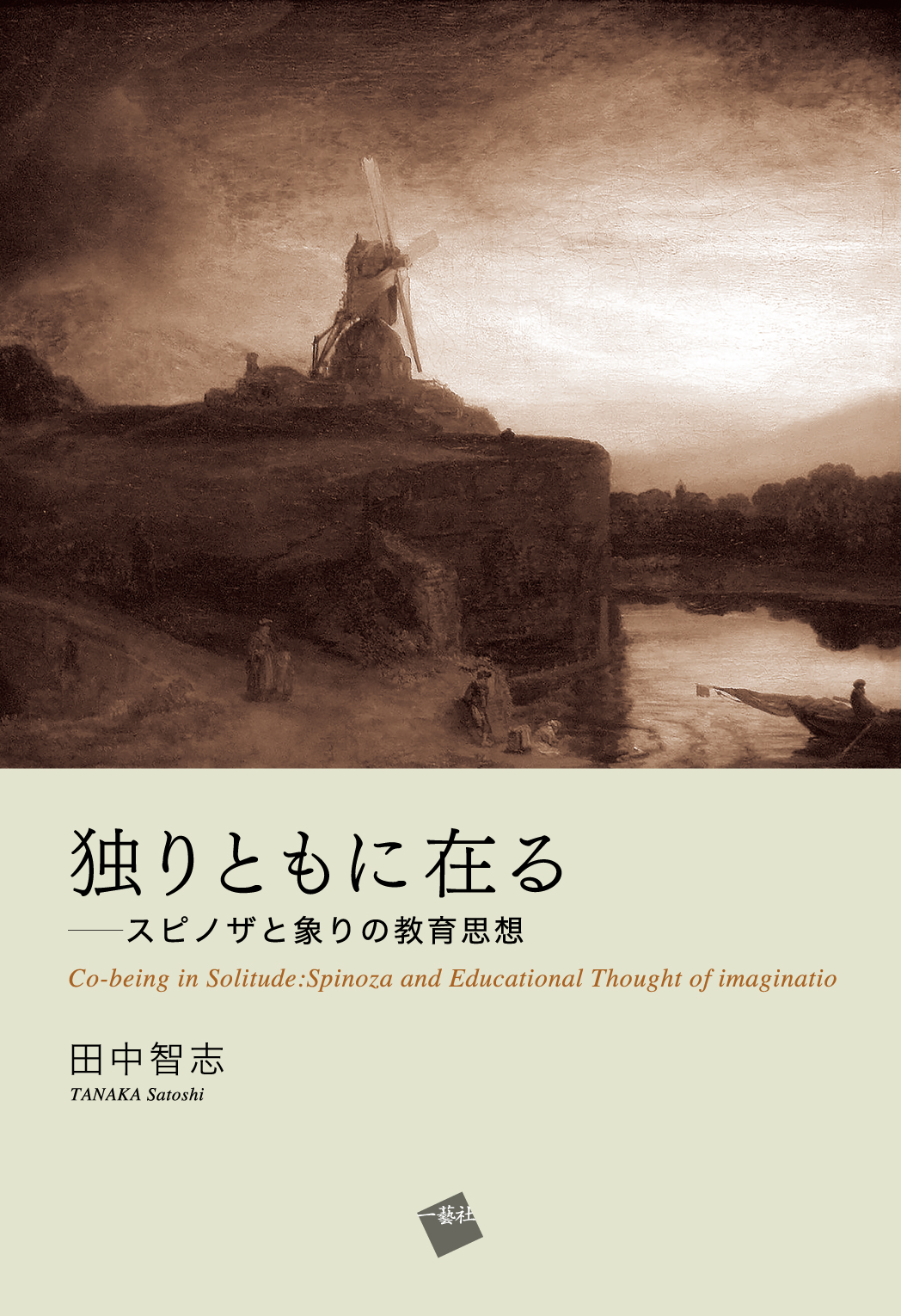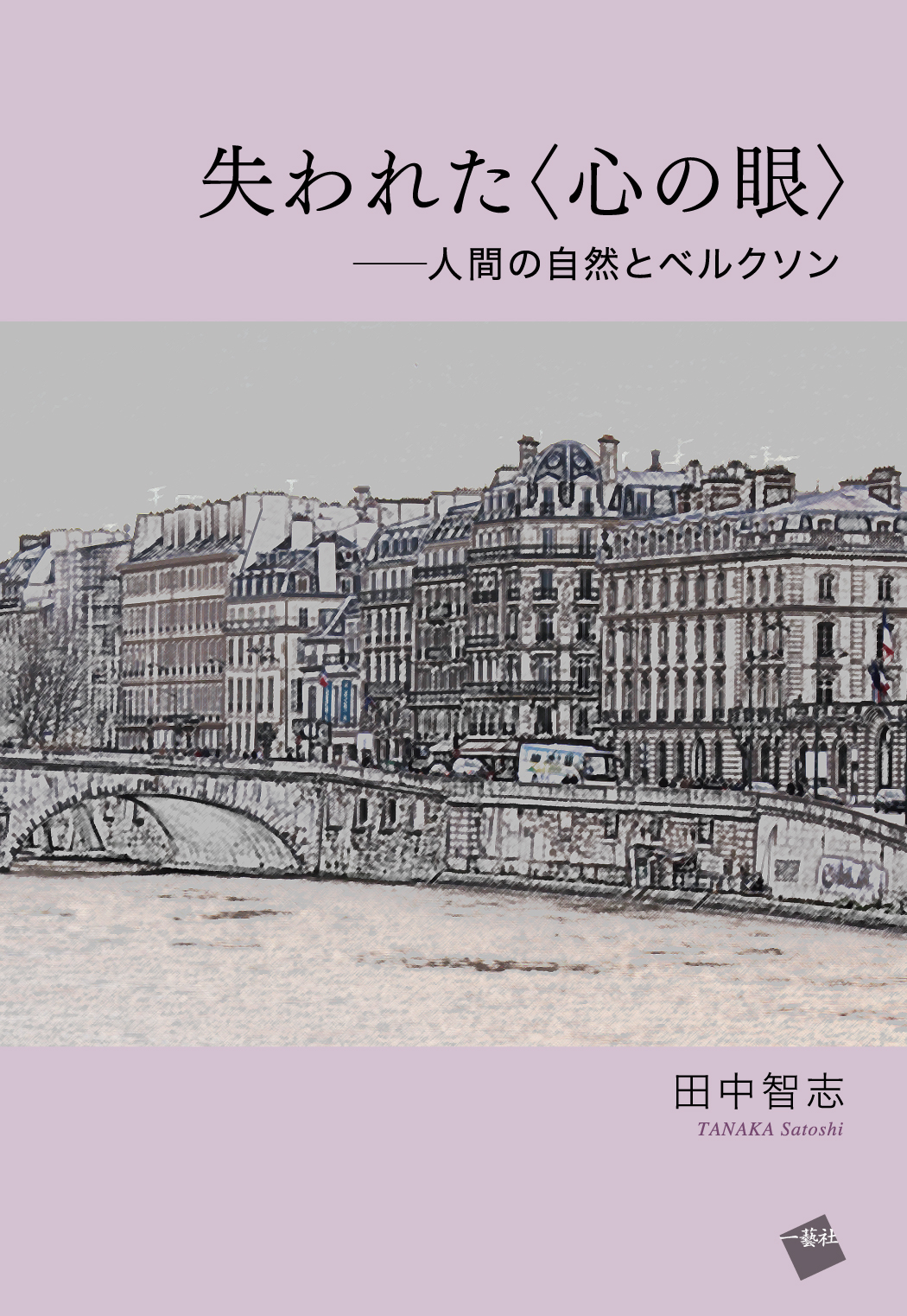現代社会には、さまざまなコミュニケーションが溢れている。人びとは、器用に端末の画面にふれ、たえず連絡をとりあい、短く速やかに情報をやりとりする。そうしたコミュニケーションは、人の孤独を暗示しているように見えるだけでなく、人が人と寄り添いつつも、独り生きる姿を覆い隠しているようにも見える。たとえば、はるか昔に死んだ会ったこともない人と、その人が書き残したものをつうじて、独り沈黙、静寂のなかで語りあう姿を。
人は、何らかの組織の一員として機能的・実利的にだれかと共同・協働するまえに、また平和、人権、公共性などの社会的価値をかかげて活動し自分を納得させるまえに、すでに他者とともに存在している。その共存在する姿は、自分の利益、自分の属している組織の利益を守り増やすために懸命になっている人たちには、見えにくいらしい。
どんなに他者と語りあっても、私たちは、独りのままである。独りは、心理学が語る個別性でもなく、欲望が作りだす自己でもなく、だれかの呼び声に応えるかぎりの人の姿である。利益、証拠、年収、学力などを熱心に語る現代社会の意味世界は、この独りも、ともに在ることも、否定ないし看過する考え方に傾いているように見える。
だれかとともに在ることは、そのだれかとのきめこまやかな交感、または圧倒的な共鳴共振に彩られている。そのつながりのなかで生きるかぎり、人は、どうしてもただ独りになってしまう。そこでは、さまざまなコミュニケーションに響きわたる、あの〈さあ、みんなで!〉という鬱陶しい掛け声は、朝日のなかの朝靄のように消え去っていく。
本書は、おもに一七世紀オランダの哲学者スピノザに助けられながら、よりよく生きようとする力を、発達・成長ではなく、超越・創始を語る〈鏡〉の隠喩のなかで、語ってみることである。そのとき、無垢が、脱構築できない概念として立ち上がる。それは、客観的事実でも、主観的想像でもなく、古来、ヨーロッパの人びとが心の奥底に見いだした〈鏡〉である。その〈心の鏡〉(speculum mentis) は、よりよく生きようとする人に、形のないまま現れる。すなわち、心そのものとして。
現代の教育のめざすところが、どれほど機能的で実用的であるとしても、つまり経済的利益と工学的技術を求めていても、そうした有用性を指向する趨勢を越える思考が必要とされるだろう。その一つが、ここで描きだそうとする〈心の鏡〉である。それは、ヨーロッパで古来、キリスト教思想のなかで語られてきたが、近代とともに忘れ去られた。それにあたる言葉は、スピノザの『エティカ』のなかでも、たった一回だけ使われているだけである。
いまさら、そんな死語にひとしい言葉をヨーロッパ思想史の地下室から引っぱり出すことは、ただの懐古趣味の道楽だ、という人もいるだろうが、その〈心の鏡〉は、現代においても、人が〈よりよく〉生きようとするかぎり、出来しうる心の状態である。少なくとも、痛々しいまでに繰りかえされるコミュニケーションの繁茂からできるだけ離れて、また利益や証拠や権力におもねることなく、できるだけ自然に豊かに生きようとするかぎり。
(紹介文執筆者: 教育学研究科・教育学部 教授 田中 智志 / 2021)
本の目次
第一章 呼応の関係へ――スピノザの認識三態
第二章 イマーゴへの与り――遠ざけられた共鳴共振
第三章 受容と感情――〈感じる〉について
第四章 概念と観念――〈考える〉について
第五章 知解と自然――〈独り〉について
第六章 先導性を象る――逆理の力動と呼応の関係
終章 遡及的に思考する――独りともに在る



 書籍検索
書籍検索