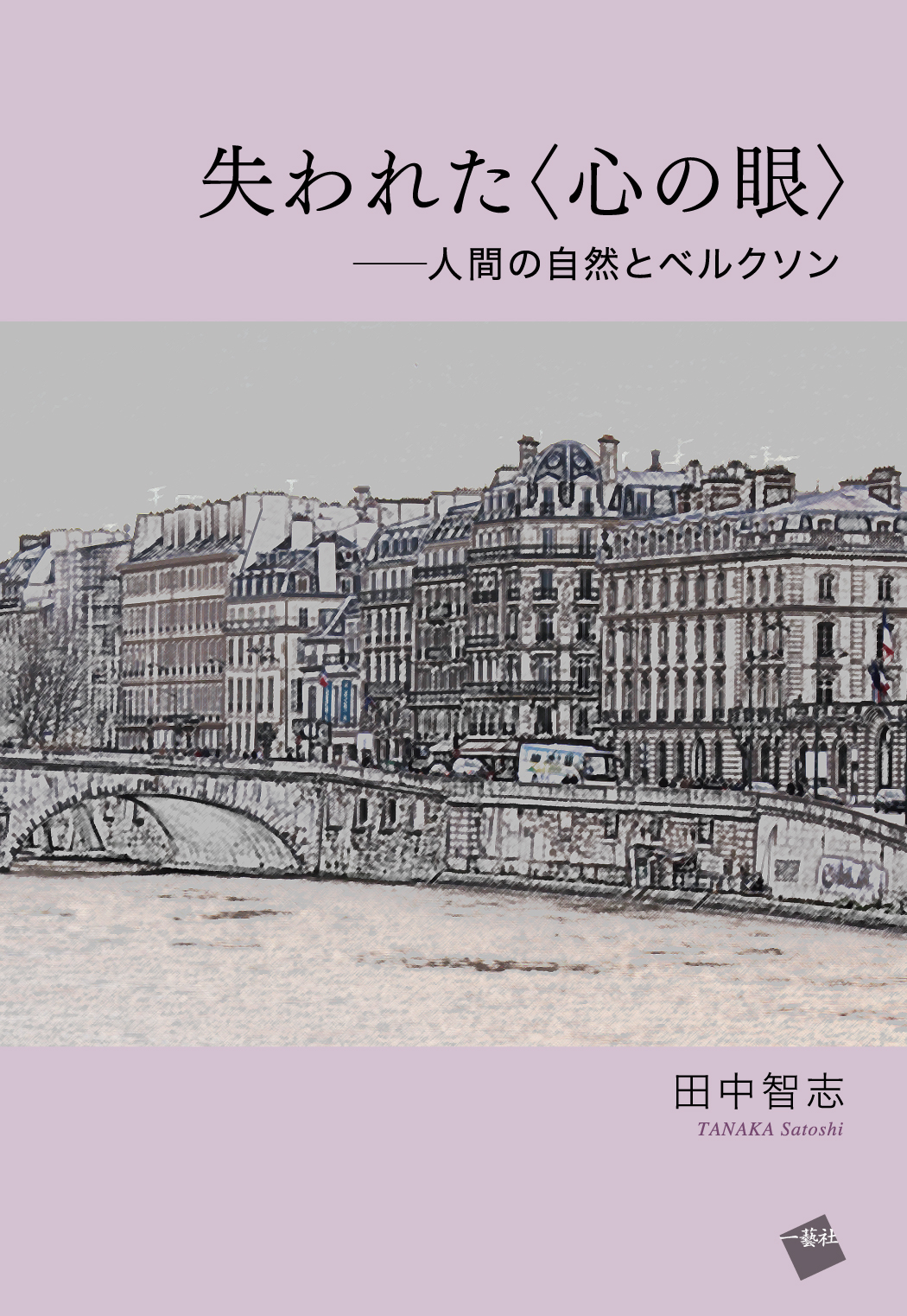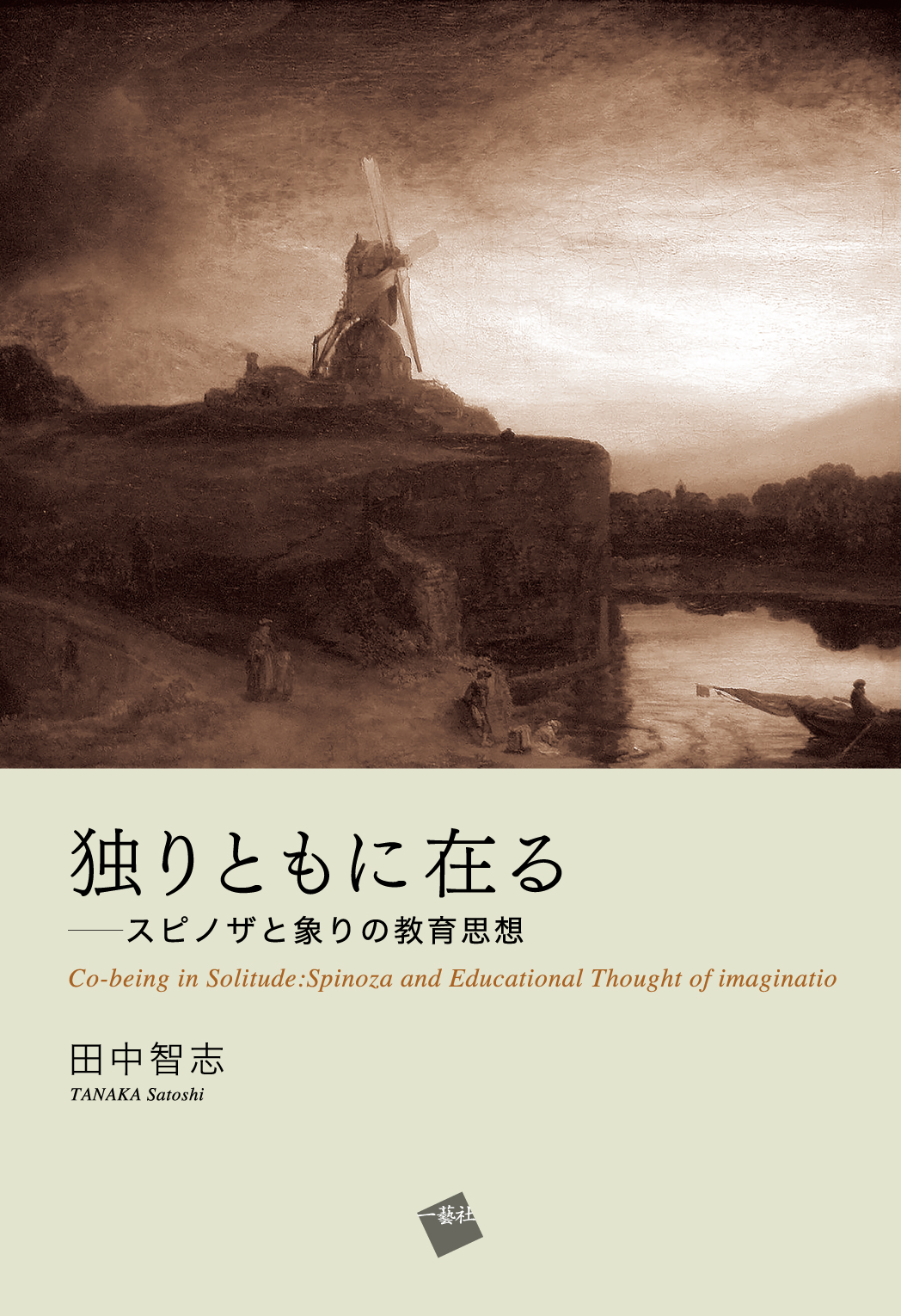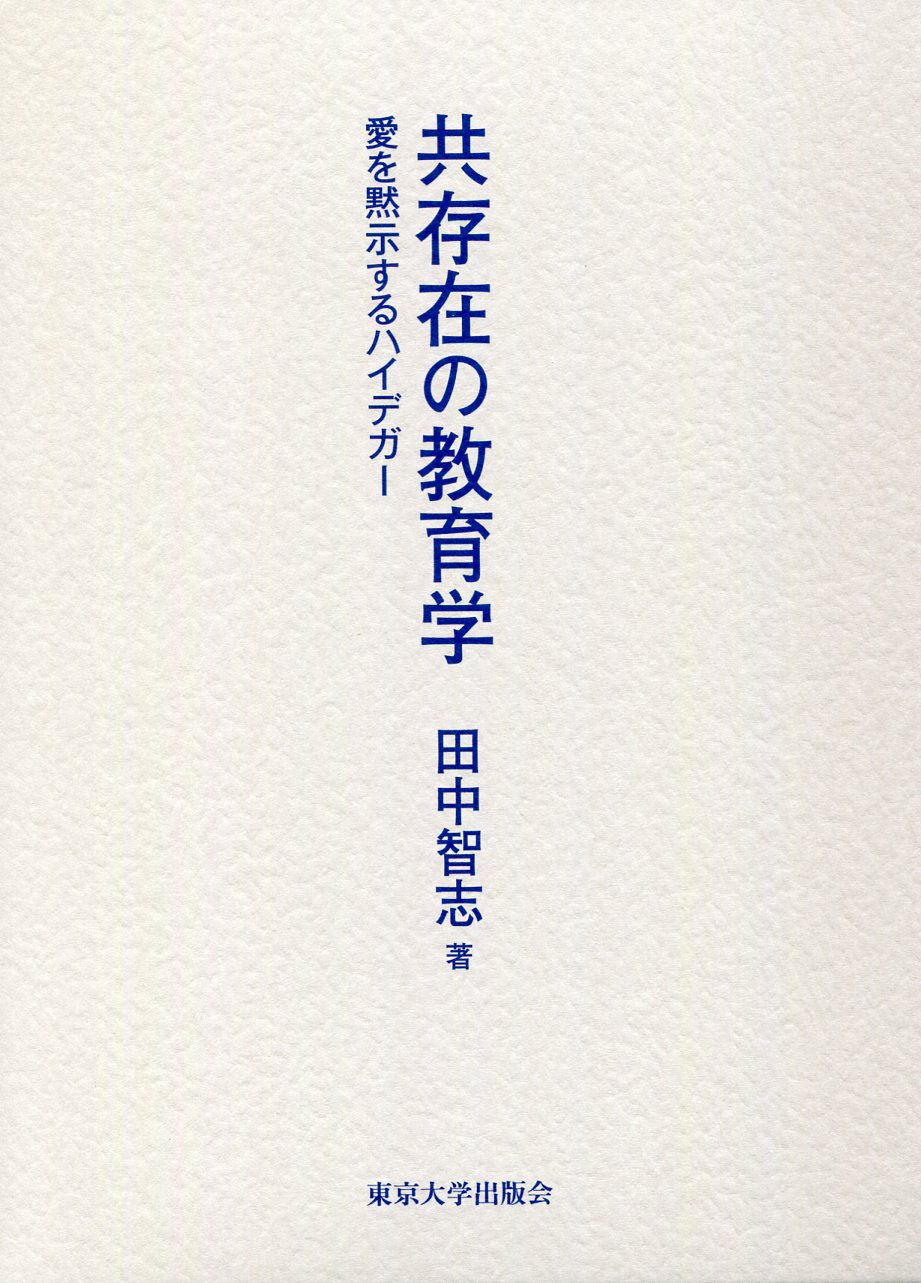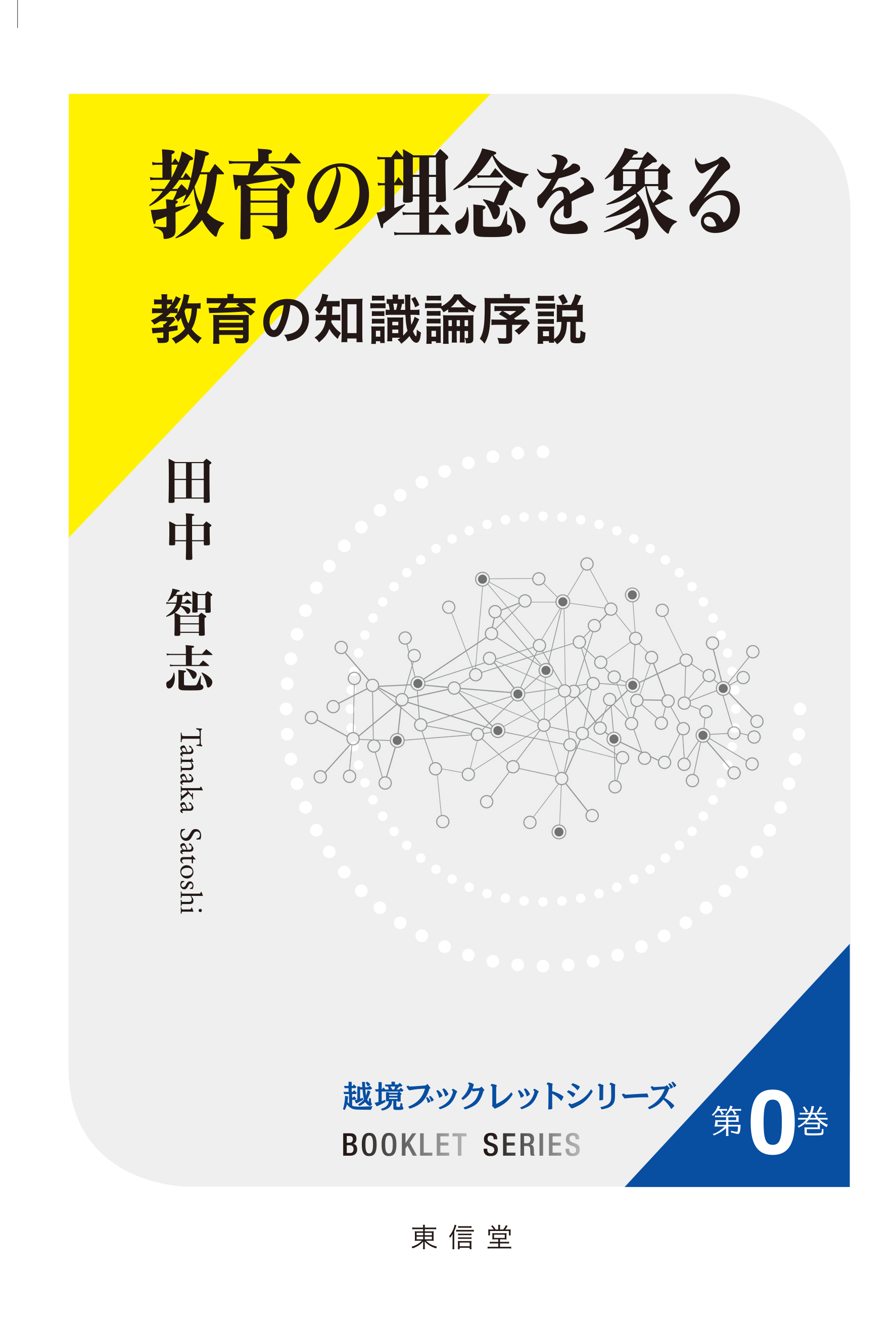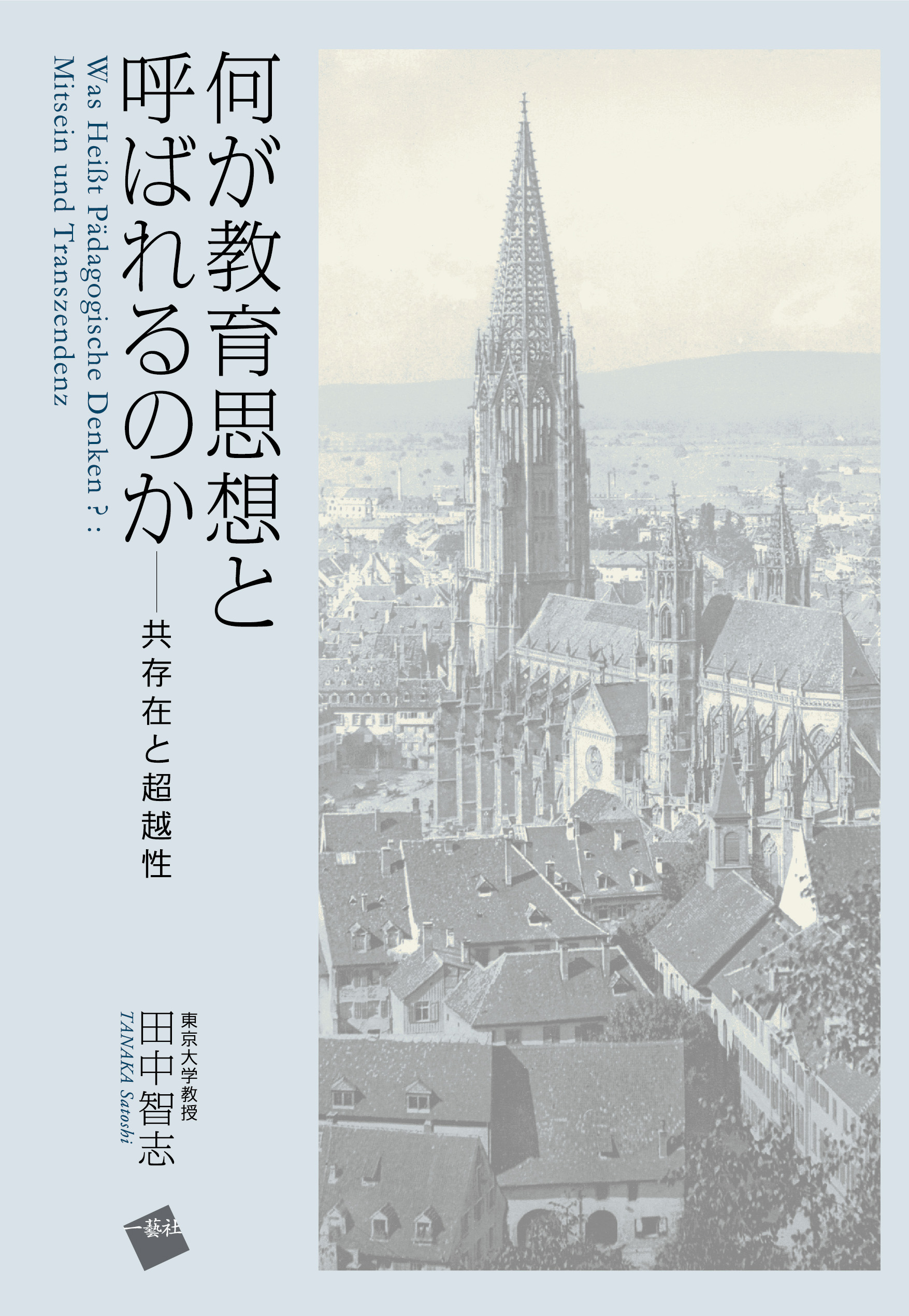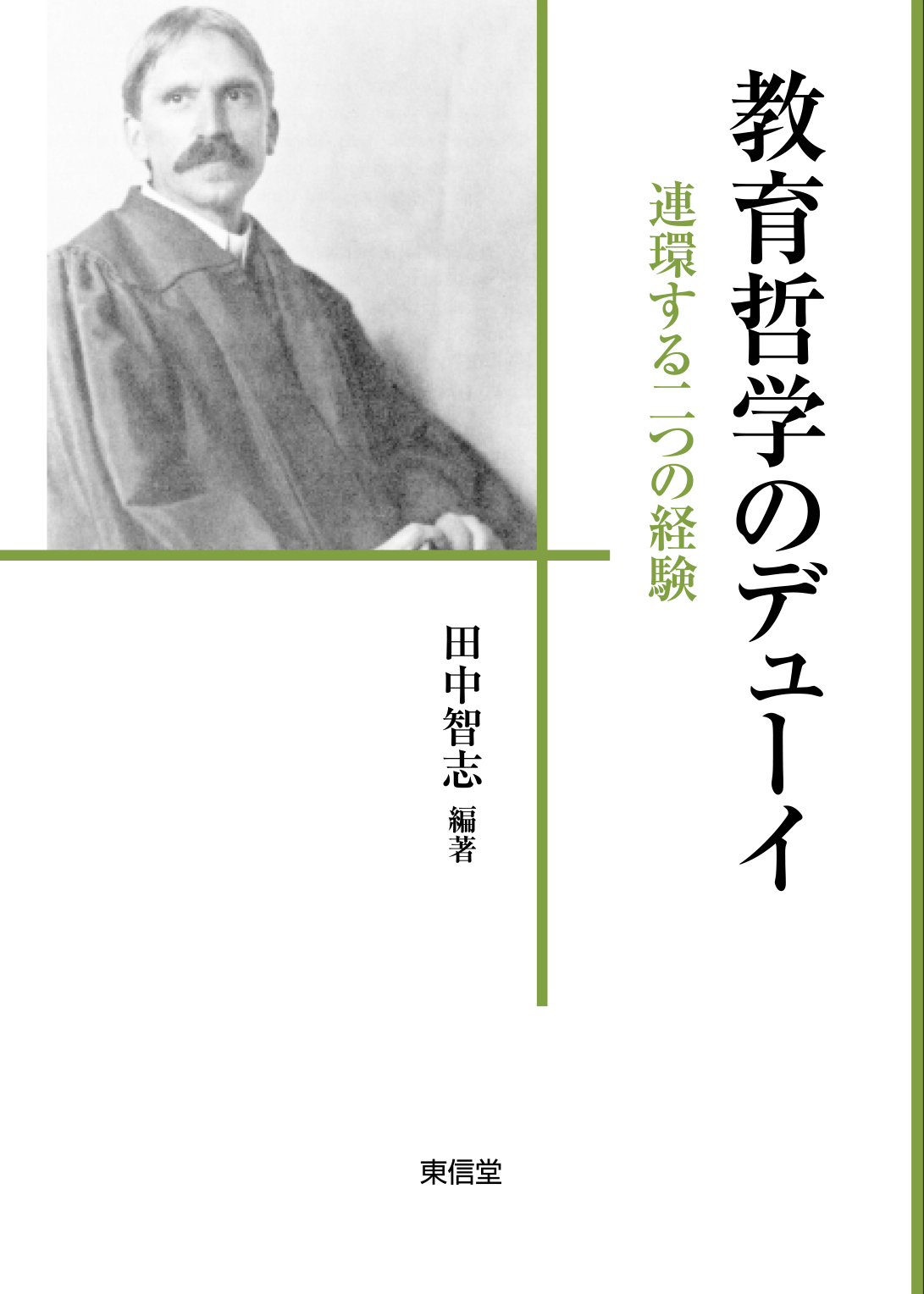本書の主題は、ヨーロッパの古いキリスト教思想の人間 (humanitas, Natura humana) の概念に立ちかえることで、現代の人間の概念を豊穣化し反時代的なものにずらすこと、そうすることで、一人ひとりの自己創出 (autopoiesis) の営みを方向づける台座を設え、あらたに選択し思考する可能性を広げることである。本書でいう自己創出は、おのずから〈よりよく〉創始することを意味している。このおのずからは、古いキリスト教思想においてアニマ (anima)、アニムス (animus)、知性 (intellectus)、霊性 (spiritus) と呼ばれた概念に見いだされる。
本書で取りあげられる古いキリスト教思想は、限られている。アウグスティヌス、トマス・アクィナス、エックハルト、エラスムス、スピノザである。彼らを取りあげたのは、彼らが神の語りがたさに挑みつづけていたように思われたからである。そのスタンスを象徴する概念が、アウグスティヌスの「心の眼」(oculus mentis)、トマスの「神を見る」(visio Dei)、エックハルトの「魂の根底」(Seelengrund)、エラスムスの「アニマ」(anima)、スピノザの「アニムス」(animus) である。これらの概念は、一つの類縁的な特徴をもっている。それは、認識の先導性であり、実存の生動性である。この先導性と生動性は、知性に見いだされる力動でもあれば、感覚 (sensus) に見いだされる力動でもある。
こうした古いキリスト教思想で語られるフマニタス (humanitas) と深くかかわる概念が、フミリタス (humilitas) である。神を宗教のなかに封じこめる時代は、このフミリタスを看過しがちである。フミリタス、すなわち無条件に他者を下支えすることは、鷲田清一に代表される臨床哲学が説得的に語ってきた「弱さの力」、すなわち弱さから多様で豊穣な力が湧出するという逆理をふくんでいる。この弱さの力の淵源は、キリスト教思想をさかのぼれば、最初にフミリタスを語ったパウロにいたるが、現在、訴求力を大きく失っているように見える。しかし、そうした世界においてこそ「弱さの力」は、くりかえし語られるべきである。
ベルクソン (Henri Bergson) の生命 (vie) 論は、ここで取りあげた古いキリスト教思想に一つの通奏低音を見いだすうえでも、また宗教内概念としての神に替わる超越性概念を構想するうえでも、示唆的である。ベルクソンの神へのスタンスは、共振的という意味で実在的である。ベルクソンの神は、心が生動化され、先導されるところに見いだされる形なき象りである。彼にとって、それは、無条件の愛としての慈愛であった。ここで取りあげた古いキリスト教思想は、ベルクソンの生命論を理解するための不可欠な文脈であり、また人間と自然の関係をとらえなおす思想的契機にもなるだろう。
(紹介文執筆者: 教育学研究科・教育学部 教授 田中 智志 / 2022)
本の目次
序 章 〈心の眼〉と人間性 ―― ベルクソンの方へ
第1章 〈心の眼〉に見える像 ―― アウグスティヌスの〈アニマ〉
第2章 〈神を見る〉という隠喩 ―― トマスの〈知性〉
第3章 〈魂の根底〉に生じる像 ―― エックハルトの〈人間性〉
第4章 恵みに与る意志 ―― エラスムスの〈アニマ〉
第5章 喚起されるアニムス ―― スピノザの〈心の眼〉
終 章 〈自然〉の分有 ―― ベルクソンと人新世
あとがき
文献



 書籍検索
書籍検索